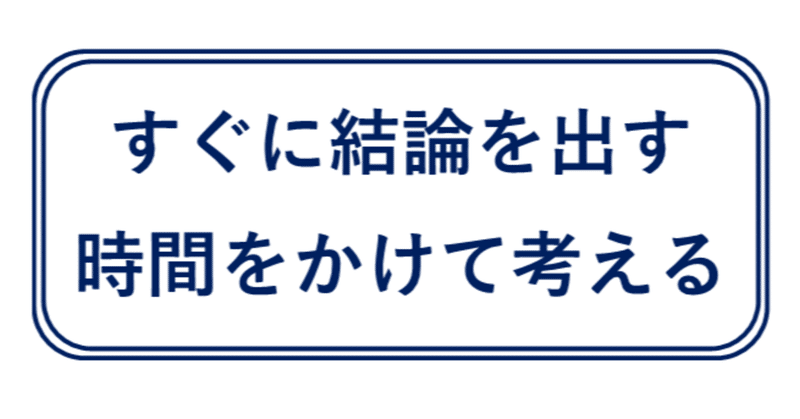
何でもすぐに結論を出さず、ときには我慢してじっくり考えることも必要
ビジネスでは、スピーディな判断や行動が求められる。そうしないと、チャンスを逃してしまうからだ。
しかし、何でもかんでもスピーディに進めるのはいかがだろう?
テーマによっては時間をかけて考えることも、必要ではないだろうか?
保留にしたままは良くないが、保留にせざるを得ないことだってある。
――― 介護の仕事を続けていて、このようなことを考えるようになった。
介護は利用者たる高齢者一人一人に合った支援計画を立てて、それを実行しては見直しをする。
最初はうまくマッチしなくても、いわゆるPDCAサイクルを繰り返しながらご本人にあったサービスプランに近づけていく。
しかし、介護従事者の中には「〇〇さんにはこういうサービスをするべきだ!」と詰め寄ったり、「××さんにはどう接したらいいでしょうか?」とすぐに方法論を求めてくる人たちがいる。
ご本人という存在の輪郭が掴めていない状態で「~べき」と言ったり、認知症からご本人の感情や行動に波があると分かっていても「良い接し方を教えてください」と言ってくる。
このような介護者を見て思うことは「すぐに結論を出したがる」という傾向である。
それは言い換えると「物事はすぐに結論が出る」と思い込んでいるということでもある。
”一知半解”という言葉があるように、自分が知っているわずかの情報や経験で「これはこういうものだ」と分かった気になる人もいる。
例えば、認知症の利用者が食事を食べなくなったり、食べること自体を拒むようになったときに「認知症が進行したんだな」と決めつけることがある。
認知症という言葉は便利である。介護者視点で「認知症だから」と結論が出た気になれるからだ。
しかし、これは思考停止である。「認知症だから」という結論に安心して、背景や利用者の気持ちなんてないがしろにしている。
もしかしたら、お腹の調子が悪いのかもしれないし、虫歯や口内炎があるのかもしれない。入れ歯が合わないのかもしれない。
介護は利用者の心身の状態を、専門職として客観的に観察および考察する必要があるのに「認知症だから」と片付けてしまうことがある。
これはあくまで例であるが、何を言いたいのかと言うと、結論を出すことを急ぐがあまり、それっぽい言葉や情報を見つけて、目の前に起きている問題に無理やり当てはめようとすることがある、という話だ。
別にそれはそれで良いと思う。しかし、その場では問題が解決されたと思っても、それっぽい結論を当てはめているだけなので、後でトラブルになったりリテイクが起きることは容易に想像できる。
こうならないように、まずは結論をすぐ出そうとせず、ときにはじっくり時間をかけて考察したり、地道に観察と検証といった行動が必要なこともあるのだ。
私たちはどうしても答えが出ないと不快感を抱き、
問題を抱えている状況に我慢できなくなる。
だから結論を早く出そうとする。
しかし、早々に出した結論に一体何の価値があるのだろう?
本当の思いを汲もうとせず、「認知症だから」といって決めつけられた利用者に提供される介護サービスに意味はあるのだろうか?
――― 私も含めて、現代人は簡単に答えが出ると思っている節がある。
その対象が人間でも、無機物でも、自然でも、宇宙でも・・・「ああなれば、こうなるはず」と勝手に決めつける。
色々な情報が得られる時代において、自分たちの頭だけで物事がすぐに結論できるという傲慢さがあるのかもしれない。
この記事だって「現代人はすぐに結論を出そうとしている」という決めつけな結論を出しているようにも見える。
・・・何だか堂々巡りになりそうだから、このテーマについてはしばらく保留にしておくとしよう。もしかしたら、時代の変化や私自身の価値観の変動によって、別なタイミングで違う視点が出るかもしれないのだから・・・。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
