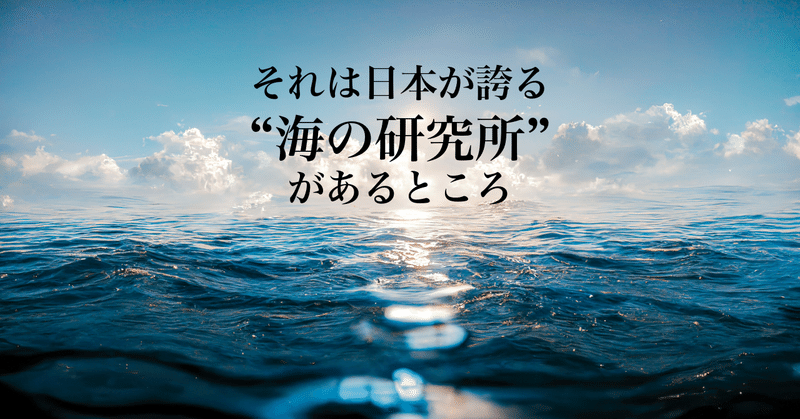
きみは「追浜」を正しく読めるか? ~『大陸の誕生』の誕生秘話~
弊社のT.W.が、4月のブルーバックスの新刊『大陸の誕生 地球進化の謎を解くマグマ研究最前線』の編集を担当しました。その制作過程のエピソードを披露します。(本記事はブルーバックスのメールマガジンに掲載した文章に加筆したものです。)

そのもとになるマグマは特別な条件で発生するようです。
地球ではいつ、どのようにして安山岩マグマの発生条件が満たされたのでしょうか?
本書はこうした謎を解いていきます
初めてのやり方
『大陸の誕生』の制作には、当初想定していたよりも時間がかかってしまいました。おおよそ5年がかりです。本書の著者、田村芳彦先生にとって初めての単著でしたので、じっくりと執筆を進めていただきました。
書きたいこと、書くべきことがあらかた出揃ってからは、田村先生と私のふたりで定期的に打ち合わせを重ねてきました。全体の構成や文章を磨く作業です。何回打ち合わせをしたか数えてはいませんが、短時間で済ませた回も含めると30回以上になるはずです。
これだけ多くの打ち合わせを繰り返す進め方は、私にとって今回が初めてでした。編集者としてどんな貢献ができるのだろうかと、試行錯誤するなかでの「実験」のようなものでした。正直に言って、うまくやれたと胸を張ることはできません。田村先生には相当なストレスをかけてしまったと思います。
「おっぱま」にて
打ち合わせでは、田村先生の所属する海洋研究開発機構(JAMSTEC)の横須賀本部を何度か訪問しました。東京から公共交通機関を利用する場合、京浜急行電鉄本線に乗り追浜駅で下車します。川崎市や横浜市を通り抜け、横須賀市に入ってすぐの駅です。ウィキペディアによれば、「横須賀市の駅としては最も北に位置する」そうです。
「追浜」──きっと「おいはま」と読みたくなった人もいるはず。正しくは「おっぱま」です。妙な響きの駅名です。私の心の中の小学生が、ずっと連呼しています。現実の私は大人なので、そんなおふざけはいたしませんが。
追浜駅からJAMSTECまで歩いていくのはちょっと大変ですから、バスも使います。本数が少なく、乗り場もややわかりにくいので、毎回不安になりました。乗車して15分ほどで到着します。
長時間の移動になりますが、決して後悔はしません。正門をくぐると、目の前に青い海が広がっていて、運がよければ(たいてい?)、研究船も出迎えてくれます。ちょっとした観光気分が味わえます。
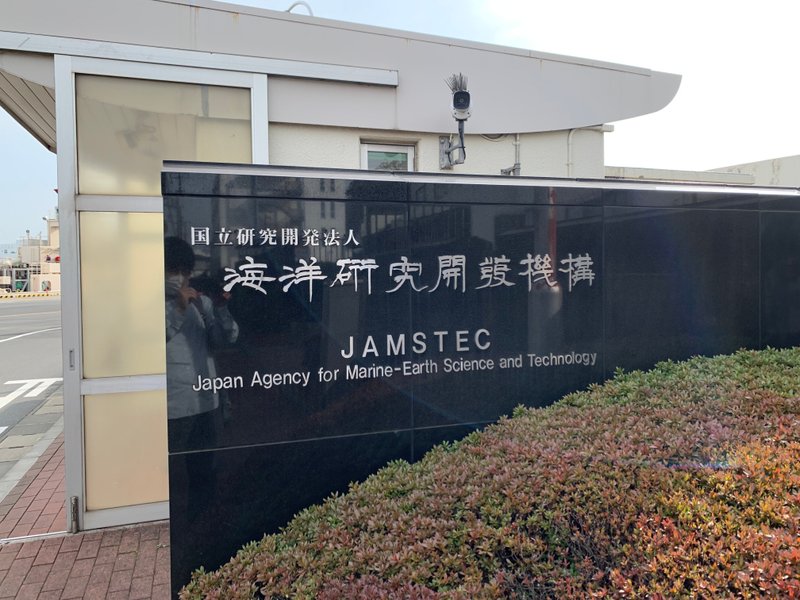


終電にまつわるうらばなし
JAMSTECでの打ち合わせは毎回午後でした。追浜駅へ戻る夕方のバスが出発するまでの数時間、田村先生の居室で話し合うのが定番コースです。
(そういえば、NHKの人気番組「ブラタモリ」〈2022年10月1日放送回〉では、タモリさんが田村先生の部屋を訪問していました。いつも打ち合わせをする部屋でおふたりが話しているのを見たときには、たいへん驚き、感激しました)。
ある日の打ち合わせに、私は「今日が勝負!」と意気込んで臨みました。いま振り返ってみても、このときの話し合いで本書の「背骨」ががっちりと組み上がり、ターニングポイントになったと思います。
じつはこの「勝負の打ち合わせ」の途中、私の心は折れかけていました。
「今日は最後までいくのは難しそうだ……。キリのいいところまでやって、残りは別の日にしよう」
そう考えはじめていたのです。しかし、田村先生は違いました。
「Wさん、今日じゅうに最後まで見直しましょう」
いつも飄々とした雰囲気の田村先生の真剣な眼差しに、すこし気圧されました。著者のこの目を見たら、編集者から「やめておきましょう」とは言えません。最後の章までふたりで読み直し、コメント・疑問出しをやりきりました。
この日は夕方のバスは見送り、深夜まで打ち合わせを続けました。帰りは田村先生のタクシーチケットで追浜駅まで乗車し、ギリギリで終電車に間に合いました──帰宅したのは午前1時過ぎでした。
終電にまつわる「うらばなし」はもうひとつあるのですが、これはまた別の機会に。
ひと皮むけた?
『大陸の誕生』はいままで担当した本のなかで、「著者と二人三脚」で作った感覚が最も強い一冊になりました。編集者としてひと皮むけたのではないかと、なんとなく今後の自分に期待したくなる手応えがあります。
私にとっては、田村先生との勝負の打ち合わせの日が、いまのところ最後のJAMSTEC訪問となっています(その後の打ち合わせは、オンラインで実施してきました)。
しかし、日本が誇る「海の研究所」には魅力的な研究者がまだたくさんいるし、私ももっと海と地球の本をつくりたい! また行くぞ、「おっぱま」へ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
