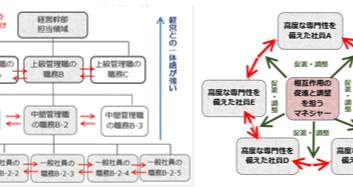
人々が同じ目的を追求するとき、力を合わせて働くために、どのような形のグループとして結集すれば、一人ひとりが生き生きと活躍し、グループとして大きな成果が出せるか? これを考えること…
もっと読む
- 運営しているクリエイター
2023年12月の記事一覧

現代日本で「就労請求権」が認められる場面【地方独立行政法人市立東大阪医療センター事件・大阪地裁令和4年11月10日決定・労判1283号27頁】
本来、労働契約とは、労働者が使用者の指示する時間・場所において指示する内容の労務を行い、その対価として賃金の支給を受けるという契約です。 すなわち、労働者にとっての労働とは義務であって権利ではありません。 そのため、日本の労働法の世界では、基本的に使用者に対する「就労請求権」は認められないものとされています。 しかしながら、自らの資格を維持するために一定の実務経験が要求される職種の場合も同様に考えてよいか? 今回は、そのような点が問題となった事例として地方独立行政法人市

















