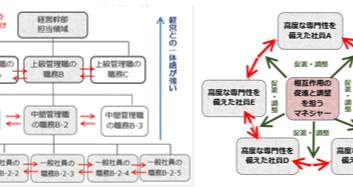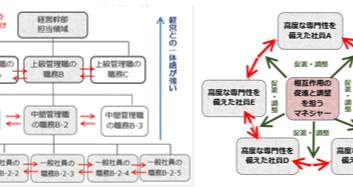百聞は一見に如かず~百見は一考に如かず~百考は一行に如かず~百行は一果に如かず
「ジャズに名演はあるが名曲はない」
ジャズ・ファンにはよく知られたジャズ評論家:野川香文氏の著書『ジャズ楽曲の解説』の中の一節
インプロヴィゼーション(即興演奏)がジャズの最大の魅力であり 名曲でなければ「自作曲を演奏すること」が必ずしもよいジャズ演奏に結びつくとは限らず 優れた作曲家で、かつ優れた演奏者だけが、それをプラスにできるということです(サライ【ジャズを聴く技術 〜ジャズ「プロ・リスナー」への道8】から一部引用)
ジャズは 楽譜通りの演奏ではないので 同じ曲を