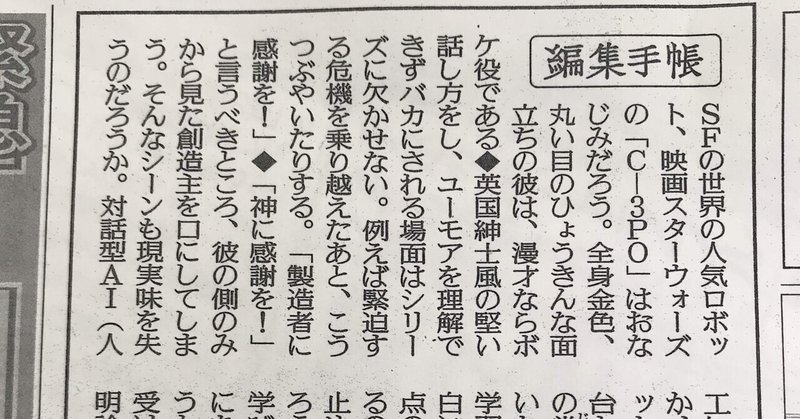
4月14日の新聞1面コラムチェック
日に日に存在感が大きくなるチャットGPT。毎日どこかでこれに関する記事を見かけます。読売新聞『編集手帳』も今日はチャットGPTの話題でした。いわく、「利便向上を止められないのは文明の法則だろう。著作権侵害や子供たちの学びへの影響など懸念は無尽蔵にある。」AIの持つ情報量並みに無尽蔵な懸念を一つ一つ丁寧に解決していかねばなりません。
AIは膨大な情報量を持ち、その中から所定の情報を取り出してくるだけだから、「思考」をしていないんだと何かの記事で読みました。記憶力という点では我々、敵うはずもありませんが、逆にAIには記憶しかないんですよね。そこが「考える」我々とは決定的に違うところなので、我々は考えることをやめてしまったらダメなんです。
新聞には考えるヒントが詰まっています。書いてあることをまず読み込み受け止め、そのうえでじっくり考える。この「じっくり考える」時間が残念ながら社畜には決定的に欠けており、会社からは「そんな無駄なことをしている暇があったら仕事をしろ」と言われてしまう。それに抗って生きていかねばならないはずが、社畜の中には抗うことをやめ、会社の言う通り、考えることは無駄であるとして社畜の中の社畜へと育っていくエリート社畜もいて、このエリート社畜たちは、会社に抗い考えることを続けようとする私のような人間の足を引っ張りまくります。もはやそれが生きがいとでも言わんばかりの社畜ちゃんには何を言っても通用しない。
朝日新聞『天声人語』は各地の大学の入学式の学長の式辞(「の」で繋ぎすぎて不細工!)について書いてありました。AIに言及したのが信州大学の学長。チャットGPTなどについて「リポート作成に際して使用することなど、ゆめゆめ考えないでください」「簡単に得たものは、またたく間に失われる」とおっしゃっています。これもまた「考える」ことの重要性を説いているように思える。広島大学の学長は「ダイパで得た知識で十分か」と問います。本当に賢い人たちは危機意識を持っているのです。アインシュタインも「重要なことは、問うのをやめないことだ」と言っていたらしい。私の周りには問うのをやめたおっさんおばはんが多い。問い続けている人たちはみんな賢い。問い続けている人を上から目線でバカにしてくる人たちには一生辿り着けないんだろう。
日経新聞『春秋』は『三省堂国語辞典から消えたことば辞典』について書いていました。三省堂国語辞典では「企業戦士」が消えたのに「社畜」が登場したらしい。「非効率な自己犠牲と服従を強いる風土は、なぜだかしぶとい」と記事には書いてあるけれど、社畜には社畜の正義があり社畜になりきれない私のような人間に社畜マウントをとってきたりするんです。考えることをやめて新しい価値観を取り入れることなく社畜的精神を押しつけてくる社畜にならないよう、「考える力」が必要だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
