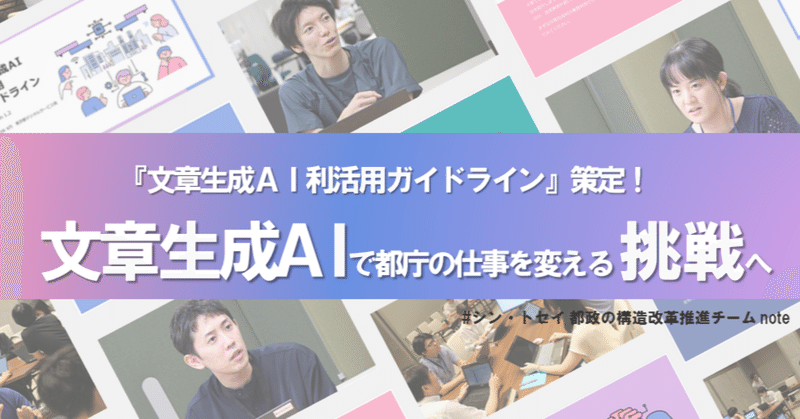
「文章生成AI利活用ガイドライン」策定!文章生成AIで都庁の仕事を変える挑戦へ
東京都では、QOS(都民サービスの質)のさらなる向上に向けて、AIなどの最新のデジタル技術導入に向けた取組を進めています。
この一環として、2023年8月から都庁全体で「文章生成AI」の業務活用を開始しました。また、それに合わせて「文章生成AI利活用ガイドライン」を策定・公表しています。
「文章生成AI利活用ガイドライン」は、職員が安全かつ効果的に文章生成AIを活用できるよう、具体的な活用事例や職員が守るべきルールについてまとめたものです。

今回は、文章生成AI導入・ガイドライン策定に至るまでの道のりや、文章生成AIの業務活用事例をご紹介します!
ガイドライン策定前の検討状況は以下のnoteをご覧ください。
ガイドライン誕生秘話インタビュー!
ガイドライン策定に携わったプロジェクトチームのメンバー、デジタルサービス局総務部の大迫さん、後藤さん、岡田さんにお話を伺いました!

■ ガイドライン策定のきっかけ
―――― 最初に、ガイドライン策定に至った経緯を教えてください。
【大迫さん】
昨年末頃から、ChatGPTをはじめとする生成AIの活用が話題になりました。
生成AIは行政の業務のあり方を大きく変革する可能性も秘めている一方、個人情報の漏洩や誤った回答の可能性など、様々なリスクも指摘されていました。
そのようなリスクを見極めつつも、業務の質の向上や効率化のために新たな技術の活用にチャレンジしたい!ということで、職員が安心して利用できるガイドラインを策定することになりました。

―――― どのような体制でガイドライン策定に取り組んだのでしょうか?
【大迫さん】
AIにも詳しい民間出身の専門人材や、情報セキュリティ部署、企画部署など、組織横断でプロジェクトチームを作りました。最終的には20名近くの職員が協力し、ガイドラインが完成しました。
■ 「べからず集」ではなく前向きなガイドラインを
―――― 文章生成AIを都庁全職員が活用できるようにするということで、非常に大規模なプロジェクトだと思いますが、ガイドライン策定にあたり大切にしたポイントはどういったところでしょうか?
【岡田さん】
行政が作るガイドラインは、「~は禁ずる」といったルールをまとめたものが多い印象があります。もちろんリスク等を考えるとそういったルールも必要なのですが、せっかく全職員が生成AIを活用できる環境を整備するので、ガイドラインも「単なる『べからず集』で終わらせたくない」「生成AIの特性やリスクを理解しつつも、『ルールに沿って積極的に使いこなそう!』という方向性にしたい」という想いはチーム内で共有していました。
その観点から、さまざまな現場を持つ各局の職員も交えてアイデアソンを実施し、具体的な活用アイデアを400個近く集めるなど、活用事例や効果的な活用方法を多く盛りこみ、具体的な業務への活用イメージが浮かぶように意識しました。


【後藤さん】
一方で、生成AIを安心して業務に活用するためには、様々なリスクに対応した利用ルールももちろん必要です。生成AIは進化スピードが目覚ましいので、まだルール化しきれていない部分もありますが、外部専門家の意見もいただきながら、現段階で設定できるルールを整理しました。

■ 白熱した議論
―――― ガイドライン策定に向けた熱い想いが伝わってきます。策定に向けて、チーム内で苦労したことはありますか?
【岡田さん】
先ほどの話ともつながるのですが、積極的に活用してもらうための「攻め」とセキュリティを確保する「守り」のバランスに一番苦労しました。積極的に使ってもらうための前向きなガイドラインにしたい!という想いはチーム内で共有しつつも、生成AI自体が新しい技術であり、技術実証が不十分だったり、国でもルールが確立していなかったりするので、「都のガイドラインでセキュリティ上どこまで制限すべきなのか」という議論はチーム内でもかなり白熱しました。
結果として、豊富な活用事例に加えて職員が守るべきルールを4つに分かりやすくまとめて提示することで、職員が安心して生成AIを活用できるようにしました。また、AI技術の進化はとても速いので、ガイドラインは今後も更新していく必要があると考えています。

【後藤さん】
利用する側の職員として、最大限のリスクヘッジは、結局「利用しない」ことにつきてしまうと思います。しかしそれではせっかく生成AIを使える環境があるのにもったいないですよね。
プロジェクトチーム内で「このガイドラインは積極的に利用するためもの」というビジョンを共有した上で、その達成に向けてときにはぶつかり合い、ときにはお互い歩みよりながら議論を重ねることができた点が苦労した点でもあり、やりがいを感じた点でもありました。
■ 多くの反響もいただきました
―――― 自治体としてこうしたガイドラインはまだあまりないのかなと思いますが、他の自治体からの反響はあったのでしょうか?
【大迫さん】
大変嬉しいことに、自治体や都民の方、メディアの方からも多数反響をいただいています。特にメディアの方からは、公表日当日に10社以上から取材の申込みをいただき、新聞やニュースなど様々な媒体で取り上げていただきました。また、おそらくそれらを見て取組を知ってくださった約20の地方自治体の方からもお問合せをいただいている状況です。(2023年9月時点)
一番多いお問合せは、「ガイドラインを二次利用したいんですけど」というものですね。使用しているイラストだけは二次利用ができないのですが、それ以外の文章など、我々が作った部分についてはそのままご利用いただけますということをご案内しています。
また、これをきっかけとして、各種講演への登壇依頼もいただいています。

■ 生成AI活用の輪を広げていく
―――― 最後に、ガイドラインを使う方に向けてメッセージをお願いします。
【大迫さん】
まずは生成AIをとにかく活用してみて、業務利用での可能性を感じてほしいです。
そしてその先に、「もっとこんな技術が使いたい」「こう使うと良いよ!」等々、我々プロジェクトチームでも想定しないような技術活用が各局から日々出てくると嬉しいですし、更なる改善にモチベーションが上がり、職員全体のリテラシー向上につながると良いなと思います。そのようなサイクルを都庁で実現し、さらには他の自治体にも広がる姿が理想ですね。
―――― 文章生成AIや今回のガイドラインをきっかけとして、都庁の働き方が変わっていくのが楽しみです。本日はありがとうございました!

文章生成AI活用事例のご紹介
つづいて、文章生成AIの活用事例についてご紹介します。ガイドラインにも豊富に掲載していますが、担当のお三方からもオススメの活用事例をお聞きしました!
■ 文章作成/要約/翻訳
たとえば、都民の方や職員向けのお知らせや説明会の挨拶などを考えるとき、得意な人はスラスラ書けるかもしれませんが、(私含め)苦手な人はなかなか筆が進みません。そんなときは生成AIの出番です!

もちろん、生成AIが作った文章をそのまま使えることは少ないと思いますが、一旦「たたき台」として作成してもらった文章を添削する気持ちで臨むと、かなり負担が軽くなります。
また、翻訳も簡単にできますので、グローバルな人材に一歩近づけます!(もちろん、作成後の文法や表現のチェックはマストです。)
<プロンプト1>
私は東京都の職員です。職員向けに行う生成AI導入に関する説明会の冒頭の挨拶を200字程度で考えてください。
<回答1>
AI導入に関する説明会へのご参加、ありがとうございます。本日は、生成AIの導入について詳しくお話しいたします。AI技術は、行政業務の効率化やサービス向上に大いに貢献できるものです。生成AIは、大量のデータを学習し、新たな情報を生成することができます。これにより、迅速かつ正確な情報提供が可能となります。本説明会では、生成AIの仕組みや導入メリット、具体的な事例などをご紹介します。AI導入によって、より効率的な業務遂行や品質向上が期待できます。どうぞ、ご受講いただき、AI導入に対する理解を深めていただければ幸いです。説明会を始めますので、ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。よろしくお願いいたします。
<プロンプト2>
英訳してください。
<回答2>
To all employees of the Tokyo Metropolitan Government, thank you for attending the briefing on the introduction of AI. Today, we will provide detailed explanations on the implementation of generative AI. AI technology has the potential to greatly contribute to the efficiency and improvement of administrative tasks. Generative AI has the ability to learn from vast amounts of data and generate new information. This enables us to provide prompt and accurate information. In this briefing, we will introduce the workings of generative AI, its benefits, and specific case studies. The introduction of AI is expected to enhance the efficiency of our work and improve the quality of our services. We hope that through this briefing, you will gain a deeper understanding of AI implementation. We will now begin the briefing, and please feel free to ask any questions or make any requests. Thank you for your attention.

■ アイデア出し
新しいイベントなどを企画する際、誰か一緒に考えたり、アドバイスしてくれる人がいるといいのにな、、と思うことがあります。もちろん上司や同僚に相談してもいいのですが、文章生成AIも相談相手になってくれます。

生成AIはフラットな立場でアドバイスしてくれるので、職員だけでは思いつかないようなアイデアをもらえることもあります。
<プロンプト>
私は東京都の職員です。職員が参加するワークショップのアイスブレイクを考えてください。
<回答>
ワークショップのアイスブレイクは、参加者同士がお互いを知り、コミュニケーションを円滑に進めるための重要な要素です。以下にいくつかのアイデアをご提案いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。
1. トリビアクイズ: 参加者全員に事前に用意したトリビアクイズを配布し、各自が解答します。その後、解答を発表し、正解した人同士でグループを作り、自己紹介やクイズに関する話題で会話を進めます。
2. パートナー紹介: 参加者をペアに分け、お互いについての情報を収集します。その後、ペア同士が交互に紹介し合い、他の参加者にも紹介してもらいます。
3. 興味・関心の共有: 参加者全員に用紙を配布し、自分の興味や関心のあるトピックを書いてもらいます。その後、グループを作り、各自が書いたトピックについて話し合い、共通の興味関心を見つけます。

■ ゆくゆくは...
行政の仕事をしていると「この課題について、他の自治体や国・海外の先進的な取組を参考にしたいな」と思うことがよくありますが、例えば47都道府県のホームページを見て該当事例を調査するのはかなりの労力です。このような仕事こそ生成AIにお願いしたいところですが、残念ながら現在の生成AIでは、どこかから実在しない事例を収集してくるなど、なかなか上手くいきません。今後、技術の進化や学習データの拡充などによって、そのような相談相手になってくれる未来がくれば、より一層頼れる存在になるかなと感じています。
現在のところは、(たまに間違うけど)いつでも相談できるアイデアマンとして、今後も積極的に業務に活用していきたいと思います!
【ご意見募集中】都政の構造改革(#シン・トセイ)やnoteに関するご意見・ご感想をこちらのフォームから受け付けております。ぜひ、ご意見をお寄せください。
