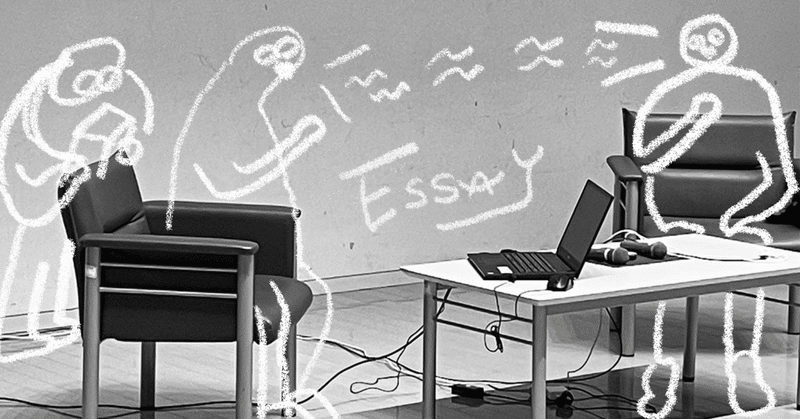
Essay|島袋道浩と安井仲治の断片の記録
今回は、2月28日に行われた安井仲治展のイベント「記念トーク|美術家(島袋道浩)から見た安井仲治の記録」をお届けします。
Records of Nakaji’s vision from Shimabukuro

大きなミュージアムホールの白い壁に縦長な写真が映し出された。安井仲治展のイベントの学芸員とのトークセッション、登壇者は、島袋道浩である。
「大ファンとか影響受けたわけではない。多才な”仕事”をされてきた人ですよね。」「安井さん、こんなに自分の写真が並んでいるの見たことないだろうね。」
博識な島袋だが、彼の喋り口は飾らないラフさとユーモアを織り交ぜている。
軽快なトークが、 美術家ならではの視点を切り口に進んでいった。
とある写真では、建物の前に置いてあった屑入れと箒に目をやり「小さいものやきれい(だけ)じゃない物に目がいく人なんだな」と観察。
《魚》イワシの干物の写真では、「田舎とヨーロッパの都会を思わせるよね。この対比の構図で、ロシアの構成主義みたいだよね」っと呟く。
電柱の写真の“ごちょごちょ”した写真には、共感し、島袋ががアフリカにいった時に撮った写真と類似していた。
「今日のトークはいっぱい脱線しますから」と前置きし話だした。
だが、そう易々と作品を解説しない。 安井作品が持つ近現代の写真史/アーティストとリンクする部分を紐解いていった。
A present for Boris Mikhailov

ロンドン滞在中に、当時名古屋市立美術館の学芸員がちょうど完成した生誕百年安井仲治展の図録を持って島袋の元に訪れていた。 彼らは、近所に住むボリス・ミハイロフの家へ 安井展の図録を持って向かった。キッチンで(キッチンショー*) ボリスは、熱血で終始怒っている様子で自身の作品の感想を島袋に聞いたり、説明したりした。 安井の図録を見せると「オリエンタルダナー。」と言った。
(図録はボリスにあげちゃったそうだ。)
島袋は、当時を振り返り「写真作品は、被写体によって(国が)決まるのか。」
例えば、日本の物をとると“日本”の作品(?)になってしまうのかという疑問を持って、ボリスの発言を捉えていた。
キッチンショーのエピソードをジョークのように笑いながら話していたが、実際はボリスの作品に対する熱意が溢れ、緊張の場面もあったに違いない。

*キッチンショー
当時の芸術家たちの中で、キッチンテーブルを囲み、食事を行いながら写真を見せ合いっこ、結構白熱していたらしい。写真を見せ合って、意見が食い違う場面も多く、中には殺し合いになったケースもあるそうだ。
Homage to Nakaji Yasui

あいちトリエンナーレ2010で島袋は、愛知県知多郡南知多町篠島という漁村でのフィールドワークを元に作品を制作した。展示場所は、名古屋市美術館。この展覧会の中で、島袋は、いくつかの安井仲治の作品(兵庫県美術館の委託)を借り、自身の作品と並べて展示した。
《きみは魚を捌けるか?漁村美術の現在》
この島にはウィリアム・デ・グーニングみたいな へんな抽象的な落書き 「いっぱいあんのよねー」だったらしい。(その落書きの主を見つけてしまうところが島袋である)
《篠島でであった一番大きな男、通称大将の日光写真》
ロトチェンコ・アレキサンドル の角を切る手法を導入。安井の作品にも重なる点が見られる。
(日光写真とは、青写真(サイアのタイプ)。2009年に兵庫県立美術館で開催された「Link-しなやかな逸脱:神戸ビエンナーレ招待作家展」でも同手法を取り入れた作品を制作している。この際は、新開地(神戸市)の市場で見つけた魚やラオス昆布を「えらいどーんと、」館内で青写真として写し取り、美術館までの道のりが案内サインにしてしまった。)
《タコ石》
たこつぼ 蛸壺の中には蛸が集めた石が入っている。 その石を島袋が集め、最後にコレクターが集めるという縮図を表現。

His Perspective power to this exhibition

安井は、多くのポートレイトを残している。その大半は「よそ見ばかり、何かを見ている」が、《流氓ユダヤ》は、アウグスト・ザンダー作品にもみられるような、「レンズを射抜くように映されていて、映る側の態度の違いがあるね。」と推測していた。
(なお、安井は、作品制作の際にネガを大胆に切り取っていたことが発見されている。ユダヤ撮影の1938年は、日中戦争に入り、写真が撮れなくなってきていた。また、ユダヤはネガが残っていないので、どういう風に切り取られたのか推測が難しいそうだ。)

展示手法に対して、「大きさが一緒で単調な展覧会場は、ただの資料展示のようだよね。例えば、壁の高いところに置いてみたりしたらどうるかなぁ」と島袋ならではのアイデアを提案していた。

展示会場を歩き作品鑑賞しただけでは味わえない、島袋の発想の自由さが炸裂したトークとなった。 「楽しさに塗れて」惜しくも時間がオーバーの為、トークは終わりへと向かった。最後は、安井の非公開のガラス板のカラー作品が投影され、終了した。 トーク中、「安井の写真は、この2枚が欲しいなぁ」とニヤッと笑っていた。(1つは、イワシの写真なんだけど、もう1つが若干記憶があやふやであってるかどうか不明。)
In conclusion
今回は、自身の手記と記憶を頼り、断片的な、トークの記録をエッセイのようにまとめてみました。 現代のアーティストが、近代の作家を自分の作品や歴代の西洋の芸術家と並べて、比べて見ている点が新鮮でした。 今後も芸術に関することを投稿していく予定です。 いいねやコメントお待ちしております。フォローしていただけると嬉しいです。
参考サイト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
