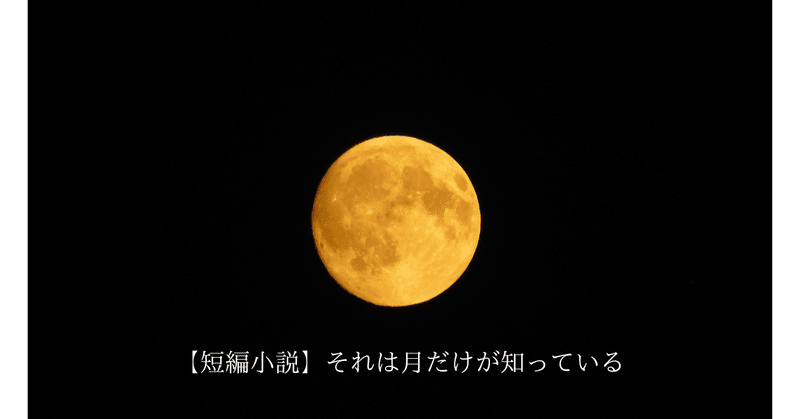
【短編小説】それは月だけが知っている
「この頃、家で仕事していても、集中できないんですよね。」
そう言って、愛想笑いのようなはっきりしない笑みを口元に張り付けると、それを聞いた相手は、画面の向こう側で、少し考えるかのように口元に手を当てた。
「在宅だと、通勤時間はないし、電話や他の人との話で、作業を中断されることはないけど、自宅ってプライベートな空間だから、自分の中で、うまくオンオフ切り替えないと、いけませんからね。」
「自分は家が好きなので、在宅は望み叶ったものですが、実際にやってみると、いろいろと不都合もあるものですね。」
半年くらい前まで、関野は契約社員として働いていた。
在宅ではなく、普通に通勤で。仕事自体は関野に多分合っていた。というか、彼は変に器用なところがあって、よほどのものでなければ、仕事は普通にこなす。
その会社は、正社員、契約社員、派遣などいろいろな就業形態の人が入り混じっていたが、形態によって仕事の量や質にあまり大きな違いがない。
関野が正社員ではなく、契約社員として働いているのに、特別な理由はない。最初から正社員ではなく、契約社員を選択した。
結婚もしておらず、一人暮らしだった彼に、正社員と契約社員の差は大きくないように見えたから。安定よりも自由度を取った。一つの会社に何十年も長居するつもりもなかった。
でも、一度、契約社員を選択すると、正社員になることは難しいと気づいた。気づいた時には遅かったが。
今は在宅で、Webライターをしている。
またもや、特定の会社の契約社員として。仕事はコンスタントに降ってくるし、家にいるのが好きだったから、それなりに充実しているのだが、このところ、仕事に対する集中力に欠けているように感じる。
半年たって、仕事に対する慣れも出てきているのかもしれない。
関野の仕事に対する悩みを聞いている相手は、同じ会社のメンターである岡だ。
岡は正社員で、入社5年目。彼女もコラムや記事を書くが、それよりも、校正や記事の割り当て、シフト、人材調整など、複数人の非正規社員のマネジメントを行っている。岡とは月2回ほど、オンラインで面談をする。
その時に、今後の仕事の仕方や悩み相談に乗るわけだ。
自分よりもかなり若いのに、カウンセラーみたいなことをして、気疲れしないんだろうか?
あまり、顔色の良くない岡の顔を見ながら、そんな仕事とは全く関係ないことを考えていると、相手がじっと彼に向かって視線を送ってくる。
「たまには、会社に出社して、仕事してみては?と言いたいところですが、関野さんのお住まいから、会社に行くには、ひと旅行になってしまうから無理ですね。」
「・・確かに。」
関野が就業している会社は、北海道にある。
もちろん、一度も行ったことはない。
入社時の面接も全てオンラインだった。直属の上司と顔を合わせたのも、数回しかない。
「近場のカフェとか、図書館とかは試されましたか?」
「ええ。でも、不特定多数の人がいる環境も、それはそれで駄目みたいです。」
「すると、レンタルオフィスとかでしょうか。」
「近くにはないですね。」
岡は更に難しい表情になった。別に時間が経てば、その内また集中できるようになるだろう。いい気分の切り替え方法が見つかるかもしれないし。彼女の気持ちを上向かせるような言葉が何かないかと探していると、先に岡の方が表情を緩めて言った。
「関野さん。一緒に仕事場、借りません?」
「・・仕事場ですか?」
「私も普段は取り引き先に出向く事が多いですし。パソコンがあれば、何とかなってしまうのですが、ちょっと集中したい時に、籠もれるところが欲しかったんですよね。職場に行くのは遠いし、だからといって自宅で仕事するのは、関野さんと同じで、気が散りますし。」
「自分はいいのですが。」
「試しにやってみません?お互い条件を書き出してみて、それに合った物件を探してみましょう。家賃とか光熱費は折半で。」
「でも、負担かかりますよ。」
「レンタルオフィスを契約するより、安くすむような気がします。」
「ねぇ、そうしましょう。」と言って、彼女は笑みを浮かべた。
実はお互いの住まいが、そう離れてはいないと分かったのは、仕事場としての賃貸物件を見繕い始めてからの事だった。彼女は自分の住所を知っている。だからこそ、こんな提案をしてきたのだ。
つまり、自分たちの面談は、別にオンラインでなくとも良かったということでは?とも思ったが、他の非正規社員と違って、自分だけ特別扱いするわけにはいかないのかもしれない。
とはいえ、自分と一緒に仕事場を借りようと言ってくるところからして、仕事の枠を超えているような気はするが。
お互いがそれぞれ仕事をする部屋、打ち合わせに使う部屋、簡単な給湯設備がある物件を見つけ、自分の仕事道具などをそこに移した。移動は自転車で済む。冷蔵庫も備え付けられていたし、電子レンジは中古の安いものを購入した。
最初、その仕事場を使うのは、もっぱら関野のみで、岡は週に1日か2日くらいしか滞在しなかった。お互いがいる時は、一緒に食事を取ったり、休憩をしたりする。
休憩時は仕事の事は話さず、プライベートの事や、日々のどうでもいいことを飽きることなく話した。
この時間が続けばいいのに、と関野は度々思ったが、岡が同様に考えていたかは不明だ。
仕事場に、その日必要なものを置いたままにしてあることに気づいたのは、既に夕食や風呂も済ませ、そのまま寝ようと思った時の事だった。
正直、気持ちとしては既に寝るつもりだったので、取りに行くのはおっくうだったし、翌朝でいいかとも考えた。しばらく悩んだ後、部屋着に薄い上着だけ、はおって家を出る。
外は雲がなく、月の綺麗な夜だった。
夜に仕事場に向かうのは初めてだ。
自分は仕事場を勤務時間と同様、9時から18時までしか使っていない。残業には無縁だし、実際任せられた仕事をこなしていれば、本当はその時間内きっちり働かなくてもよかったりする。自分の裁量に任されているところが多かった。
それでも結局、職場に通うように、仕事場に通っている。その方が自分の中で、オンオフの切り替えがつけやすい。
せっかくの在宅勤務だというのに、普通の会社員と変わりない。やはり、どんなことにもメリットとデメリットは存在する。
岡と仕事場を共にするのにも、彼女と同じ時間を共有できるというメリットと、それ以上の関係に踏み込めないというデメリットがある。
どんなに一緒に過ごそうが、それは仕事上の関係でしかなく、それ以上を望んだら、多分壊れてしまうだろうことが、感覚として分かる。
ようやく着いた仕事場には明かりがついていた。
明かりがついているということは、こんな夜中なのに、岡が中にいるということだろう。
関野が手をかけた玄関のドアノブも抵抗なく回る。息を殺して中に入ると、女物の靴が一足揃えられているだけで、岡以外の人が来ているわけでもないらしい。
このまま、足を踏み入れていいものか。関野は少し躊躇したが、考えてみると、「ここは自分の仕事場でもある。何をためらう必要がある」と思い直し、そのまま打ち合わせスペースにもなっている部屋に、足を進める。
関野が部屋に入るのと、岡がその赤い顔を向けるのは、ほぼ同時だった。岡は、関野を見ると、その顔を嬉しそうに崩した。
「あれ、関野さん。何でこんな時間に?」
「忘れ物を取りに。というか、岡さんこそ、こんな夜中に何してるんですか?」
「ちょっと、会社でいろいろありまして。」
そう言って笑う岡の前のテーブルには、発泡酒の缶が2つほど転がっていた。手にもさらに1缶持っている。赤い顔は酔っているためだったようだ。
「だからと言って、飲みすぎじゃないですか?」
「明日は休みですし、これくらい大丈夫です。それより、関野さんのラフな姿、初めて見ました。」
「それは・・普段は仕事ですから。」
「そうですよね。関野さんも一杯どうですか?」
そう言って立ち上がり、冷蔵庫の方に歩こうとしたが、危なっかしく体が揺れる。関野は倒れそうになる岡の体を慌てて支えた。
「もう、止めましょう。」
「・・関野さん、私、異動することになりました。」
関野の腕の中で、岡がポツリと呟く。
「異動ですか?」
「はい。本社勤務になりました。」
「本社って、つまり、栄転ってことじゃないですか?おめでとうございます。」
「・・本社は北海道です。ご存知ですよね?」
そう返されて、関野は言葉を失う。
そう、自分は行ったことのない北の大地。
「自分の力が認められての異動ってことは嬉しいです。」
「・・・。」
「でも、引っ越さないといけませんし、この仕事場も・・もうおしまいです。」
「それは、そうですね。」
無意識に岡の体に回した腕に力が入る。岡は話しながらもずっと目を伏せていて、その表情は読み取れない。
「関野さんともお別れです。」
「前の関係に戻るわけではないんですか?」
「・・本社のどの部署に異動になるかは、まだ分からないので。仕事内容も変わるかもしれません。」
これが岡との完全な別れになると思ったら、関野の口の中が急激に渇きを覚えた。岡の手に持った缶を取り上げると、残りをごくごくと飲み干す。その様子を岡が呆けたように眺めて、その後プッと噴き出した。
「関野さん、いい飲みっぷりですね。」
笑い過ぎたためか、岡の目尻に涙が浮かぶ。
「岡さん。この仕事場は、いい環境だったと思いませんか?」
「はい。だからこそ、私はこんな形で終わりにしたくなかった。」
「別に仕事場が北海道にあっても、自分としては問題ないんですけど。」
関野の言葉に、岡は少し視線を泳がせた後、何かに気づいたように、その目を見開く。
「それ本気で言ってますか?」
「自分は、このまま岡さんと別れてしまう方が嫌です。」
「・・あまり優しい言葉をかけられると、調子に乗りますよ。」
「むしろ調子に乗ってくれた方が、気を許してくれたみたいで嬉しいです。」
自分達の言葉にひとしきり笑いあった後、2人がどうしたかは、カーテンの隙間から見ていた月だけが知っている。
終
私の創作物を読んでくださったり、スキやコメントをくだされば嬉しいです。
