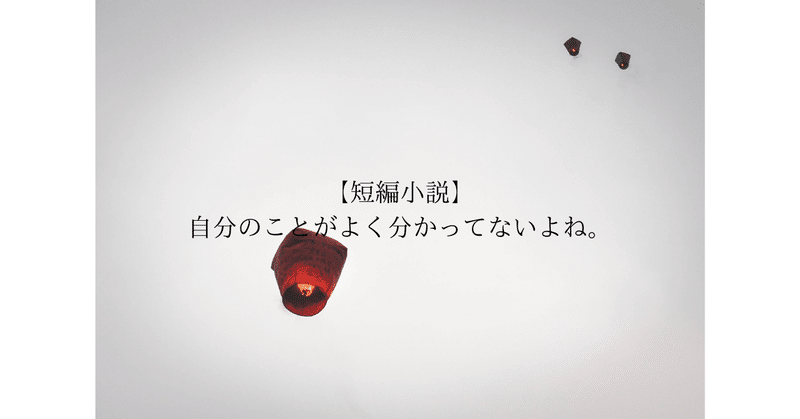
【短編小説】自分のことがよく分かってないよね。♯一つの願いを叶える者
「貴方は選ばれました。貴方の願いを一つ叶えましょう。」
そう言って、現れる白い服、白い肌、中性的な面立ち。
彼、彼女は、誰かの前に決まり文句を吐いて現れ、相手の願いを一つ叶えてくれると言う。
都市伝説のような、怪しい話。
そもそも、願いを叶えたら、その叶ったことすら忘れてしまうと言うのだから、その話が広まっていることすらおかしい。だが、救いのない今の世界には、好意的に受け取られ、広まった。
いや、実際に見た事のある人は、ただ一人としていない。
私だって、目の前で決まり文句を吐かれなかったら、信じられなかっただろう。
「何、泣いてんの?おねーさん。」
仕事帰りに、こらえ切れなくなって、公園のベンチで泣いていた私に声をかけてきた相手は、先ほどの決まり文句を吐いた後、こちらを不思議そうに眺めている。
髪は短く、年齢は自分より下、高校生ぐらいに見える。中性的な容姿だが、その口調から男の子ではないかと思った。今日、お別れした私の教え子たちと同じくらいの子。
白のオーバーサイズのパーカーに、白のチノパン。スニーカーも白。肌も白。彼の背後の外灯に照らされて、白い人型の輪郭が目に焼き付く。
「・・今日、私の教え子たちとお別れしてきたの。だから、悲しくて。」
「おねーさんは、先生なの?」
「学校じゃなくて、塾のね。もう何度も経験してるけど、やっぱり辛いわ。」
ただ、今回は、毎年の別れとは少し違う。
今回の教え子の中に、一人特別な子がいたから。
塾というのは、生徒を志望校に合格させるのが目的だ。
生徒には全て公平に接し、もちろんえこひいきなどあってはならない。
それなのに、私はその内の一人の生徒に恋をした。
年齢など、10歳以上離れている。
私はその気持ちを周りに知られないように必死で押し殺した。
当の本人にも、私の気持ちは伝えていない。
気づかれてはいないはずだ。私もそれなりに大人として、社会人としてやってきたのだから、仮面をかぶるのには、慣れているつもり。
「それで、話を戻すんだけど、一つの願いを言ってほしいんだよね。」
「・・泣いている相手をからかって遊んでるのかしら?」
「そんな面倒な事しないよ。でも、おねーさんが選ばれたから仕方ないんだよね。まぁ、話を聞いてみてよ。」
彼は、私の隣に腰かけると、淀みない口調で自分の役目について語り始めた。
変な子だと、席を立って、帰ってしまってもよかったけど、好きな人や教え子と同じくらいの子というのが、私の警戒心を緩め、その場に引き留めることに、成功していた。
彼の役目は、選ばれた人の元に行って、一つの願いを聞き、その願いを叶えること。願いを叶えれば、彼はこの場から消えるし、私は彼と会ったことを忘れてしまう。
願いは何でも構わない。お金、地位、名誉、永遠の命、病気の治癒その他諸々。願いが叶うと、それに合わせて周囲も矛盾がないように補正され、願いが叶った本人も、その事を忘れてしまうから、何の問題もない。
叶えられる願いは一つだけ。それを複数に変えることはできない。
「理解した?」
「理解はしたけど、なぜそんなことをしているの?」
「それは知らないので、答えられません。先生。」
「やっぱり、からかってるでしょう?」
「・・・おねーさんの名前言ったら、信じる?」
私の耳横に手を当てて、彼が囁いたのは、確かに私の名前だった。
「確かに。」
「では、一つの願いをどうぞ。」
耳元に当てていた手を外して、私に向かって差し出してみせる。
私はそれほど迷うことなく、彼に向かって答えた。
「私の好きな人が、幸せな人生を送れますように。」
ただ、彼は私の願いを聞いて、首を傾げた。
「おねーさんの好きな人は誰?」
「名前を言わないといけないの?」
「おねーさん、僕を魔法使いか何かと勘違いしてない?おねーさんが教えてくれないことは、分からないよ。頭の中が読めるわけでもないし。」
私は、顔が熱くなるのを感じながら、今日別れた教え子の名を口にする。
別れる時、何か言いたげではあったけど、私はその言葉を促してあげるほどの余裕は持てなかった。寂しそうな表情ではあった。別れて清々したという様子ではなかったはず。
相手は、私の前で人差し指を立て、左右に軽く振りだした。
「残念だけど、それは叶えてあげられません。」
「何で?」
「言ってしまうと、僕が叶えなくても叶えられる願いだからです。」
「?」
「でも、叶えないわけにはいかないから、どうしようかな。」
彼はそう言って、うーんと唸りだす。私は、訳も分からず、彼が考えているのを邪魔しないようにと、考えがまとまるのを待っていた。
しばらくすると、彼がハッとしたように、顔を上げ、私の顔をまじまじと見つめた。そして、ニンマリと顔を緩めて笑う。
「おねーさんの願いをちょっと変えます。」
「は?」
「・・くんとおねーさんが、幸せな人生を送れますように、でどう?」
「・・あまり、違いが分からないのだけど。」
「人って、自分のことがよく分かってないよね。」
彼は、うんうんと頷いているけど、願いに私が入ったところで、どう変わったのかはよく分からなかった。
「でも、それで願いが叶うのなら、私はそれでいい。」
どちらにせよ、好きな人が幸せになれるのなら、それでいいのだから。
私が頷くと、静かな眼差しで見つめていた白い人物は、とらえどころのないふんわりとした笑みを浮かべた。
「貴方の願いは叶えました。」
憧れのウェディングドレスを着た私は、初めてその姿を見て、呆けたようにその場に立ち尽くしている彼を見て、笑う。
「どうかな?」
「・・とても、綺麗。」
「・・くんもかっこいいよ。」
「いつまでも、生徒扱いは止めて。」
「心からそう思ってる。本当に。」
彼は、私の言葉に照れたように笑う。彼とは10以上も年が離れている。いつも、それがコンプレックスだったが、彼はその度に「私がいい」と口にしてきてくれた。そして、今日という日を迎えられたのだ。
「貴方は僕が幸せにします。」
「それは違うよ。」
「?」
「君と私は、共に幸せな人生を送るんだから。」
そう言って、私は彼に微笑んでみせた。
終
マガジン化してます。
私の創作物を読んでくださったり、スキやコメントをくだされば嬉しいです。
