
「ダイナモ人」が未来への鍵を握る理由(3)
これまで紹介してきた調査(「ダイナモ人」が未来への鍵を握る理由(1)・(2))はその最初の一歩ですが、一般社団法人知識創造プリンシプルコンソーシアム(KCPC:Knowledge Creation Principle Consortium)では、知識創造プリンシプルに基づいて、企業の枠に捉われない個と組織への転換・加速を支援するダイナモ革新(Dynamo Revolution)を提言していく予定です。
ここであらためて、「ダイナモ人(dynamo)」のコンセプトのインスピレーションとなったデービッド・メイスター氏の研究と実践について触れておきたいと思います。筆者がずいぶん前に紹介、解説を加えた氏の著書『脱「でぶスモーカー」の仕事術 なぜ"わかっていてもできない"のか』(2009、日本経済新聞出版)からのエッセンスも紹介していきましょう。

苦しいダイエットを経てはじめて得られる革新の成果
日本企業の停滞がどこまでのものか、いろいろな意見がありますが、やはり深刻な現状を認めざるを得ないのではないでしょうか。経済界の一部や識者はそう信じていないかもしれません。ところが、ついこの間まで日本的経営の復権が叫ばれていましたが、最近は停滞を認める発言も増えているようです。しかし、どうあろうと、時代は変化していくと思いますー「前」の方に。
1980年代は日本企業が世界で存在感を誇り、その組織やリーダーが世界から評価された時代でした。一方、その間、米欧企業は日本企業の「成功」のリバースエンジニアリングを行ない、さまざまな対策、コンセプト、システムを打ち出し転換を図っていきました。今日本企業が躍起になっているオープンイノベーションやアジャイルアプローチ、両(手)利き経営などの多くのアイデアは、すべてにおいてではありませんが、当時の日本企業経営研究に発端やルーツを持っています(つまり逆輸入)。
たとえば筆者が翻訳した『アジル・コンペティション―「速い経営」が企業を変える』(1996、日本経済新聞出版:アジルとはアジャイルagileのこと、最初にアジャイル概念を打ち出した書籍)は、米国産業界の次世代製造業研究であり、その魁のひとつでした。そこでは重厚長大(大量生産大量消費)で鈍重な19-20世紀型製造業に対して、「個」に焦点をあてた俊敏で機動的な製造や、あるいは日本のケイレツに代わるオープンで臨時的な企業共同体つまり「仮想的企業体(virtual enterprise)」などが提唱されていました。
こういった流れがさらにDXやオープンイノベーションの概念を生み出していったのです。とくにそれがインターネットの登場(1995年)以降、劇的な勢いで現実化し、気がつけば時代やゲームは大きく変わっていきました。こういったことはもう言うまでもないでしょう(当時日本ではインターネットの脅威を「ウェブの世界」のこととして「対岸の火事」のごとく専門家が説明していただけにとどまった感があります。しかしその間、製造業=モノづくりに、ソフトウエア開発の手法や思考法がどんどん転写されていったのです)。
けれども、ここで目を向けたいのは、この「日本の失われた期間」に欧米企業が相当の痛みに取り組み、変化への超努力を長期にわたって経てきた、ということです。その前後では産業界や企業の様子、顔ぶれはがらっと変わってしまいました。
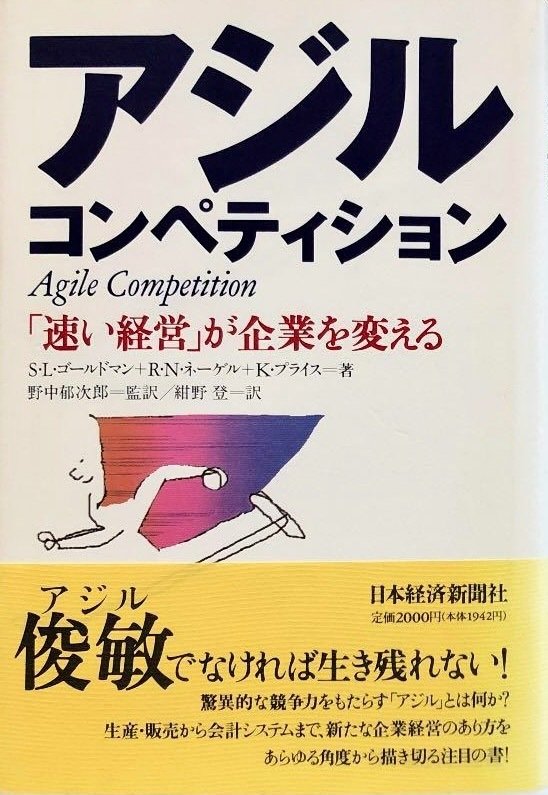
ところで『脱「でぶスモーカー」の仕事術』の翻訳では、デービッド・メイスターの住むボストンまで行って二人でいろいろな議論をしました。そのあと日本語版序文を書いてもらいました。彼はその終わりにこう結んでいます。
一九八○年代、われわれ西欧人の目から見て、日本のリーダーは、長期的な観点を重視する規律正しい人間であることによって、従業員からすぐれた成果を引き出すことに長けていた。
新世紀に入り、日本がいまも競争上の優位を保っているかどうかは不明確だ。日本の会社も多くの西欧の会社と同じ混乱状態にあるように見えるーすなわち、自分たちの知っていることが長期的には「正しい」道だとわかっていても、そこから離れて短期的な目標を達成せざるをえない状況に追いこまれている。
今後日本の会社は、長期的な利益を生むダイエットやエクササイズを根気よく実行することがよりうまく(それとも下手に)なるだろうか。伝統的文化の最良の部分を維持していくだろうか、それとも嵐のような短期的プレッシャーに負けてしまうだろうか。
これが書かれたのは2009年のことですから、そこからすでに十数年が過ぎています。ところがまだ日本企業はなすべき「ダイエット」はやっていないように見えます。日本の組織が持っていた長所について、その過去(在りし日の日本的経営)の姿を礼賛するのでなく、いますぐここから、長期にわたるかもしれない超努力に向けてその力を発揮すべきことを迫っているのです。
ただし、それは従来型・工業社会時代のモデルにおけるエクササイズでなく、知識社会・経済の時代の知識産業(製造業の場合、これを「知識製造業」と呼んでいます)のモデルを目指して行わなければならないのです。これは日本企業にとって真にハードルの高いチャレンジです。
デービッド・メイスターについて
ここでデービッド・メイスター(David Maister)本人についてすこし触れておきたいと思います。メイスターは元ハーバード・ビジネススクルール教授で、PSF(Professional Service Firm)を研究、その後独立し、注目され、「PSF経営のグル」と呼ばれた、「コンサルティング企業のコンサルタント(アドバイザー)」として有名です。
PSFとは法律事務所、会計事務所、経営コンサルティング会社、研究開発機関、エンジニアリングサービス、設計事務所あるいはデザイン事務所、医療・健康サービス、政府機関など、顧客との関わりのなかで人間が知識を創造・活用して価値を生み出す知識ベース組織を指します。
これらのファームはかつてはモノづくりをする製造業とは別物と考えられてきたのですが、知識経済・社会の時代になり、製造業が知識化するなかで、メーカーの研究開発、デザイン部門、経営企画部門、さらにはメーカー自体が新たなビジネスモデルを纏ってPSFとして機能すべく求められるようになっています。
PSF経営の知見は現在の日本の製造業(顧客へのソリューションサービスや社会課題起点のイノベーションへと基盤をシフトしつつある)にとっても有意義です。そのメイスターの打ち出した概念がダイナモ(人)というわけです。

氏には多くの著書がありますが、関心があれば『脱「でぶスモーカー」の仕事術』で筆者がその要約一覧を紹介しているので参照してください。
変化はなぜむずかしいのか
メイスターは企業がなすべき変化はダイエットのようなものだといいます。これは各所で紹介している(イノベーションとダイエットには共通点がある)のですが、ダイエットではエクササイズ・マニュアルからダイエット日記帳、ダイエット研究書、成功事例集まで、ありとあらゆる書物や情報があるけれどなかなか思うようにはいかない。多少カイゼンするけれども、自分が思い描くようなスタイル、理想的な健康状態まではほど遠い。
たとえばイノベーションを取り巻く状況も同じように見えます。「イノべーション」というタイトルのついた従来型ワークショップのマニュアル(エクササイズ・マニュアル) 、海外からの紹介本、成功事例集(後づけの美しいストーリー) 、実は中味は昔ながらの戦略本、マンガ風の概説書など、ありとあらゆる書物や情報があふれています。もちろんこれらはすべて有用だし素晴らしい作品もあります。
しかし、そもそも人間は本来やるべきことをどんどん後回しにしてしまうのです。「言い訳」はいろいろあります。この現象が起きるのは、短期の成果が見えにくい努力(イノベーションの試行錯誤を苦行とするなら)に対して、目の前の快楽(利益)がトレードオフで勝ってしまう、という人間の性(さが)ゆえです。ですから言葉で変化を訴えても、自分も周囲も動かないのです(実はイノベーション活動を快楽と、現業を苦行と考える社員もいるのですが)。
ダイナモ人
結局、経営者が新たな方針や戦略を出しても、組織の個々人の心が動かなければ無意味とさえ言っていいのです。これはあまりにも常識ですが、現実はこの無意味なことが多くの企業で毎年、毎四半期、日々繰り返されている。そこでダイナモ人が鍵になるのです。
すでに述べてきたように、ダイナモ人は新人類でもスーパーマンでもありません。基本的には知識社会・経済のナレッジワーカー、ナレッジ・ピープルとして生きている人たちで、彼ら彼女らはその内なる能力・知識・意識を、そのような場において顕在化(出現)しようとするのです。でもその可能性が既存組織によって潰されてしまっていることが多いのです。
ドラッカーをすでに引きましたが、ナレッジワーカーの仕事の生産性を高めるには、ナレッジワーカー自身が自律性をもって生きることが条件だと指摘されています。そこでは伝統的な官僚制的ヒエラルキーが最も大きな制約となるでしょう。いかにダイナモ人を活かせるかは組織の場づくりによっているのです。
まず目的から始める
最近、経営における目的の重要性について、だいぶ理解が広がりました。すでに『脱「でぶスモーカー」の仕事術』では、「変化はまず目的から始めよ」としています。それは単に「目的経営」を標榜することではないのです。
宣言された目的が組織のよりよい業績に寄与するかどうかは、その、目的を市場が信じるかどうかで決まるのではない。むしろ重要なのは、その目的やミッションにもとづいてすべての決定がなされていると、組織のなかの人々が本当に信じているかどうかだ。
目的やミッションが本物であると彼らが信じて初めて、すぐれた結果を生むより多くのエネルギー、コミットメント、協力、献身、長期的思考を引き出すことができるのだ。
そして、実際に機能する目的を定め実行するには、その目的追求に力を貸そうという従業員だけを集めなければならないといいます。
KCPCが知識創造プリンシプルという新しい時代のプリンシプルを提言するのも、ここに通じます。そして、そのプリンシプルがダイナモ人、ダイナモ組織のコンセプトに繋がっていることはいうまでもありません。「どれだけうまくできるかではなく、どれだけやりたいか」(同書の見出しより)を念頭におくべきなのです。
目的、感情、場
振り返ってみると、メイスターの思想の背後には、アリストテレス的な実践知、つまり賢慮(フロネーシス)が横たわっているといえます。それは優れた人間の知の卓越性のひとつなのですが、いわゆる素晴らしい頭の良さ(エピステーメーやソフィア)や、ものづくりの器用さ(テクネー)のことではありません。
人間が生きる上で本質的な目的(=Purpose 良い目的のもとで実践的判断力に基づいて行動する)、感情(=Passion 信念、パッションを共有する)、そして日常の行動・習慣を支えたり変化させたりする場づくり(=Place 人は日常の小さな行動からしか変化しない)、につながるものです。そして何といっても、変化を捉える視点(=Perspectiveパースペクティブ、新たな観点のこと)。
これら4Pが知識創造プリンシプルの骨格である6つのPの中核を形成している知の結晶体(正四面体)と考えていいでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
