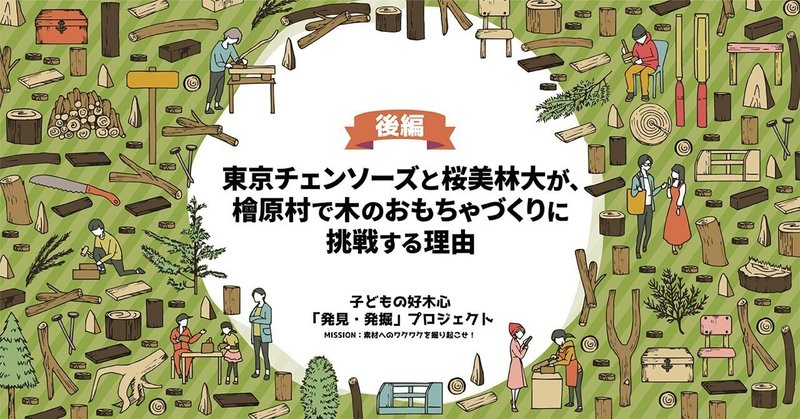
【後編】東京チェンソーズと桜美林大が、檜原村で木のおもちゃづくりに挑戦する理由
東京都檜原村と、同村を拠点に活動する林業会社・東京チェンソーズ、そして桜美林大学芸術文化学群ビジュアル・アーツ専修の林ゼミが連携し、木を素材にしたおもちゃを開発する「子どもの好木心『発見・発掘』プロジェクト」。全14回・半年間の授業のなかで、檜原村の山林を舞台にしたフィールドワークや、幼稚園・保育園でのニーズ調査などのプロセスを経て、木のおもちゃを開発していきます。
前編では、東京チェンソーズの高橋さんと、桜美林大学の林先生それぞれから、今回のプロジェクトが立ち上がった経緯についてお話を伺いました。後編では、木のおもちゃの魅力や、プロジェクト名に込められた思いを紐解いていきます。

木のおもちゃは、最先端のプロダクトであり最高の教材
━━その後、林先生は木のおもちゃのデザインプロセスを体系化し、2022年には『子どもを育む木製玩具のデザイン論』という本を出版されました。林先生の視点から見た木のおもちゃの魅力についても、教えていただけますか?
林:木は天然素材だからこそ、同じ形でも木目が違ったりと、全く同じものは一つとしてありません。だからこそ味わいがあって面白いし、心惹かれるものがあるなと思います。
また、木には生き物ならではの温かみがあり、五感に訴えかけてくるものがあると思いませんか?木と木がぶつかる時の柔らかい音は、耳に心地良く響きますし、木の優しい香りは、何となく癒されるような感じがしますよね。

保護者の方に聞くと、「プラスチックのおもちゃは壊れたら捨てるけれど、木のおもちゃは捨てない」と仰る方が多いんです。それは恐らく、木はデニムや皮革製品と同様に、使えば使うほど味が出る素材だからだと思います。だからこそ、時代を超えて使っていける。そういうプロダクトは、大量生産の工業製品では決して作ることはできませんでした。
━━大量生産・大量消費からの脱却が叫ばれている現代では、木のおもちゃのようなプロダクトが最先端になっていくのかもしれませんね。
林:絶対にそうだと思いますし、プロダクトの多くは人工的なものから人間的なものに変わってくると思います。画一的な大量生産ではなく、もっと人間に寄り添って、1つ1つ違うものがあってもいい。そういうプロダクトを作るデザイナーが増えるといいなと思います。
━━そこで今回、ゼミで木のおもちゃのデザインを題材として扱うことにしたんでしょうか?
林:木のおもちゃのデザインをゼミの授業課題とする主なメリットは、次の3つの事柄を、理論と実践の両方から学べることです。特に②は、ゼミとしての重要なテーマになっています。
①国産材の利活用などの社会課題を理解し、デザインで解決策を見出す
②人間中心のデザイン方法論を理解し実践する
③産学連携によりデザイン実践力を養う
学生にプロダクトデザインの提案をさせると、ほとんどの学生は自分自身を中心にして、欲しいものをデザインする傾向にあります。その問題に対し、子どものためのおもちゃのデザインを課題とすることで、ユーザー中心の発想を学んでもらう狙いがあるんです。
高橋:自分からちょっと遠い存在である子どもに対してものづくりをするには、まずは子どもや保護者の興味関心を実際に調べなくては、という思考になるということですね。

林:その通りです。今の学生は、これまで見たことがない新しいものを考え提案する際、まずインターネットで参考になるものを検索し、それをそっくり真似てアイディアスケッチをする傾向にあるようです。でもデザイナーとして本当に大切なのは、現場で見たり聞いたりしたことを手掛かりに、自分で思考すること。自分の目で課題を発見して、それをもとに様々な発想へ結びつけることが大切なんです。
子どもたちの、素材へのワクワクを掘り起こせ!
━━「子どもの好木心『発見・発掘』プロジェクト」というプロジェクト名の由来についても、教えてください。
高橋:今回のプロジェクトを始めるにあたって、東京チェンソーズが普段ワークショップや林業体験で関わっている幼稚園や保育園の先生方に改めてお話を伺いにいきました。すると、先生方が僕らに求めているのは、ただの木のおもちゃではないと分かったんです。
木のおもちゃ自体は、日本各地の作家さんの作品のほか、海外製でクオリティの高いものもたくさんあります。ただ、きっちり仕上がっている木のおもちゃは、子どもにとっては遊ぶための"道具"でしかない。だから林業会社であるチェンソーズには、もっと自然や木の本質的な良さや魅力を子どもたちに伝え、ワクワクさせることに挑戦してほしいという要望があったんです。

だからこそ、学生さんにも「子どもたちが木という素材に対して、どんな風に興味を持ち、楽しんでくれるのか」を深掘りしてほしいという思いがあり、このようなネーミングにしました。
━━いいおもちゃをつくることだけが目的ではなく、「子どもたちの自然や木に対する好奇心を、どうすれば掻き立てられるか」を探究する取り組みなんですね。
高橋:そのエッセンスを発見できれば、おもちゃづくりに限らず、ワークショップなど様々な形で活用できるはずです。僕たちも答えを持っているわけではないので、みんなで一緒に探っていけたらと思っています。
━━このプロジェクトで完成したおもちゃは、いつ頃手に入るんでしょうか?
高橋:2024年4月頃の発売を目指しています。授業自体は今年の7月末までで、まずは学生全員にプロトタイプを作ってもらいます。その中から選ばれた学生たちと林先生と一緒に、実際に子どもたちに遊んでもらいながらブラッシュアップをする期間を経て、4月までに商品として完成させられればと考えています。
林:学生が作ったおもちゃで子どもが遊ぶって、最高ですよね。
高橋:本当ですよね。どんなおもちゃが生まれるのか、僕も楽しみです!

このnoteでは、学生たちがおもちゃをデザインするプロセスを、学生たち自身に発信していってもらう予定です。ぜひ引き続き情報をチェックしていただき、おもちゃが出来上がっていくプロセスを一緒に楽しんでもらえたらと思います。
「プロジェクトの見学がしたい」「完成したおもちゃを使ってみたい」など、ご興味をお持ち下さった方は、東京チェンソーズのプロジェクト担当、高橋さんまでご連絡ください!
執筆・編集/高野優海(ライター・檜原村地域おこし協力隊)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
