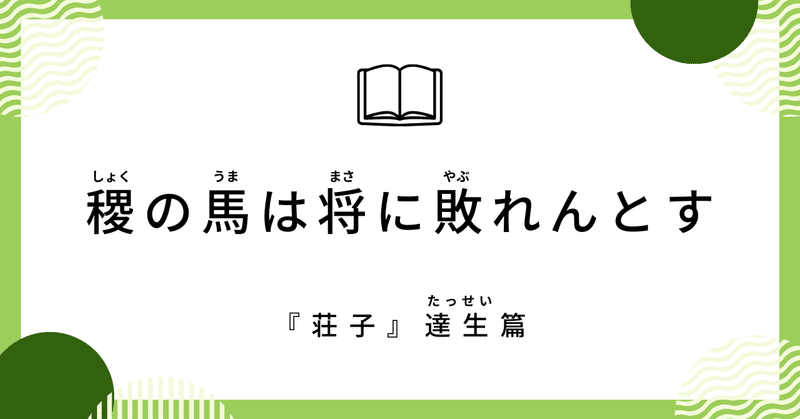
期待を背負ったときこそ、自然体でいることを意識する(『荘子』達生篇)
今回取り上げるのは『荘子』達生篇からの言葉。
稷の馬は将に敗れんとす。
(読み:ショクのウマはマサにヤブれんとす)
稷が走らせている馬は、(力を使い果たしているので)おそらく死んでしまうだろう、という意味。
つまり、限界を超えて無理をしたりせず、いつでも自然体で取り組みなさい、ということですね。
今回の言葉をよく理解するために、『荘子』のエピソードをご紹介しましょう。
むかしむかし、あるところに東野稷(とうやしょく)という乗馬の名人がいました。
彼は自慢の乗馬技術を披露しようと、衛国の君主である荘公に会いに行きます。
お目通りが叶うと、東野稷は自身の乗馬技術を披露し始めました。
前に進むも、後ろに進むも、まさに自由自在。
左に回っても、右に回っても、まるでコンパスで描いたかのように正確な乗馬技術です。
関心した荘公は、東野稷に次のように命令します。
「お前の乗馬技術は実に素晴らしい。どれ、試しに周囲を100周してみてくれないか」
荘公からの直々のお言葉に興奮した東野稷は、意気揚々と周囲を走りに行きます。
このとき、東野稷と入れ替わるように、荘公の重臣である顔闔(がんこう)が入ってきました。
顔闔は東野稷を一瞥すると、荘公に告げます。
「東野稷の馬はおそらく死んでしまうでしょう」
はたして顔闔の予言どおり、東野稷の馬は途中で死んでしまいました。
荘公は尋ねます。
「どうして東野稷の馬が死んでしまうと分かったのだ?」
顔闔は答えて言いました。
「馬の力はとうに尽きていました。それにもかかわらず、東野稷は限界を超えて馬を走らせようとしていたからです」
というお話。
悲しいことに、東野稷の馬は、限界を超えて無理をさせられたために死んでしまいました。
荘子はこのエピソードを踏まえて、「力まず、無理をせず、何事も自然体で取り組む」ことが大切だと主張しているのです。
誰かに褒められたり、期待されたりするのは、とてもありがたいことです。
私自身も、誰かに期待をされるととても嬉しくなります。
そして、何とかしてその期待に応えようと頑張ってしまいがちです。
しかし、その頑張りが時には自分自身を苦しめてしまうことがあります。
誰かの期待に応えるため、疲れているのに体に鞭打って働いたり、自分の気持ちに蓋をして頑張ったり。
周囲の期待に対して必要以上に重荷に感じてしまって、心身を疲弊させてしまうのです。
期待に応えようと頑張るのはモチベーション向上の面では良いことですが、それに対して必要以上に責任を感じる必要はありません。
過度な緊張は心身の毒になります。
東野稷も、荘公の期待に応えようと懸命になりすぎたために、自身の馬の限界を見誤ってしまいました。
荘子が説くように、「力まず、無理をせず、何事も自然体で取り組む」ことを忘れずにいたならば、東野稷の馬も無事に走り切ることができたことでしょう。
期待されているからこそ、重要な場面だからこそ、いつもと同じく平常心で取り組むことが大切なのです。
現代でも、プロスポーツ選手などは試合前にいつも同じ動作(ルーティン)をしています。
だからこそ、重要になってくるのがルーティーンだろう。サッカーに限らずスポーツ選手の多くはルーティーンを持っていると言われる。本番前に同じ行動をとって心を整えることが、100パーセントのパフォーマンスを出すうえで重要だと知っているからだ。
野球のイチロー選手が打席入り前に行うルーティンは有名ですが、サッカー選手も色々なルーティンを持っているんですね。
この記事を書きながら、プロスポーツ選手の事例を調べている際に初めて知りました。
最近はサッカーも見るようになったので、今度確認してみようと思います。
皆様もぜひ、自然体で取り組むためのルーティンを探してみてください。
稷の馬は将に敗れんとす。
(読み:ショクのウマはマサにヤブれんとす)
今回は、限界を超えて無理をしたりせず、いつでも自然体で取り組みなさい、というお話をご紹介しました。
周囲の期待を意識しすぎると、期待に応えようと頑張りすぎてしまうかもしれません。
しかし、限界を超えて頑張るのは心身に良くありません。
過度なストレスは自身のパフォーマンスも低下させます。
何より大事なのは、常に自然体でいることです。
「力まず、無理をせず、何事も自然体で取り組む」ということ。
自分の力を存分に発揮するためにも、自然体で取り組むためのルーティンを取り入れていきたいですね。
古典を楽しみたい方には、Kindle UnlimitedやAudibleもおすすめです。
『論語』をはじめとする、さまざまな書籍を読むことができます。
先日にはAudibleに『老子』も追加されました!
もっと手軽に古典に触れてみたい方にはメンバーシップもありますので、色々な場面で古典を身近に感じていただけると嬉しいです。
サポートをいただけますと励みになります!いただいたサポートは資料の購入や執筆環境の整備などに使わせていただきます!より良い記事をお届けできるように頑張ります!
