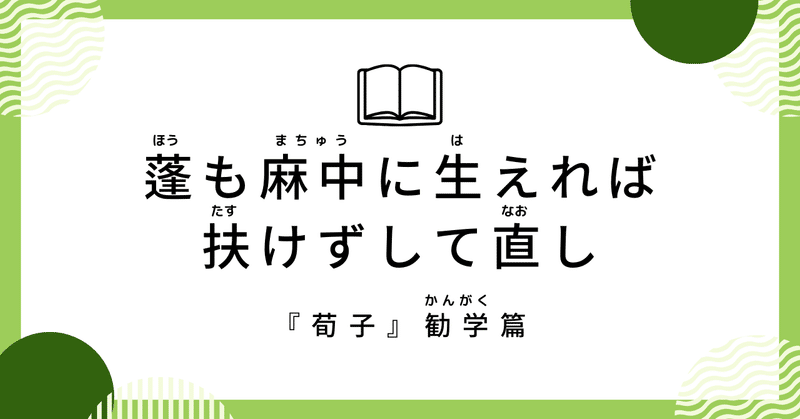
より良い学びの機会は、より良い読書環境から始まる(『荀子』勧学篇)
今回取り上げるのは『荀子』勧学篇からの言葉。
蓬も麻中に生えれば、扶けずして直し
(読み:ホウもマチュウにハえれば、タスけずしてナオし)
地面に広がって生えるヨモギも、真っ直ぐに伸びる麻の中で育てば、何もしなくてもまっすぐに伸びるものだ、という意味。
周囲の環境の大切さを語った言葉です。
つまり、良い環境にいれば、人は自然と正しい方向に進むものだ、ということですね。
「麻の中の蓬」という言葉でご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
鎌倉時代の説話集である『十訓抄(じっきんしょう)』にも同様の言葉があります。
人者善友にあはむ事をこひねがふべき也。
麻のなかの蓬はためざるにおのづから直しといふたとへあり。
人は皆、善人に出会うことを願うべきだ。
「麻のなかに生える蓬は自然とまっすぐに育つ」という例えもあるのだから、という意味。
つまり、善人と交流することで良い影響を受け、自然と自分自身も善人になることができる、ということですね。
明らかに『荀子』の言葉を意識していることが分かります。
鎌倉時代の知識人たちの中でも、中国古典はある種の教養として、当たり前のように認知されていたのでしょう。
中国古典から日本の歴史につながり、それが現代にも伝わっていることを考えると、なんだがワクワクしてきます。
そして、実はこの言葉には続きがあるのです。
良い環境にいれば良い影響を受ける、ということは、その反対もありえるということ。
荀子は以下のように続けます。
白沙も涅にあらば、これとともに黒し
(ハクサもドロにあらば、これとともにクロし)
白く美しい砂も、泥の中に混ざってしまうと一緒に黒くなってしまう、という意味。
悪い環境にいると自身も悪影響を受け、いつのまにか周囲に染まってしまう、ということですね。
これらを踏まえて、文章全体としては以下のような主張になります。
物事は周囲の環境によって影響を受け、そのあり方を変えてしまう。
人もまた同じであり、自ら良い環境を選んでいかなければならない。
努力と教育を重んじた荀子らしい主張だと思います。
人は周囲の環境に染まる生き物なのだと気づいていたんですね。
これは私も「その通りだなぁ」と思います。
私の今の職場はビジネス書を読む方が多いため、自然とビジネス書の話が耳に入ってきます。
私はもともと古典や歴史がメインだったので、前職まではあまりビジネス書を読んできませんでした。
頭のどこかで「ビジネス書よりも古典を読んだ方が勉強になるよね」と思って、若干ビジネス書を敬遠していたのだと思います。
しかし、気がつけば私もいつのまにかビジネス書を読むようになっていました。
完全に周囲の影響ですね。
嬉しい誤算だったのは、いざ読んでみると良い意味で期待を裏切る良書がたくさんあったことです。
最新の研究結果に基づいた科学的な話だったり、日常で役立つ考え方やテクニックだったり。
私が古典や歴史で培ってきた部分を補強してくれて、かつ視野を広げてくれたので、ビジネス書を読むようになってとても良かったと思います。
中には微妙な本もありましたが、そこは人によって合う合わないがあったり、そのときの状況や背景知識の量によって感じ方が異なったりすると思うので、とにかく気軽に色々と手に取って見るのがおすすめです。
私はどちらかというと紙の本の方が「読んでる感」があって好きなのですが、移動中などにも気軽に読むために、電子書籍やオーディオブックも愛用しています。
Amazonの読み放題や聴き放題だと、気になった本を色々つまみ食いできるので便利です。
Kindle Unlimitedはここ一年ほどで中国古典関連の本が色々と増えてきたので、私も隙間時間に利用しています。
Audibleの方は移動中や寝る前に聞き流すことが多いです。
ながら作業をしながら読書ができるようになるので、結果的に本に触れる時間が大幅に増えました。
司馬遼太郎さんの本もいくつか聴き放題の対象に入っているのが嬉しいですね。
三国志に出てくる武将も、字が読めない人は友人に読み上げてもらって内容を覚えたといいます。
そう考えると、オーディオブックの原型は遥か昔からあって、学習方法として割と合理的なのかも、と思いました。
蓬も麻中に生えれば、扶けずして直し
(読み:ホウもマチュウにハえれば、タスけずしてナオし)
人は周囲の環境の影響を受ける、というお話をご紹介しました。
「環境が人を作る」とも言いますし、孟母三遷のように周囲の環境を変えるのも大事なことだと思います。
とはいえ、いきなり周囲の環境をガラッと変えるのはなかなか難しいと思いますので、まずは身の回りの読書環境から整えていくのが個人的にはおすすめです。
読書習慣のない方は、まずは軽めのビジネス書を読んだり、聞いてみたりするのが良いでしょう。
そして、いつか中国古典も手に取っていただけると嬉しいです。
サポートをいただけますと励みになります!いただいたサポートは資料の購入や執筆環境の整備などに使わせていただきます!より良い記事をお届けできるように頑張ります!
