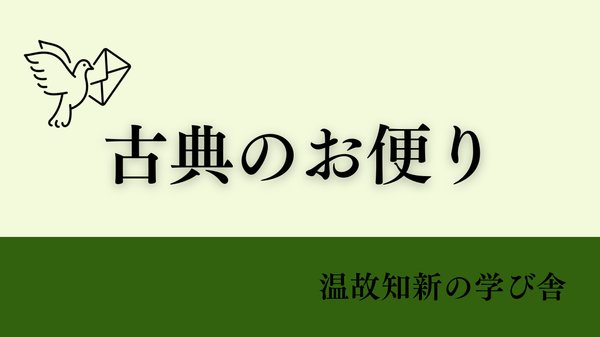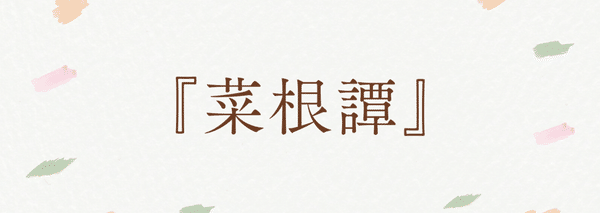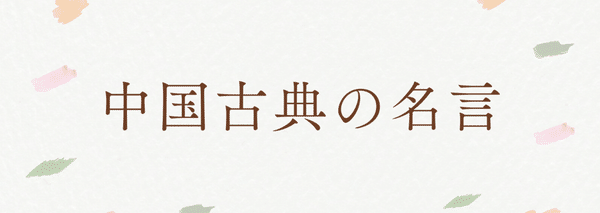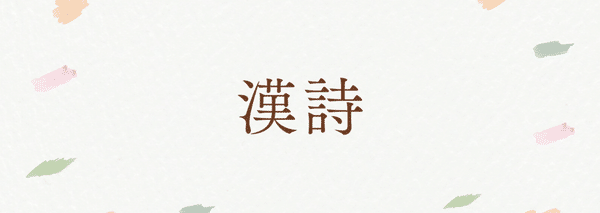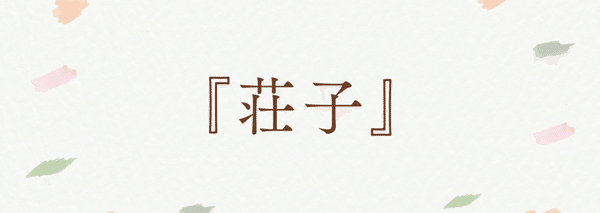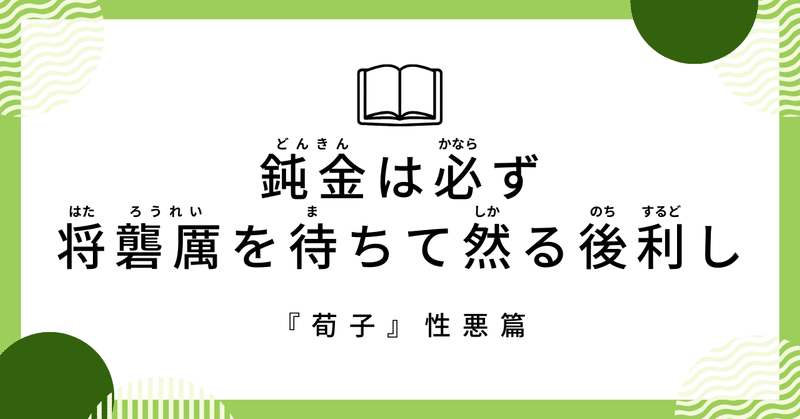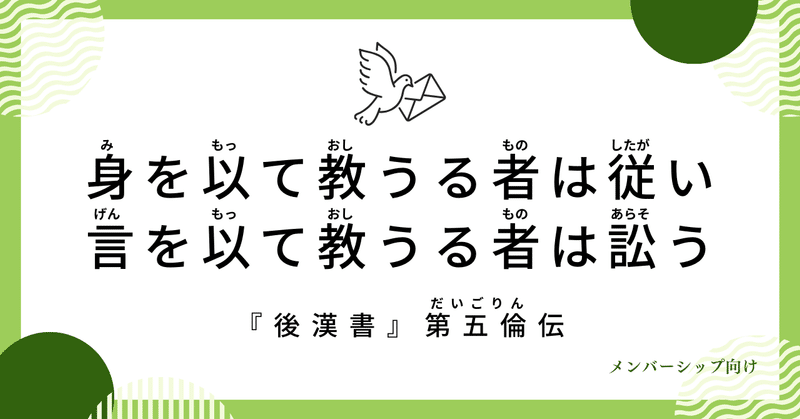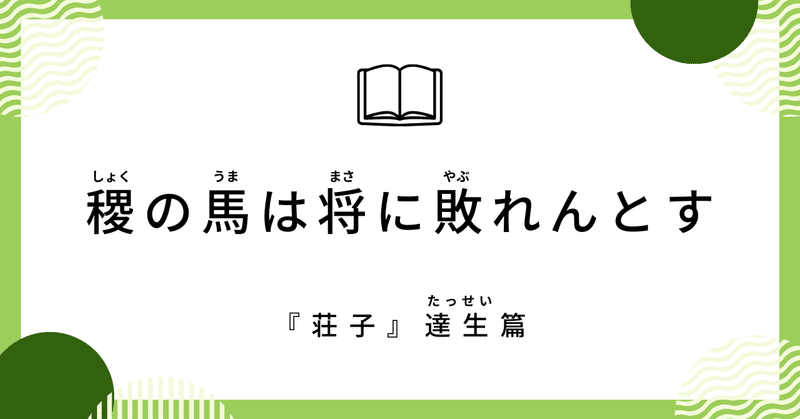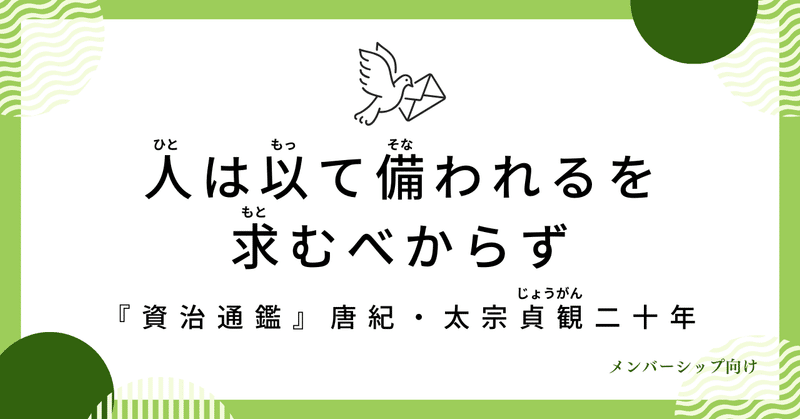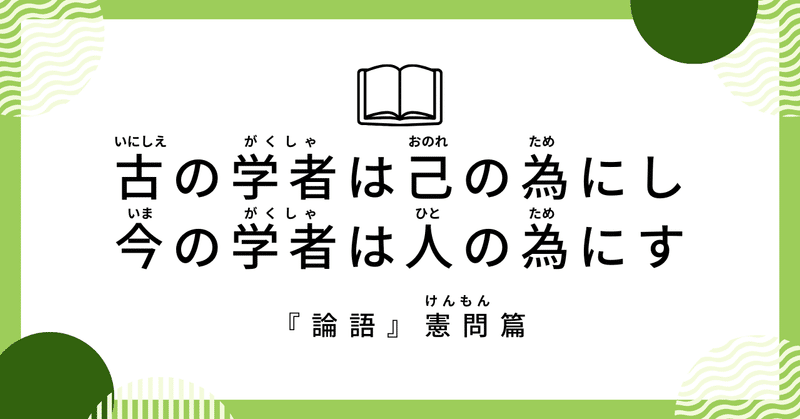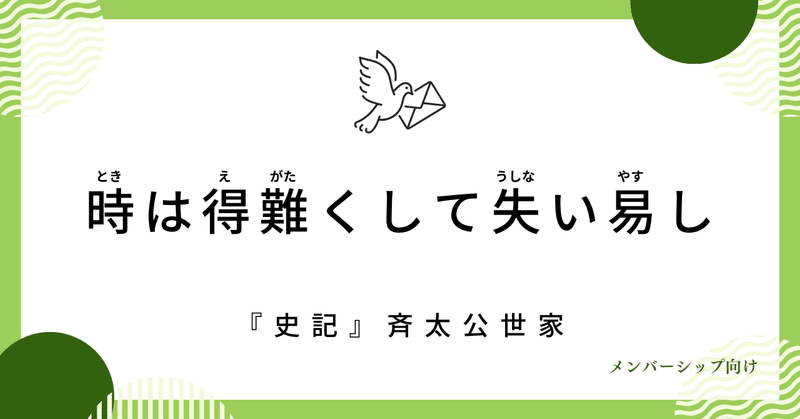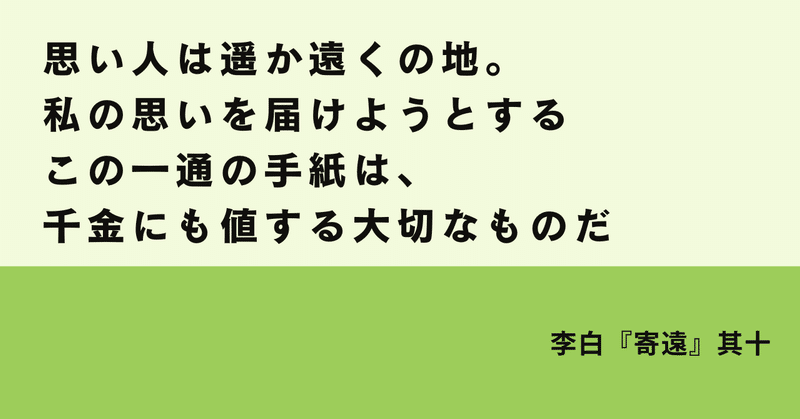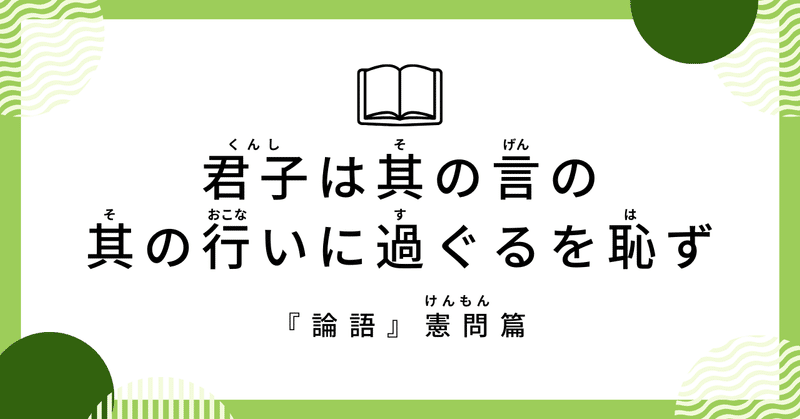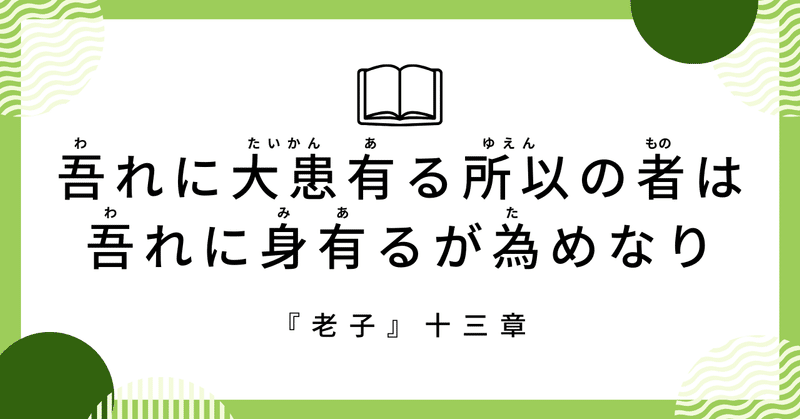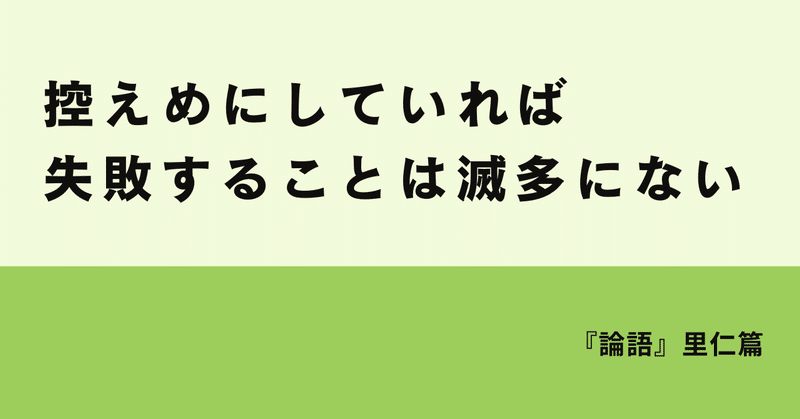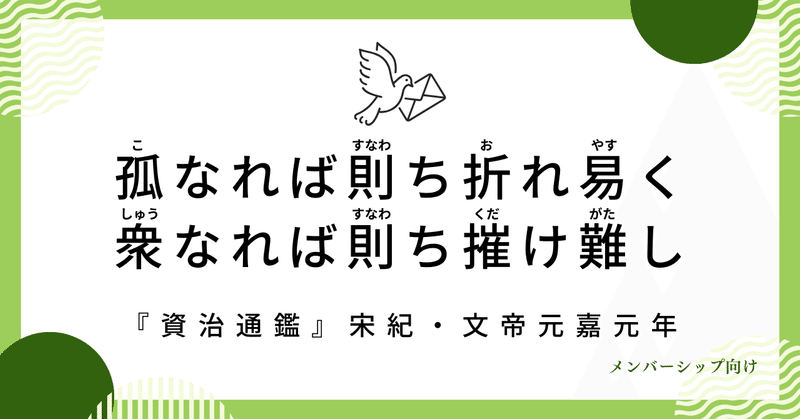記事一覧

皆様いかがお過ごしでしょうか?
今日は特別展のお知らせです📢
記事はGW明けに再開しますね😊
あべのハルカス美術館では「尾張徳川家の至宝」が開催中です。
三代将軍家光の長女の嫁入り道具をはじめ、複数の国宝も展示されています🍀
https://www.aham.jp/exhibition/future/ieyasu/
固定された記事