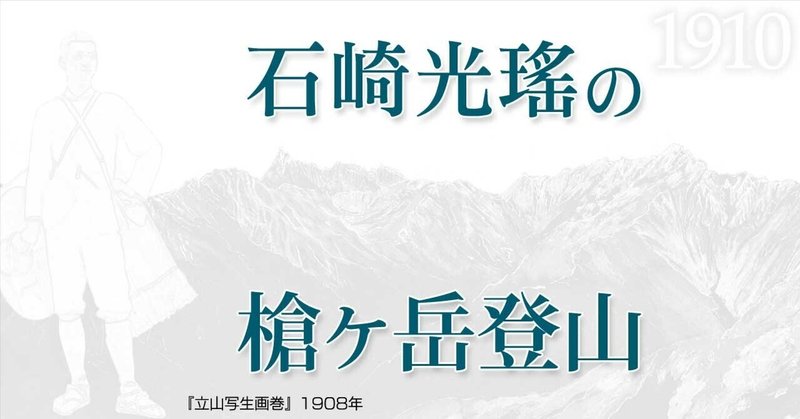
第5章 日程推定と写真分析
光瑤の「日本中央アルプス跋渉」は、『高岡新報』明治43年8月5日から9月11日まで連載された。
文章は計27回約35000字、写真のみを含めると計32日分である。署名は「特派員 石光生」。「特派」であるから高岡新報社が経費のいくらかを負担したのであろう。
この記事には、行動の具体的な日付が記されていない。読み解いていくと、明治43年7月28日か29日ごろに立山温泉を出て針ノ木峠を越えて大町に出て、その後、徳本峠越えで上高地に至り、槍ヶ岳登頂して上高地に戻る14日間または13日間であったとみられる。
推定の理由は、8月11日に掲載された囲み記事「石光生の葉書便」である。8月4日付差し出したはがきで、辻村伊助・三枝威之介・中村清太郎・河田黙と出会ったことが記されている。『山岳』第5年第3号の会員登山報によれば、三枝と中村が上高地に着いたの8月3日である。5日には辻村・三枝・中村が霞沢岳に向かっている。とすれば、光瑤が出会ったのは3日か4日とみられる。光瑤が上高地に着いたのは第7日なのでそこから逆算すると、7月29日か30日ごろの出発となる。
※『山岳』「三枝威之介中村清太郎氏は三十一日黒部五郎岳に登り蓮華岳に達し同山頂に一泊、八月一日風雨の為滞在、二日雨中を双六岳を経て鎌尾根を南走し槍ヶ岳を越えて坊主小屋下に野営、三日上高地に出で、越えて五日辻村氏と共に霞澤岳を極められたり」
また、9月11日付の最終回末尾に、下山した翌日の豪雨で、松本から上高地に届いた新聞に、豪雨の惨状が書かれていたとある。明治44年の長野県の水害は8月10日ないし11日と記録されている。また東海道の水害は8月9日ないし10日である。その新聞が8月11日付だったとすれば、上高地に届いたのが12日か13日。光瑤の槍ヶ岳登頂は8月11日か12日となる。
※気象庁の過去のデータでは、松本市で一日降水量は8月9日26.7mm、10日62.6mm、11日11.0mm、12日は欠測し、13日25.6mm、14日29.8mmである。高山市では10日104.6mm、11日12日はあまり降らず13日29.6mm14日26.1mmである。富山県伏木では10日に50.9mm、11日23.6mm、12日はあまり降らず13日12.2mmを記録している。『高岡新報』明治43年8月19日3面によると、8月18日夕現在の内務省調べで大雨被害は1府17県で死者計1048人、行方不明者383人、全壊家屋1369戸、半壊2615戸、家屋流失3850戸。浸水家屋は44万3209戸、堤防決壊1922か所であったという。
連載がスタートした8月5日に、光瑤は上高地にいたのだから、連載前半の記事の出稿をある程度済ませておかないと、連載はできない。行路のなかで最も郵便事情が良いのは松本か大町かである。そこを通過したのは8月2日か3日と推定される。そしてその8月2日か3日の記事は8月22日か23日に紙面掲載されている。つまり8月22日か23日より前に、富山(高岡)に帰って来ていれば、連載は滞りないわけである。
連載記事を読むと上高地滞在は7日間または8日間の記述で終わっている。連載記事の後にも滞在した可能性はある。一方、撮影した写真を現像して新聞紙面に載せるまでには相当の時間を要する。連載前半の写真は事前に準備されていたもので、上高地以降の写真は帰ってから現像したものと見るのが妥当であろう。
また、福光美術館には、7月25日の消印で高岡市の光瑤あてに出されたはがきが所蔵されている。差出人は佐野彦四郎。槍ヶ岳登山を励ます内容であるとみられる。
実撮影は13枚のうち7点か
連載「日本中央アルプス跋渉」には、13枚の写真が掲載されている。このうち明治43年に光瑤が撮影したものは7点とみられる。4点は明治41年の撮影、1点が他雑誌からの転載である。残り1点は不明だ。当時は撮影から現像、製版まで相当の時間を要するから、旅の前半は既に撮影済みの写真を使い、後半は実際の旅で撮影したものと推測される。
いちばんの謎は8月22日付の「徳本峠より見たる穂高の一角と梓川の上流」である。記事本文では、徳本峠は濃霧で「無情なる雨伯は我に此壮観を免さなかった」とあるので、この写真と不整合を生じている。他日、他人の撮影した写真か絵である可能性が高く、今のところ特定できていない。
では27日以降の河童橋の写真2枚はどうかという疑問も生じるが、「雨後」とあるので記事本文とは矛盾を生じない。「河童橋より望見せる雨後の穂高山」は不鮮明な図版ながら傑作のように見え、原版を見てみたくなる。
石崎光瑤「日本中央アルプス」写真一覧(明治43年)
(2)8月6日付 【写真】立山より見たる槍ヶ岳 ○ 明治41年撮影か。『万山@@』に同じ写真あり。
(7)8月11日付 【写真】立山佐良佐良越 ○ 明治41年撮影か。『山岳』@年@号に同じ写真あり。
(9)8月13日付 【写真】浄土谷国有林より見たる立山半面 明治41年撮影か
(10)8月15日付 【写真】針の木嶺の一部 明治41年撮影か。マヤクボか。
(11)8月16日付 【写真】英国山岳雑誌所載 ×
(20)8月22日付 【写真】徳本峠より見たる穂高の一角と梓川の上流 ?
(21)8月27日付 【写真】梓川に架せる河童橋 明治43年撮影か
(24)8月30日付 【写真】河童橋より望見せる雨後の穂高山 明治43年撮影か
(25)8月31日付 【写真】上高地の放馬 明治43年撮影か
(26)9月1日付 【写真】田代池畔の牛 明治43年撮影か
(27)9月2日付 【写真】田代池の一部 明治43年撮影か
(28)9月3日付 【写真】田代池の一部 明治43年撮影か
(29)9月4日付 【写真】中尾峠(焼岳噴火の惨害) 明治43年撮影か。同日「焦林」を撮影
1910年7月29日か30日出発 8月10日か12日終と推定
※( )は推定日
A推定〈連載日を重視〉
第1日(7/29)立山温泉~黒部平
第2日(7/30)黒部平
第3日(7/31)平~籠の渡し~針ノ木谷
第4日(8/1)籠川(扇沢か)~大町(対山館)
第5日(8/2)大町~島々
第6日(8/3)島々~徳本峠
第7日(8/4) 徳本峠~上高地 峠越えて雨で穂高は見えず。
第8日(8/5) 上高地温泉滞留
第9日(8/6) 午前10時頃雨止み田代池で撮影
第10日(8/7) 焼岳
第11日(8/8) 上高地温泉滞留
第12日(8/9) 雨、坊主岩小屋に泊
第13日(8/10) 槍ヶ岳登頂し下山 強い雨
第14日(8/11) 上高地温泉 松本から豪雨惨状を報じる新聞
B推定〈修正解釈〉
第1日(7/30)立山温泉~黒部平
第2日(7/31)黒部平
第3日(8/1)平~籠の渡し~針ノ木谷
第4日(8/2)籠川(扇沢か)~大町(対山館)
第5日(8/3)大町~島々
第6日(8/4)島々~徳本峠~上高地 峠越えて雨で穂高は見えず。午後4時半着。はがき書く?
第7日(8/5)上高地温泉滞留 午前10時頃雨止み田代池へ
第8日(8/6) 焼岳
第9日(8/7) 上高地温泉滞留
第10日(8/8) 雨、坊主岩小屋に泊
第11日(8/9) 槍ヶ岳登頂し下山 強い雨
第12日(8/10) 上高地温泉 松本から豪雨惨状を報じる新聞
連載「日本中央アルプス跋渉」見出し写真一覧
(1)8月5日付 発端
(2)8月6日付 発端
一、立山より望みたる山岳の位置/一、槍ヶ岳の雄姿と標高/一、越中人士の採るべき行路 【写真】立山より見たる槍ヶ岳
(3)8月7日付 第一日(富山~立山温泉)/第二日(立山温泉~平)/獰猛な磧の中央/池一面に湯気/岩桔梗や兎菊
(4)8月8日付 先年此処を通過/御花畑の称も調和/冬が四分の三強/追々分水嶺が近く/日本海から吹送る
(5)8月9日付 天正の昔/白檜の蓊鬱/急に黒部谷/巌白く水黒き/人跡不到の地/鍋に代ふる
(6)8月10日付 日は暮たが二人共/第三日は朝三時/籠の渡し/アワヤ銀湍雪渦/針の木行路へ一歩
(7)8月11日付 一里も分行った/宛然大海嘯の後/先に見たる大惨劇/或は倒れ或は流失/昨年奈良岳で踪跡/石光生の葉書便(4日上高地)/【写真】立山佐良佐良越
(8)8月12日付 前方の断崖の上/熊の踏むだ跡/板を立てた様な/愈々心を決して
(9)8月13日付 此時の感懐/鶴翼の陣/第三紀の終/高山植物/【写真】浄土谷国有林より見たる立山半面
(10)8月15日付 【写真】針の木嶺の一部
(11)8月16日付 【写真】英国山岳雑誌所載
(12)8月17日付 人に逢はぬ二日間/胸中不安の念/白髑髏と同じ運命/其白い雲の中から[午後1時に針ノ木岳登頂か]
(13)8月18日付 懐しい立山連峰/八面玲瓏たる富嶽/真摯な自然愛賞家/瓦落瓦落の花崗片[針ノ木峠]
(14)8月19日付 越中方面の雪/漸く雪渓の上部/幾條の懸瀑/雪渓の尽くる処[長野県に入る]
(15)8月20日付 磊々たる巨岩の上/重き大石も本流/峰の雪も凍結/夫れこそ悲惨な運命
(16)8月21日付 高瀬川右手の磧/火勢熾にして天も/何処迄もS字形/一人一日の草鞋[~宿泊 5時40分出発~]
(17)8月22日付 第四日は高瀬川=大町 何時迄も磧の通行/千紫万紅の可憐/優美な平安朝時代[~10時野口~正午過ぎ大町對山館]【写真】徳本峠より見たる穂高の一角と梓川の上流
(18)8月23日付 第五日(大町=明科=松本=嶋々) 此間景色は平凡/昔此橋場と嶋々/断崖に美事な橋
(19)8月25日付 第六日 嶋々より徳合峠に至る 小村嶋々に宿舎/明れば第六日目/美しい橋が無数に/山苺は珊瑚の如く/甘中酸味を含み
(20)8月26日付 第七日(白壁の瀧…… 植物の保護) 数多き橋を送り/広き胸を張り/金范緑葉の巴草/神聖なる処女/冷酷な濫採家/槖駝師の仕業
(21)8月27日付 第二日目(徳本峠……上高地温泉) 此処より路は/峠の方に人音が聞え/濛々たる濃霧/宮川池が明鏡/衣の襞の美妙な/峠沢橋と落合橋【写真】梓川に架せる河童橋
(22)8月28日付 第八日(槍岳登山見合わせ=上高地帯留)/六十幾里の長程を/西に穂高の連峰/越中街道たりし/梁には蛇の抜け殻/白馬会の洋画家
(23)8月29日付 第九日=田代池行=クラシックな物語 十時頃に雨も/岳蕗が惇黄色の/穂高見命の後/山岳文学の泰斗/姫は父を失ひ/冷艶雪の顔して
(24)8月30日付 第九日=田代池行=クラシックな物語 小梨の森を大分/一行中の一人/続いて二頭三頭/一番槍否一番玉/茶褐色の無地/種牛の獰悪狂暴/【写真】河童橋より望見せる雨後の穂高山
(25)8月31日付 【写真】上高地の放馬
(26)9月1日付 【写真】田代池畔の牛
(27)9月2日付 第十日=幽趣に富める田代池 太古以来/水は樹よりも緑/彼処に二群/上高地を評価/【写真】田代池の一部
(28)9月3日付 第十日=活火山焼岳登攀=(標高八千百八十七尺) 朝七時支度/血汐を塗抹/前雲去れば後雲/大噴火の惨害/【写真】田代池の一部
(29)9月4日付 【写真】中尾峠(焼岳噴火の惨害)
(30)9月5日付 第十日=焼岳の噴火口= 山一面の噴煙/一旦此火山が破裂/空間に大なる波動/呼吸器へは竹串/新噴火口の直径/老猟師上條嘉門治/外堅の上に立ち
(31)9月6日付 第十一日=雨又到る=登岳中止=有名なる導者 雨の温泉宿/有名な三人導者/無双の精通家/唯一の好案内者
(32)9月9日付 第十二日=雨を冒して槍岳へ強行=坊主小屋 頂山の石室/時鳥が朝靄の裡/有毒菌は猛烈/山も谷も白い/木が将棋倒し
(32)9月10日付 第十三日 咫尺を弁ぜざる槍ヶ岳の絶巓 降雨益々猛烈/石室の裡には/此坊主小屋/槍の峰頭に立
(32)9月11日付 第十四日目は稀有の豪雨 何等の恨事/此時の感懐/鷲の如くに下り/翌日も又凄じい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
