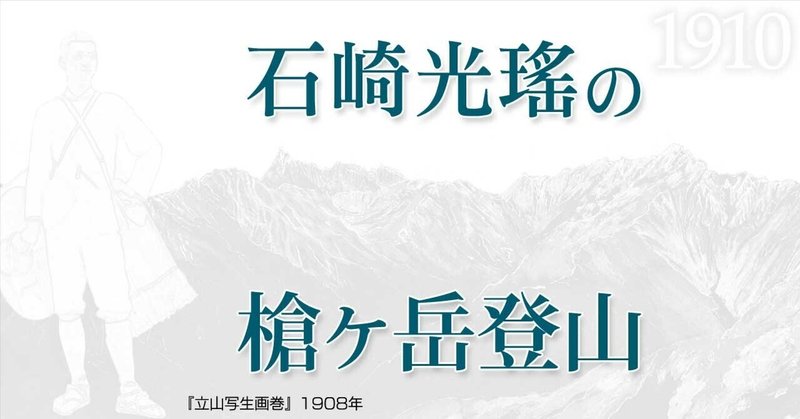
序章 概説
はじめに ―「掉尾を飾る」山旅

日本画家の石崎光瑤といえば登山家として知られた人だ。明治42年夏、剱岳に登山家として初登頂し、その時撮影した写真は近代登山史を語る上で重要な1枚となっている。光瑤イコール剱岳であるわけだが、その光瑤が槍ヶ岳に登っていた事実は意外なほど知られていない。
生誕140周年の2024年春、出身地の富山県南砺市福光で開かれたプレ記念展(横顔展)を観覧した時、《信州槍岳之図》を見つけて思わずうなってしまった。やはり描いていたのか……、そりゃそうだ、人生を転換するほどの登山だったのだから。

左は部分 福光美術館蔵
光瑤は明治39年、神戸・京都から郷里富山に戻った。再び上洛するまでの約5年間、登山に打ち込んだ。それは「登山熱中の5年」と言ってよい。日本山岳会の機関誌『山岳』に多数の写真や紀行文が載っている。しかし、5年の掉尾を飾る槍ヶ岳登山についてはわずか2行の記述があるだけだ。
あの世の光瑤は言うだろう。「掉尾を飾る」じゃない、「掉尾の勇」と言ってくれ、と。
この稿では、光瑤自身が地元紙『高岡新報』に寄稿した連載記事「日本中央アルプス跋渉」からその山旅を詳しく読み解いていきたい。

4つの先行研究
はじめに光瑤と山岳に関した先行研究を挙げておこう。
『山の写真と写真家たち』(1985年)
元新聞記者で『岳人』編集長でもあった杉本誠氏の『山の写真と写真家たち』(1985年)は山岳写真史をまとめた基本資料である。杉本氏は1960年代の『岳人』で「日本山岳写真史ノート」を連載し、その後の研究成果も含めてこの本に集大成した。光瑤を、「草創期」2人(河野齢蔵・高野鷹蔵)に続く「開拓期」3人(三枝威之介・辻本満丸・石崎)の一人と位置付けている。杉本氏によれば、日本山岳会編の写真集『高山深谷』第1~8集(明治43年~大正6年)に収録された写真は計96枚、このうち光瑤の写真は11枚で、辻村伊助38枚、高野鷹蔵15枚に次いで3番目に多いという。[1]『山の写真と写真家たち』には、《渓》と《劍岳の絶巓(遠景は白馬連峰)》の2枚が収録されている。
『絢爛の花鳥画 石崎光瑤』(1995年)
次いで、郷土史家の八尾正治氏による『絢爛の花鳥画 石崎光瑤』(1995年)がある。1980年代からまとめられたもので、その後の光瑤展図録の年譜はしばらく八尾氏の研究成果に依拠していた。山岳関係は『山岳』をもとに論述している。
「花鳥画家、石崎光瑤がみた山」(2003年)
比較的新しい論考として、富山県立山博物館の学芸員だった吉井亮一氏の「花鳥画家、石崎光瑤がみた山」『らくてぃぶ』14号(2003年10月)がある。同館は1998年に「山を撮る」展を、2000年に開館10周年記念の「石崎光瑤の山」展を開催し、これに関連して光瑤の幻の書『印度窟院精華』を復刻するという極めて重要な仕事に取り組んだ。[2]ただ2000年の企画展ではインド・ヒマラヤに傾斜する一方で、国内の光瑤の登山については整理が進まなかった感がある。
「早期岳人の消息-石崎光瑤あての絵葉書発見-」(2009年)
そして忘れてはならないのが松村寿氏の研究である。松村氏は富山日報の記事を発掘して1960年代の『山書研究』で「剣岳先踏前後」を数回連載した。これは新田次郎に小説『点の記』の題材を提供することにもなった先駆的研究である。そして2009年、福光美術館の求めに応じて光瑤宛の絵葉書を解読して「早期岳人の消息-石崎光瑤あての絵葉書発見-」を発表している。
『山岳』にわずか2行
以上の先行研究は、いずれも『山岳』を基本していて、槍ヶ岳登山については触れられていない。『山岳』第5年第3号(明治43年11月)の会員登山報には次の記述がある。
○石崎光瑤氏は八月初めより、上高地に十三日間滞在せられ、絵画及び写真の製作に従はれたり。
この2行には「鎗ヶ岳」「槍ヶ岳」の文字はない。紀行文も写真も絵も『山岳』には掲載されていないのである。そのため、これまでの略年譜では明治43年「上高地に赴く」などと記すにとどめられてきた。明治42年7月の剱岳も、絵や写真はあるが、文章がないために、光瑤の登山が過小評価されている一面がある。
本ブログでは、山岳画家の吉田博に焦点を当ててきた。明治42年立山での吉田博と光瑤の出会いの逸話や、吉田博の視点からインド写生旅行を比較した。また明治40-42年の剱岳について、新聞記事を読み解いて小説『点の記』と史実との差異を明らかにする作業を行ってきた。いずれも先行研究の成果の上に書き綴ってきたもので、ここであらためて敬意を表したうえで先へ進めたい。(つづく)

◇
[1]『高山深谷』第1集に3枚。第3・4集は無し。他の集は未調査。
[2]富山県[立山博物館]の『山を撮る』展図録(1998年)では、光瑤が英国型の組み立て暗箱を使ったガラス乾板を使っていたことが記され、2本の愛用レンズが写真入りで紹介されている。また立山室堂内部の写真は、『山岳』第5年第2号の同名のそれと似ているが別コマである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
