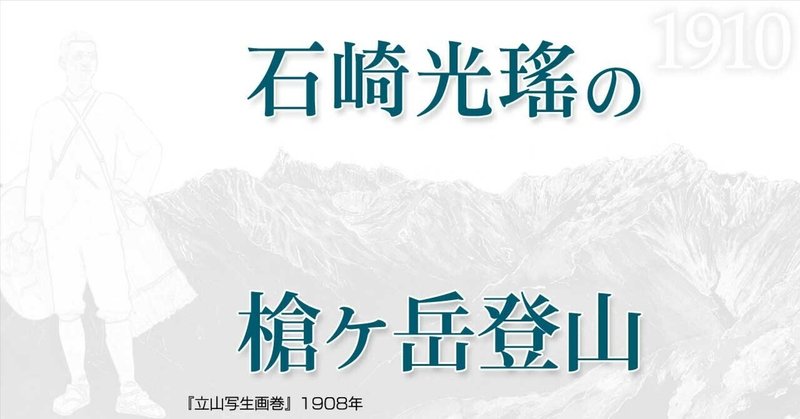
第1章 謎多き5年間
明治39年6月から明治44年6月まで、文献上明らかになっている光瑤の主な山行は約10件ある。槍ヶ岳登山の前に、主な山行をおさらいしておく。
槍ヶ岳登山にのみ興味がある人は飛ばして「第2章 針ノ木越え再び」から読んでください。
明治39年(1906) 夏の立山①
光瑤の本格的登山は22歳のとき越中立山から始まった。父和善が明治39年6月5日、58歳で亡くなり、一つのきっかけになったとみられる。立山登山は慰霊のためと記す人もいるが、正確には分かっていない。

南砺市立福光美術館には、高山植物の淡彩素描《立山写生 高山植物》が1枚残されている。画面に「越中国立山室堂附近にて採集し写す 明治三十九年八月二十七日 海抜八千五百尺の地位」とメモ書きがあり、「立山頂上」などの朱印も押されている。絵画作品と言うよりは思い出の記念品という感じだ。輪郭線が少なく、根の部分も描かれ、ボタニカルアートというよりも、本草図譜とか薬草図とかのようにも見える。「非常に花を愛した。本草学にも通じていた」父石崎和善(1848-1906)の影響か。それとも博物学の谷村西涯(友吉、1848-1923)の影響か。[2]
雑誌『山岳』の創刊
明治39年の山旅での写真は未見であり、撮影があったかどうかは分からない。そもそも光瑤がいつどのように写真術を身につけたのかは詳しく分かっていない。ちなみに、光瑤の師、竹内栖鳳は写真をよく利用して描いていたことで知られる。[3]
この明治39年は山岳関係の出版が相次いだ。2月に初の山岳辞典『日本山岳志』(高頭式編)、4月には山岳会の雑誌『山岳』が創刊された。7月には小島烏水『山水無尽蔵』が出ている。小島とははがきのやり取りがあったことが分かっている。
雑誌『山岳』を光瑤が愛読していたことは間違いない。明治39年から40年にかけてのいつかの時点でこれらの本や雑誌を手にして、元来好きだった山への関心を一気に高めた可能性が高い。
明治40年(1907) 夏の白山①
7月ないし8月、白山に加賀側から登り飛騨側に下りた。いわゆる白山の裏山越え(裏山越し)である。
《白山絶頂にて》という明治40年の写真が福光美術館にある。「加賀白山絶頂にて一等三角 標上更に六尺を写真三脚を組み立て記念写真撮影す(午前五時)」「海の如く白雲の上に長鯨の如く現はるるは木曽の御岳、左方極く淡く見つるは信州鎗ヶ岳、乗鞍ヶ岳等の連峯とす」と注釈がある。この時点で既に槍ヶ岳を意識していたとみてよい。映っている3人のうち、左は光瑤で、右が河合良成とみられる。2年後の剱岳登頂時の写真と比べると、シルエットが似ている。

富山県[立山博物館]『山を撮る』(1998年)から転載、着色
左は「加賀白山を越して飛騨へ入るべく出立し□/越中、中田万年寺にて」
「July.26.1907」とある
右は白山登頂時の写真、「Aug.1.1907」とある

『山岳』第4年第1号と第6年第1号の紀行文にも回想があり、河合良成と同行者がもう一人いたようだ。
明治40年の『高岡新報』に「白山の裏越して飛騨に出づ」という短信記事が近年、新たに見つかった。末尾に「赤尾村にて光瑤」と署名がある。記事では、同時期に行われた『高岡新報』の集団登山「立山探検隊」に対して光瑤が共感を寄せていて、光瑤と『高岡新報』の間に何らかの関係があったことが推認される。登りルートは不明。下りでは途中斜度50度の斜面で氷滑りを楽しんだことが書かれている。
「飛騨の山間に入れば実に神々しき風色に御座候今日五箇山に出で候が目の肥えし我等には風物平凡人里近き小風景は何等快感も興り不申候」とあり、下山後の高揚感とやや若気を感じさせる文章になっている。

また「頂上紀念とすべき印影無之まま採集せし草花を押して一行探検の紀念葉書と致し候」とあり、「印影無之」という記述と上記写真との不整合は今後の検討課題である。
『山岳』第4年第1号39ページの回想によれば、「シナクラ」の釣り桟橋で河合良成を画面に入れて写真を撮影したという。これは『山の写真と写真家たち』に収められた《渓》という写真であろう。

左はその部分。河合良成か。シナクラの釣り桟橋の可能性
右は飛騨叢書2『飛騨山川』(岡村利平著、明治44年11月3日発行)「白山登山道吊桟橋」
探検ブームの当時は、縦走登山と裏山越しが関心を集めていた。『山岳』第2年第1号(明治40年3月)に「険阻といふことに就いて」という一文がある。筆者は山岳会の発起人の一人、高頭式(仁兵衛)。高頭は「試に断案を下して暫く三宅[雪嶺]氏の説に左袒して、白山の裏山越と、立山の裏山越即ち針木嶺とを以て日本絶無の最険阻と呼ばう、殊に峠の称があって立派な道路らしく想はるるだけに針木を主張したいのである」と書いた。光瑤はこれを読んで触発されたのか、白山裏山越えに続いて翌年、針ノ木越えに挑む。[4]
なぜか浄土山の挿絵
なお、明治40年7月の『高岡新報』に「夏の立山写生」という表題の記事が出ている。表題のすぐわきに「(其八 石崎光瑤」とある。線画が2枚、月夜の浄土山と室堂内の囲炉裏を描いたものらしい。粗い筆致はおよそ光瑤らしくなく、他人の筆である可能性も小さくない。文章は100字の候文で、はがきに認めたようでもある。

この年の夏は白山に登っているから、光瑤が前年の立山登山を思い出して書いたものか。それとも、例えば高岡新報記者の大井冷光が光瑤に宛てて書簡体の記事を仕立てたのか。「其八」とあるので連載記事であったことは間違いない。8月4日の光瑤署名記事も書簡体なので、やり取りするような紙面展開があった可能性もある。[5]
山岳会入会前なので『山岳』第2年(明治40年)に「光瑤」の文字はまだ見つからない。
『高山市史』上巻(1952年)によると、飛騨高山の安川通りにある住伊書店(住廣造)が明治42年9月、飛騨絵はがき十数種を発行した。そのうちに光瑤の白水の滝があるという。未見。

福光美術館蔵の《白山の霊華》は明治43年ごろ制作と推定されている。光瑤の白山は、40年夏・41年秋・43年春の山旅がある。尾山章氏が「花鳥画家 光瑤の山と雪」『石崎光瑤の山』(富山県[立山博物館]編・2000年)で、クルマユリ・ハクサンフウロ・クロユリと書いているので、季節としては40年夏に見て描いたものではないか。
『山岳』第4年第2号(明治42年6月)によると、山岳会第2大会が明治42年5月16日、一橋帝国教育堂で開かれ、光瑤は、立山連峰写真5葉、画《白山絶巓の朝暾》横物1幅、画《絹本極彩色高山植物画帖》マクリ 1帖を出品している。《白山絶巓の朝暾》は明治40年の成果であろう。
明治41年(1908) 夏の立山②、針ノ木越え、白馬岳
5月に山岳会に入会、会員番号は150、とされる。7月から本格的な山行が始まったとみられる。『山岳』に120字の記事があり、その足跡がうかがわれる。
8月1日、立山に2回目の登頂を試み、その後、植物の写生と風景撮影を行った。8月20日に立山温泉まで下り、さらに黒部川を渡り針ノ木峠を越えて大町に出て、そこから白馬岳に登った。白馬岳に登頂したかどうかまでは分からない。帰路は糸魚川に出て伏木に戻った。伏木に戻ったとすればおそらく汽船であろう。[6]
翌年の『山岳』に、このとき高瀬川で野宿したと追想があるが、おそらく籠川であろう。
明治時代末は探検ブームである。「悪絶剣絶天下無比」と称された針ノ木越えは挑戦する人が相次いでいたものと思われる。この旅の手記らしいものは見つかっていない。明治43年に同じく針ノ木峠を越えたときの『高岡新報』の連載に使用された写真は、実はこの年に撮影した可能性が高い。詳細は後述する。

(全体では31cm×576.5cm)富山県美術館蔵
富山県美術館には、明治41年制作の《立山写生画巻》が所蔵されている。このうちの1面は一ノ越から龍王岳東岩稜と槍ヶ岳遠景をとらえたもので、空の部分に左から「槍ヶ岳」「雲ノ平」「笠ヶ岳」と小さく添え書きがある。このスケッチは明治43年夏の槍ヶ岳登山の伏線ともいえる重要な意味を持つ。辻本満丸が同年10月発行の『山岳』第3年第3号に寄稿した写真「立山龍王岳と槍ヶ嶽」とほぼ同じ構図で興味深い。[7]

富山県[立山博物館]蔵
※寸法不明
富山県[立山博物館]には、『写生帖 第三十四号』が所蔵されている。同館によると、1ページ物が24点、見開き物が5点、表紙1点だが、調査が完全には終わっていないという。このうち「弥陀ヶ原風景」のみがWebで見られる。なお「花鳥画家、石崎光瑤がみた山」『らくてぃぶ』14号(2003年10月)には、天狗平付近から立山三山から剱岳にかけた稜線を描いたものがカラーで掲載されている。
高岡市美術館が所蔵する素描《立山写生 巻二》の植物全18図もこの旅の成果である。根っこまでを描いたものもあり、胴籃に入れて持ち帰り、宿に帰って写したものか。
山岳関係の写生帖が、富山県内3館(県美術館・立山博物館・福光美術館)に分かれて(もしかしたら県外にも)存在することが、光瑤の山旅を詳しく読み解くときのハードルになっているのかもしれない。
志村烏嶺との交流
明治41年8月の白馬岳登山の記録はまだ見つかっていないが、福光美術館所蔵の《高嶺百花譜》の「序」に、志村烏嶺(本名寛1874-1961)が41年夏に白馬岳で邂逅したと記している。『山岳』の会員登山報の「志村寛氏は、八月八ヶ岳、御岳、白馬岳に登られたり」という記述とも合致する。

この「序」には「己酉春」「凌雲亭烏嶺」とある。十二支の「つちのととり」すなわち明治42年春に志村が書いたものであり、光瑤に頼まれて序文を記したと考えられる。
志村が光瑤に宛てて明治41年9月24日に差し出したはがきが、松村寿氏によって解読されている。松村氏は8月1日白馬岳登山とみているが、これは立山の誤認だろう。谷村西涯の「高山植物見本帳」によれば、白馬岳登山で植物採集した日は8月23日ないし25日となっている。8月20日に立山温泉に下り、おそらく21日から23日にかけて針ノ木越え、23日昼には大町に出て、その日うちに白馬岳の麓まで来たかどうか。いずれにしても志村との関係は今後さらなる調査が待たれる。[8]
志村烏嶺は長野中学教諭、山岳会会員で高山植物に詳しく写真も撮る。光瑤よりも10歳年長である。
志村は明治40年7月に『やま』(前田曙山と共著)、そして大正2年9月に『千山万岳』を上梓した。『千山万岳』の中に光瑤の作が2点盛り込まれた。挿絵として使われた《越中立山より見たる北日本アルプスを望む》という写真は、後述する「日本中央アルプス跋渉」でも用いられている。また、口絵の《合戸峠より御岳を望む》は、合戸峠遙拝所(標高1050m)から描いた作品である。大正2年までの間に、光瑤が御岳登山を行った可能性を示すもので、今後の調査が必要だ。

志村烏嶺『千山万岳』増補再版(大正3年6月)挿絵
光瑤は明治41年10月、ふたたび白山に向かう。頂きを極めるのでなく、紅葉の美しい白水の滝を写すのが目的だった。『山岳』第4年第1号に「小矢部川上流より越中桂、飛騨加須良を経て白山地獄谷付近の秋色を探る記」という長い表題の紀行文がある。これは『山岳』に載った初の紀行文で、約13000字ある。口絵図版として《白山裏山白水の瀑》なども掲載されている。

明治42年(1919) 医王山 夏の立山③、剱岳・大日岳
明治42年5月、光瑤は医王山に登った。『山岳』に約8300字の紀行文がある。「此山に一万尺の頭に於ける如き行楽は、元より望まる可くもあらざれども、桧舞台の開かるるを待つ間のわざとして、一遊を試み」とあることから、夏の剱岳登山への闘志を示すものだったとされる。[9]
この紀行文は、冒頭「春来能登半島に遊び、偶々稀有の暴風雨に会し」とあるのが注目される。明治44年7月の『高岡新報』の写真連載「怒涛」がその成果であるかもしれない。光瑤と言えば山であるから、海にも美を見いだしていたことは今後の調査が待たれるところだ。
この年7月から8月にかけての登山は、剱岳の登頂があまりにも有名である。頂上で撮影した写真《劍岳の絶巓》は日本登山史に残る記録的な1枚とされる。杉本誠氏がプリント原版を収集したことで、今も高精細で見ることができる。

『山岳』第5年第1号(明治43年3月31日発行)
明治42年7月24日撮影
杉本氏はオリジナルプリントを意識されて『山の写真と写真家たち』(1985年)に収録されたが、濃淡がきつく顔の表情まで見ることはできない。その後、1997年の没後50年展で顔が判別できるまでに調整されたが画質はよくないし白馬は見えなくなった。布川欣一編『目で見る日本登山史』(2005年)ではやや暗部が見えるように調整して掲載されたもののまだ不鮮明である。富山県[立山博物館]は2013年、さらに調整を加えてプリントを公開した。当ブログも調整を加えた拡大画像を掲載している。
《劍岳の絶巓》 調整済み高精細
琴月と冷光の時代 第5章第3節 淡白だった剱岳第2登取材
剱岳初登頂記事と〔午山生〕(5)陸地測量部内で起きた波紋
芸術作品としてはオリジナルプリントを尊重すべきであるのはもちろんだが、資料写真としてみた場合はより情報量を増やす仕上げがより重要と考えるからである。ご寛容にごらんいただきたい。
7月24日の剱岳登頂については、吉田孫四郎が『山岳』第5年第1号(明治43年3月31日)に詳細な登山記を寄稿していて、物議を醸す内容があった。ここではそれに触れない、詳細は他の資料(琴月と冷光の時代第5章第3節の注6参照)に譲る。この寄稿によって吉田孫四郎がこの登山のリーダーであるかのような推測がなされてきたけれども、その推測は根拠が弱い。私は光瑤がリーダーとみているので、ここにあたらめて注意を喚起しておく。
吉田孫四郎も山岳会の会員である。この『山岳』第5年第1号は、吉田が文章、光瑤が巻頭画・写真と分担することになった。もし光瑤が文章も書いていたならどうだったであろうか、と想像する。もしかしたら『高岡新報』に連載記事を書いていたのではないか。明治40年の同紙で光瑤のスケッチ連載があったようであるから、十分考えられる。残念なことに、『高岡新報』の原紙が見つかっていないため確認はできない。[10]
『富山日報』7月29日3面に、大井冷光記者による光瑤からの聞き取り「劔山登攀談」が掲載されている。その中で注意したいのは「帰りがけに絶巓のすぐ下の行者窟、それは三人許り入れる洞穴ですが其処に一行の名刺を缶詰に入れて紀念に遺しました」という記述である。
実際、7年後の大正5年に剱岳に登った村本栄三の一行が、その名刺の入った缶詰を見つけ、「吉田孫四郎」と「野村茂」「河合良成」「光瑤石崎猪四一」の名刺を確認したのだが、吉田の名刺がなぜか明治41年の7月24日になっていたらしい。[11]

『富山日報』に大井冷光が書いた連載「天の一方より」には、光瑤が描いた可能性のある3枚の線画が載っている。「弥陀ヶ原嘱目」「積雲に包まれたる剣岳」「龍王の月」。もしこれが光瑤筆なら剱岳と龍王岳という岩峰に美を見いだしていたとみることもできよう。「嘱目」とは即興を意味する。筆力や構成力をうかがうことができる。洋画家吉田博の新聞挿絵も即興で素晴らしいが、光瑤のそれも引けを取らない。
「天の一方より」では、光瑤の他に鷲田碌翁・島田神水・高山富雄・塩崎逸陵・富田秀法・吉田博らの画家が挿絵を描いていて、個性を比べることができて興味深い。比較的強い線を控えめに描き、余白を生かすのが光瑤らしさである。
大日岳については、7月29日に「奥大日岳の絶巓」を撮影している。早月川の谷に切れ落ちる北斜面の雪渓を写した1枚。「恐ろしい狂暴な大亀裂」と説明がある。また登山者が少ないことから「花一輪摘み採っても、雪一埃掬っても、純潔で清爽な気が溢れてる」という。頂上の三角標の中に、乱獲のため見られなくなっていたクロユリを見つけたとある。『高山深谷』第1輯所収。

小島烏水『日本アルプス』第3巻(明治45年)p48-49
『山岳』第5年第3号に写真説明
明治42年8月17日には「立山大汝より信飛境上の諸峰を望む」「立山深渓の雪と雲」という写真も撮影している。いずれも『高山深谷』第1輯所収、『山岳』第5年第3号に写真説明が掲載されている。未見。
それでは次回からいよいよ「登山熱中の5年」の最終年にあたる明治43年に入る。
明治43年(1910) 春の白山
明治43年は1回目の立山登山から数えて5年目、「登山熱中の5年」の最終年である。夏の槍ヶ岳の前に、光瑤は5月上旬から白山に挑んだ。
白山は3度目である。明治40年夏に登頂、41年秋に紅葉の白水の滝周辺まで、そして43年には残雪期に頂点を踏むことになった。この残雪期の白山登頂は「近代山岳史上残さねばならない記録」とされる。[11]『山岳』第6年第1号(明治44年5月5日発行)に約17000字の詳細な紀行文「春の白山」があり、ザイルを結び合う「アルプス式登攀」や、ライチョウの記録などの観点からも比較的知られている。一般書では、山岳紀行の名文を集めた『日本の名山』シリーズ(博品社)「18 白山」(1998年発行)にこの紀行文が収められた。ただ残念ながら《雨後白水瀧》《湯の谷の残雪》などの挿絵は入っていない。

『山岳』第6年第1号(明治44年5月5日発行)
この旅で光瑤は、雨中で気を紛らすため日ごろ愛吟する頼山陽の漢詩を唱えたり、宿泊した旅館で謠曲を「一番お相手を」と所望されたり、趣味の多い一面をうかがわせている。
一方、この山旅は、『高岡新報』の石黒剣峯(憲輔)記者が同行し、第三者の視点で書いた記事が存在する。連載「飛越深山探検」(5月10日~31日・15回)と、1年後の後日譚「光瑤君と僕」である。特に、ライチョウについては興味深い内容を書いているほか、酒が飲めない下戸であったとか宝生流謡曲「桜川」を唸ったとか、光瑤の人柄がよく伝わってくる。
光瑤によると、高岡駅で待ち時間があったので高岡新報社に訪れたら、そこで記者同行が決まったという。それは出発@日前の5月@日のことで、「少時無沙汰をするからと暇乞ひに来られた」とある。いとまごいとあるので、光瑤が日ごろから『高岡新報』と関係があったことが推測される。紙面に挿絵を描くとか写真を載せるとか仕事を受けていたのだろうか。
なお、光瑤が残した写真に、明治43年頃撮影と推定されている「野営地」という貴重な1枚がある。図柄から季節や場所を読み解くことができない。案内人2人と帽子姿の1人の計3人が写っているように見えるので、明治43年ならば白山登山での一コマになる。ただ、白山では野営はあまりないので、明治42年か明治41年の可能性も十分ある。

春の白山行で紹介しておきたいのは、光瑤の写生と撮影にかける執念である。それは吉田博のそれとも通じる。写生が本業で撮影は趣味などと分けるのはまったく無意味で、どちらの仕事にも手抜きをしない。
然れど頂上は寒冷頗る激甚にて、烈風吹き荒み尚ほ空気は愈々希薄となり頭痛甚だしく、正に身は沍寒中に朔風に曝さるる感がある。手指は凍えて知覚を失ひ、光瑤君は付近の撮影に際し器械□み吹浚はれんとし手指にアルミニユーム製の洋盃に雪を取り、アルコール洋灯にて溶解し、熱湯を作って手指を温めつつ撮影せられしほどである。
翌日猟師が薪木を伐りに行って居る間に、両人連立って、猟師の他は曽て人の訪づれぬ無名の瀧を探らんと、瀧壷から流れ来る氷水を股まで浸して徒渉し、愈々瀧壷に到達すると君は股から雫を垂らしながら飛瀑の霧の虹を現はすを消えぬ間にと不動の姿勢で一心に写生に就かれた。此麼所を見ると画家も隨分な荒仕事だ。
光瑤にとっては、山旅としての「春の白山」は少々物足りなかったようだ。最後にこう書いている。
自然勢力の偉大、人をして毛髪悚然たらしむる底の趣がないから、白雪を被って居ても、想ったよりは見惚れなかった。一言にして云へば甚だ単調であった。余り想像の輪廓を大きくしたのにも、いくらか起因するだらうが、北アルプスへ此頃登ったなら、こんな訳のものではない事は言を俟たぬと、信ずる。
槍ヶ岳登山を予感させる一文だ。

明治43年春、残雪期の白山を極めた光瑤は飛騨高山に下り、書店経営者で山岳会員でもあった住廣造(1880-1964)の仲立ちで、若き洋画家の蒲生俊武(1885-1914)と会って語り合ったらしい。蒲生は2年後の明治45年、大井冷光とともに長野側から針ノ木越えと御山谷遡行から立山登頂を行い、雑誌『少年世界』にいくつもスケッチを残している。冷光と光瑤、光瑤と蒲生、意外な縁である。吉田博もそうだが、若き光瑤の周りに洋画家がいたことがその後にどんな影響を与えたのであろうか、興味あるところだ。
住廣造が発行人となっている『飛騨山川』(岡村利平著、明治44年11月3日発行)に出ている挿絵「白山頂上社殿」は、『高岡新報』5月31日2面に掲載された挿絵「白山絶頂の社殿と陸軍三角測量標」と、構図が酷似している。たぶん書き写したものであろう。そうなると『飛騨山川』に出ている白山関係の写真や挿絵は、光瑤のものである可能性もある。ただ、住が巻末に書いた謝辞には光瑤の名前がない。今後の調査が待たれる。[13]

右は「白山頂上社殿」『飛騨山川』264ページ

◇
[1]『花鳥画の煌めき 没後70年石崎光瑤展』図録の渡邊一美「石崎光瑤その画業」によれば、光瑤は「15歳の時家族とともに兄の住む兵庫県神戸に転居」したという。15歳なら明治32年か。2023年に高岡市美術館で開かれた『ヘテロジニアスな世界 光瑤×牛人』展の略年譜によれば、明治39年に「父が逝去し、栖鳳塾を休学して富山に戻る」とある。
徴兵検査がきっかけではとする見方が従来あった。たとえば富山県山岳連盟創立50周年記念誌『太刀の嶺高く』(1998年・井上晃編)、斎藤清明「ヒマラヤを描いた初の日本人」『岳人』641号642号(2000年)では、「20歳の徴兵検査」をきっかけに帰省と書いている。しかし時期が少々ズレているようである。ちなみに『官報』7259号(1907年9月7日発行)によると明治39年3月30日勅定の従軍記章が授与された人の名簿に「工兵二等卒 石崎猪四一」とある。
[2]父の本草学については、光瑤のエッセイ「早起の辯」『国画』2巻9号(1942年9月)による。本草学関係と谷村西涯は富山県[立山博物館]『越中立山の近世本草学』(2023年)を参照。
[3]海の見える杜美術館(広島県廿日市市)のうみもりブログ(2014年8月、2020年7月)等参照。
[4]山岳会の高頭式(1877-1958)・志村寛(1874-1961)・大平晟(1865-1943)の3人が明治39年8月、白馬岳・針ノ木越え・立山を極め、このうち大平はさらに加賀から白山に登って飛騨の大白川に下りた。『山岳』第1年第3号(明治39年)の会員登山報。大平はその後、『山岳』第3年第1号(明治41年3月)に「加賀白山の裏山下り」を書いている。
[5]高岡新報社の「立山登山隊」は富山県内の新聞社として初の団体登山ツアー。7月28日出発、30日に登頂し、8月2日下山と推定されるから、8月1日に白山に登頂した光瑤はまったく別行動していたことになる。この企画には、当時同紙記者だった大井冷光も参加していて、2年後の剱岳登頂直後に室堂で光瑤は冷光から取材を受けることになる。
[6]『山岳』第3年第3号(1908年10月25日発行)p165「会員登山彙報」には次のようにある。「○石崎光瑤氏は、八月一日立山へ第二回登山を試みられ二十日間立山連峰に植物の写生と、風光の撮影を試みられ、二十日立山温泉に下り、黒部川を渉り、針木嶺を踰えて大町に出で、四谷の北城村より、白馬岳に登り、植物写生を試みられ、糸魚川より、伏木に帰らる」
[7]『高岡新報』大正5年1月にも「龍王岳の暁色」がある。光瑤にとっては龍王岳の山容は強い印象に残っていたと思われる。

画面左奥に槍ヶ岳、その右に笠ヶ岳を描いている
[8]松村寿「早期岳人の消息(三)光瑤あての絵葉書発見」『山書月報』558号(2009年7月)。『山岳』第50年(1957年)の志村「日本山岳会創立前後之見聞」によると、明治41年は「七月下旬、白馬山第六回登山。七月二十六日より八日間、木曽御岳及び駒が岳登山」とあり、光瑤の白馬登山とは齟齬が生じる。誤植なのか記憶違いなのか。
[9]安川茂雄『増補 近代日本登山史』(1976年)217ページ。
[10]松村寿「早期岳人の消息(二)光瑤あての絵葉書発見」『山書月報』557号(2009年6月)には、『山岳』を編集していた小島烏水が光瑤に宛てて書いた明治42年9月16日付のはがきに、出稿の分担を示唆する内容が書かれている。またその中には、小島が吉田博のアトリエを訪ねて油彩と水彩画を見たと書いている。光瑤は剱岳下山後に立山室堂で吉田博と出会い、あの夕映えの逸話が生まれている。
『高岡新報』は明治39年から42年11月27日まで原紙の所蔵が確認されていない。明治42年11月28日からは辛うじて残っている。また東京大学明治新聞雑誌文庫「牧野新聞」として、明治40年夏のほんの一部が残っている。
[11]村本栄三「踏破、一万尺巓(劔岳登攀記)」(九)『高岡新報』大正5年8月29日1面。大正2年8月11日で「南日重治」他4人、大正4年7月25日で「南日重治」「木暮理太郎(第二回登山)」「南日実」の名前などがあったという。
[12]山崎安治『日本登山史』新稿(1986年)459ページ。
[13]『ぎふ百山』(1975年)244ページに積雪期の「白山頂上社殿」がよく分かる白黒写真が出ている。参照されたい。なお、飛騨叢書2『飛騨山川』改版(1926年)313ページには吉田博「阿保峠の森林」の図版があるのでここに書き留めておく。
明治期における石崎光瑤の登山一覧
![●光瑤の明治期登山一覧
明治39年(1906)8月 立山 『立山登山 高山植物』(8月27日淡彩素描・福光美術館蔵)
明治40年(1907)7月~8月 白山 同行者・河合良成他1人 1日登頂 飛騨平瀬に下山 小白川で籠の渡し ※出立時の写真 越中中田万年寺で7/26に撮影(草鞋姿)「加賀白山を越して飛騨へ入るべく出立」 ※立山登山高山植物(淡彩素描・福光美術館) ※『山岳』第4年第1号に追想
明治41年(1908)5月 日本山岳会入会(会員番号150)
明治41年(1908)7月~8月 立山・針ノ木越え 8月1日に立山第2回登頂、写生と撮影20日間 8月20日に立山温泉 その後、黒部平~針ノ木峠~大町~白馬~糸魚川~伏木 ※『山岳』第3年第3号(1908年10月25日発行)p165による ※『立山写生画巻』(風景植物雷鳥彩色素描全13図・富山県美術館蔵)其一は龍王岳東岩稜 ※『立山写生』(巻二・植物蝶彩色素描全18図か・高岡市美術館蔵) ※『高嶺百花譜』(上巻下巻・福光美術館蔵) ※『山岳』第5年第2号「立山室堂の内部」「佐良佐良越」「針木越行路」「黒部籠渡し」この写真4枚は撮影年要検討 ※『高山深谷』第1輯に《立山大汝より信飛境上の諸峰を望む》《立山深渓の雪と雲》の写真説明(8月17日撮影)
明治41年(1908)8月 白馬岳 8月23日~25日あたりと推定される。富山県[立山博物館]編『越中立山の近世本草学』(2023年)によれば、光瑤が8月23日ないし25日に採集した植物3種が谷村西涯の「高山植物見本帳」に貼付されているという。
明治41年(1908)10月 白山 14日福光出発~ 15日越中桂 (野宿)~ 鳩ケ谷~平瀬18日~飛騨大白川(白水の滝付近)で写生撮影鉱山事務所跡~(同行者・井村勇吉) ※「小矢部川上流より越中桂、飛騨加須良を經て白山地獄谷附近の秋色を探る記」『山岳』第4年第1号 ※前年高瀬川で野宿したと追想
明治42年(1909)5月5日 医王山 同行者・井村勇吉、広岡悦三 「越中国医王山に遊ぶ記」『山岳』第4年第2号 能登半島について言及あり
明治42年(1909)7月17日 立山 立山第3回登攀
明治42年(1909)7月25日 剱岳 同行者・吉田孫四郎、河合良成、野村義重/案内 宇治長次郎、佐々木浅次郎、立村常次郎 ※「劔山登攀談」『富山日報』7月29日 ※『山岳』第5年第1号に 巻頭画「富士の折立より望みたる劍岳」(三色網版)と写真5枚「劍岳頂上の南望」「劍岳の絶巓(遠景は白馬連峰)」「雪渓の登攀」「劍岳の大雪渓」「劍岳の頂上」
明治42年(1909)7月26日~ 立山温泉 立山第4回登攀 29日奥大日岳 30日立山温泉 8月3日[立山]第5回登攀 8月11日下山 ※『山岳』第4年第3号 ※『高山深谷』第1輯に《奧大日岳の絶巓》の写真説明(7月29日撮影)この写真は『日本アルプス』第3集所収
明治43年(1910)5月 白山 同行者・高岡新報記者石黒劍峯 8日城端~9日東赤尾泊 10日平瀬泊 12日平瀬~岩井谷~白水瀧~鉱山事務所跡泊 14日登頂 ~高山~富山 ※『高岡新報』「飛越探検」 ※「春の白山」『山岳』第6年第1号 ※『白山の霊華』(福光美術館蔵)→明治41年の可能性
明治43年(1910)7月~8月 針ノ木越え・槍ヶ岳 『高岡新報』「中央日本アルプス跋渉」 立山温泉~針ノ木峠~大町~島々~徳本峠~上高地~槍ヶ岳 ※『信州槍岳之図』(水墨・福光美術館蔵)](https://assets.st-note.com/img/1715691611820-zFoqXp1NIK.jpg?width=800)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
