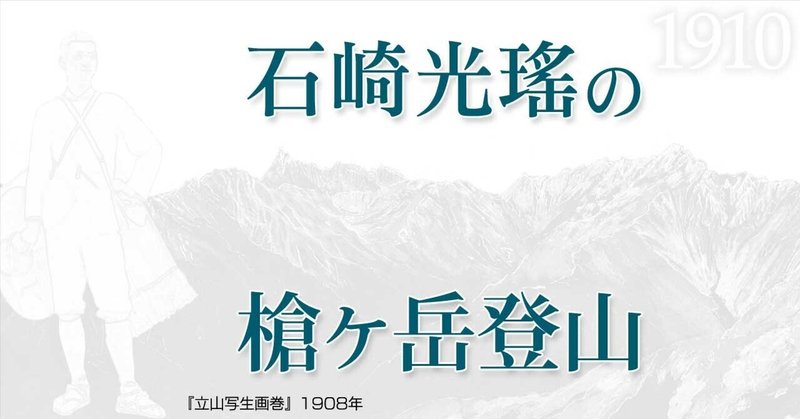
第4章 変わる山旅
水墨画は何を物語る
2024年春、福光美術館で展示された《信州槍岳之図》をあらためて見る。山容を流麗にデフォルメした水墨画である。風雨で写生も撮影もかなわなかったかわりに、想像して筆を執ったのであろうか。それとも登山前に憧れの山を想像で描いたのであろうか。

同じような水墨画としては、剱岳を描いた《山頂図》があるが、その山頂にはあの問題になった測量のための柱が具体的に描かれている。

左は部分剱岳の図には測標が描かれている
実際に登ったことの証といえる
槍ヶ岳の山頂には明治35年、二等三角点の測量ための櫓が造られた。その8年後、光瑤が登った明治43年の時点でそれが存在したかどうかは不明だけれども、光瑤の絵は櫓は書き込まれておらず、少なくとも写実からは程遠い。
慰労会で痛切な謝辞
槍ヶ岳の後、光瑤の山旅はめっきり減った。『山岳』に寄稿した山旅は、大正3年晩秋の立山、そして大正5-6年のあのインド旅行(日本人初のヒマラヤ遠征・1917年5月4日マハデヴ 峰Mt.Mahadev 3966m登頂)となる。「千載の恨事」が光瑤を山から遠ざけたのだろうか。頂きを踏むことを目的にした登山の、天に見放されたときの徒労感。それが画業の道にどれだけ有益なのか。光瑤は自らに問いなおしたのかもしれない。[1]
槍ヶ岳の登山から10か月後、光瑤は京都・竹内栖鳳の画塾に復塾することになった。
光瑤のための送別会が富山県高岡市の景望楼(後の高岡ホテル)で開かれたのは明治44年6月である。それは異例づくめの盛大な文化イベントだった。
『高岡新報』明治44年6月24日3面などによると、2日間にわたり朝8時から夕方5時まで、書画展観4席をはじめ揮毫・煎茶・明清楽・瓶花盆栽・抹茶・囲碁・詩会・謡曲・酒飯の計12席が設けられた。入口には「光瑤、石崎画伯送別会」と木彫りの看板が掲げられ、会場の至るところに数々の名品が飾られた。その価額は合計で何十万円と報じられている。現在だと数十億円相当か。
これらを段取りしたのは富田北溟(九兵衛)という人物である。光瑤は明治41年頃から明治44年6月まで高岡市一番町にあるこの富田北溟の家に寄宿していた。
新聞広告などから、富田は書画を取り扱う北溟堂を営んでいたとみられる。北溟堂印刷部(高岡市通町15番地)は大正元年に始めたらしいが、詳細は不明である。光瑤との関係も分かっていない。[2]

光瑤は前列中央に紋付袴姿で正面向き70人近くの人が
写っているが着物姿が圧倒的に多い
「石崎光瑤生誕140周年 知られざる光瑤の横顏」展で展示
2024年3月2日~4月14日
※この写真は発掘された1994年当初、
「明治36年8月・19歳のとき」と見られていた
その後研究が進み、復塾する際の送別会で撮られたことが分かった
2日間の送別会が終わり翌26日さらに、同じ場所で有志による慰労会が開かれた。そこで光瑤が述べた謝辞と抱負の要約が『高岡新報』に出ている。
要約の全文を引用しよう。
成すべき事の徒らに大にして而も何等端緒に就かざる微々たる未成品の一青年に対し、如何なれば斯くも連日に亘り懇篤なる同情を寄せらるる事が感極って涙の滂沱なるを禁じ得ず。顧みて余の絵画に志したる起因は極めて単純にして只一片の愛好心により生じたるものなるが、変遷多かりし半生に於て已むなく生活の一小技たる観を呈したるは最も心外たりし所なり。今日以後真の本務を完ふせんが為め生涯を徹し如何なる幸福、如何なる運命も犠牲に供して闘ふ可く、而して最後の目的とする所、名に非ず、富に非ず、只だ自己を欺かざる会心の作品を完成するに在り。然れば将来に有形の絵を故山に飾るは不可能にして又た本意に非ず。不朽の作を成し無形の□□を□へすを得ば、初めて自己の生存の意味を完ふしたるものなり。今日美術奨励の結果、画家は一種の富裕的生活を得るものの如く観らるるに至りするあるも真摯なる画家の本務を尽くさんと思へば世に画家程一面に於て悲惨なる生活は非ず。画界に於ても悉多太子の如き沈痛なる人材を要求して止まず。
印字がつぶれて読めない部分があり少し残念だが、それでもこの謝辞と抱負は、光瑤の人生を考える上で重要な意味があるように思われる。
記者が書いた本文には、「謹厳なる態度」「言々肺腑より逆り満座を粛然たらしむ」とある。周囲に「痛切」と感じさせる謝辞の何たる崇高さ。「自己の生存の意味をまっとうする」とはまるで哲学者か修行僧のようでもあり、「悉多太子」は後のインド旅行をも連想させる。「登山熱中の5年」から自らを解放し、日本画家として真の道を進もうとする決意。それは、針ノ木越えで槍ヶ岳登山に挑んだ気概と通じるようにも思える。
1年前に春の白山の旅で同行した『高岡新報』記者の石黒剣峯(憲輔)は、送別の意を込めて『光瑤君と僕』という連載エッセイを残した。そこには、驚愕の逸話が含まれるのだが、それを踏まえて、次のように光瑤を評している。
翻って思ふと熱烈な感情の半面に又た冷静な理性の閃めきが窺はれる。僕は十日許りの旅行中に君は明かに思想の人であると云ふことを看取したのである。今年[明治44年]も亦君と旅行を共にする約を結むで居たが、君は何か大に感ずる所があって研鑚三昧に入って居られて、遂に中止となった。(中略)要するに君は萬事に誠意の人であるから其作品にも一般軽薄な作家の夫れとは趣きを異にし高潔な人格と至誠が横溢して居る。
明治39年に京都・竹内栖鳳の画塾を休学した時、師匠との間にどんなやり取りがあったのだろうか。5年後には必ず戻ると決めていたのだろうか。決めていたのなら、槍ヶ岳登山は5年の掉尾を飾る登山であったと総括できよう。もし5年が既定路線ではなく、進路の迷いなどの理由でモラトリアムという時期に入っていたのだとしたら、槍ヶ岳登山は「千歳の恨事」を味わうことで自分を見つめ直し、画業に再び軸足を移す決意のきっかけになったといえよう。
抑えられぬ登山の虫
光瑤が再び雑誌『山岳』に紀行文を寄せたのは、第9年第3号(大正4年3月10日発行)の「晩秋の立山」である。大正3年10月、30歳となった光瑤の、久しぶりの山旅だった。文体は、それまでの白山裏山越や針ノ木越え、槍ヶ岳の紀行文とは違って書簡体である。候文を多用してユーモアをにじませ、一方で冷静さを感じさせる。書き出しは気負いがなく、こう始まる。
とても堪へ切れぬ登山欲を、此夏は、とある製作の方に殺がれ候為、十月三日の夕、最終の筆を擱くと同時に、発作的に其夜十時五十六分の列車にて、京を飛び出し申候。日本アルプスに対する積年の憧憬を、今度は満たす考にて例の立山に向ひ申候。
光瑤と案内人2人の合わせて3人は人気のなくなった晩秋の立山室堂に一泊し、その後光瑤は無事登頂を果たす。槍ヶ岳や龍王岳などの眺望を楽しみ、雪化粧した御前沢圏谷(御前沢氷河)などを写真に収めて大満足する。だが、天候急転を察知して案内役に「緊急動議」し予定変更し下山した。

締めの文章はこうだ。
雪の期待よりも少かりしは、遺憾に候ひしも、若し此降雪に鎖され、数日の後に温泉に下ったとしても温泉も無人の境、且つ雪の深き事も察せられ候へば、不慮の災禍を招きしや測り難く、ここで虫を抑へて満足致し申候。
「虫を抑えて満足」というのが緩くていい。槍ヶ岳の「千歳の恨事」とは対照的だ。
あの世の光瑤は言うだろう。大正6年のシシャナーグ(sheshnag・シェシュナグ)の時も撤退をしただろう。あの勇気を認めてほしい、と。
「晩秋の立山」は光瑤の登山に対する心境の変化を如実に物語る。
一方、注目されるのは、京都を夜行列車で出て、高岡に一泊、帰りも高岡で一泊していることだ。『高岡新報』大正3年10月5日2面の短信に「昨日帰岡、両三日滞在の筈」とある。帰岡ということは、記者は光瑤を高岡の人とみているのだ。明治44年に送別会を開いてもらった人たちとの縁がまだ続いていたのであろう。
今に続く高岡との縁
高岡との縁は続く。
『高岡新報』の翌明治44年の正月紙面に《千歳の雪(越中劔山麓)》が掲載され、さらにその年の夏の紙面には涼味企画として《怒涛》と題した能登の海岸写真が連載された。そして大正4年の正月紙面には《芙蓉峰》、同じく大正5年には《龍王岳の暁色》が出ている。一ノ越から見た龍王岳の岩稜はずっと忘れられぬ風景だったに違いない。暁色はどんな色であったのか、実物があれば見てみたいものである。[3]
光瑤は1947年3月25日に62歳で亡くなった。7年後の1954年3月、石崎光瑤遺作展が高岡市立美術館で開かれた。富山県内の所蔵家から《晨朝》など日本画25点を借りて展示した。5日間の会期で5632人もの来場があったという。[4]
さらに時は下って、1978年、同美術館で没後30年を記念して初の大規模回顧展が開かれた。出品は47点、代表作《熱国妍春》《燦雨》のダブル展示がこの時点で既に実現している。当時としては立派な図録が制作されている。
さらに2023年には高岡市美術館で「ヘテロジニアスな世界 光瑤×牛人」展が開催された。光瑤と高岡との深い縁を考えると本来、渇筆画の篁牛人とかけ合わせる必要はないのだが、うがった見方をすれば、福光美術館に敬意を表して生誕140年展の先取りを控えたということになろう。
◇
[1]インド旅行記は「甲谷陀より金剛宝土及サンダクフへ」『山岳』第15年第3号(大正10年4月)。石崎光瑤のインド行については、富山県[立山博物館]が2000年復刻した『印度窟院精華印度行記 幻灯用彩色硝子板作品』を参照されたい。写真集と紀行文を合わせた復刻で、「印度行記」が紀行文にあたる。原著『印度窟院精華』は1919年2月に限定200分制作された。
[2]「石崎光瑤画伯の壮志/両日に亘盛なる送別会」『高岡新報』1911年6月15日3面。送別会の発起人には木津太郎平・菅池貞次郎・大坪富次郎・篠島久太郎・井上孝太郎・土倉為之丞・金森次平の7人が名を連ねている。「再び竹内栖鳳画伯の門に入り修養すべく今月末に出発」と書いてある。『山岳』第6年第1号(明治44年5月)の会員名簿の住所にも富田九兵衛の名がある。
富田北溟については、『屑籠から 富山郷土史研究資料』下巻(昭和8年)に翻刻された書画会案内状に氏名がある。これは、明治15年4月19日・20日に梶原淵町の称念寺で開かれた書画会に関するもので、周旋列名19人の一人として「富田北溟」がある。この時の会主は佐伯春芳。また市立高岡図書館の『郷土史料展覧会出陳目録』(大正14年12月10日発行)に「富田九兵衛 皆川淇園時鐘銘送状」とある。皆川淇園(みながわ・きえん 1734 - 1807)江戸中期の儒学者。また『北陸タイムス』大正2年2月12日3面に広告「北溟堂印刷部 通町15番地 活版石版印刷、和洋帳簿調製」があるほか、『高岡新報』明治43年8月19日に書画展開催の案内広告がある。また、昭和3年4月の「公園地使用願」に出願人延対寺みよの保証人として「富田九兵衛」が出てくる。
[3]『高岡新報』大正9年の正月紙面には《九皐清唳》がある。《芙蓉峰》は富士山のことで、あれだけ嫌っていた富士山を扇の中に描いて見せたところを見ると、大正4年には山への過度な執着心はなくなったとも想像できる。『高岡新報』大正3年の正月紙面にも「社頭の杉」がある。
[4]『博物館研究』1巻4・5号(1984年6月)3月12-15日、目録1000部作成。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
