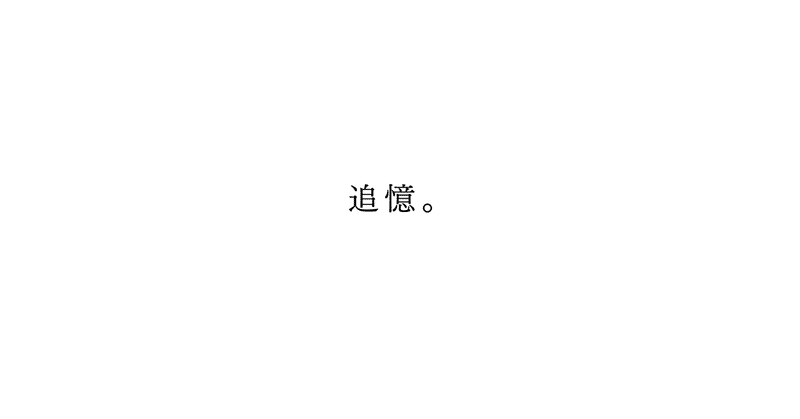
追憶。_サルバドール・ダリ/記憶の固執より
タイトル|追憶。
「誰かによって傷つけられる、なんてことは本来的にはないんじゃないかな。自分を傷つけられるのは自分だけだよ。」
同居人、酒井塔子がそう言って私に笑いかけたのは、ある晴れた日の午後のこと。当時の私は途方に暮れていた。私が選んだ選択を肯定してくれる究極目的が存在しない限り、その認めがたい事実を受け入れることは到底不可能に思われた。事の発端は「恋」だった。それは疑いをかけたら一瞬にして溶けてしまうような、脆さを孕んでいる。既に人生がままならないことを知っている。あの事件を境に私に生きる価値なんてものはないんだろうと勝手に信じている。積極的ニヒリズムに転向するのは私にとって難しい話だ。
「一度、スペインへ足を選んでみるのもいいかもしれない。」
私の思考回路がまた再帰したことを察したのだろう、酒井がそんな言葉を唐突に放つ。即座にから地球の歩き方を取り出して、喫茶店のテーブルにスペインの地図を広げて見せた。
「スペイン北東部に位置する、カタゲス。その入り江はポルト・リガトと名付けられている。カンピーナス通りの最先端に立つアトリエに訪れてみてほしい。マリアはきっと力になってくれる。」
大学在学中にスペインへ留学のために1年間滞在していた酒井はその辺りのことに詳しかった。これまで渡航経験のない私は若干の戸惑いを覚えつつ、ニヒリズムな心境に陥っていたこともあり、その日のうちに酒井の言うままにエアチケットを購入し、数日後には成田国際空港からスペインの地へと渡っていた。
彼女の言う通り、ポルト・リガトの入り江は潮風にさらされて風化した奇岩が至るところに点在していた。おびただしい数の凹凸が付いた岩や奇妙な形の穴が開いた岩石は見る角度によって、姿形を変え面白い表情を見せた。
そんな岩石を横目にカンピーナス通りを歩く私は、酒井が帰り際に発した言葉を想起する。
「弱さは正義ではない、弱さは弱さでしかないから。」
傷つくのは自分の弱さであり、正義ではない。だから、弱さと正義を混同しないだけの強さを私は持たなければならない。
黒いワンピースを着た女性がこちらに近づいてくる。トウコの言っていた「テルミー」だ。彼女は、1年前に自らと別れたことが起因となって恋人に死なれたらしい。それがずっと、蟠りとして彼女の中で途方もないほどに生き続けているという。どうにかしてほしいとトウコに頼まれたのは約1か月前のこと。この世とあの世の仲介として兄のアトリエに居続ける私は、快く彼女の要件を受け入れた。
アトリエに招き入れた彼女の黒い瞳は美しかった。これまで沢山の景色をその目で見てきたんだろうと、思わずにはいられなかった。
「兄があなたに見せる景色は残酷かもしれない。それをただ肯定でもなく、否定でもなく、ただ受け入れることをトウコは望んでいます。」
老婆の声にはっとしてアトリエを見渡す。この世とあの世の境界線を描くが如く、フィクションのような現実が広がっている。彼女の言葉が何を意味するのか、まだ私には理解できなかった。黒服の紳士が入ってきた。彼女は微笑みながら駆け寄った。兄と呼ぶ男性は私に意味深な笑みを浮かべた。
「私は永遠に生きる。天才は死なないものだ。」
放たれた言葉に若干の違和感を感じる。呆然と言葉を受け止める私に彼は言葉を続ける。
「間違いは神聖なものだ。正すより合理的に考え、誤りを理解しなさい。」
彼女に急かされ、彼は回れ右をして部屋から出ていこうとする。扉の開かれる音がして、私ははっとして振り向いた。しかし、老婆と彼の姿は消え、最後の言葉だけがその場に残った。
「そうすれば間違いを昇華することが可能になる。」
彼の言葉の真相を追いかけるように、扉を開き足を踏み入れた。途端、落ちた、と思った。無法地帯が私の前に現れる。広がり落ちていく無数の記憶の粒。無重力空間に1つ1つの彼との思い出が光りを放って浮遊している。
これまでずっと忘れていた私の発した言葉の数々が今ここで聞
き届けられる。そこで思った。引き受けろ、と。一番、私が恐れていたことであり避けていたことだった。自らが生んだ結果を引き受けていくことは紛れもなく私自身の責務だ。彼が死んだのは、私のせいかもしれなかった。けれど、それは認めざるを得ない。私の世界は私の選ぶ言葉から出来ている。言葉は、私の世界の対極にあって、一番大切な何かを一蹴できてしまうほどの迫力があって、世界を呑み込んでしまう、可能性以前に、可能性に賭けるための必要条件となる要素に全て、沈黙の一線を画してしまう。拾い忘れた記憶を拾い上げた先に、私でいるための十分条件が存在している。もし、時間を巻き戻すことが出来たら、私は彼を殺さなかっただろうか。結局、私が扱う言葉の裏には沢山の無意識が存在しているから、やはり分からない。
前向きでも、後ろ向きでもなく、私はこの世界でこれからも生きていく。できるだけ失敗しないように全力を尽くしながら、それでも失敗して、そのことを引き受けて、それを絶対に忘れないようにして生きていく。自分が自分を傷つける様をじっくり見届けて、そして強くなりたい。
私はそんなことを感じながら日本への帰路についた。
執筆意図
私たちの悩みを取り巻く基本原則として、私たちは自分の意志で人生を自由に選択することが出来るが、その一方で選んだ人生を肯定してくれる究極目的は不在している、この矛盾に苛まれていることが根底にあると感じている。これを受けて、恐らく3つの要素に分類が可能だ。1つは、ニヒリズムになること、2つは目先の目標や欲求を満たすこと、3つは何か変わりに依存出来るものを探すこと。宗教によって究極的な信念が特定されていない国においてこのような生きづらさを感じることは往々にしてある。
今回、サルバドール・ダリの背景を織り交ぜて物語を創作した。主題となるのは、言葉によって創られる世界。サルバドール・ダリには、彼が生まれる9か月前に死去した兄がいた。家族は、彼に同じ名前をつけ、まるで死んだ兄のように彼に接した。そこで、死人のように育てられた彼は死に対する恐怖心を植え付けられることになる。
それは、死と同居する生活である。私たちは、生きていく中で決して1人になることは出来ない。人との繋がりがあってこそ、成り立つ社会である。その中で、普段扱う言葉でさえも、時に凶器になり得る。自身の経験から紡がれる言葉は自身の生存バイアスがもたらしたもので、ある人にとっては暴力的であるかもしれない、その先で誰かを殺してしまうことだってなり得るかもしれない。殺すという直接的な行為に至らずとも、影響し合う中でその人に加害を与える可能性は否めない。
サルバドール・ダリの「死」に対する恐怖心は絵画にどのような影響をもたらしたのか。自ら天才と称し奇人のように振舞っていたが、その裏にはどんな背景があったのか。サルバドール・ダリの代表作となった「記憶の固執」からそれらを解きたいと考えた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
