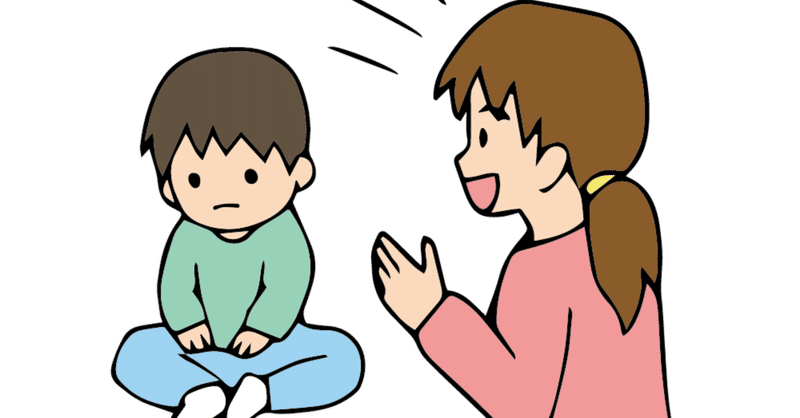
リクエスト回答【No.2】難聴との重複障がいがある場合の進路や情報収集方法について
皆さん、こんにちは。岩尾です。
かけはしへのリクエストで、質問をいただきました。
難聴と、知的や自閉症などの重複障がいがある場合、どのような進路があるのか?また、どのように情報収集すればいいのか?
かけはし自体は重複については専門ではないため、以下、専門家や現場の方に聞いた内容をお伝えします。
聾学校は言葉やコミュニケーションの指導を目的としますので、まだ、生活基盤を作る段階のお子さんは、知的障害の通園施設で育て、言語指導段階に育ってきたら、聾学校に入ることになるのが一般的のようです。
トイレットトレーニングや着衣練習(ADL指導)などは知的療育施設の方がプロでもあるとのことです。
現状では、聾学校幼稚部がADL指導を優先すれば、言語指導につける教員がいなくなり、本来の聾学校の責務が果たせなくなります。
身辺自立ができなければろう学校には入れないというルールがあるかはわかりませんが(学校によりけりかもしれません)、そのあたりは状況を見ながら家族と話し合って決めていくケースが多いのではないかと思います。
ただし、指導内容を考えると、知的な状態に応じて同じ発達段階のお子さんが集まっているところで育つ方が、相互作用が生まれるので、よく育つとのことです。
先生方にもその方面の専門性があるというのもあるかもしれません。
知的の施設には聾学校から補聴器関係について連携して、補聴器のことを配慮した指導が継続するようになっているのではないかとのことです。
こちらは自治体によって連携する施設は変わるでしょうが、ろう学校、もしくは療育センターが担ってくれるはずです。
ただしこの辺は地域によって変わってきます。
全国的に言えることは、地域の相談支援事業所の相談支援員を付けることが有効なようです。
中でも、基幹相談員をつけると良いようです。
基幹相談支援センターというのが、各市町村にあるので、そちらで相談してみるのがいいかと思います。
「市町村名 基幹相談支援センター」で、インターネットで検索すると、お住いの基幹相談支援センターの情報が出てくると思います。
難聴との重複障がいについて、専門で相談を受けているところなどはこちらでは探せませんでした。
詳しい方に聞いても、そういうところは聞いたことがないとのことでした。
現状では、難聴は、聴覚専門の療育センター、ろう学校などへ相談、
知的な部分は、発達障がい・知的障がいに関する療育センター、特別支援学校などへ相談ということになるようです。
専門家の方に聞くと、まずは知的方面から学校などは在籍するのが一般的なようです。
もちろん、程度によっては、ろう学校にも重複クラスがありますので、ろう学校に通うこともできます。
そして、知的の学校に在籍したときも、補聴器を付けて音をしっかり入れていくということをしなければ、聴覚が使えるようになりません。
聴力にもよりますが、知的方面に行ったとしても、まず聴覚での療育方法は確認して、音を入れていくことは、日常的に行う必要性があると思います。
ここが遅れてしまうと、聴覚を活用することができなくなってしまいます。(聴力や音を入れ始めた時期により変わります)
聴力によっては、人工内耳にするか、手話での生活を選ぶかという選択肢もあります。(手話に関しては、聴力によらず選択ができます)
ただし、知的の症状との兼ね合いもあるはずなので、ここは医師や専門家としっかり話をして、母語を何にするか考える必要があるかと思います。
もちろん、ここでの決定を一生続けなければいけないわけではありませんが、日本語か日本手話か、一度に両方獲得できる方法は今のところないので(日本語と日本手話は全く違う言語です)、ある程度の方向性は早い内に決めておく必要があると思います。
以上となります。
求めていた回答には程遠いかもしれませんが、まずは地域の基幹相談支援センターと連絡をとってみるのがいいかと思います。
こちらが、その地域ではうまく情報収集もできるのではないかと思います。
何かありましたら、またご連絡ください。
どうそよろしくお願いいたします。
言葉のかけはしの記事、活動に共感いただきましたら、ぜひ、サポートをお願いします! いただいたサポートは、難聴の啓発活動に使わせていただきます。 難聴の子どもたち、難聴者と企業双方の発展、そして聞こえの共生社会の実現のため、どうぞよろしくお願いします!
