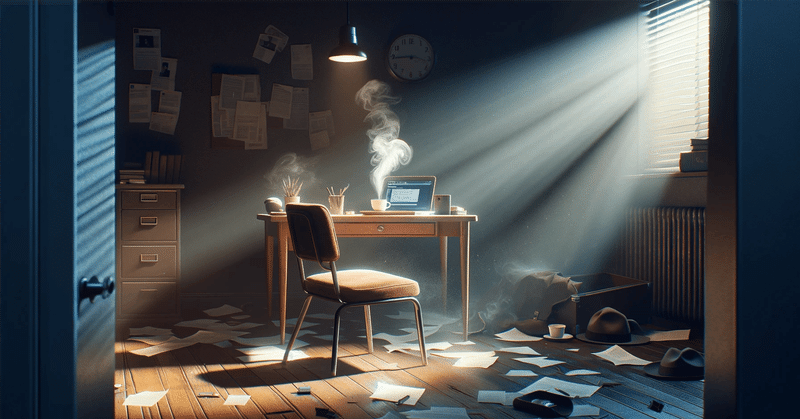
介護保険料の高騰と未来予測
介護保険料のアップがXでも話題になっています。
※この記事はAmazonアフェリエイトリンクを含みます。
2000年 2,911円 ←介護保険スタート
2012年 4,972円
2018年 5,869円
2024年 6,225円
実は今後期高齢者のみなさんは通常40歳から払込が始まる介護保険料を40歳当時は納めていない、いわば介護保険制度の試験状態であったというわけですね。
ちなみにAIにこの先の保険料の値上がりをシュミレーションしてもらいました。
介護保険料の未来の価格
介護保険料が高騰しています。
2000年 2,911円 ←介護保険スタート
2012年 4,972円
2018年 5,869円
2024年 6,225円
これら4つの価格推移から2028年、2032年、2036年、2040年の価格を予測してください。
AIの回答は以下でした。
このデータを見ると、年を経るごとに保険料が徐々に上昇していることがわかります。
次に線形回帰直線の方程式を求めます。最小二乗法を用いると、
y = 195.94x - 388986
となります。ここでyが保険料、xが西暦年を表します。
この式を使って、求める将来年の保険料を予測すると、
2028年: y = 195.94 * 2028 - 388986 = 6681円
2032年: y = 195.94 * 2032 - 388986 = 7137円
2036年: y = 195.94 * 2036 - 388986 = 7593円
2040年: y = 195.94 * 2040 - 388986 = 8049円
と予測されます。
ただし、この予測は単純な線形モデルに基づくものです。実際には様々な要因で予測から外れる可能性があることにご注意ください。
介護の現場
長い在宅介護経験から、介護保険制度をしっかりと勉強し、点数計算も暗算でできてしまうほど慣れたものになりましたが、一般的な労働市場で換算すると、これは肌感覚ですが、とてもじゃないが、試験スタートの価格では維持できないでしょうし、2040年時点の価格であったとしても、少子高齢化の推移を考えると次のようになります。
AIの回答
はい、少子高齢化の進展を考慮に入れることができます。
少子高齢化が進むと、現役世代が負担する介護保険料は更に上昇することが予想されます。なぜなら、
高齢者人口が増加し、介護サービスの需要が高まるため
現役世代の人口が減少し、保険料の負担者数が減るため
この2つの要因が重なり、1人当たりの保険料負担がより大きくなると考えられます。
具体的には、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計をもとに、介護保険料の上昇率を年々徐々に大きくする調整を行うことができます。
例えば、線形回帰式の傾きを以下のように年々徐々に大きくしていきます。
2028年: y = 200 * 2028 - 388986 = 7064円
2032年: y = 210 * 2032 - 388986 = 8572円
2036年: y = 220 * 2036 - 388986 = 10,128円
2040年: y = 230 * 2040 - 388986 = 11,736円
このように調整することで、少子高齢化の進行に伴う介護需要の増大と負担者数の減少を、保険料予測に反映できます。
ただし、実際の介護保険制度の改革や、社会情勢の変化などによっては、この予測から大きく外れる可能性もあります。あくまで目安として参考にしていただければと思います。
私たちにできること
筆者の尊敬するメンターの中には、ヘルパーサービスは利用する、しかし、介護保険制度は使わない(40歳からの払込をしていない世代)、すべて自費で利用するというポリシーを持った方も実際にいらっしゃいます。
介護保険制度は、受け取っている年金の受給額によって、1割負担、2割負担、3割負担と負担割合が変わってきます。
当然介護度にもよりますが、3割負担の方の月々の介護費用というのはとんでもない額になるわけです。
それを10割負担で乗り越えようとなると、日本では大富豪の部類になるのではないでしょうか。
高齢になっていくにつれて助けてもらわなければいけないことがたくさん出てきます。
これは物理的な身体を持って生きている以上仕方のないこと。
1、健康寿命を伸ばす
今、これから介護保険料の払込が始まる方は、将来的に介護保険を使う前提となりますが、やはり健康寿命を如何に維持できるか?というところに注視しながら生きていくということが重要になってくるのではないか?と思います。
高齢の方であっても介護や医療とは全く無縁の方もいらっしゃいます。
2、延命の倫理観を学ぶ
昨今は随分と雰囲気や空気感も変わってきましたが、それぞれ延命の定義と、希望、どういう最後を迎えたいのか?
臓器は提供するのかしないのか?
100%訪れる死に対する準備が現代人はあまりにも疎かになっています。
この世に絶対という概念はかなり少ないですが、その中でも人の死は100%、絶対に存在します。
例えばご両親が、突然救急搬送された場合、各種書類にサインがすぐにできますか?
延命はどこまでしますか?
胃ろうはしますか?
点滴から栄養は摂りますか?
挿管はしますか?
即答できる人は少ないのではないでしょうか?
医療や介護従事者だけでなく、私たち国民一人ひとりがこれらの答えに即答または、すぐに判断できるように延命と命に関する倫理観を学んでおく必要があります。
