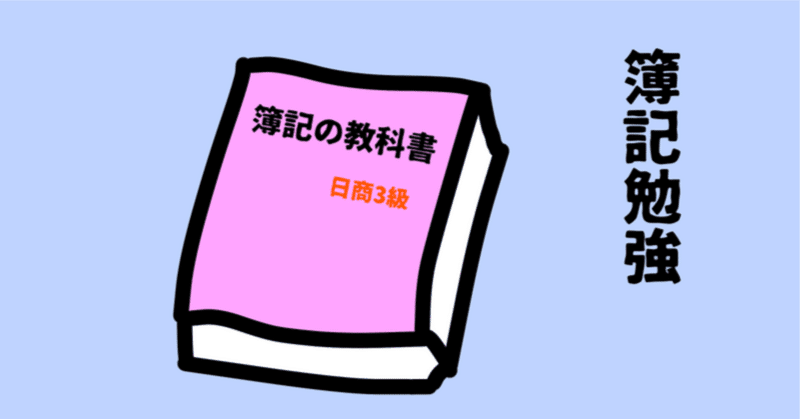
おすすめしない簿記の勉強法
え、タイトルからなんだかやばめの雰囲気伝わりますね笑
この記事を見ていただきありがとうございます。今回は簿記の勉強でおすすめしない勉強法をお伝えしていきます。
これを見るメリットととしては、
①時間の効率的な使い方(ノートまとめとかテキストに線を引くとか余計なことに時間を使わない為)
②丸暗記勉強の脱却(簿記は丸暗記では楽しくない為)
この2つがあるかなと思います。では早速書いていきます。
1.勘定科目の丸暗記
学生の頃社会科(地歴公民)の勉強法って皆さんどうでした?恐らく丸暗記というのが多く、「歴史は流れを掴もう」と言われてもよくわかんないっていう経験があったかなと思います。
語呂合わせで、
な(7)んと(10)見事な平城京
710年平城京に都を移す。
日本の人は(18)降参(こう(5)さん(3))さ。
1853年ペリーが浦賀に来航する。(黒船来航)
このように語呂合わせで覚えられた方も少なくはないのかなと思います。社会科であればテストでうまく点数を取れたりしたかもしれませんが、簿記の場合は丸暗記をしても、勘定科目の使い方がわからなければ意味がありません。
よって、テキストで新しく勘定科目が出たり新しい仕訳が出たらまずは読んで、問題集を解いていきましょう。
数学の公式も丸覚えでは全く使えないのと一緒ですね。😊
2.まとめノートを作る
学生の頃、勉強熱心な方ならしたことはあるかなと思います。自分なりにイラストを描いたりマーカーや色ペンを駆使して、「僕だけのオリジナルノート」。
きつい質問しますが、「それをして点数や学力は伸びましたか?」恐らくそんなに伸びた経験は少ないと思います。(こういう僕も高校の時に化学反応式をまとめノートを作成してテストの点にあまり反映されなかった経験があります。😂)
よって、まとめノートを作るぐらいなら問題を解きまくるノートを作りましょう。
問題を解いて間違えたら、「何故間違えたのか」「次はこのようにしたら正解」と考えながらメモを取りながら復習することをおすすめします。
3.過去問だけをひたすら解く
「資格試験は過去問に始まり、過去問に終わる」どこかで聞いたことはあるかなと思います。
資格試験のパターンを学んで、とりあえずこれが来たからこう解くという点数が取れれば良いという勉強法ですね。
確かに点数は取れるかなと思いますが、過去問パターン勉強だけをしていると応用が効きにくくなります。特に簿記3級の試験の第2問は少々難易度が高めで、様々なパターンで勘定記入等の問題が出てきます。
詳しくはこちらの記事にまとめてるので見ていただけると嬉しいです。😊
パターンを覚えているだけだとT勘定の問題や少々捻ったような仕訳問題が解きにくくなり、やはり「何故こうなるのかな?」としっかりと知識を定着させる必要があります。
また、簿記の勉強には2種類あります。
①知識を定着させる勉強
これはテキストを見て読んで、問題集でどのように使えば解けるのかという勉強です。ここでは理解不足をなくしていきましょう。
②時間内で合格点を取る勉強
これは過去問や予想問題集を使って実際に時間を計って合格点を目指す勉強です。簡単に言えば模擬試験ですね。自分が合格点に到達するには、後何分縮める必要があるか。苦手分野はどこなのか。これらが把握できます。これらの課題が出たら①知識を定着させる勉強に立ち返りましょう。
ここまで読んでくださりありがとうございます!今後もみなさまのお役に立てたらなと思います。
ではまた次回にお会いしましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
