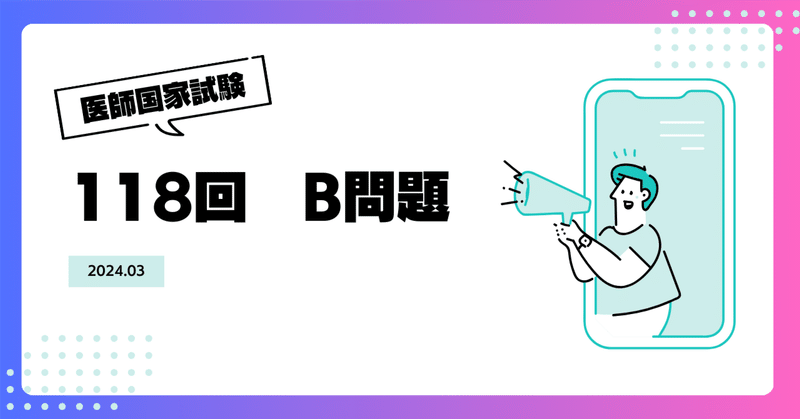
118B45,118B46
次の文により45、46の問いに答えよ。
77 歳の女性。突然の胸背部痛と疲労感を主訴に救急車で搬入された。
現病歴 : 本日未明に突然の胸背部痛で目覚めて 30 分ほどベッドに横になっていたが、身の置き所のない疲労感が増悪するため救急車を要請した。
既往歴 : 糖尿病、高血圧症で内服加療中。
生活歴 : 80 歳の夫と 2 人暮らし。問題なく家事をこなしていた。喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。
家族歴 : 特記すべきことはない。
現 症 : 意識は清明。身長 150 cm、体重 51 kg。体温 36.1℃。心拍数 96/分、整。上肢血圧 102/70 mmHg、下肢血圧 114/60 mmHg。呼吸数 15/分。SpO2 98%(room air)。呼吸音に異常を認めない。胸骨左縁第 3 肋間を最強点とする Levine 2/6 の拡張期雑音を聴取する。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。頸部に痛みはない。両肩の痛みを訴えるが、圧痛と可動域制限を認めない。
検査所見 : 血液所見:赤血球 391 万、Hb 11.9 g/dL、Ht 37%、白血球 8,600、血小板 16 万。血液生化学所見:総蛋白 6.4 g/dL、アルブミン 3.0 g /dL、総ビリルビン 1.7 mg/dL、AST 98 U/L、ALT 134 U/L、LD 263 U/L(基準 124~222)、CK 74 U/L(基準 41~153)、尿素窒素 24 mg/dL、クレアチニン 0.6 mg/dL、Na 139 mEq/L、K 4.8 mEq/L、Cl 105 mEq/L。CRP 6.8 mg/dL。
心電図(A)、胸椎エックス線写真(B)及び胸部単純 CT(C)を別に示す。
118B45
最も疑われる疾患はどれか。
a 緊張性気胸
b 急性心筋梗塞
c 胸椎圧迫骨折
d 急性大動脈解離
e 急性僧帽弁閉鎖不全症
正解:d
解説
この患者は、突然の胸背部痛と疲労感を主訴に救急搬送されています。身体所見では、上下肢血圧の差(上肢血圧 102/70 mmHg、下肢血圧 114/60 mmHg)と拡張期雑音(胸骨左縁第3肋間)が認められます。これらの所見は、急性大動脈解離を強く示唆します。急性大動脈解離は、大動脈内膜が裂け、中膜の層が断裂することで、大動脈壁内に血液が流入する病態です。突然の胸背部痛や上下肢血圧の差、大動脈弁閉鎖不全症による拡張期雑音などが特徴的な所見です。
他の選択肢について:
a 緊張性気胸:呼吸音に異常がなく、気胸を示唆する所見はありません。
b 急性心筋梗塞:心電図にST上昇や異常Q波などの所見がなく、典型的な心筋梗塞の所見とは異なります。
c 胸椎圧迫骨折:胸背部痛はありますが、上下肢血圧の差や拡張期雑音は説明できません。
e 急性僧帽弁閉鎖不全症:拡張期雑音は大動脈弁閉鎖不全症を示唆しており、僧帽弁閉鎖不全症とは異なります。
考察
急性大動脈解離は、致死的な疾患であり、早期の診断と治療が重要です。臨床所見や画像検査(CT、経食道心エコーなど)により診断し、Stanford分類に基づいて治療方針を決定します。Stanford A型(上行大動脈に解離が及ぶもの)は、緊急手術の適応となります。Stanford B型(上行大動脈に解離が及ばないもの)は、内科的治療(降圧療法など)を行い、合併症がある場合に外科的治療を考慮します。この患者では、胸部CTによる解離の範囲の評価と、速やかな治療方針の決定が必要です。
118B46
諸検査の後、痛みはやや改善したが疲労感は続いている。胸部単純 CT 終了後、心拍数 108/分、整。血圧 92/62 mmHg。SpO2 98%(room air)。
次に行うべき対応で適切なのはどれか。
a 経過観察
b 緊急手術
c 胸腔ドレナージ
d 心臓カテーテル検査
e 大動脈内バルーンパンピング〈IABP〉挿入
正解:b
解説
この患者は、急性大動脈解離(Stanford A型)と診断されています。Stanford A型大動脈解離は、上行大動脈に解離が及ぶタイプで、致死的な合併症(大動脈破裂、心タンポナーデ、冠動脈閉塞など)のリスクが高いため、緊急手術の適応となります。手術では、人工血管置換術により、解離した大動脈の修復を行います。
検査後、痛みは改善したものの、疲労感は持続しており、心拍数の増加(108/分)と血圧の低下(92/62 mmHg)が認められます。これは、大動脈解離の進行や合併症の発生を示唆する所見であり、速やかな外科的介入が必要です。
他の選択肢について:
a 経過観察:Stanford A型大動脈解離は、緊急手術の適応であり、経過観察は適切ではありません。
c 胸腔ドレナージ:大動脈解離では、血胸や胸水貯留を合併することがありますが、この患者では胸腔ドレナージの適応となる所見は明らかではありません。
d 心臓カテーテル検査:急性期の大動脈解離では、カテーテル操作により解離の進行や大動脈破裂のリスクがあるため、適応となりません。
e 大動脈内バルーンパンピング〈IABP〉挿入:大動脈解離では、IABPによる大動脈の損傷や解離の進行のリスクがあるため、禁忌です。
考察
Stanford A型大動脈解離は、死亡率の高い疾患であり、診断後は速やかな外科的治療が必要です。手術までの間は、厳重な血圧管理(収縮期血圧を100~120 mmHg程度に維持)と、合併症の監視を行います。また、疼痛管理や臓器保護のための治療も重要です。
手術では、人工心肺を用いて体外循環を確立し、大動脈を切開して解離腔を確認します。解離した内膜フラップを切除し、人工血管を用いて大動脈を置換します。必要に応じて、大動脈弁置換術や冠動脈バイパス術を併施します。
術後は、集中治療室で厳重な循環管理と合併症の監視を行います。血圧管理、疼痛管理、臓器保護、リハビリテーションなどを行い、患者の回復を支援します。
Stanford A型大動脈解離は、早期診断と迅速な外科的治療が予後を大きく左右する疾患です。臨床所見や画像検査から速やかに診断し、適切な治療方針を決定することが重要です。また、多職種によるチーム医療を行い、患者の生命予後と生活の質の向上を目指す必要があります。
=============================
【質問や感想、ご相談の募集について】
このブログを読んで感じたこと、質問したいこと、相談したいことなど、どんなことでも歓迎します。
特に期限は設けていませんので、過去の記事に関するものでも大丈夫です。
他の読者の方にも参考になりそうな内容を優先的に取り上げさせていただきますが、できるだけたくさんの方のお声にお応えできるよう努めます。
ご相談いただいた内容は、プライバシーに十分配慮した上で、このブログ等で紹介させていただくことがあります。
なお、ご自身の体調に関する事や医療相談はご遠慮ください。
体調に不安のある方は、医療機関の受診をおすすめします。
ご相談・ご質問はこちらのアドレスまでお寄せください。
dr.kousei.taro@gmail.com
みなさまからのメッセージをお待ちしております!
作者:厚生太郎
Twitter : https://twitter.com/kosei_taro
質問受付: dr.kousei.taro@gmail.com
=============================
【免責事項】
本ブログの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、著者及び関係者本ブログは医療行為の勧誘や医療助言を目的としたものではありません。
本ブログの情報を利用して行った医療行為等により損失が生じても、著者及び関係者は一切の責任を負いません。=============================
