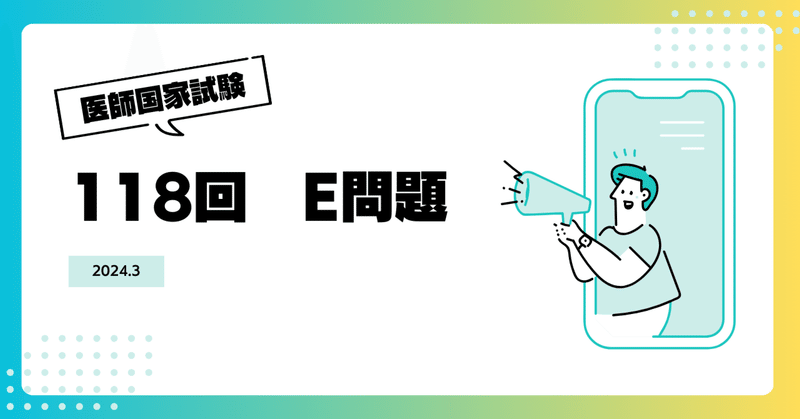
118E43、118E44
次の文により43、44の問いに答えよ。
23 歳の女性。最近、普段と様子が違うことを心配した母親に伴われて精神科を受診した。
現病歴 : 6 か月前から気分が沈み、自宅近くの内科診療所を受診し、抗うつ薬が処方された。1 か月前から遅くまで働いた後に友人と外出し、帰宅後は明け方まで電話をするようになった。毎日出社していたが、取引先とトラブルを繰り返すようになった。抗うつ薬は処方されたとおりに服用していた。
既往歴 : 特記すべきことはない。
生活歴 : 両親と 3 人暮らし。大学卒業後、会社に就職している。喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。
家族歴 : 特記すべきことはない。
現 症 : 意識は清明。多弁で気分が高揚している。身長 160 cm、体重 53 kg。体温 36.2℃。脈拍 76/分、整。血圧 114/66 mmHg。呼吸数 15/分。SpO2 99%(room air)。神経診察で異常を認めない
118E43
精神科受診時にこの患者にみられる症状はどれか。
a 幻視
b 離人症
c 聴覚過敏
d 抑うつ気分
e 睡眠欲求の減少
正解:e
解説
この患者は、6か月前からの抑うつ気分に加えて、1か月前からは気分の高揚、多弁、活動性の増加などの症状を呈しています。これらの症状は、双極性障害(躁うつ病)の躁状態を示唆するものです。
躁状態では、以下のような症状がみられます。
気分の高揚または易刺激性
活動性の増加
多弁
睡眠欲求の減少
思考の加速
注意の転導性
自尊心の肥大
行動の無謀さ
選択肢の中では、睡眠欲求の減少(選択肢e)が、この患者にみられる躁状態の症状として最も適切です。
他の選択肢については以下のように考えられます。
a. 幻視:躁状態では通常みられません。統合失調症や精神病性うつ病などでみられることがあります。
b. 離人症:自己や周囲が非現実的に感じられる症状ですが、躁状態では典型的ではありません。
c. 聴覚過敏:躁状態では、感覚の鋭敏化が生じることがありますが、聴覚過敏は必ずしも典型的ではありません。
d. 抑うつ気分:この患者は、6か月前には抑うつ気分を呈していましたが、現在は躁状態にあり、抑うつ気分はみられません。
以上より、精神科受診時にこの患者にみられる症状は、睡眠欲求の減少(選択肢e)と考えられます。
考察
双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返す気分障害です。病相期には、社会生活や対人関係に大きな支障をきたします。
この患者の場合、当初はうつ状態で発症し、抗うつ薬が処方されていました。しかし、その後に躁状態に転じたと考えられます。双極性障害では、抗うつ薬の投与によって躁転(うつ状態から躁状態への移行)を来すことがあり、注意が必要です。
躁状態では、睡眠欲求の減少により、日中の活動性が高まります。睡眠時間が減少しても疲れを感じにくく、仕事や交友関係など、様々な場面で活動的になります。しかし、その一方で、無計画な行動や衝動的な行動が増え、対人トラブルなどを引き起こすことがあります。
躁状態の治療には、気分安定薬(リチウム、バルプロ酸など)や非定型抗精神病薬が用いられます。また、躁状態の行動を抑制し、睡眠を確保するための環境調整も重要です。
双極性障害は、適切な治療により、病相期の症状をコントロールし、社会生活を維持することが可能です。しかし、治療の中断や不規則な生活により、再発することも少なくありません。
したがって、双極性障害の患者に対しては、薬物療法とともに、規則正しい生活リズムの維持や、ストレス対処法の習得など、心理社会的なサポートが重要となります。
また、家族に対する支援も欠かせません。双極性障害は、家族の負担が大きい疾患です。家族に病気の理解を深めてもらい、患者を支える役割を担ってもらうことが重要です。
医療者は、双極性障害の症状と経過を理解し、適切な診断と治療を行うことが求められます。また、患者と家族に対して、病気の説明と生活指導を丁寧に行い、治療への主体的な参加を促すことが大切です。
双極性障害は、適切な治療とサポートにより、多くの患者がよりよい社会生活を送ることができる疾患です。医療者は、患者の尊厳を尊重し、希望を与え続けることが重要です。そして、患者と家族に寄り添い、共に歩む姿勢を持つことが、診療の基本であると言えるでしょう。
118E44
この患者への説明で正しいのはどれか。
a 「転職を考えてみましょう」
b 「薬を変える必要があると思います」
c 「精神疾患とは考えないでよいでしょう」
d 「このまましばらく様子をみてみましょう」
e 「元気なうちにやり残した仕事をしてしまいましょう」
正解:b
解説
この患者は、双極性障害の躁状態にあると考えられます。現在の症状は、抗うつ薬の投与による躁転の可能性が高いです。したがって、この患者に対しては、抗うつ薬の中止と、気分安定薬や非定型抗精神病薬への変更が必要と考えられます。
選択肢bの「薬を変える必要があると思います」が、この患者への適切な説明と言えます。
他の選択肢については以下のように考えられます。
a. 「転職を考えてみましょう」:躁状態では、衝動的な行動や判断力の低下がみられることがあります。現時点で転職を勧めるのは適切ではありません。まずは、躁状態の改善が優先されるべきです。
c. 「精神疾患とは考えないでよいでしょう」:この患者の症状は、双極性障害の典型的な症状であり、精神疾患として診断し、治療することが必要です。精神疾患ではないと説明するのは適切ではありません。
d. 「このまましばらく様子をみてみましょう」:抗うつ薬による躁転が疑われる状況で、そのまま様子を見るのは適切ではありません。早期に薬物療法の変更を行い、躁状態のコントロールを図ることが重要です。
e. 「元気なうちにやり残した仕事をしてしまいましょう」:躁状態では、活動性が高まり、仕事などに熱中することがあります。しかし、それを医療者が助長するような発言は適切ではありません。躁状態の行動を抑制し、安定化を図ることが優先されるべきです。
以上より、この患者への説明で正しいのは、「薬を変える必要があると思います」(選択肢b)です。
考察
双極性障害の治療において、薬物療法は中心的な役割を果たします。特に、躁状態の治療には、気分安定薬や非定型抗精神病薬が有効です。
この患者の場合、抗うつ薬の投与によって躁転をきたしたと考えられます。抗うつ薬は、双極性障害のうつ状態には有効ですが、躁状態を誘発することがあるため、慎重な使用が必要です。
抗うつ薬による躁転が疑われる場合は、速やかに抗うつ薬を中止し、気分安定薬や非定型抗精神病薬に切り替えることが重要です。これにより、躁状態の改善と再発防止を図ることができます。
また、薬物療法と並行して、心理社会的なアプローチも重要です。患者に対して、病気の理解を深めてもらい、治療への主体的な参加を促すことが大切です。
具体的には、以下のような点について、患者と話し合うことが望まれます。
双極性障害の特徴と経過
薬物療法の必要性と副作用
規則正しい生活習慣の重要性
ストレス対処法の習得
家族や周囲の人々との関係調整
医療者は、これらの点について、患者の理解度や受容度に合わせて、丁寧に説明していく必要があります。患者の疑問や不安に耳を傾け、共感的な態度で接することが大切です。
また、家族に対する支援も欠かせません。家族に病気の理解を深めてもらい、患者を支える役割を担ってもらうことが重要です。家族の協力は、患者の治療adherenceの向上や再発防止に大きく寄与します。
双極性障害は、慢性の経過をたどる疾患であり、長期的な治療とサポートが必要です。医療者は、患者と家族との信頼関係を構築し、継続的な支援を提供することが求められます。
患者の尊厳を尊重し、希望を与え続けること。そして、患者と家族に寄り添い、共に歩む姿勢を持つこと。それが、双極性障害の診療において、医療者に求められる基本的な態度なのだと思います。
=============================
【質問や感想、ご相談の募集について】
このブログを読んで感じたこと、質問したいこと、相談したいことなど、どんなことでも歓迎します。
特に期限は設けていませんので、過去の記事に関するものでも大丈夫です。
他の読者の方にも参考になりそうな内容を優先的に取り上げさせていただきますが、できるだけたくさんの方のお声にお応えできるよう努めます。
ご相談いただいた内容は、プライバシーに十分配慮した上で、このブログ等で紹介させていただくことがあります。
なお、ご自身の体調に関する事や医療相談はご遠慮ください。
体調に不安のある方は、医療機関の受診をおすすめします。
ご相談・ご質問はこちらのアドレスまでお寄せください。
dr.kousei.taro@gmail.com
みなさまからのメッセージをお待ちしております!
作者:厚生太郎
Twitter : https://twitter.com/kosei_taro
質問受付: dr.kousei.taro@gmail.com
=============================
【免責事項】
本ブログの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、著者及び関係者本ブログは医療行為の勧誘や医療助言を目的としたものではありません。
本ブログの情報を利用して行った医療行為等により損失が生じても、著者及び関係者は一切の責任を負いません。=============================
#医師
#医学部
#国試
#医師国家試験
#医師国家試験対策
#医師国家試験解説
#第118回医師国家試験
