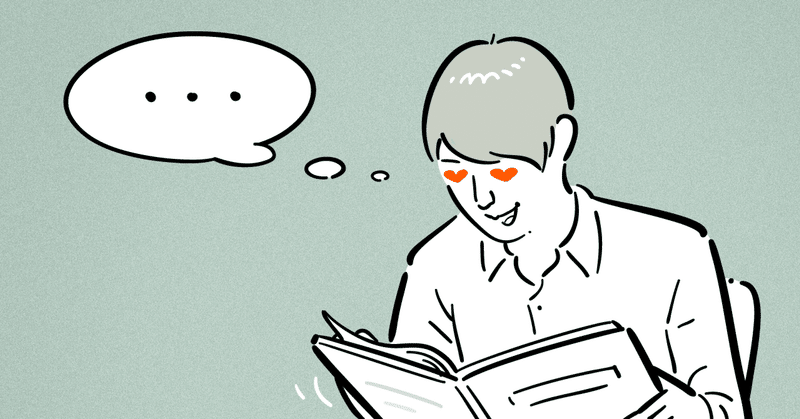
私の面白いがみんなの面白いにならないわけ
お笑い学校の先生のインタビューで
「だいたいの人は”面白い”を持っています。
それは紛れもなく面白いんです。
だけど、その面白いを100%で
伝えることが出来る人は100人に1人も
いません。ましてやそれを150%や200%で
伝えることが出来る人は生徒の中で
年間一組いればいいところでしょう」
これはいかに伝えるということが難しいかを
表しているのだと思います。
自分もマンガを描くのですが
「最高に面白いぜ」という設定を25年もった
まま、それを表現する技術がないまま
腐らせています。
じゃあ、どうやったら”面白い”が伝わるかを
考えてみます。
「好き」を育てるマンガ術 鈴木重毅
著者の鈴木さんは
講談社のデザート(少女マンガ雑誌)の
編集長を務められたかたです。
本書を通じて書かれているのが
「あなたの好きを作品にしてください」です。
好きを作品にする=熱量のある作品が出来る
というふうにもとれます。
流行はあれど、それに乗る制作作業は
続けられないし、出来たとて
その作品は温度の無い作品に
なってしまいます。
温度のない作品は読者に対して
影響力の無い作品となります。
だから”何を描きたいのか?”を
明確にしてその”何”に対して
必要なことだけを積み上げていく。
そういうのが大事なのだと思います。
他にも、マンガを描く人以外にも
参考になることが沢山ある書籍です。
次に
どうやったら読者に受ける
作品がかけるのか?
について考えてみます。
感情から書く脚本術 カールイグレシアス
に書かれてことで一番印象に残ったのが
「面白い脚本はどうやって書くの?」
「そんなの簡単だよ ページの最後に
次はどうなるんだろう?
って思わせたらいいのさ」
これはマンガでいう”引き”だったり
テレビの次回予告で流れるハイライトの
切り取りシーンだったりで
よく使われる手法です。
当たり前のことですが
続きが気になってさえ貰えたら
ずっと読んでもらえます。
表現方法は数えきれないほどあります。
いつか、あなたの好きが
世の中に広まることになりますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

