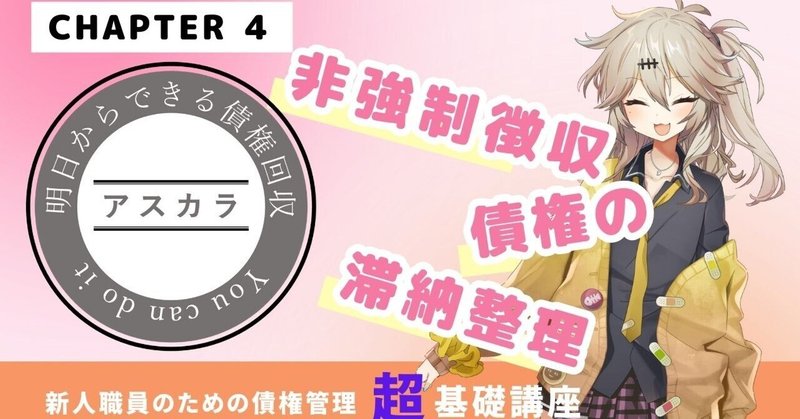
[改訂版]新人職員のための債権管理『超』基礎講座_非強制徴収債権の滞納整理

それでは早速、今日の講座を始めたいと思います。
今日は、チャプターフォー、非強制徴収債権の滞納整理です。
非強制徴収債権とは、住宅使用料や奨学資金、学校給食費などになります。
いわゆる、私債権といわれるものがメインのものです。
前回お話しした、税などと違って、滞納処分ができない債権になります。

今日のテーマは、5つです。
1、強制執行は義務
2、強制執行の前提手続き
3、訴訟代理人として裁判にのぞむ
4、裁判の実態
5、強制執行の申し立て
これらを順番に説明していきます。

それでは、はじめに、『強制執行は義務』というテーマについて説明していきます。
強制執行とは、いわゆる差押えや競売のことです。
これらも、法律により、『しなければならない』と規定されております。
これをやらないで、放置してしまうと、『不作為』や『怠る事実』といって、
法律違反を問われる可能性があります。
最高裁判所の判例でも、債権の放置は認められないとの見解が示されています。

続いて、強制執行の前提手続きについてです。
私債権は、税や介護保険料とちがって、
徴収職員が直接に差し押さえすることができません。
差押えをするためには、『債務名義』というものが必要になります。
債務名義って、すごい抽象的なものなので、
具体的には、確定判決や和解調書、仮執行宣言付支払督促などと覚えてください。
そのほかにも種類がありますが、余裕のある方は、法律を読んでみてください。

債務名義を取得するためには、裁判を経由しなければならないケースがあります。
確定判決や裁判上の和解をするケースです。
裁判って、『時間もお金もかかって大変そう』ってイメージされる方が多いと思います。
地方自治体の債権の場合は、担当職員が出頭して裁判を行うことができます。
一般的にも、簡易裁判所までの訴訟であれば、本人で行うこともできますが、
地方自治体の場合は、地方裁判所以上の訴訟でも担当職員で行うことが可能です。
そのため、簡単な内容であれば、担当職員が出頭して、数回の口頭弁論で終わらせることができます。

続いて、裁判の実態をご紹介します。
法廷のイメージ写真を載せてみました。
裁判においては、債権者を原告、債務者を被告、と呼びます。
基本的には、債権債務についての争いはないことが多く、
どうやって支払いしていくかを話し合うこととなります。
もちろん、一括請求も可能です。
支払い請求の場合、債務を認めているのであれば、3回以内で終わることが多いです。
一回で終わることも少なくありません。

続いて、裁判の実態をご紹介します。
裁判の実態はいかがでしたか?
少しはハードルが下がったのではないでしょうか?
裁判が終わると、その終わり方により、確定判決や和解調書などの
『債務名義』を取得することができます。
その債務名義をもとに、強制執行を申し立てしていくこととなります。
強制執行できる財産は、税などと同じように、債権や不動産などが対象となります。
今回は、超簡単に強制執行関連のお話をしてきました。
もう少し深く知りたい方は、債権回収が得意な法律事務所や弁護士の先生が
解説しているホームページでチェックしてみてください。
機会があれば、私も、もう少し踏み込んだ内容の動画を作りたいと思います。
最後に、この内容の動画を公開していますので、貼り付けておきます。
よければ視聴してみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
