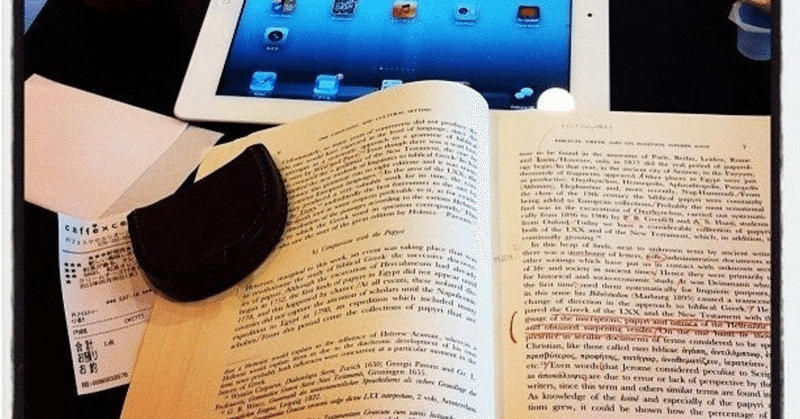
忘れる読書 を読んで 自分の読書術をアップデートする
今回も続けて書評です。
デジタル読書を行う上で、いつも気にしているのが自分の本の読み方がどうなのか 、ということです。
その意識が常にあるからか、読書論や読書術についての著書が出るとついつい手を伸ばしてしまいます。
今回の著書は忘れても良い 、という読書法らしいです。
目を引いたので購入し読んでみました。
では、書籍のメタデータを貼っておきますね。
今回も読書ノートからの書評ですので、小理屈野郎の読書ノート・ローカルルールの凡例を以下に示しておきます。
・;キーワード
→;全文から導き出されること
※;引用(引用の背景で示されていることもあります)
☆;小理屈野郎自身が考えたこと
書名 忘れる読書
読書開始日 2022/11/06 16:59
読了日 2022/11/09 09:26
読了後の考察
本文の論調が徐々に変わっていること が印象的だった。
最初は読書の仕方について少し丁寧に述べている、このまま続くかと思われたが途中からは自身の良い意味でのポジショントークが始まる。その中に自分なりの読書の仕方、というものを展開しているという感じになっている。
論陣としてはかなり整頓されていると思うが、なんだか結論をがっつり断定している ので、若さをすごく感じる。著者が年齢を重ねたときにどのような論陣に変容しているのか 、ということが楽しみだと思った。
びっくりしたことに著者は落合信彦の息子 らしい。信彦氏の博識はたくさんの読書とたくさんの人と会って話をすることから出来ていたことが息子の著者である陽一氏のこの著書から十分分かる。
そして、著者は小さな頃から多読家 であり、元々読書量に裏付けられた自分のポジションがあった 。だからこそ今回の著書のような自身のポジションが修飾され、またそれを表現する、ということに長けているためにポジショントークがしっかりと出来ているのではないか、と考えた。
論点がどんどん目移りしていて、内容をおっていくのが大変と感じるところもあった。
著者の読書の大きなポイントは結構俯瞰して読書をしているということが多い 、ということだ。何かを掘り進めるときは作品の中に没入しているが全体の情報をとるときは普通の人よりまだ一段以上俯瞰しているような印象を持った。
著書の中に出てきた「失敗の本質」は自分も読んでみたが、完全に教訓としてしか読んでいなかった し、その他の著書とリンクする、ということも特にしていなかった。おそらく著者は読書量でこのような高みに立てたのではないかと考えた。
確かに、読書量は必要だがここまでボーダーを上げてしまうと音を上げてしまう人が多いのではないか 、と思う。
そういう意味では著者は本のナビゲーターとして活躍する 、というのも一つの手ではないかと思える。これなら読書量に音を上げる人も共感できるのではないか?
選書家 、と言っても良いかもしれない。
結構緩い系の選書家はいるが、このようなしっかりとした系統の選書家というのはいないのではないか?と考えた。
また、電子書籍に対する考え方 もかなり面白い。電子書できはパラパラとページをめくって読むことに弱いと言われており、個人的には通読する読書スタイルなので電子書籍は使いやすいと考えているが、著者はキーワード検索をしたりしている とのことだ。
その他個人的には本を置いておくスペースがないこと、そして老眼になって活字を追うことがつらくなってきたことが電子書籍(専用端末)を導入する一番の理由だった。彼の場合は、これらの一般的な理由を超越した利用法をしている。そういう意味では新鮮だった。
著者が本文で上げた本はたくさん買ってみた。
積読がかなり増えているが、コツコツ読んでいこう。
キーワードは?(Permanent notes用)
(なるべく少なく、一般の検索で引っかかりにくい言葉、将来もう一度見つけてみたいと考えられる言葉)
#電子書籍
#読書法
質問1 概略・購入の経緯は?
朝日新聞の書籍広告欄を見て購入。
デジタル時代の教養を身につける、というのが主眼。どのような主張を出してくるのか楽しみである。
本の読み方とともに著者の選書集がついているらしい。
必要であろうと思われる本はこれを見て購入したい。
質問2 本の対象読者は?
読書論に興味のある人
本の解釈について考えたい人
質問3 著者の考えはどのようなものか?
読書とは
→著者の考える読書の意義3つ
思考体力をつけるため
気付く力をつけるため
歴史の判断を学び今との差分を認識するため
とのこと。
→読書をした内容をすべて覚えておく必要はない 。10%も記憶していればOKと著者は考えている。それより大事なのは自分なりに解釈して、その著書から知識のフラグを立てることが重要 である、説いている。
自分の読書ノートのフォーマットを完成させるときに実際に感じたことそのままだった。これは痛快だった。
著者は地頭が非常に良いので、フラグ立てをかなり系統的に出来るだろうし整理して頭の中に収納できるが、個人的には難しい。そしてこれからの時代の価値ある情報とは混沌とした中から浮き出させてくる知識の集合知、というところもあるので、読書ノートをつくり、キーワードを索引化していると、これに寄与しているのではないかと思った。
→上記の方法でそれぞれの本の脳内マップをつくり、読書中にそれと対応する本を無意識に探している よう。
これはなかなかまねの出来る仕事ではないと考える。
→ザッピング読み を意外と利用している。
→読書は抽象化する練習 になる。点と点をつなげる練習になる。
→単に多読するのではなく、ある程度俯瞰して物事を見てみようという姿勢で読書する のが肝要。
→本にカリカリとして向き合うだけではなく、オフライン的な時間を作って、ぼんやり考えながら読む、というのも良い こと。これらの組み合わせ、そのシェアが問題なのだろう。
→マンガも悪くはない。特に思考のフックをかけながら読める場合は秀逸 とのこと。個人的にはここまで考えてマンガを読んでいないな、ということが丸わかりだった。
→著者はあえて読書ノートやメモをとったりしない。これは著者の地頭の良さとも関連しているところがあると思われる。
→目次は読まない 。目次はそれほど注意してつくられていないのではないか、との読み。池上氏は、目次を見るとだいたい本の構成が分かる、と言っていた が完全に反目している。個人的には、目次を使う本と使わない本がある ような気がする。とき応じて臨機応変に対応すれば良い のではないかと考えた。
→速読は身につけておいて悪くない技術 、とのこと。何度かトライしたがなかなかうまく出来ない。
また気が向いたら一度やってみても良いかもしれない。
→通読する本は読もうと思って読む本だけに限る 。(これは自分の読書スタイル。おそらく新聞を読むような感じでなんとなく読んでいる本が著者の場合は多いのではないか と考えた)
→著者の読もうと思って読む本の類型3つ
コンセプト探求のための古典本
これは、時折読む本の中に入っている。読書ノートもまとまりのあるものになる 。データ収集のために読む本
日経BP系の本はこれが多い のではないか?だからこそ自分の読書スタイルで通読すると物足りないのにハイライトの部位が多くなる のではないか?
こういう本は、キーワード検索などで遣ったら良いのではないか と思われた。書評を書かなくてはいけない本
著者独特の類型ではある。個人的には書評を書く必要はないが読書ノートを付ける、という習慣にしているので、結局全部の本がこのようになってきているのだろう。
自分の読書ノートを付けるときに上記の分類をある程度意識しつつつくれば良いと思う。
コンセプト探求のための古典本などは読書ノートも長くなるし、データ収集のためならあっさりしてて良い。
他人に紹介したい本の場合は(=書評)は中ぐらいの長さになってくるのではないだろうか?
→著者は通読するのは月に10冊程度 とのこと。それ以外にも雑多な活字メディアに目を通しているのでこの程度の冊数になるのだろうが実際には本ベースで換算すると1日1冊以上のペースで読んでいる のではないか。
→**「この人は面白い」** と思える人の薦める本や選書は買うべき。
→多作な作家は外れが少ない
→先人が言語化した思考を下敷きにして、それを上書きすることで、より精緻に、自分が感じている世界観を記述できる。だから読書をしたあと内省の時間(読書ノートをつくる時間)を持つことは大事 ではないか。おそらく著者はその代わりに複数回読んでいる(読み込んでいる)のではないだろうか?
→古典を読むと言うことは時代を超えた価値を確かめながら先人と行う**「哲学のリレー」** と考えれば良い。;著者の言語化の巧みさには目を見張る。
→伝記を読むときは年代や年齢などの時間軸を抑える ことで、時代的なセンスを身につけられることもある。
教養とは
→以前と教養の定義が変わっていると考えている。
教養とは、持続可能な教養と考え、自分なりの文脈に気付き、俯瞰して情報を位置づけられること と定義し直している。
実際に自分が読書を通してやっている作業はこれに近いと考えられ、少し安心はした。
→結局は**「気付く能力」のある人のことを言う** のではないか。
気付く能力、というのは言い換えれば課題を見つける能力のある人 。実際に企業はこれを求めている。企業に迎合するつもりはないが、課題を見つけると言うことは新しいものを作れる余地が出てくると言うこと。このようなことを現在の企業は求めているが、それを供給する(この発想が元々間違っているのかも)大学や高校がそれに対応できるような教育をしているとは到底思えない。
→これと同時にある程度多数の人がベースとして知っている知識を得ること 、も教養の一つ。しかし現在はこれに重きを置きすぎているようなきらいがあると思う。
→抽象化できるかどうか 、というところも大事。そして抽象化できる、ということは言語化できる 、ということでもある。
→同時代を生きる人の著書を読むときは、自分と著者の立場の差異を確かめ、自分の考えを再認識する ように読む。
→何か一つの価値観をインストールして一発で解決しようとするのではなく、価値と価値の間を動き回って、それをやり続ける という行き方をしていけば良い。;色々な思索法やその結論に触れ、必要なものを自分のものにしていく 、ということ。これが著者の言う持続可能な教養と言うことなのだと考える。
本とは
→著者はパッケージ として本を考えている。
一つのことを深く考えるとき、SNSでは短すぎる。それより少しマシなのがnoteのようなブログ類似媒体。そしてそれより上の段階にあるのがパッケージとしての本。
あと、著者は上げていないが本(特に紙媒体)の場合は、編集者がいるのでこの存在も非常に大きいのではないか(書籍の価値を上げているのではないか) と考えた。
→言葉を紡ぐときの身近なブレインストーミング相手のようにも感じている。
他の著書の表現から自分の表現がインスパイアされる、ということ。
→そのパッケージの中に熱量(主張の熱さ)が保存されている 。ある著書の引用をするとその主張の熱さももれなくついてくる、ということ。
→情報の圧縮度・解像度が非常に高い 。自分から情報を取りに行くつもりで読まないと内容は血肉化できない。
→意欲的に学び続けていって、誰かに指摘されなくても内省するモードが組み込まれていれば、その人の成長のループは続く。内省モードを持っていることが大事。読書によってこれはある程度身につけられるのではないか?
→販売法が変わってきている;自著を100冊買ってくれたら講演します、等という販売方法をとる人も出てきている。自分の本に対する価値観を変えていく必要があるのかもしれない。
アート思考とは
結局アートだけではなく、思索するにはアートを作るような過程が必要 と言うこと。つまり、抽象化しながら思考し、点在する知を自分の文脈でつないで物語り化すると言うこと。
これはいわゆる普通の仕事でも十分必要なことではないか? これがかけている、ということはいかに定型的な仕事をしている人が多いか と言うことにも帰納するのではないかと考える。
→独自に問いを建てて、仲間とその知にを共有しながら、正しい答えを自ら見つけようとする 、これを意識的にした方がいい。
グローバル化
グローバルに活躍したいと考えるならオールラウンダーよりスペシャリストの方が活躍しやすい(一教科だけ1万点、みたいな)
しかし活躍しようとすればある程度の常識が要るのが現状。これからは情報化社会となり個人ベースでの活動が増えてくる。そうなるといわゆる常識が徐々に消滅してくるので結局スペシャリストがグローバルで活躍できるだろう、というのが著者の視点。
問題解決の糸口
いわゆる理系的な考え方をすれば良い
未知のものは何か
与えられているものは何か
条件は何か
結構忘れやすい、と著者が言っているがその通りだと思う。はまったときにとっさにこれを思い出すことが出来ればそれがフックになって助かる可能性が高いと思われる。
人間に価値がある疑問を投げかけるためのキーワード
→5つ定義されている
もしこうなら (what if)
これはどうだ (How about)
どうして (How come)
こうしたらどうなる (What happens by doing this)
あっちならどうだ (What about that)
その考えにどのような印象を持ったか?
常に色々な知識に触れ自分をアップデートする必要を痛感した。
途中は自著の宣伝のようにも受け取れるが、それに目をつぶっても納得できるところは多いと感じた。
類書との違いはどこか
単なる選書でもなく、単なる読書論でもないところ。
関連する情報は何かあるか
哲学的な思考、理論的な思考法について
キーワードは?(読書ノート用)
(1~2個と少なめで。もう一度見つけたい、検索して引っかかりにくい言葉を考える)
#アート思考
#持続可能
まとめ
非常に面白い本だった。
著者の若さを感じる本だった。
これからどのように円熟していくかを見ていきたいと思った。
今回も読書ノートを自分の言葉で書いてみたので少しバラバラとした感じがあると思います。スミマセン。
時折出てくる読書論について見てみるのは良いことだな、と思いました。
よろしければサポートお願いいたします。 頂いたサポートは、書籍購入や電子書籍端末、タブレットやポメラなどの購入に充当させていただきます。
