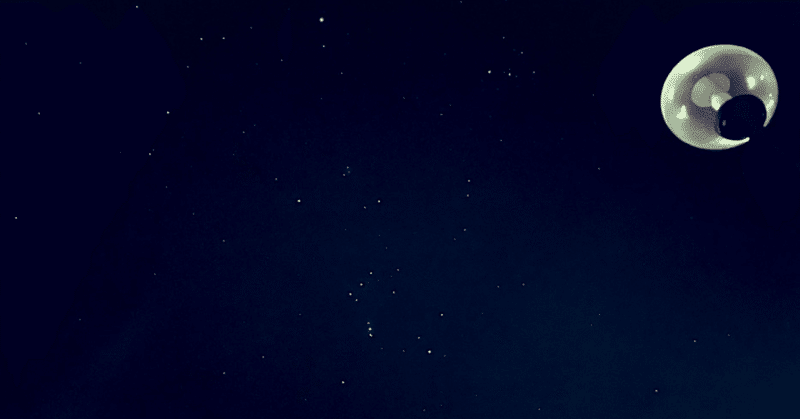
自己解釈
自分の作品を自分で解釈するなんて変な話だけど、聞き手がどう解釈してもいいと思う。たとえそれが作者でも。
今回解釈していくのは以下の短歌である。
(正直、現段階でこの方向性でこれを超える短歌は書ける気がしない)
君の言う夜は好きがメタファーだった世界が嫌い星はどこに座す
まず作者としてこの句は四句切れのつもりで書いた。また、鉤括弧をつけるのなら
君の言う「夜は好き」がメタファーだった世界が嫌い
星はどこに座す
になる。が、あえてつけなかった。それは単純にその方が解釈の幅が広がると思ったし、実際に正解があるとも思っていないからである。
また、星が座すという気に入っている。星には座すという動詞がとても似合う気がしたし、響きもよいからだ。
以下は作者ではなく、読者としての私の解釈である。
はじめに、わかりにくいと思うのは
夜は好きがメタファーだった世界が嫌い
の部分だと思う。これをわかりやすく書き直すと
「夜は好き」がメタファーだった(のかな。君が)世界が嫌い(と思っていることの)
倒置法が使われており、意訳としては
君の「夜は好き」という発言は世界(世間)を疎むことのメタファーだったのかな、、
となる。完全に経験則だが厭世的な人は夜が好きな人が多い気がする。それは夜は世間を感じにくい一人だけの時間であったり、なんとか乗り越えた一日を自己で労ったり、素の自分をさらけ出せる、楽しめる時間帯であり、まあとにかく日中を、社会を、嫌がる反動故か夜が好きな人が悲観的な人には多い気がするのだ。
君の発言の「夜は好き」にはそんな文脈があるのかもしれないと君の心中に主人公が気づく描写であるのが伺える。
それを
夜は好きがメタファーだった世界が嫌い
と紡ぐことで、そんな世界を同じく主人公も嫌っていることをうまく表せているような気がする。つまり、世界が嫌いはダブルミーニングで
(君は)世界が嫌い
と
(僕も君が嫌う)世界が嫌い
が掛かっているのである。
ここで僕と君はそれくらい深い関係性であるのだろうと愚推してしまう。
次に結句である
星はどこに座す
についてだが、結論から言うとこれもダブルミーニングである。いや、トリプルミーニングなのかもしれない。
1つ目
先に述べたように君の言う「夜は好き」が「世界が嫌い」のメタファーであるとき、君の見ている夜は本当に夜なのか?という疑念が一つ浮かぶ。もちろん、夜なのだろうけどメタファーである以上、本質的な夜ではない。そんな君の見ている夜の中に浮かぶ星はもしかしたら星座を成していないかもしれないし、月は二つあるかもしれないし、なんでもありかもしれない。そういう意味での
「君の見ている夜の中で星はどこにあるのか?」
という表現であるという解釈。
なので、この一文は一見するとおかしい。だって本来の夜は星の場所はほとんど決まっているし、わかりきっていることだからである。しかし、主人公は敢えて聞くのだ。どこに星があるのかと。なぜならそれは「君」の見ている夜はでたらめの夜(メタファーとしての夜)であり、主人公は「君」がその夜を見ていることを肯定したいし、肯定しているからである。そして、それは逆説的かつ同時に君の「世界が嫌い」に同調しているのだ。
2つ目
死者は星になるという考え方が私は大好きなのだが、この言葉の本質は人は魂を持っており、その魂が後に星となるということだと思う。つまり、魂=星とも考えられる。そこで
「君の嫌う世界がすべてであるこの世の中で君の魂(星)はどこに行ってしまうのか(どこにいこうとしているのか)」
という解釈。
3つ目
世界と星という単語は親和性が高そうに感じる。2つ目の解釈と似ているが「君の目指す世界(の星)はどこにあるんだろうね」
という解釈。
解釈をするのはとても楽しい。今からなら古典の授業をもう少し楽しめた気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
