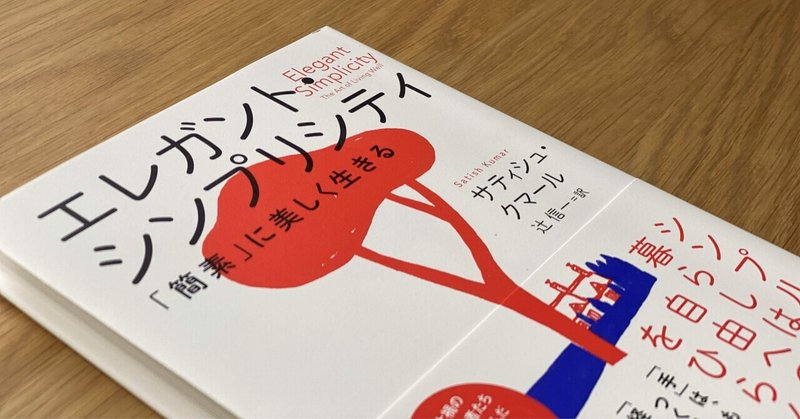
美と真実の欠乏は何をもたらすか。『エレガント・シンプリシティ』の言の葉 vol.1
宝石のような言葉がちりばめられている。
ページを繰るたびに、きらきらと星屑が胸に落ちてくるよう。
『エレガント・シンプリシティ 「簡素」に美しく生きる』(サマティシュ・クマール著 NHK出版)は、そんな本だ。
などと書き出している今、まだ読了したわけではない。
なれど、せっかちな私は、この宝石をもう誰かに手渡さずにはいられない心境なのだ。
それで、読み進めつつ、同書からの引用を、多少の所感を添えつつお届けすることにした。よろしければおつきあいください。きっとあなたの心にも、このきらめきが届くから。

(サマティシュ・クマール著 NHK出版)
シンプルに生きるとは
シンプルに生きることは、怠けることや活動しないことではありません。じつは、私たちを怠惰に、不器用に、不活発にするのは消費者としての生活のほうです。それは機械化、工業化、そして大量生産に依存させられた結果です。<エレガント・シンプリシティ>という理想を支えているのは、美術や工芸、つくるという行為、そして、より少ないモノでよりよく生きる技術(アート)です。大切なのは、どれだけ所有しているかといった「量」ではなく、「質」です。
ドストエフスキーの『ある男の夢(おかしな男の夢、との邦題も)』という短編がある。30代前半にこの短編を読み、衝撃を受けた。それからというもの、私は「文明とは何か」を考え続けた。なぜなら、「文明は必ずしも人類を幸福にするものではない」という答えがチラホラ見え隠れしたからだ。文明を否定できるほど強くはない私は、必死になって別の答えを見出そうとした。
その結果、たぶん、きっと、これが答えの一つだろうと結論づけたのが、「江戸時代の日本」だった。
人生を複雑にするのは対立の二元論
サティシュ・クマール氏は、さらにこのように述べている。
私たちの人生が複雑になるのは、「善/悪」「苦痛/快楽」「得る/失う」といった対立の二元論にとらわれるときです。いっぽう、いちばんシンプルなのは、平静なこころを育てること、そして、対立していたはずの二項が一緒に踊る、その踊りに加わることです。
江戸時代の日本が、文明と人間としての幸福のバランスをかろうじて取ることが出来たのは、まさに「対立の二元論」がなかったからだと私は考える。
604年に聖徳太子が十七条憲法を発布してからというもの、戦を完全になくすことはできなかったにせよ、太子が提唱した「和」をなんとか実現しようと努めてきたのがわが国の歴史ではないだろうか。とりわけ第十条にある「違いをあげつらって互いに争うのではなく、一致するところを見出して歩み寄れ」という内容は、まさに「対立の二元論」からの解放を実践的に説いている。
これがあるから、武士は合戦が終われば戦死した敵を弔いもしたし、生き残った兵を必要以上に殺戮することはなかった(会津戦争では残念ながらそれが失われたが。だから会津の怨みは理解できる)。
なお、心の平静を育て、二元論から自由になることとは、武士のあり方といっていい。
日本の「わび」「さび」に見いだせるシンプリシティ
サマティシュ・クマール氏は、たびたび日本の文化について触れている。特に「わび」「さび」については、何度も出てくる。たとえば
日本には「わび」「さび」という美学的な概念がある。そこには、「飾り気がない」「気取らない」「謙虚」などの意味が含まれている。高級そうで、華やかで、大げさで、目立つものである必要はない。ザラザラ、ゴツゴツしていたり、あっさりしていたりしてもよい。ありのままで、手がこんでいない。まさに「わび」と「さび」には、<エレガント・シンプリシティ>、簡素で美しい生き方が表現されている。作家のパウロ・コエーリョが言ったように、「優美(エレガンス)は余計なものがすべてそぎ落とされたときに現れる」。
「わび」「さび」といえば茶の湯をイメージする人は多いと思う。
実際、千利休が「わび茶」をほぼ完成させてから、武士が熱中したことも手伝って、日本文化の一翼となった。特筆すべきは、これが戦国時代という「乱世」の出来事だったことだ。平和な時代に文化が発展するのは世界的に見られるが、次はいつどこで戦争が起きるかわからない不安な世の中で、悠長に(?)仲良くお茶をする生活文化が花開くとは。もちろん茶道具などをこぞって手に入れ、それにより権威づけをしようと必死になったのは確かだ。そのぶんを差し引いたとしても「和敬静寂」を旨とする茶の湯が受け入れられたことの特異性はもっと認められてもいいだろう。
美と真実の欠乏が衰退の原因である
サブタイトルに「簡素」に美しく生きるとあるように、シンプルであることは「ほんもの」であり「真」であり「自由」であり「美しさ」であるということを示す。
そのあり方と相反するのが大量生産、大量消費社会であることをサマティシュ・クマール氏は述べる。
大量生産という産業のありかたは、醜い文明をこしらえてしまったのではないか。私たちは数字に支配され、経済にとりつかれ、スピードのとりこになっているが、これら三つは美しさの天敵だ。物質主義という醜い怪物がつきまとって近代的な社会を悩ませてきた。美の女神は人間性という家庭から追い出されてしまったようだ。美を失うとき、同時に私たちは真実も失う。「美は真なり、真は美なり」とイギリスの詩人キーツは書いた。私たちの時代の衰退の根っこには、この美と真実の欠乏がある。
私は高度経済成長の波に乗る頃に生まれ、バブル時代を経験した。
荒唐無稽と感じる人もいることを承知で白状すると、いつの時代かはわからないが僧(尼僧?)だった過去世があったことを十代半ばには感じていた(あくまでいくつもある過去世のひとつだが)。
そんな私にとってバブル時代は辛い時代だった。もう日本にはいられないと思い詰めたこともあった。
中学時代に出家しようかと思ったり、十七歳でヨガにのめり込んだりしたのも、この過去世のせいなのではないかと思う。
別に高尚な精神性を持っている、などと言いたいのではなく、言葉にならないジレンマと悲しみに似た想いを抱えていたのは、サマティシュ・クマール氏がいう「三つの美の天敵」のなかで生きることが辛かったからなのだ。
これもまた白状するが、私は「不登校」という言葉が存在しない時代に軽く不登校だった。「軽く」とわざわざ言うのは、一年のうち一ヶ月ほど(つまり出席日数ギリギリ)の不登校だったから。
偏差値や通知表など評価されることに対して、それが数字と経済とスピードで成り立っている「社会」に出るための重要なチケットであることに対して、言葉には出来なかったけれど、やりきれない想いを抱えていた。あの息苦しさは今も忘れられない。
もっとも、おかげで強く生きていくためには、武家の末裔らしく武士道を学ぼう、などと思えたのだけれど。
サマティシュ・クマール氏の宝石のような言葉をもっともっと引用しようと思っていたのに、ずいぶん自分の事ばかり語ってしまった。ちょっと恥ずかしい。
今回はこのあたりにしておいて、またつづきを書くことにする。
ここまでご高覧くださり、ありがとうございました。
みなさまからいただくサポートは、主に史料や文献の購入、史跡や人物の取材の際に大切に使わせていただき、素晴らしい日本の歴史と伝統の継承に尽力いたします。
