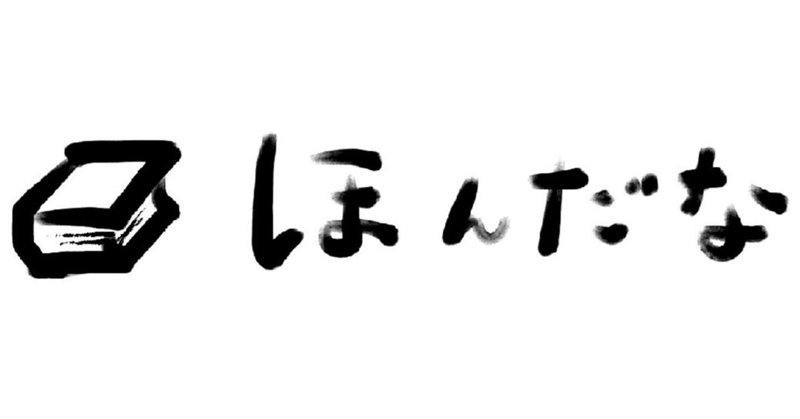
「ではずれますと」(『このあいだ』第5号 2021/2)
いしいももこ/ぶん、あきのふく/え『いっすんぼうし』福音館書店、1965
レベッカ・ソルニット、東辻賢治郎訳『迷うことについて』左右社、2019
保育園の先生が、娘たちのクラスみんなが昼寝をする前に、昔話をしてくれる。だからだと思う、家の絵本棚から娘が『いっすんぼうし』をリクエストしたのは。
兵庫県立美術館が秋野不矩展を開催した年だと思う。娘の生まれる数年前、たぶんその展覧会には結局行けなかったのだろう。『いっすんぼうし』の絵本だけが、そういった展覧会のあったことの思い出なのは、その年何か思うところあってそれを購ったことによるのだ。
これを娘に、と買ったのではない絵本を彼女に読むときは、いつも不思議な感じがする。子に本を読むというより、本のほうに子どもを紹介しているような。それに自分が親の蔵書から世界の文学を取り出したときのあの手の感触が再々思い出されないでもない。予定をはみだした雲のようなものが、時間に乗って流れている。
気が急くなかで読み聞かせていると、どうしても文字を追いかけることに気が向きがちなのだが、その文字の語ろうとすることを理解するなかで、いっすんぼうしが「たんぽぽよこちょう つくしのはずれ」を「ではずれますと」という表現がぼくには新奇に映った。
「出外れる」という言葉は辞書にも載っているが、ぼくは見たことも使ったこともなかった。
そもそも、出外れるという言葉がぴったりくるような、視界の広がりや境界をからだで感じることがあるだろうか。車や電車では長い長いトンネルを抜けても、スピードがからだの感覚と乖離していて「出外れた」と感じる余裕がない。いっすんぼうしのからだで、つくしの野原を抜けきってみなければ到底わかるものではないのではないか。
それでも、「出外れる」という言葉がひっかかるくらいの経験は、心的には自分にもあったのだと思う。だからいっすんぼうしを故郷から都へと送り出す川の前での最後のひと押しのような「ではずれますと」を声に出したときに、思いがそこでふと歩みを止めたのだと思う。ああ、自分もそこを抜けきったような経験がある、と。
去年、ソルニットという人の『迷うことについて』という本を読んだ。その中にこんな一節がある。
「生まれながらにして十二分な、そうでなくとも疑う必要のない自我を備えている者がいる。一方で、生き延びるため、あるいは自らを満たすために自我をつくり直すはるかな旅に出る者がいる。ある人びとは、価値観や習慣を家のように相続する。けれどもわたしたちのなかには、その家を焼き払って自分の立つ大地を探し、内面的な変身のためにゼロから建てねばならない者もいる。」
ところで、いっすんぼうしの場合の都への旅立ちは新たな自我への旅だったのだろうか。彼には満たされるべき欠損した自我があったのだろうか。おじいさん、おばあさんががっかりし、村の子どもたちに「ちび ちび」とばかにされる生活を心のどこかで嘆息していたのだろうか。
話は変わるが、あまりに心の美しい主人公に出会うとき、それに反感を抱く人は少なからずいる。「こんなやつはいない」と決めてかかるか、「こんな人いる?」と表面上は疑問の形にするかだ。かつてはぼくがそうだった。
しかし映画や小説はリアルでなければならないという要求、何かしら現実を暴いてくれるものへの期待や、醜さを覆い隠す欺瞞への怒り、いったんそれらを脇に置いて、作り話のたわごとや昔話に耳を傾けることも時には必要と思う。得てして昔話の主人公は純真なものだし、人の心の奥には「あまりに心の美しい主人公」がほんとうにいるのだから、彼らを互いに出会わせる機会を作ってやるべきだと思うのである。
最初から最後のページまで、画家の描いた絵を見るにつけて、いっすんぼうしは翳りがなく屈託のない青年だったと思う。都へ行くことを父母に願い出たのは、村にいても誰かのために「ひとはたらき」できる場がなかったからだ。自分の誕生をお天道様に祈った愛情豊かな父母さえ「がっかり」するくらいである。もし馬鹿にされる毎日から逃げ出したいのであれば、都へ行けば自分をからかう人口が増えはしても減りはしないと考えるべきである。いっすんぼうしが出外れたのは、自分を取り巻く尺度からだった。都に行けば、異なる尺度で自分を遇し、それゆえにこそ自分もまたために働いて役に立てるような人に出会えるかもしれない。いっすんぼうしは自分の大きさへの旅に出たわけだ。たんぽぽやつくしなど、いっすんぼうしの「身の丈」を出外れたところに、だから大きな川が流れていた。しかも都へは川をさかのぼるのだった。いっすんぼうしの自我は十二分に強かった。
だから打出の小槌を手にした姫に問われ、いっすんぼうしが「わたくしの のぞみは、わたくしのからだが おおきくなること」と答えるとき、そこに驚きがある。彼は自分が小さいことを気に病んでなどはいないと思うから、「そうだったんだ」と意外に感じるのである。だが、よく考えればそれも彼自身のためではないということに気がつく。姫が小槌を振り、そのたびに「ずん」とからだが大きくなるのだが、彼はそれがどこまでの大きさになるかを姫の手に委ねていた。どこで姫が小槌を振るのをやめるのか、任せているのである。そうすれば、姫の眼差しとより近く出会うことができるとわかっていたからだ。彼は自由な旅人だった。
生き直すことはしんどいことかもしれない。しかし先述のソルニットの本は、道に迷うことの豊かな意味をさまざまに示してくれる。敢えて出外れてみることを試みる勇気が必要な「とき」がある。そんなことを思った。
誰も閉じ込められてはいけない。家庭も人格も密閉するものではないのだ。窓を穿ち、雲の通り道を子どもたちに「どうぞ」と遺しておきたいものだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
