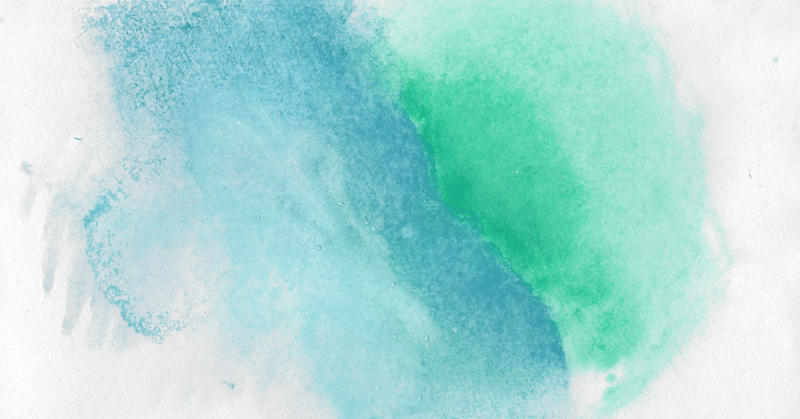
SNSやブログは何のためにやるのか? #SNSの教科書 が考えるヒントになった
最近、SNSやブログの使い方を迷走中です。
400日以上連続投稿してきたnoteも、「単にだらだら続けるだけじゃだめだな~」という思いがあり、連続投稿を切らしてしまったタイミングでしばらくおやすみしてしまいました。
はてなブログをProにして独自ドメイン化を試みてみたものの、「ブログを書き続ける=課金をし続けなければならない」という構造が、「ブログを書き続けたい」という欲求に反していることにソワソワしてしまい、2日でProの解約手続きをしてしまいました。
ブログやSNSをどう使っていけばいいか、インターネットで情報収集しようにも、収益化、アフィリエイト、SEO、Webマーケティングの情報が多い。
ブログを書き続けていけばお金がチャリンチャリン入ってくると思うとちょっとやってみたいですし、収益化を一つの指標にすると、読み手視点のコンテンツを生むトレーニングになるとも思ったので、興味はあったんです。
でも。Amazonのアフィリエイトくらいならいいのですが、私がすごくいいなと思ったサービスを熱量を込めて紹介し、その先にやたら目立つCSSで彩られた(○○を使ってみる)というボタンが表れて、「あーこれアフィリエイトなんだな~」と思っちゃうような記事を、自分の名前下のブログであんまりやりたくないなぁ、と思った。
じゃあ完全匿名でやるかというと、その時間がもったいないと感じてしまう。
SNSはというと、長くやってはいてそれなりに育ってはいるものの、「会社の人格とは別人格」という意識が長かったので、(特に隠してはいなかったものの)プロフィールに所属を入れ始めたのは最近のこと。あまり攻めた投稿もせず、身の回りの投稿ばかりで、フォロワー数の割に影響力の小ささを悩んでいたところでした。
SNSの使い方を勉強してみた
そこでSNSの運用について基礎から勉強したいと思って手にとったのが、徳力基彦さんの『「普通」の人のためのSNSの教科書』です。
この本では、実名や所属を明らかにしながら、仕事に活かすためのSNSの活用方法について紹介しています。
紹介している内容は基本的なところからです。実名アカウントを開設することについてどうやって会社に許可を取るか、といったことから書かれています。
思い返せば、Twitterアカウントを開設したのは大学生のころでした。最初こそ匿名アカウントでしたが、当時建築学生だった私は、学外のコミュニティと交流するときに「匿名アカウントじゃ覚えてもらえないぞ」と思って実名アカウントに切り替えました。当時知り合いになった建築関係の方は、実名でアカウントを運用されていた方が多かったのも大きいと思います(エンジニアさんと先に知り合いになってたら、ハンドルネームにしてたかも)。
この本で紹介されている、「情報を蓄積し発信をしていたら、相手から声をかけてもらえる」というプル型のコミュニケーションは、私自身も何度も経験してきたことでした。これまで、自分が発信することで、たくさんのチャンスやネットワークを掴んできています。
ただ、たとえば戦略的にTwitterを運用してきた方が数か月で1万フォロワーを達成したりするような、SNS全体のスピード感がどんどん上昇しているようななかで、私の速度はまったりしすぎなんじゃないかと。
この本には、「自分だけのメモ」としてのブログを推奨しています。再現性があり、徳力さんによる作例(すごく立派なので、気後れするかもですが……)もあり、「こんな感じのメモを書けるようになりたいな」とモチベーションが上がります。
さらに、徳力さんご自身の成功体験のほか、SNSを利用してビジネスや個人的な活動に役立てている方の「ハプニング」事例、すなわち思いがけないポジティブな状況が舞い込んできたエピソードもたくさん紹介されています。お知り合いの方、名前を見かけたことのある方も何人もいました。
「私は何のためにSNSやブログを使うのか?」と考えたとき、自分の学びや内省のために虚空に向かってつぶやき続けるのも悪くないのだけど、やっぱり発信がきっかけで、何かおもしろいことが起きてほしい。
そんな気持ちを新たにすることができる本でした。
お読みいただきありがとうございました! よかったらブログものぞいてみてください😊 https://kondoyuko.hatenablog.com/
