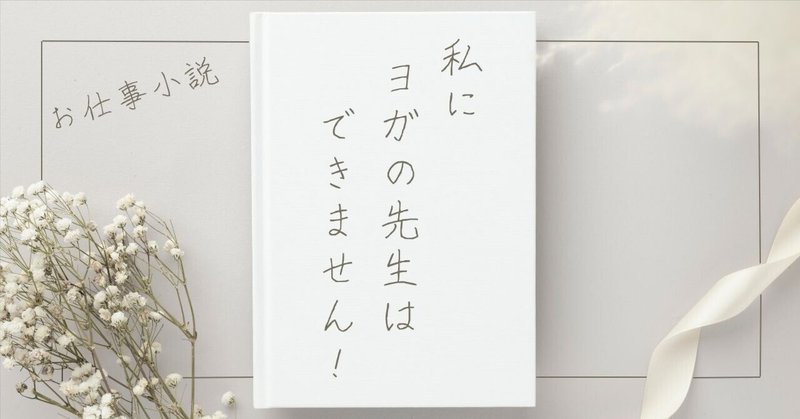
私にヨガの先生はできません!【第四話】あの日のこと
【第四話:あの日のこと】
私は市民会館のステージ袖で、小さく深呼吸した。
ステージの真ん中にはマイクの置かれた演台があり、隣の高校の生徒が、『部活動から学んだチームワーク』についてスピーチしている。
聞き取りやすい声、ここぞというときの強調、間の取り方、どれも大人が見せるお手本みたいだった。
この素晴らしいスピーチの後に続くのは、私だ。
どうしよう、という五文字が頭の中をよぎる。二か月前からついさっきまで、自分ならできるとすっかり信じていた。授業中の音読は得意だったから。
クラスメイトの誰もが、当たり前のように市内の高校生弁論大会の一年生部門に私を推薦した。先生も「あなたなら入賞を狙える」と言ってくれた。
それで、つい調子にのってその気になってしまっていたんだ。
あの自信が嘘のように、指先が小刻みに震えた。膝から下の力が抜けそうになり、立っているのが辛くなる。
「怖い」
私の小さな呟きは、ホール中に響き渡る大きな拍手の音に飲み込まれる。さっきまでスピーチしていた生徒に向けられたものだ。
会場に進行役のアナウンスが流れる。高校名と名前を呼ばれていよいよ自分の番がきたのだと理解したとき、ステージの上の無機質な演台が、得体のしれないモンスターのように見えた。
あそこまで歩いていかなくては。それからお辞儀をして、マイクに向かって暗記している文章を読み上げなくては。
そう思い、足を一歩前に進める。
ステージの床はこちらをあざ笑うように鈍くテラテラと光っている。
ああ、いやだ。
会場の広さ、人間の顔が規則正しく並びこちらを見てくる感じ、頭上から降り注ぐ照明灯による熱、床から放たれるワックスのツンとした刺激臭……。
こんなの知らない。
でも、逃げられない。
私はなんとか演台の前まで足を進めて、頭を下げた。膝の震えが嫌でも目に入り、緊張しているのだとあらためて自覚する。
聞こえてくるのは、さっきよりも控え目な拍手の音。巣に逃げ帰る子リスのように、一目散にステージ袖に駆け戻りたい。
そんな思いを押しやり、体を起こす。
震える足に鞭を打ち、背筋をぴんと立て、ぐるりと会場を見渡す。ぱちぱちという音が止み、空気がピンと張りつめる。
私はゆっくりと口を開いた。
「みなさんは『地域のゴミ問題』と聞くと何を想像しますか?」
どこかにあるスピーカーが、私の声を会場中に響かせる。
ありがたいことに、最初の一文を言葉にすると、いくらか気持ちが落ち着いた。客席は想像していたよりも暗く、人の表情まではよくわからない。
これなら、大丈夫かも。
私は何度も練習した通り、ときどき語りかけるように、ときどき強調するように、スピーチを繰り広げた。
「そして……」
あ、やばい。なんだった?
スピーチも中盤に差し掛かったとき、突然、言葉が途切れた。文字通り、頭の中が真っ白になった。会場はシンと静まり返る。
まだ、間に合う。早く思い出さなくては!
ダメだ、でてこない。
ああ……。いっそのこと、ここら一帯が停電になってくれればいいのに。そうしたら、また後日やり直せる。
いや、そんなことを考えている場合じゃない。
思い出せ! 早く! 早く!
「無理!!!!」
叫んだ声は、市民会館のホールではなく、一人暮らしをしているマンションの一室に響く。ああ、まただ、とすぐに理解する。
「またか……」
私はベッドに寝そべったまま呟いた。
高校生のときの、思い出したくない黒歴史だ。しばらく見なくなっていたのに、ここ最近、また悪夢にうなされる理由はわかっている。
「はあ」
結局、あの後、文章を思い出すことはなかった。脳裏に浮かびかける言葉は焦るほどに消えていった。まるで、さっきまで仲良くしていた文章たちに、一方的に裏切られたような気分。
一分、二分、三分、そのくらい経ったかもしれない。ステージ袖からスーツを着たスタッフがやってきて、事前に提出してある原稿を静かに置いた。
私は無我夢中でそれに目を通し、再びマイクの間で口を開いた。
おわった、と思いながら……。
もちろん結果はランク外。最優秀賞をとったのは、私の前にチームワークについてスピーチしていた生徒だった。よりによって、こんなできる人の直後になるなんて……。授賞式ではホール中の拍手の音を聞きながら、自分の運も呪ったっけ。
学校では、誰も弁論大会のことに触れてこなかった。会場にいた友人のカレンは「残念だったね」とだけ言って慰めてくれた。このまま、あの恥ずかしい出来事は誰にも知られず、入賞できなかったという結果のみが伝わればいいのに。
そう思った。
でも、現実は厳しいもので、二年生、三年生のときの弁論大会には、誰も私を推薦しなかった。
みんな、私に何があったのか、きっと知ってるんだ。よくよく考えれば、こういうのって保護者や他校の友達経由で、すぐに広がるから。
そのことが、みじめでたまらなかった。
もしも、二年生や三年生のときに推薦してもらえていたのなら、私は思い切ってリベンジできていたかもしれない。そしたら、今こうやって悩みの種になることもなかったのに……。
仮に、インストラクターとしてデビューすることになり、同じような状況になったら、と思うとぞっとする。
例えば、レッスンの構成を忘れ、あたふたするとか。
どうしても思い出せなくなったら、私はきっと予定終了時刻よりもずっと早くレッスンを切り上げるだろう。
そうしたら、どうなる?
月額費を支払って通ってくださっている会員さんは失望するに違いない。フロントではクレーム対応に追われ、スタッフはひたすら謝罪を求められる。うちの評判も落ちて、そのまま入会者が減るなんてことにもなりかねない。
学生のときは、私がただ受賞を逃し、恥をかいただけで済んだ。でも、仕事は違う。
そのことを考えれば考えるほど、怖くなってしまう。
イヤな思い出から意識を逸らすように、枕元のスマホに手を伸ばす。彼からのメッセージが届いていることを知り、勢いよく上体を起こす。
「……なにそれ」
そこに書かれていたのは、仕事の都合が悪くなり、夕食の約束をキャンセルしたいという内容だった。
これで、今月は二回目だ。でも、大人だから仕方ない。
私は文句を言いたい気持ちを我慢して、了解のスタンプをひとつ返すことにする。
シュポンと軽やかな音を立てて、指をグッドの形にしているくまのイラストが送信される。そのくまは笑っているけれど、私の心は泣いている。
いつものことだ。
私は再びベッドの中にもぐりこむと、目をぎゅっと瞑り、胎児のように丸くなった。
今のメッセージもイヤな記憶も、いっそのこと夢ならいいのに。
この連載小説のまとめページ→「私にヨガの先生はできません!」マガジン
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

