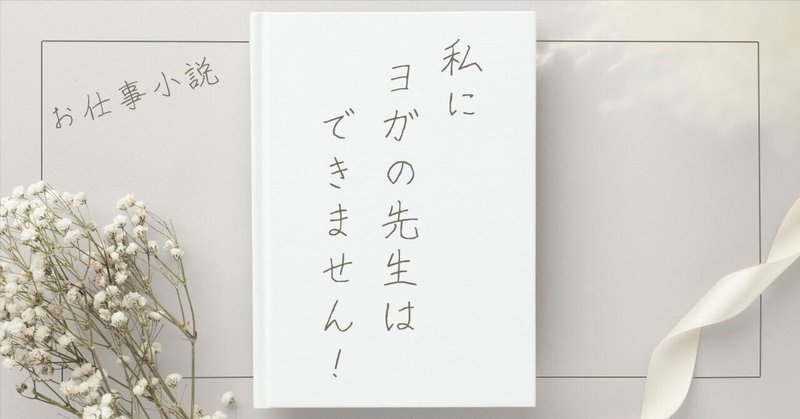
私にヨガの先生はできません!【第二話】ペンタスガーデン
【第二話:ペンタスガーデン】
私が勤務しているホットヨガスタジオ・Vegaは、三年前にリニューアルオープンしたビル『ペンタスガーデン』の三階にある。
メインストリートから一つ角を曲がったところにそびえるスタイリッシュな石の壁。そのキューブ型のビルを囲うように、濃い緑の植物がずらりと植えられている。
このおしゃれな雰囲気に惹かれて現職に応募したといっても大袈裟じゃない。だって、こういうビルに出勤するって考えると、胸が躍るもの。
それに、ホットヨガっていうのもなんだか素敵な響き。空きさえあれば、スタッフは無料でレッスンに参加OK! さらに、立ちっぱなしのフロントと、座りっぱなしの事務仕事、どちらもできるだなんて、バランスも最高だ。
そんな風に思って面接を受けたら、相性が良かったのか、運が良かったのかとんとん拍子で採用された。
「やったあーって思ったんですよ。そのときは」
私は『ペンタスガーデン』の一階に入っているカフェ・くじら座のカウンターでぼやいた。
二年前にオープンしたのだとえりかさんが言っていたっけ。
同じビル内にあるカフェなのに、意外と会員さんがいないと気づいたのは入社してわりとすぐの頃だ。考えてみれば、ヨガの前後にコーヒーを飲むことはあんまりないのだろう。
それ以来、勤務の前後や休憩中など、肩の力を抜いて一息つきたいときに来店するようになった。二人掛けのテーブル席が四つに、カウンター席が四つ。広すぎないところが気に入っている。
「あー。一年経ってみたら、予想していなかったお仕事を任された状況ってわけですね」
オーナーの一ノ瀬さんが笑うと、ミルクがたっぷり入ったココアみたいな色のエプロンが小さく揺れた。色素の薄い柔らかそうな髪もさらりと動く。
「そーです」
もう! 笑い事じゃないって伝えようと思ったけど、彼のほのぼのした笑顔を見て、まあいいかと思い直した。
なんだか、一ノ瀬さんを見ていると、懐かしくてあったかい気分になる。私には妹しかいないけれど、お兄ちゃんがいたらこんな感じなのかなって。
たぶん、私よりもいくつか年上。聞いたことはないけれど、二十七か八くらいじゃないかな。
「研修はもうはじまっているんですか?」
一ノ瀬さんが尋ねる。
「はい。昨日、一回目だったんです。突然、上司に命じられて困惑している私みたいな人がたくさんいるだろうって思ってたんですけど……」
「違ったんですね?」
私はうなずく。
「むしろ、ヨガが好きで、先生になりたかったって感じの子ばっかりで、びっくりです」
一ノ瀬さんが拭いている真っ白なお皿がつやっと光る。受講生たちのキラキラした瞳を思い出しそうになり視線を逸らす。
「へえ。笹永さんは? ヨガ、好きじゃないんですか?」
「好きですよ。でも、他の人の好きとは違うって実感しました。私のは……。こう、なんていうか、雰囲気がなんとなくいいみたいな感じ」
自分で言っていて、恥ずかしくなる。これじゃ、私が表面的なことしか見ていない、ぺらぺらな女性みたいじゃないか。
「あはは。まあ、いいじゃないですか。嫌いじゃないなら」
一ノ瀬さんはそう言うと、べつのテーブルのお客さんに呼ばれてカウンターから出て行ってしまう。
「はあ」
小さく息を吐く。
そろそろ、行かなきゃ。
今日は、十四時から二十三時までの遅番だ。私はトレンチコートを手にとると、レジへと向かった。
「あ! お疲れ様です」
カフェを後にして、エレベーター前ですれ違ったのは、フリーランスインストラクターとしてダンスやヨガのレッスンを担当しているナミさんだ。ショートヘアがよく似合う、スポーティな印象の女性。
もともとは、姉妹店のフィットネスクラブ・Altairの社員さんだったと聞いている。
「あ、笹永さん。これから出勤?」
「そうなんです。ナミさんはもう一本でしたっけ」
彼女はさっきまでうちで二本レッスンをしていたはずだ。これからアルタイルに移動してあと一本。
それが火曜日のルーティンらしい。
「そうそう。お互い、頑張りましょ」
「はい!」
軽く会話を交わして銀色のエレベーターにのりこむと、薄いオレンジ色の光に包み込まれる。「閉」と「3」のパネルボタンを押し、鏡を見て髪の乱れを直した。朝まで降っていた雨のせいか、いつもより毛がいうことを聞かない。
まあ、いいや。肩下のミディアムヘアは、仕事をするにはちょっと長い。あとでひとつにまとめるのだから。
気を取り直し、正面を向く。
私は長方形にきっちり切り取られたこの静かな空間が好きだ。なんだか非日常への秘密の入り口みたいで。
リン、と高級ホテルのベルみたいな音を立てて、エレベーターの動きが止まる。
エレベーターの扉が静かに開くと、視界いっぱいに温かみのある木に包まれた世界が広がった。
まず目に入るのは、ウッド調のフロントデスク。壁には「ホットヨガスタジオ・Vega」というロゴのオブジェがはめ込まれている。
「笹永さん。お疲れ様です!」
明るい声と笑顔で出迎えてくれたのは、新しく入ったばかりのアルバイトの天野さんだ。ポニーテールがよく似合う大学生。キャメルカラーのポロニットは、ここの制服だ。カジュアルになりすぎない色味とデザインがお店の雰囲気にマッチしていると、私は思っている。
「お疲れさまー」
波の音が心地良いリラクゼーション系のバックグラウンドミュージック。ほのかに漂うジャスミンのアロマの香り。
ここが私の職場、女性専用のホットヨガスタジオ・Vega。
ヨガというと、スピリチュアルなイメージを持たれることもあるけれど、実際はスタジオによってさまざまだ。ここで提供しているのは、瞑想も取り入れつつ、引き締めや柔軟性改善などを目的としたエクササイズ系。
それから、リラックスを目的としたレッスンも。
つまり、心と体の美と健康をサポートする、とっておきの空間なのだ。
「ねえ、思ってたんだけど……」
えりかさんが声をかけてきたのは、二人それぞれが黙々とパソコンに向かい合っていたときだった。
ホットヨガスタジオの仕事は、受付だけじゃない。お休み予定のインストラクターの代行探し、八人いるアルバイトのシフト作成、見学・体験の問い合わせ対応、月会費の未払いの確認など、いろいろある。レンタルウェアやタオルの洗濯や清掃も忘れちゃいけない。
「はい?」
私はキーボードを叩く指を止めて、えりかさんの方を見る。
「いと葉って、けっこうこの仕事好きよね」
えりかさんはそう言って、こちらを向いた。
「え、どうしたんですか? そりゃあ、好きですけど」
「ふふ。出勤してくるときの表情見てると、そうなんだろうなって思ってた」
「なんだかそれ、恥ずかしいですね」
私は思わずえりかさんからパソコンへと視線を戻す。
「いいことでしょう?」
「そうですけど。あ、それで、なにか思いついたんですか?」
えりかさんはなにも考えずに仕事中に話をふってくるタイプじゃない。
「それなのに、どうしてレッスンだけ、かたくなに嫌がるのかなって」
「……あー」
私は口ごもる。
「あ、言いたくないなら、いいの。まあ、フロントとレッスンじゃ、そもそも種類が全然違うものね」
こちらの様子を察したのか、えりかさんはさっと身を引いて、再びすらりとした指でキーボードを叩き始めた。
察しがいい、と思った。
たしかに柔軟性は心配していることのひとつ。前屈も、後屈も、側屈も自信がない。でもそれ以上に、私には気がかりなことがあった。えりかさんになら話してもいいかもしれない。そう思うものの、わざわざ人に言うようなことでもない気がした。
会話はそこで終わり、私達がスタッフルームと呼んでいる小さなオフィスには、カタカタとキーボードの音だけが響く。
フロントとスタッフルームを隔てた扉の向こうでは、ときどきアルバイトスタッフの天野さんと会員さんの笑う声がする。
いつものありふれた仕事風景。たまにクレームがあったり、トラブルが起こったりもするけど、だいたいは穏やかに時間が過ぎていく。
私の前職は事務職だ。短大卒業後、二年半働いた。
デスクがぎちぎちに詰められた狭いオフィスで黙って作業する日々。電話がけたたましく鳴る音や、古いコピー機が苦しそうに紙を吐き出す音を聞きながら、ただただ書類を作っていたっけ。
ほとんど誰とも話さずに淡々と作業をする。むしろそういうのがいいって人もいるけれど、私にはあまり向いていなかった。
あのときと比べると、やっぱりこの職場はありがたい。なにより好きだ。でも……。自身がヨガのインストラクターとしてレッスンを持つ、となると話は違ってくる。
「いと葉。じゃあ帰るから、あとよろしくね」
今日は平日だから、私とえりかさんとで交替制のシフトだ。社員は私たち二人がメイン。他はアルバイトスタッフだから、二人ともが出勤するときは、どうしても九時から十八時の早番と十四時から二十三時までの遅番に分かれてしまう。勤務時間が長く重なるのは、営業時間の短い土日や祝日、それから休館日くらい。
えりかさんはこの後、とあるアパレルメーカーのモデル撮影があるらしい。流行に疎い私でも聞いたことのある、有名なブランドだ。
しっかりケアされているであろう美しいウェーブヘアを揺らし、ヒールの音を鳴らし、彼女は颯爽とスタッフルームを去っていく。
「いいなあ。美人だし、なんでもできて」
ぽつりと呟いた声は、店舗内に流れるヒーリングミュージックにかき消されていく。顔が整っていて、現役モデル。おしゃれなビルにあるホットヨガスタジオに勤務していて、仕事もできる。なにげない日常を切り取っただけで、こう、なんていうか映える。
なんだこれ。まるで、ドラマの主人公じゃないか。そういえば、週末はデートだって言ってたっけ。
私はというと……。
付き合っている彼からのメッセージは一昨日から届いていない。まだ半年しか交際していないのに、もうそっけないなんて。最初の頃は、よく食事やドライブに誘ってくれていたのに……。
はあ、とため息を吐く。
「えりかさんには、悩みとかないんだろうなあ」
そう呟くと同時に、チリン、チリンと呼び出しベルが鳴る。フロントにいる天野さんからのSOSだ。
私は急いで立ち上がり、スタッフルームからフロントへと飛び出した。
この連載小説のまとめページ→「私にヨガの先生はできません!」マガジン
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

