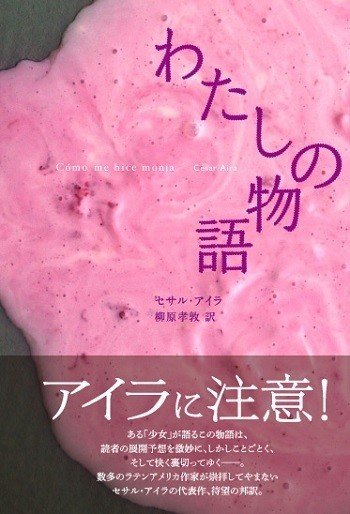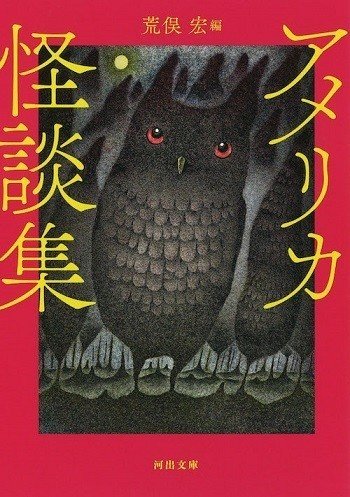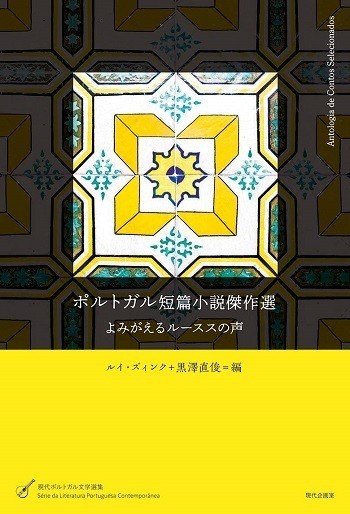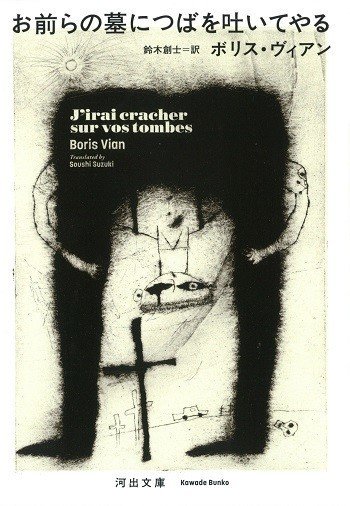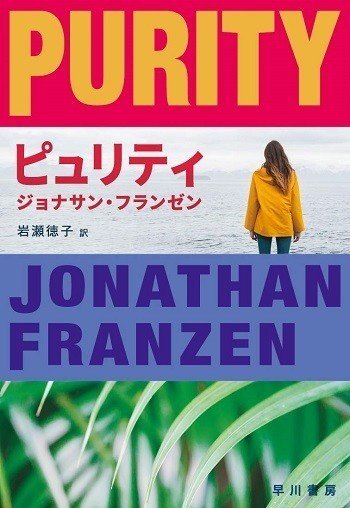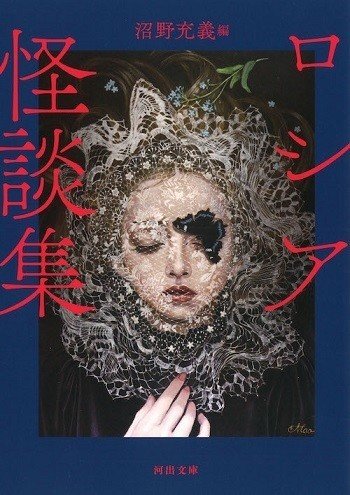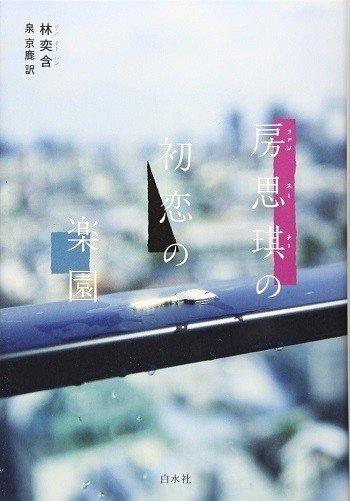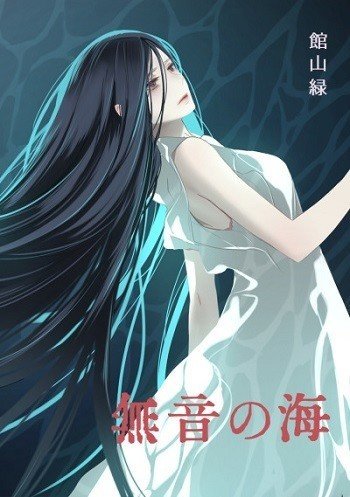【読書備忘録】わたしの物語から無音の海まで
色々小説を読んでいると、体力を奪う夢魔のような作品に出会うことがあります。読書中は精神を掻き乱されて、中断していても心は休まりません。そして、読書を再開するさいには自分を奮い起こしてきたるべき動揺に備えます。当然読了後にはドッと疲労が出ることになります。
こう話すと否定的な印象を抱かれる人もいるでしょう。読んでいて疲れるのはプロットが破綻していたり悪文だったりするせいではないのか、と。実際は逆であることが多いです。ここで語る動揺とは筋・人物・表現といった物語の構成要素が濃厚であるが故に生じる波紋のようなもので、往々にしてジャンルの枠を超越し、独自の文学観・世界観で構築された大作を読んでいるときに体験します。何度もこうした「疲労をともなう傑作」に出会ってきました。もっともあくまで個人的な感覚ですし、精神に波紋を起こさないタイプの大作もたくさんあります。だから波紋の度合いが評価の基準になるとは限らないと断らせていただいた上で「面白さの感じ方にも色々あるのですよ」と一例を紹介してみました。物語で疲れることは必ずしも悪いとは限りません。読者を疲労させ、途中で逃げることを許さず、覚悟を決めさせる驚異的(脅威的)な物語とは類まれな発想力の結晶であり、この世に創出されたこと自体に大きな価値があると私は信じているのです。
* * * * *
わたしの物語
*松籟社(2012)
*セサル・アイラ(著)
*柳原孝敦(訳)
物語における事象に明確な答えを求める人は混乱するかも知れない。修道女の回想録として始まる『わたしの物語』は少女時代の体験談で構成されているのだが、彼女が語る事柄には常に違和感が付きまとう。ことの発端は序盤のアイスクリーム事件である。父親が買ってくれたアイスクリームを口に含むと、尋常ならざるまずさに少女は嗚咽を漏らす。けれども激高した父親は彼女の主張を受け入れず、無理矢理完食させようとする。癇癪を起こす娘と叱責する父親。構図だけならよくある風景ではある。ただ、圧力をかける父親の風貌が不気味で恐ろしく、溶けだしたアイスクリームが唾液のようで気持ち悪い。意地の張り合いを超えた悪魔との攻防戦を思わせる情景は妙にグロテスクである。果たして実際に奇妙なのか、それとも少女の語りがグロテスクな情景を描いているのか。物語の始めに感じる薄気味悪さは最後まで続く。少女の名前はセサル・アイラ。女性でありながら周囲の人は男性として接しており、語り手に対する疑念は深まるばかりである。ちなみに作者のセサル・アイラ氏は男性だが、本人曰く本作品は「自伝的小説」らしい。自伝であることと自伝的であることは別物とはいえ、フィクションの枠を超越し、意外な結末で読者を呆然とさせる『わたしの物語』は粘液のごとく記憶にまとわり付く。
アメリカ怪談集
*河出文庫(2019)
*ナサニエル・ホーソーン(著)
ヘンリー・ジェームズ(著)
ハワード・フィリップス・ラヴクラフト(著)
アルフレッド・ヘンリー・ルイス(著)
メアリ・エリザベス・カウンセルマン(著)
ヘンリー・S・ホワイトヘッド(著)
メアリー・エレノア・ウィルキンズ・フリーマン(著)
イーディス・ウォートン(著)
アンブローズ・ビアス(著)
エドガー・アラン・ポオ(著)
ベン・ヘクト(著)
レイ・ブラッドベリ(著)
デヴィッド・ヘンリー・ケラー(著)
*荒俣宏(編訳)
佐藤清(訳)
鈴木武雄(訳)
谷口武(訳)
野間けい子(訳)
奥田祐士(訳)
飯島淳秀(訳)
野崎孝(訳)
吉田誠一(訳)
伊藤典夫(訳)
怪奇幻想文学と宗教は不可分の関係であり、キリスト教に影響されてきたヨーロッパの怪談を起源とする近世アメリカ怪奇小説も例外ではなかった。けれどもアメリカでは疑似科学やオカルトをとり入れた独自の心霊学が構築されていき、怪奇幻想小説・推理小説・SFなどの興隆に多大なる貢献をしたエドガー・アラン・ポオを始め、恐怖のかたちをジャーナリスティックな視点で表現したアンブローズ・ビアス、異次元の怪物と超常現象を織り交ぜて宇宙的恐怖を創造したハワード・フィリップス・ラヴクラフトといった偉大なホラー・アーティストが誕生した。中には世界的SF作家として愛読されているレイ・ブラッドベリの名前も含まれている。錚々たる顔触れだ。博覧強記の荒俣宏氏によって編集された『アメリカ怪談集』は、アメリカにおける怪談の潮流を伝え、その魅力を饒舌に語る贅沢な詞華集である。収録されている一三編の恐怖譚は国境も時代も超えて、現代日本で暮らす私たちにも強烈な印象を残す。
ポルトガル短篇小説傑作選 よみがえるルーススの声
*現代企画室(2019)
*ルイ・ズィンク(編)
黒澤直俊(編訳)
*マリオ・デ・カルバーリョ(著)
ヴァルテル・ウーゴ・マイン(著)
ゴンサロ・М・タヴァレス(著)
イネス・ペドローザ(著)
ドゥルセ・マリア・カルドーゾ(著)
ジョルジュ・デ・セナ(著)
テレーザ・ヴェイガ(著)
テオリンダ・ジェルサン(著)
ルイザ・コスタ・ゴメス(著)
エルベルト・エルデル(著)
ジョゼ・ルイス・ペイショット(著)
リカルド・アドルフォ(著)
*木下眞穂(訳)
近藤紀子(訳)
後藤恵(訳)
上田寿美(訳)
水沼修(訳)
残念ながらポルトガル文学は日本に浸透しているとはいいがたく、現代の重要な作品は未訳のままという。そこで現代ポルトガル文学を牽引する作家たちの作品を翻訳する企画が生まれ、現代企画室より現代ポルトガル文学選集として刊行されたのが本書『ポルトガル短篇小説傑作選』だ。しかし本邦に現代ポルトガル文学の専門家を欠いていることもあり、翻訳作業は困難を極めたようである。巻末の解説ではアドバイザーを務めたリスボン大学教授のルイ・ズィンク氏を始め、多数の翻訳者と校閲係を交えた訳出の過程が語られていて、大がかりな計画をささえる関係者の苦労がしのばれる。実際自分も『ガルヴェイアスの犬』を読んだのでジョゼ・ルイス・ペイショット氏の名前は知っているけれども、ほかの作家は初めてお聞きする方ばかりである。本書を読まなければ知らないままだった。それだけに厳選された一二編の佳品を拝読する機会に恵まれたことを幸運に思う。民主化革命前後の時代を舞台とした鮮烈なもの、不遇な人生を歩んできた女性が過去をふり返るもの、コミカルでありながら底知れない恐怖を覚えるもの、理不尽なまでに切ない恋の行方を語るもの。この『ポルトガル短篇小説傑作選』には彩り豊かな物語が織り込まれており、読者を飽きさせることはない。これも編集・翻訳に携わった方々の努力の賜物だろう。現代ポルトガル文学がますます身近な存在になることを願う。
ダイヤモンド広場
*岩波文庫(2019)
*マルセー・ルドゥレダ(著)
*田澤耕(訳)
カタルーニャ文学を象徴する恋愛小説であり、生前のガブリエル・ガルシア=マルケスもスペイン語翻訳版と原文カタルーニャ語版を読み込み、惜しみない賞賛の言葉を送った。おおまかな筋はクルメタことナタリアの半生に迫るものである。野生児のまま大人に成長したようなキメットとの結婚。命がけの出産。家中を飛びまわる鳩たちの飼育。家庭を切り盛りする中でナタリアはキメットのわがままな言動に悩まされ、次第に神経を弱らせていく。そして内戦の勃発により彼女はさらなる苦境に立たされてしまう。終わりの見えない武力衝突に怯え、失望と憧憬の念を抱えながらも生きる道を模索するすがたには胸を締め付けられる。戦争がもたらす悲惨な現実に恋愛を詩的に織り交ぜた『ダイヤモンド広場』は著者が公言する通り恋愛小説に相違ないが、優れた戦争文学にも含められるのではないかと私は感じた。また、本作品はカタルーニャ語で書かれている点も重要である。ロマンス諸語であるカタルーニャ語にはフランコ政権時に排斥されてきた歴史的背景があり、解説によればカタルーニャ語の潜在的読者は六〇〇万人程度。それでも文学を通して母語を語り続ける作家は存在する。今は亡きマルセー・ルドゥレダもその一人だった。
物語は人生を救うのか
*ちくまプリマー新書(2019)
*千野帽子(著)
人間とは意味付けをかさねることで事象を把握する生きものである。意味付けする行為とは因果関係を作ることであり、ときには辻褄を合わせるため存在しない事物を生むこともある。人は日常的に物語を構築している。千野帽子氏は前著『人はなぜ物語を求めるのか』で、こうした物語化の構造を噛み砕いて解説した。今回の『物語は人生を救うのか』は前著で書けなかったテーマをとりあげているので、続編よりはA面に対するB面に近い。このB面では前回同様物語論を基礎としながら、虚構表象(フィクション)と非虚構表象(ノンフィクション)、偶然性と必然性の具体的な相違点に触れるとともに、自分あるいは他者にもたらされる物語化の影響を解釈していく。物語化とは個人だけの問題だけではなく、社会に根付いている一般論もまた物語化された概念であり、往々にして明確な根拠を欠いたまま人の行動に干渉するものだ。文中ではこの一般論を個別の理解をささえる図式・世界観・人間観とした上で、如何なる影響を及ぼすのか具体例を交えて説明される。物語は常に身近にあるものなのだ。
お前らの墓につばを吐いてやる
*河出文庫(2018)
*ボリス・ヴィアン(著)
*鈴木創士(訳)
報われることも救われることもない復讐の行く末を、乱暴に蹴り飛ばすような口語文で描き尽くした飽くなき憎悪の物語。人種差別が横行する中、黒人である弟を抹殺した白人に復讐するため本屋の雇われ店主として町に滞在し、表面的に溶け込もうとするリー。顔見知りになった青少年たちと乱痴気騒ぎをしていると、彼の前に上流階級の美しい白人姉妹が現れる。憤怒と情欲をアルコールに浸したようなリーの激情ぶりはカタルシスを感じるほど胸に響く。ここには黒人差別が蔓延する終戦後の世相に対するボリス・ヴィアンの怒りが間接的に仄めかされているとも解釈できる。そもそも『お前らの墓につばを吐いてやる』はボリス・ヴィアンが架空の作家ヴァーノン・サリヴァン名義で出版したものなので、少なからず一石を投じる意図があったことは想像に難くない。けれども結果的に本作品は「社会道徳行動連合」なる右翼団体に風俗紊乱を理由に告発され、発禁処分と罰金刑に処せられるはめになった。国を問わず時代を問わず、意欲的で挑戦的な作品は叩かれる運命にあるようだ。本作品は後に映画化もされたのだが、ボリス・ヴィアンが書いたシナリオはプロデューサーに拒否されて別のシナリオが採用されることになり、彼はまたしても挫折を味わうはめになった。そして不満を抱えたまま映画試写会に出席すると、鑑賞中に心臓発作を起こして三九年という短い生涯を閉じたのであった。
ピュリティ
*早川書房(2019)
*ジョナサン・フランゼン(著)
*岩瀬徳子(訳)
家族間の人間関係で生まれるストレスを追究すると如何なる物語ができるのか。正解はないだろう。しかし、ピュリティ(純粋)と名付けられた娘を通し、とどまることなく流動する時代と、受け継がれる家族間の葛藤を緻密なプロットに組み込むことに成功した『ピュリティ』はまぎれもなく一つの回答である。奨学金ローンによる経済的困窮にあえぎながら、社会活動家たちとシャアハウスで暮らしているピップことピュリティ・タイラー。彼女はまさしくストレス社会に生きていた。母親は隠遁者さながら浮世離れした日常を送っており、父親は行方不明で名前も知らされていない。母親も父親に関して何も教えようとはしない。募るものは哀しみと焦りと苛立ちばかりである。ところが彼女は期せずしてリーク情報公開組織サンライズ・プロジェクトの主催者アンドレアス・ヴォルフの招きでインターンとして務めることになり、組織の関係者を始め、複雑怪奇な人間模様に踏み込んでいく。どこかにいるはずの父親を捜し続ける娘。複数の語り手を経て明かされる真実。その真実は実際に読んで噛み締めていただきたい。そして、一緒に思案に暮れていただきたい。人は如何にして家族になり、家族であり続けるのだろうか。冒頭に付け加えておこう。ジョナサン・フランゼンという現代アメリカ文学界の怪物が表現したピュリティ(純粋)とは、家族間におけるストレスの原因に対する回答であると同時に新たな問いでもある。
ロシア怪談集
*河出文庫(2019)
*アレクサンドル・プーシキン(著)
ミハイル・ザゴスキン(著)
ニコライ・ゴーゴリ(著)
ウラジーミル・オドエフスキー(著)
アレクセイ・トルストイ(著)
イワン・ツルゲーネフ(著)
フョードル・ドストエフスキー(著)
アントン・チェーホフ(著)
フョードル・ソログープ(著)
ワレリイ・ブリューソフ(著)
アレクサンドル・グリーン(著)
アレクサンドル・チャヤーノフ(著)
ウラジーミル・ナボコフ(著)
*神西清(訳)
西中村浩(訳)
小平武(訳)
浦雅春(訳)
栗原成郎(訳)
相沢直樹(訳)
川端香男里(訳)
池田健太郎(訳)
貝澤哉(訳)
草鹿外吉(訳)
沼野充義(訳)
沼野恭子(訳)
諫早勇一(訳)
不勉強故にロシアと怪談の組み合わせには不思議な印象を抱いていたのだが、象徴主義の流行した二〇世紀前後のロシアでは、数多くの怪奇幻想小説が書かれていた。リアリズム文学のイメージで凝り固まっていると、フョードル・ドストエフスキー、イワン・ツルゲーネフ、アントン・チェーホフといった作家たちが怪談を手がけている事実に意表を突かれることだろう。ところが彼らも霊的な恐怖小説の書き手なのだ。ドストエフスキーは『ボボーク』で墓場で歓談に興じる幽霊たちを、ツルゲーネフは『不思議な話』で死人に会わせる神業の持ち主を、チェーホフは『黒衣の僧』で優秀な学士に憑いた不気味な僧を、それぞれ卓越した文体でグロテスクなまでに表現している。このアンソロジーはロシア文学の奥深さを教えてくれる。もっともロシアの怪奇幻想文学は社会主義時代を迎えて下火になり、戦後文学に怪談が現れる機会は激減したようである。怪談集の大とりを務めるウラジーミル・ナボコフの『博物館を訪ねて』に一抹の希望を託して、また新たな恐怖譚が生まれることを願いたい。
房思琪の初恋の楽園
*白水社(2019)
*林奕含(著)
*泉京鹿(訳)
読者の世界観を揺さぶる痛烈な小説だった。台湾・高雄の高級マンションで暮らす房思琪と劉怡婷。文学を愛する彼女たちは、姉のような存在である許伊紋を交えて平穏な時間をすごしていた。ところが房思琪は下の階に住む国語教師李国華に目を付けられ、作文を読むという口実で誘い込まれて強姦されてしまう。一方、許伊紋は資産家である夫からのDVに苦しめられていた。三人称と一人称を交錯させる独自の文体で、鮮烈に描きだされる未成年者に対する性的虐待・家庭内暴力はあまりにも痛ましく、社会的地位のある加害者に事件を隠蔽される理不尽さは目もあてられない。しかし、冒頭で述べられる「これは実話をもとにした小説である」という著者の言葉が示す通り、この理不尽な世界はまぎれもない現実なのだ。ここで語られている実話性を著者自身に求めるのは早計と思われるが、社会に蔓延する悪意を小説技法で表現したことは意義深く、高度な技巧と併せて賞賛に値する。それだけに次回作が永遠に生まれないことが悲しい。幼少期から類まれな才能を見せてきた林奕含は、デビュー作となる本書を出版した二ヶ月後に自殺。二六年という短すぎる生涯を閉じた。
無音の海
*granat(2019)
*館山緑(著)
純粋故に残酷であり、残酷故に愛らしい。『無音の海』は妖怪伝承の残る離島で繰り広げられる凄惨な恋愛譚である。主人公は夜待島に住んでいる成本旋。彼は大栢島の中学校に通う身で、巳子島に住む従姉と定期船で通学する日々を送っていた。人付き合いには若干消極的で、SNSでも同級生と交流するのではなく、波止場で撮影した写真に一言添えてアップロードするだけである。彼の日常は淡々としたものだった。しかし、無人であるはずの波止場で撮影したある写真がきっかけで、平穏無事だった日々は一転して恐怖に染まる。島々に伝わるヨブコという海に出没する妖怪。どこかから流れてくる透き通った女の声。不穏な空気がじわじわと浸透してくる展開に恐れつつも引き込まれる。凄惨な恋愛譚という表現に戸惑う人もいるかも知れないが、恐怖と恋愛は両立するものである。純粋な愛とは非常にデリケートであり、制御できなければ血なまぐさい事態の原因になり兼ねない。館山緑氏の小説を読んでいると、青春期ならではの鋭敏な性質を通して、この紙一重の世界を垣間見ている気持ちになるのだ。
〈読書備忘録〉とは?
読書備忘録はお気に入りの本をピックアップし、短評を添えてご紹介するコラムです。翻訳書籍・小説の割合が多いのは国内外を問わず良書を読みたいという筆者の気持ち、物語が好きで自分自身も書いている筆者の趣味嗜好の表れです。読書家を自称できるほどの読書量ではありませんし、また、そうした肩書きにも興味はなく、とにかく「面白い本をたくさん読みたい」の一心で本探しの旅を続けています。その旅の中で出会った良書を少しでも広められたい、一人でも多くの人と共有したい、という願望をこめてマガジンを作成しました。
このマガジンはひたすら好きな書籍をあげていくというテーマで書いています。小さな書評とでも申しましょうか。短評や推薦と称するのはおこがましいですが、一〇〇~五〇〇字を目安に紹介文を記述しています。これでももしも当記事で興味を覚え、紹介した書籍をご購入し、関係者の皆さまにお力添えできれば望外の喜びです。
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。