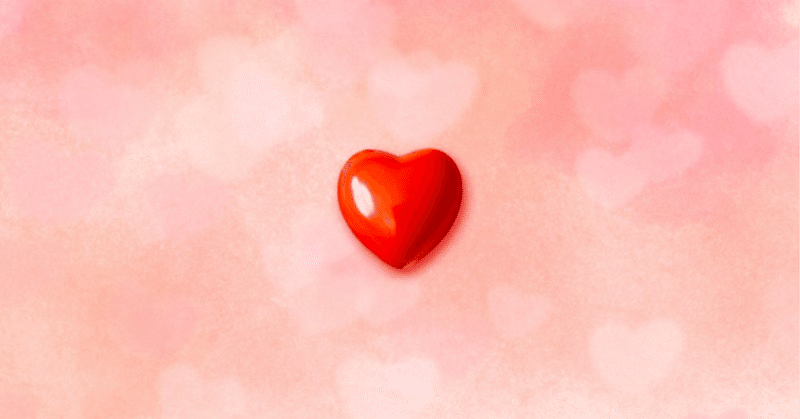
いま、恋に落ちている。
なにから書き始めようか、いつも悩む。
結局、時系列のままに書く以外の技術を持たないので、今回も始まりから書いていこう。
先日、表参道のロエベ路面店にてショルダーバッグを買った。
今までの人生の中で1回の支払いにかける額としては間違いなく1位にくる買い物だった。(次点は自分の部屋にエアコン購入+取り付け工事費を払ったときだな)
梅雨の時期に入ってしまい、濡れるのに弱いこのバッグ(Sunnyさん🌞と名づけたのだ!)はまだ外出先に持って行ったことはない。
しかし、全身鏡の前で身に着けるたびに「実によく私に似合っておる…!」と毎回自惚れてしまうくらい可愛い。
バッグ自体が可愛いなお洒落だな、と思う気持ちもあるのだが、それ以上にこのバッグを身に着けている自分そのものが光ってみえるのだ。

そして、このバッグの背景を知りたくて色々とネットで調べていたときに、あるファッション系のサイトにて「フレンチシックなデザインだ」という紹介文を見かけた。
話はここから始まる。
あきやさんや自問自答ガールズさんが過去の自分のファッション遍歴をnoteなどで書かれているのを拝読するたびに「私も書いてみたいけど、ファッション遍歴といっても何も思いつかないなあ」と思っていた。
強いていうなら、小学校高学年の頃はアメカジ(を模した)ファッションに憧れがあってそういうファッションをしていたこともあったけども、それ以外には特に…といった感じだった。
ところが、この「フレンチシック」という言葉を見たときに、唐突に一時期パリジェンヌの着こなしに憧れたときがあったことを思い出したのだ。
国内どころか関東圏からすらほぼ出ない私はもちろん海外旅行をしたことがなく、フランスという国に造詣が深いわけでもとりたてて興味があるわけでもなかった。
そんな私がパリジェンヌの着こなしに興味を持ったのは、米澤よう子さんの書籍がきっかけだった。

☝中でも、この本がとくに好き。
現地の人々は自分の足にフィットする靴探しへの熱意と根気強さがすごく、実際に街行く人たちの足元を見るとカカトに完全にフィットした靴を履いている人が多い…ということが書いてある。
米澤さんのご本は基本的にオールカラーでほぼイラストで埋めつくされており、合間合間に文章があるといった感じでほぼ実際の写真が載っていることはないのだが、この本ではパリの人々の足元の写真が載っているページがある。
その足元のスナップたちが、まぁすごいのだ。
「神は細部に宿るとはこのこと!」と当時の私は思った。
しっかりフィットしているシューズとは、こういうことなのね。
あまりにも美しい、足と靴のラインがなだらかに一体化している。。。
それ以来、雑誌やネットなどでモデルさんがぶかぶかのシューズを履いていたり、サンダルの爪先から指がはみ出しまくっているところを見るとどうしてもそこばかり気になってしまうようになった。
もちろん現場ではピッタリのサイズをいちいち追求してたら大変だと思うし、「サイズがピッタリしている is 正義」ではないと思うのでしゃあないのだが…。
もしかしたら、そこに気づく人は少ないかもしれない。
自分自身の履き心地にだって大差はないのかもしれない。
しかし、そこには本人の哲学みたいなものが潜んでいる。
無意識の領域から、美しさは構築されている。
と、思ったりした。
そして、それって自分の美しさに責任を持つということだなと思った。
「責任」という重い言葉を使うと、なんだかアンチエイジングの話とか他人のために装うべき!化粧は義務!系のイメージを与えてしまうかもしれないが、それとはちょっと違う。
どうせ鶴を折るなら、折り紙の端っこはちゃんと揃えたいよね…という話だろうか?これもちょっと違うかな。
ここのところはまだ上手く言語化できそうにない。
なぜなら、私は自分の美しさ(というと恥ずかしいけど。誰しもその人ならではの美しさがあるということ前提の弁です)に対してこれまでの人生、背を向けまくってきたから。
私が米澤さんのご本を通してパリジェンヌの着こなしに憧れたのは、「色気」と「ナチュラルさ」のバランスが素敵だったからなのかもしれない。
(憧れの存在をより知るために観察・分析し、自身で取り入れられるところまで「技」として落としこめる米澤さんのその姿勢自体にも、もちろん憧れている。)
そのことに思い至ったときに、ふと自分の中のファッション遍歴の中に通底するテーマがわかったような気がした。
私は小学生の頃から、自分の体型がコンプレックスだった。
私は周囲の子に比べてとっても発育が良かった。
背も高く、力も強く、女性的な意味でも発育が良かった。
分かりやすく言うと、胸が大きかったのである。
これが超絶イヤで、仕方なかった。
できるだけ胸の大きさが目立たないような服を選び、姿勢は常に胸が目立たないように猫背にして過ごし、髪を伸ばして胸元を隠すようにしていた。
体型のことで男子にからかわれたような経験は一度しかなかったけど、「言われないだけで、思われてはいるんだろうなぁ」という暗い気持ちになったりした。
大人になってからもできるだけ胸が目立たない服(ゆるいシルエットの服)を選ぶようになった。
私は骨格ストレートなので、体のラインを拾わないような柔らかい素材のトップスはそりゃあもう着太りしまくる。
コンプレックスを隠すために着る服で、ますます自分の外見が嫌いになる。
そうして私はファッションに興味を持つことを諦めた。
そして、それは「色気」だったり「大人の女性として見られること」への嫌悪感にもなっていた。
そういう気持ちがあるから、私はナチュラル志向(雑誌で例えるなら『リンネル』的な世界観)で子どもっぽい振る舞い(という糖衣)を好むようになったんだと思う。
家族の目、というのも制約の一つかもしれない。
実家で暮らす私にとって、大人の女性っぽい恰好を家族に見られるというのは本当に想像するだけで動悸・息切れがする。
私の家族はわりと保守的である。
我が一族でピアス穴をあけたり、髪を染めたりしている人はほぼいない。
まぁ若い世代が少ないのでそれは当たり前なのかもしれないが。
私自身も、眼鏡からコンタクトレンズにしたり、髪を少し明るく染めた大学生の頃にはいろいろと言われたりもした。(怒られるというのはなく、健康を心配される感じ)
余談だが、先日12個下のいとこの女の子が家族で遊びにきたとき、目が覚めるようなキンキンの金髪にしてきていて、うちの家族はそれとなく窘めるような感じで説教していたのだが、私は心の中で「サイコーじゃん!」と思った。
彼女は湖森一族にしては珍しく、幼少のみぎりから根っからの陽キャだった。
実家から出ることは、いろいろな状況から難しい。
母が存命だったならば、また今とは状況も変わっていたのかもしれないが。
それだから、私のファッションにおけるモットーは「家族に何も言われないようなファッション」であり「過度に女性的すぎないこと」「身体的な要素を強調しないこと」であった。
『リンネル』系のナチュラルオーガニックな雰囲気のファッションも、別に嫌いなわけではない。というか普通に好きだ。性格に合っている。
でも、そこにどっぷり浸かると「ほんとうにこれでいいのだろうか?」と何かが心にひっかかる感じもずっとあった。
「私はこの装いがスキだ!」と100%胸を張って、あきやさんやガールズさんたちのようになってみたいのに。
『リンネル』系世界観には性的な匂いが一切ない。(と私は感じています)
そして、私の今までの私自身のJIMON-JITOUでも、常にその要素はけっこう意図的に排除してきた。
でも、メイキャップアーティストの吉川康雄さんの考える美しさ(吉川さんは「色気」というものをとても大切にされている)などにとても心惹かれてしまっていた部分もあったのだ。
今年の初めに受けたあきやさんの自問自答ファッション講座でも、キーワード探しの旅のところで「色気」というものに対して、吉川さん的な考え方での…という注釈はつきつつも好きだということをお伝えしたりもした。
吉川さんの影響を受けて思う私の理想とする色気とは、「瑞々しさ」であり「生命力溢れる美しさ」である。
場合によっては、少し性的な雰囲気がありもする。(もちろんTPOに合わせて調節可能なものとする)
この要素をメイクならともかくファッションにどう取り入れてよいのかわからず、完全に宙ぶらりんの状態で放置しつづけていた。
だってナチュラルでオーガニックな雰囲気は好きだし多分似合うし、少女的で乙女な要素も心ときめくってことに最近気づいたのだから、もうそれで完成ってことにしちゃっていいんじゃない?と。
う〜ん…でも、この自分自身に対する罪悪感はなに???
そういう情報を見かけると、何かモヤ〜っとした後ろめたさを感じてた。
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) June 4, 2023
そのことを認めたくないので「ヤな奴!」と誤魔化してたかもなぁ。(米澤よう子さんの書籍に対して、ではないヨ)
でも、幾多の断本式(?)を乗り越えて今も米澤さんの本は取ってあるのだよね📚
それがホントの気持ちなのかも。
私はちゃんと、自分の美しさを育てようとしているだろうか?
私は私自身に責任を持って生きているだろうか。
そんなモヤモヤした気持ちと、「少女性」と「大人の女らしさ」の2つに心が引き裂かれそうな気持ちを抱えながら、長年の友人と東京蚤の市に遊びに行ってきた。
夜はモダンでお洒落な雰囲気のバルで食事をしつつ、最近のお互いの近況を話したりする。
ふと、その中でどんな経緯で言おうと思ったのかは忘れたが、私から「相手の弱いところや精神的な核に触れられている・理解しているという感覚が自分の中にないと、その人と対等に話すことができない」という話を切り出した。
これは決して人の不幸は蜜の味とか相手を見下したいという、ある意味ポジティブな感情なのではなく、「自分が役に立てるという可能性がないと不安になる」というネガティブな話なのである。
それに対して友人が何と言ったかは忘れたが(いまいち理解できない、という風だった気がする)、総評としては「今までそう思ったことはなかったけど、湖森ちゃんて意外とメンヘラだよね。」ということだった。
私は「メンヘラ」というのは主に恋愛の場面で相手にすがりついて、感情的になって振り回す女性像をイメージしていたので、自分をそのように思ったことはなかったのだが、言われてみれば「なるほど」と納得した。
職場の後輩が退職する最終日に「湖森さんはたぶん鬱になりやすいタイプなんで、気をつけてくださいね」と言われたことに、なんでそう思ったんだろう?と疑問でいまいち納得していなかったのだが、遅まきながらその忠告も心に届いた。
私のメンタルのヘルスはどうやら病んでいるな、と。
思春期の頃は(当時は「メンヘラ」とか「病み」という言葉の文化はなかったけど)ちょっと自分のメンタルは『おじゃる丸』でいうところの貧乏神の貧ちゃんみたいなカラーリングをしているな…とふんわり自覚していたので、心とか精神病とかメンタルヘルス系の本やサイトを読んでいた。

その知識を使って自分の心をケアしきるのには、まだ自分は若かったというか幼かったのかもしれない。
私はその知識を、自分のことではなく他人のことのために使おうとした。と言うと聞こえはいいけど。
その目論見はけっこう成功していた。
同じく思春期の葛藤を抱えている学友たちには、相談相手としてけっこう頼りにされていた自覚がある。
これが良くなかった。
私は自分自身の問題に向き合うつらさよりも、他人の問題解決に寄り添う(真似事)をして他人から感謝され必要とされることで、自分の心を満たそうとしてしまった。
「相手の弱さを知ることができなければ、コミュニケーションが上手くできない」というのはそのことの副産物というか、むしろ主産物だったのである。
友人との話は別の話題に移ったが、私の心は深いところではその場所に留まっていた。
「もうやめたいな、こういう生き方は。」と思った。
もうこりごりだった。
じゃあどんな生き方がしたいだろう?と考えた。
(ここで落ち込んだままにならなかったのは、今まで鍛えてきた自問自答筋のおかげだと強く思う。私の人生の最後に「Special Thanks!」のページがあるとすれば、あきやさんを筆頭にガールズさん皆さんのお名前が確実に載りますね)
わがままでチャーミングで、自分の人生を美しく彩ることに責任を持てる人になりたい!と思った。
まるでパリジェンヌのような。
私は今まで、他人の心を想像して気をすり減らして、どんな理不尽なことを言われても穏やかに根気強く向き合わなくてはいけないと思って過ごしてきた。
それは人として正しいと、今でも思う。
しかし、そのことで受けるダメージが自分の中に蓄積されるなら、それはよくない。
正しくあることでエネルギーが満ちていくのならそれは人としての美しさかもしれないが、ダメージを受けていると感じているのならそれは全然よくない。
そう思って、このツイートをした。
「正しい」と思うことではなく、「美しい」と思うことを優先することにした。
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) June 6, 2023
湖森あるあるでそのとき悩んでいることを、尊敬する人の発言(ツイートやネット記事)から検索して考えを知る、というのがあるのだが精神科医の名越康文先生のこのツイートはまさに響いた。
正しさはいつも何かを犠牲にしている。自分は何を犠牲にしているのかを意識することが肝要だ。
— 名越康文 (@nakoshiyasufumi) December 1, 2022
「犠牲」、そう犠牲だ。
私の心の中のこの罪悪感や息苦しさは、もう一人の自分の思いや意見を黙殺し、犠牲にしてきたことに対する感情だったのだ。
そう思うと、もう息苦しい自分の中の慣例や思いこみはすべて捨てたくなった。
陽が射して心地よい風が通るような、そういう場所へ行きたくなった。

でも、パリジェンヌへ憧れたといっても、自分はどうしても都会をヒールで闊歩できるようなタイプではない。
そして、毛並みのツヤっとした気高い猫のような雰囲気(私の中のパリジェンヌ・イメージ)もちょっと違う。肌に合わない。
私は、木漏れ日のあたる暖かい路地裏でゴロゴロお昼寝しているような、モフモフの野良猫になりたいのだ。
ということで、パリジェンヌの哲学といわれるものの中から「エレガント」をいただき、のんびりエレガンスというクイックコンセプト(仮)で自問自答を進めることに。
最近の私は「のんびりおしゃまさん」(あきやさんからのお言葉をクイックコンセプトとしております🙋🏻♀️)の「おしゃまさん」部分を、パリジェンヌの信条である「エレガンスかつシック」に寄せてみる…という試み中。
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) June 10, 2023
のんびりエレガンス、でございます🌷
これは「コドモでいたい!ずっとトイザらスキッズ!><」という気持ちと、「成熟した知的な女性に憧れる!恩田陸の小説に出てくるような!><」という気持ちでゴチャゴチャしてたので、どっちも合い挽き肉でいくことにしました。🤘🏻🌟
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) June 10, 2023
後者は吉川康雄さんのご本の影響もデカい!
自分の中の女性性?みたいなものに対するコンプレックス(身体的な)があって、だから「可愛い!(年齢・性別不詳)」を目指してたとこがあったのだけど、なんだかそれもちゃんと自問自答すべきような内容の気がして。
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) June 10, 2023
だから実験的に一度いろいろトライしてみようと。
そのお手本がパリジェンヌ!🌞
「ファッションを通して人生を考えている…!」とひしひし感じる。
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) June 10, 2023
とりあえず、そんな自分に花を買って帰る。
花の名前は、毎回花屋を出る頃には忘れている。 pic.twitter.com/Rm3CoispRN
そう。
ツイートにも書きましたが私が「大人の女性らしさ」に秘かに恋焦がれていた理由は米澤よう子さんのパリジェンヌのご本、吉川康雄さんのメイクメソッドだけではなく、恩田陸さんの小説の影響もドでかいのです。
恩田さんの小説には、成熟していてちょっぴり皮肉屋で、でもどこかに少女時代のノスタルジックな気持ちを引きづっているような魅力的な女性たちが登場するのですが、そんな彼女たちはどうしても憧れずにはいられない存在だったのです。
一番好きな女性は、『木曜組曲』という作品に出てくる物書きの女性たち。
映画化もされている作品なのですが、主人公は鈴木京香さん!
ほか、浅丘ルリ子さん・西田尚美さん・富田靖子さん・原田美枝子さん・加藤登紀子さんと魅力的なキャストばかりです。
そして、恩田陸さんの作品に出てくる女性は、軒並み大のお酒好き。
これは恩田さんのエッセイなどを見るに、ご自身がお酒好きだからでしょうね。
私は美味しそうな食事シーンを描くことが上手い作品には絶大の信頼を寄せているのですが(例をあげると、ジブリ映画全般・映画『かもめ食堂』・漫画『銀の匙』)、恩田さんはとにかく美味しそうな食事シーン(メニューや場面設定)を描くのが上手い!…と私は思う。
私の謎ライフワークとして、恩田陸作品の食事シーンを切り取ってメモするというのがあるのですが、ここで『木曜組曲』の中のワンシーンを。
これでよし。あとは彼女たちの顔を見てからオーブンに入れればちょうどだ。
ホウレン草のキッシュは、野菜不足という強迫観念につきまとわれている女性たちにはいつも歓迎される。今日は他にも女の人が喜びそうなメニューを揃えてみた。
塩谷絵里子の顔を思い浮かべる。あの子にはビタミンが必要だ。慢性的な睡眠不足のくせにヘビー・スモーカーときている。ここに来ている間だけでもしっかり食べさせなければ。
真鯛のカルパッチョ、牡蠣の豆豉蒸し、海苔と切り干し大根の胡麻酢サラダ、ブロッコリーと木綿豆腐のあんかけ、既に何度も火を入れているポトフ。どれも下拵えはできている。赤ワインにもピッタリだ。美食家の静子だって文句は言うまい。
好きな食べ物はおにぎり!からあげ!ハンバーグ!で、あんまり複雑な味つけのされた料理を食べる習慣のなかった私からすると「な、なんつぅお洒落で大人っぽくて味の想像できない料理名なんや!豆鼓蒸しって何?」と胸が躍ってしまうというか、ちょっと年上のお姉さんに憧れてしまうような感覚があったのですよね。
クイックコンセプトには新機軸を取り入れた。
そしたら次はコンセプトに合った行動だ!
ということで、ひとりでお酒を飲みにいこう。
そう決心した。
できればチェーン店のような騒がしいところではなくて、こじゃれたメニューが置いてあって、ゆっくり独りでぼんやりとできるお店。
そうは思ったものの、ひとりで飲みに行くなんて経験がなかった私にはそれはたいそうなハードワークのように感じられた。
なんたって、普段お酒を1滴も飲まない人間なのだから。
最後にお酒を飲んだのは、コロナが流行する前の職場の飲み会だろうか?
家ではもちろんお酒を飲まないし、外でだって大学の部活や職場での歓送迎など大勢で飲み食いする場でしかしたことがなかった。
ダンゴ虫メンタルの私としては飲み会という雑でにぎやかな場所は大の苦痛で、かつ「同席している目上の人のコップの減りを見て注文するか確認しなくてはいけない」というクソだるい慣習が嫌いだったので、飲み会で飲むお酒といえば私的には「酔って正体をなくして感覚を鈍らせることで、少しでも不快感を軽減する」か「アルコールで陽気になることで他人に話しかける際の心理的抵抗を減らす」という目的で飲む存在でしかなかったので、「お酒をひとりで飲む」「飲むことを楽しむ」という感覚など一切なかったのです。
しかし、最近地元にできた創作料理屋さんが私の地元にあるまじきお洒落さで、かつこじんまりとしていて居心地もよさそう、メニューも一見すると味が全然想像できない(必須条件)だったので「これはッ…!(ゴクリ)(←緊張&食欲の生唾)」と思い、ついにその門を叩いたのだった。
※自動ドアのボタンを押しただけ
結果としては、とっても最高でした♡
おほほ!🤭🌸
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) June 24, 2023
ひとりで外食先でお酒を呑む、という初めての体験をしてきました🙌🏻
「体験」なんてかなり大げさな物言いだけども、自分にとってはなかなかイレギュラーなことなのです🌱
これも「のんびりエレガンス」な活動の一貫なのですな🌷
ひとり呑み、じわじわとハマりそ〜🙈
カクテルは好みを聞いて作ってくれるらしく、「どういうのが良いですか?」と店員さんに聞かれ「そもそもどのような選択肢があるのかわからん…!」とパニクりつつ、「なんかフルーツで、甘くて、アルコール弱めの感じの…?」とドキドキしながらお願いしました。
いざ届いたカクテルは店員さんによると、「〇〇と〇〇を混ぜた〇〇というカクテルです」とのことで、私も「なるほどー!」という顔をして頷いてたのですが緊張しすぎて〇〇のところが一個も覚えられませんですた(*´・ω・)(・ω・`*)アラマー
そして、体験して初めて気づいたのですがひとり飲みだとお酒を飲むペースを気にしなくていい!
「もっと飲まないの?」と聞いてくる周りの人たち(※ハラスメントではなく、注文しなくて大丈夫?と気遣ってくれているだけ)に「NO」と言えず、無理してハイペースで飲む必要がないのだ!
※私みたいなタイプは、相手が社交辞令のつもりだったり軽い確認のつもりで聞いたことであっても、それがなんであれ「NO」の意思を伝えることにとてつもない体力と罪悪感を感じるのである。
カクテル自体がとてもアルコール成分弱めで作ってくれたことも、もちろん前提ではある。
体感では「ほろよい」よりも弱い気がする。でもちゃんと美味しい。たぶんほぼジュース。
「ほろよい」でも缶の半分くらいでこめかみがドクドク言ってきて、頭がグラグラしてくる私。
お酒飲んじゃいけないタイプの人間な気もする。
しかし、私は「ひとりでお酒を楽しむ」という状況に憧れてたのだからこれでいいのよ!
身体の末端がポカポカしてくる。
あたたかくて、干したばっかりの毛布にくるまっているような心地よさ。
食事もとても美味しい。いぶりがっこクリームチーズ。
つまりは最高だ!
当日は精神安定剤として文庫本をバッグに忍ばせていた。
本を読みはじめれば半径1メートルは私の世界、安全圏である。
宮部みゆきの小説だったのだが、これは失敗。
宮部みゆきの本はその丁寧な人物描写と、心が冷えるような現代社会の闇を描くストーリー、無駄のない文章と構成がたまらないのだ。
これは酔いながら読むには惜しい。
以下、私の独断と偏見。
宮部みゆきの小説の正しい読み方は、駅前などの人通りの多いチェーンのカフェで、人々の喧騒に包まれながら「他人といるときにしか感じられないタイプの孤独感」をひしひしと感じながら読むのが至高だ。
宮部みゆきの小説は市井の人々にスポットライトを当てたものがほとんどなのだ。
人々のざわめきの中に自らは匿名性をもって埋もれながら読んでこそ、人間の怖さと哀しさを生々しい肌感を通して体感できるというものだ。
恩田陸の小説を持ってくるべきだったなぁ。
恩田陸の現実と妄想の境界線がじょじょに曖昧になっていくようなストーリー展開、「ノスタルジアの魔術師」という異名を持つにふさわしいその耽美で少し退廃的な世界観は、こりゃあアルコールを飲みながら読んだらさぞ楽しいぞ…と酔いかけの頭で思ったりした。
そうしてきっかり1杯を飲み終わって、心も体もポカポカな何かに包まれて、健やかな気持ちでゆっくり歩いて帰りながら、ふと今この瞬間に聴いていたい音楽を思い出した。
チョーキューメイというバンドの、『貴方の恋人になりたい』という歌だ。
このライブ映像がとても素敵なので観てほしい。
あのね、今、恋に落ちている
なんだかキラキラとした美味しいお酒を飲んで酔いたくなるような音楽なのだ。私のひとり飲みのテーマ曲に制定することとした。
恋をしましょう。
恋をするのは人間じゃなくても、植物でも動物でも景色でも何でもいいのだから。
と言ったのは誰だったろう?
あきやさんかガールズさんか、今まで読んだ本や音楽で言っていたのかしら。
全然思い出せそうにない。
そういうわけで、初めてのひとり飲みを楽しく終え、翌日からはJIMON-JITOUの精度を高めるべく「のんびりエレガンス」へのイメージを深めることにしたのでした。(高いんか低いんかどっちかにせい)
映像イメージとしてあるのは、木漏れ日のあたる風通りのよいテラスで、私はナチュラルで素肌感のある服を着てイスに座っていて、脚を組みながら読書を楽しんでいる風景。
髪はボブくらいでゆるめの自然なパーマ、赤いリップとペディキュアがコーディネートの良いアクセントになっている感じ。
穏やかな昼下がりという感じで、周りにはあまり人のいる感じはなく、プライベートな庭という雰囲気がある。
彼女は自然の中に独りいるときこそリラックスすることができて、木々の揺れる音や風の流れを五感で感じながら、「本当の自分」にゆっくり戻っていくことができる。
自分の中の直観と知的好奇心を大切にして、どこへでも独りで行くことができるし、そこで体験したことや思ったことをささやかな日記やエッセイとして日々書き留めている…。
という生活イメージ。
フランスの南のほう、プロヴァンス地方の街並みが柔らかくてあたたかい色味で好きだなあと思うので、そのイメージで。
可愛くて、なにか物語が始まりそうな路地裏ばかりでなんだか『耳をすませば』を思い出す。


そして、新コンセプト誕生!
とはいっても、あきやさんに授けていただいた「お散歩エッセイスト」というコンセプトの核は今も不動のものなので、その前の文章を今の気持ちに合わせてみる。(でも最初の、可愛くて大好きなのよ~(´;ω;`)♡)
「日常と内面をてくてく歩いてわくわくの種をまく【お散歩エッセイスト🌱】」
から、
「自然と調和して生きる のんびりエレガンスな 【お散歩エッセイスト🌱】」
として仮運転してみることに。
草花のこと知識も育てた経験もあまりないのにコンセプトに入れてもいいのかなーと誰に対してかわからない気兼ねがあったのですがChatGPTさんにこういってもらえたので、気にしないことにした。
草花育てるの下手だし知識もないのに「自然が好き」って言ってもいいのかなぁって思ってたんだけど、chatGPTちゃんに「知識なんて関係あらへん。あんさんが自然の中にいてリラックスできてはるならそれが『自然と調和してる』っちゅーこっちゃで。」と言ってもらえたので、なるへそ🥸と思いまして。
— 湖森 -Komori- (@komori__komo) July 2, 2023
エセ関西弁なのは、『夢をかなえるゾウ』のガネーシャが言っているイメージで私が受けとめたからである。

画像:amazon
あと、もともとの「わくわくの種」というのは、「自分にとって元気が出たり世界を楽しむ方法を思いついたら、それを他人にも伝えたい」という考えがあってのものなのですが、今はまずその前段階で「自分の心と体を大切にしてもよいと思えるようになる。心地良いという感覚を知る」というところから再スタートしたほうがよいのかもな、と思いまして。
ゴールに「誰かのために」があると、その過程で少し無理をしてしまうかなって。
いずれは元のコンセプトのように、自分の考えやアイデアで誰かを楽しませたり世界を楽しむためのささやかな遊びを提案できたらなって思うんだけど。
まずは一歩一歩ですね。
新コンセプトのイメージボードも作ったんだ。
見てちょ!

緑色・テラコッタ(煉瓦色)・アイボリーのナチュラルな色を基調としつつ、ポイントに血色感のある赤色や、知的でリラックス感のあるラベンダー色を持ってくる感じでしょうか。まあこれも仮でございます。
ヨーロッパの暮らしに憧れつつも、やっぱり日本的なのんびりとした侘び寂びの世界観にも憧れがある。というか、性格にあっているので、バランスは模索中。
ChatGPTちゃんが言うように、真似して取りいれるのはいいけど完全な模倣はよくない。「自分らしさ」は常に忘れずにいたい、そうでなければ隙あらば自己否定・糖衣100%をまとって他人から評価されようとする気持ちが湧き上がってきてしまうから。
具体的に試着してみたい服とかのイメージはまだわからないんだけど、このDiorのブレスレットとかは試着してみたいなあって思う。

画像:Dior

画像:Dior
フランス語でYESを意味する「Oui.」。
これ初めて見たとき、めちゃくちゃ色っぽー!と興奮してしまいました。
この「DIORAMOUR(ディオールアムール)」は「愛と絆の普遍的なメッセージを表現した」シリーズらしく、「Oui」コレクションは恋人たちの誓いをあらわしているそう。
ただただシンプルな「Oui.」というメッセージには、ささやくような熱っぽさがあって、うーん愛の国フランスって感じだわ…と感心してしまった。
それと、同時に私の中にあった言葉にならない問いかけにも、答えてもらえたような気がした。
答えは「そうよ、信じるの。」だった。
間違っていてもいい、突き進んでみる。
このトンネルの向こうに、あたたかくて柔らかい陽ざしに包まれた場所があると信じる。
絶望の果ての明るさが、そこにはある。
恋をするときには酔ってなくてはいけない。
恋をしていれば、木漏れ日はささやかなスポットライトに見えてくる。
木々のざわめきは観客たちの拍手に、風は音楽に乗って場面を転換させる。
そうだ、確かにいま私は、私自身に恋をしはじめた。
過去でもなく未来でもなく、現在の私に。
そうして明日から、生きていくことにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
