
まちをおこさず、残す。キャンプから紐解く、脱成長時代の地域振興論
いま、日本に何度目かのアウトドアブーム、キャンプブームが訪れています。
このキャンプをアカデミックな視点から考え、発信しているのが、國學院大学のランタントークという試みです。國學院の教授陣が教育、歴史、考古学などそれぞれの専門分野から、縦横無尽にキャンプを語っています。
このnoteは、より広い方々に「キャンプ×アカデミア」のおもしろさに触れてもらうことを意図した、いわば出張版。ランタントークにも登場する教授がもう少し柔らかい語り口で、自身のキャンプ体験なども交えながら話す入門編と位置づけています。
連載4回目に登場するのは、行政学、地方自治を専門とする、法学部の稲垣浩准教授です。

近年、空き地をキャンプ場として活用し、地域活性化の一手とする例が全国的に増えていますが、「そこにはいくつかの落とし穴がある」と稲垣さんは言います。
行政主導のこうした地域振興がうまくいかない理由とは。人口減少社会の日本で、地域振興とはどうあるべきなのか。父親が元行政職員というルーツを持ち、歴史研究からフィールドワークまで、幅広い手法で地方自治を研究する稲垣さんに聞きました。
行政主導の地域振興がうまくいかないワケ

── 「高度成長期から現在に至るまで、行政主導の地域振興にはうまくいかないことが多い」と稲垣先生はおっしゃいます。なぜでしょうか?
行政職員が専門家ではないからですよ。いや、福祉や土木の専門家はいるかもしれませんが、例えばリゾートの専門家なんて基本的に行政にはいないですよね?
1987年にリゾート法ができたことで、リゾート施設を作ると国から補助金が下りるようになりました。だからどこの自治体もこぞって開発に勤しんだわけですが、自治体の職員に限らず、当時の日本人にとってリゾートや余暇なんて言葉はほとんどなじみがありませんでした。だから見よう見まねでやるしかない。その結果、山にはスキー場、海辺にはマリーナ、それ以外にはゴルフ場といったように、似たような施設が全国で山ほど作られることになりました。
その後リゾート法は見直しが進められていますが、こうした問題の構図はいまも続いています。国や県から補助金を受けるために、他の自治体でもやっていることや、テレビやネットで権威付けされたようなもので構成されたプランばかり作ってしまう自治体は少なくありません。
そもそも「三割自治」と揶揄され続けてきた日本の自治体で、お金がふんだんにあるところなんて東京都くらいしかありません。となると、国や県など、どこかがお金を出してくれそうなプランを書いて出さざる得ない。そういうことが繰り返されているんです。
── ……いきなり重い話で始まってしまいました。
地域振興がうまくいかない理由はもうひとつ、自治体職員のあり方にもあります。「自治体職員」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?
── まじめで手堅いイメージ、でしょうか。
なぜ手堅くなるんでしょう?
── 失敗すると叩かれるから?
そうですね。ひとつのことだけで叩かれるのならまだいいんですよ。改善のしようがあるから。でも役所の職員の場合は、なにかをしようとすると、なにかに欠けてしまうことが少なくない。
たとえば、生活保護が必要な人を助けようとすれば、当然お金がかかる。すると「財源をどう考えているのか!」という意見に始まり、ときには「そんな人たちに税金を使ってほしくない」などと言って叩かれることもある。特にこの20年くらいは、税金をなにに使うかにみんなが厳しくなっていますから。そうすると余計に硬くなり、無難な仕事しかできない方向に向かいがちになる、というわけです。
行政とは、なにかとなにかをつなぐハブ

── すごくかわいそうな役回りという気がしてきました。
でも、どこから叩かれるか分からないということは、自然といろいろな方向に気を配るようになるとも言えますよね。
そもそも、「総合行政」と呼ばれる地方自治体の仕事は国の省庁とは違って、さまざまな分野にまたがっています。そこで働く職員も、若いころからいろいろな部署を異動して、あらゆる仕事をすることになります。そうすると、真面目に仕事をしていれば自然と、いろいろなつながりができてくる。
普通の住民でここまでのネットワークを持っている人はなかなかいないでしょう。もちろん、それぞれの仕事の中ではネットワークをお持ちでしょうが、分野、年齢、階層など関係なく、仕事を通じてすべてにまたがる地域のネットワークを作る機会を得るのは自治体職員だけです。
そうやって培ったネットワークを使ってなにかしようとするのか。それともどこから叩かれるか分からないからなにもしないのか。ここが分かれ目です。
要するに、自治体職員がハブとしての役割を強く理解し、活用しているところは成功するし、そうでないところはうまくいかないということなんです。

ハブとしての役割とはすなわち、なにかとなにかをつなぎ合わせることです。たとえば、一方にはうまい魚を釣れる場所があるとする。また一方にはきれいなお皿を焼く職人がいるとする。二つをつなげて料理を出せば、その町にしかない和食の店ができるかもしれない。
でも、彼らの役割はあくまでハブですから、その役割を自覚せずに主導権を握ろうとすると、途端に歯車が狂い出します。
── ランタントークに登場する埼玉県のときがわ町には、ハブとしての役割を全うする職員がいたということでしょうか?
あのインタビューを読んでもらえれば分かると思いますが、ときがわの職員さんは自分たちから積極的に「こうやろう」とはあまりおっしゃっていませんよね。
アイデアを持ってきたのは外の人たち。職員さんが行ったのは、持ち込まれたアイデアに対して場所や機会をちゃんと用意すること、そして、町にもともとあった林業という資源をつなげることでした。
── それまでに培ってきたネットワークを生かしたわけですね。
ええ。とはいえ、行政や職員に対して住民が過剰な否定感情を持っている町では、それも難しいでしょう。行政の無駄や不正をただすことは重要ですが、行政職員を潰しかねないようなバッシングは考えモノです。社会を持続的に維持していくためには、地域の人々が職員の活動を正当に評価できるのが理想だと思います。
キャンプ客を前に「名前」を失う町

── このあたりで、もう少しキャンプに絡めたお話も伺いたいと思います。キャンプブームもあって、空き地の有効活用として地方にキャンプ場を作る例が増えていますが、先生にはどう映っていますか?
都心から来るキャンプ客のマナーの悪さが問題になっていますよね。観光客全般の問題とも言えますが、キャンプ客には普通の観光客とはまた違った問題があります。
たとえば栃木の日光市なら日光東照宮など、観光客には必ずその土地のものが目的としてあるじゃないですか。でも、キャンプに来る客には、案外そうではない人も多いのではないでしょうか。
極論すれば、BBQさえできれば、ときがわ町であろうと奥多摩であろうとなんでもいい。そういったキャンプ客を前にすると、どの町もみんな色を失い、匿名になってしまうんです。すると「後は野となれ〜」みたいなことも起こりやすくなる。
── うーん、なるほど……。
「関係人口」という言葉を聞いたことがありますか? 地域や地域の人々と多様に関わる人々の数を指すのですが、以前はこれとよく似た意味の「交流人口」という言葉が盛んに言われていました。「交流」から「関係」へと置き換えられたのは、中長期的な関係にこそ価値があると考えられるようになったからです。
観光地には、リピート客が多いところがありますよね。同じ場所に繰り返し訪れると、地域や地元民との関係性が生まれ、さらにその土地への愛着が高まるでしょう。顔の見える間柄では、訪れる側も自分本位な振る舞いはできなくなりますし、地元の人もお客さんの期待に応えられる町にしたいと考えるかもしれない。けれども、キャンプやBBQができさえすればいいという場合はそうはいかない。匿名では中長期の関係を築くことはできませんから。
もちろん、キャンプに来る人たちがその町の経済を支えてくれるケースはありますよ。地元のスーパーなどには、夏のキャンプ客の売り上げに大きく支えられているところも少なくありません。しかし、それで利益を得るのはスーパーのオーナーくらいです。その裏では住民が皆、マナーの悪い客に対して苦い顔をしているかもしれません。
このように利益を得る人と不利益を被る人の両方が出てくると、町の中で分断も起きてしまう。とても、町ぐるみで訪れる人たちを優しく迎え入れよう、ということにならないのではないでしょうか。
── 匿名ではない、その町ならではのもので人を呼ばないといけないということだと思うのですが、そうした資源はどこにでもあるものでしょうか?
それは見方次第ではないですか? 一発当てよう、一大ブームを起こして儲けようと思えば、そんな資源はどこにでもあるものではない。それこそメディアを使うなりして、背伸びしたり、大きく見せたりしないといけなくなる。そんなことをいつまでも続けることは難しいでしょう。
結局、どういう施策を打つべきかは、自治体として、どれくらいの人に来てもらいたいのかによりますよね。
ときがわ町だって「そこにしかないもの」なんて特に多いわけではないですよ。ですから、おそらくはそんなにたくさんの人は来てくれない。でも、そんなには来ないからこそ、たまに来た人はゆっくりすることができる。山のことをよく知っているから、地域の木材をコモリバで活用することもできる。無理をしないから、地元の人たちにもそこまで迷惑がかからない。自分たちが町のことをよく知っていて、それを活かしながら無理をしないやり方でやっている、ゆえに持続可能なんです。

ときがわ町のキャンプ場、コモリバ
(写真提供:ときたまひみつきち COMORIVER)
ときがわ町のいいところは、変な商売っ気を持っていないところです。自分たちの町に来てくれる人に対しては、ちゃんと場所を提供する。森や林を始めとして、町のことならなんでも知っているから、相談に乗ることもできる。でも、それ以上の無理はしない。そういうことだと思うんですよ。
どれくらいの人に来てもらえれば「成功」と言えるのか。その基準を示すのは行政ではなく、政治です。政治ですから、その基準というのは常に変わり得る。たとえば、その時の町長がどう考えるかで、すべてが変わってしまうものなのです。
だからこそ、自治体職員はどちらに振れても対応できるようにしておかなければならない。そのために、ハブとしていろいろなことを知っておかなくてはならない。そうした行政職員の活動の積み重ねが、ひいては町の財産になっていくわけです。
私が聞いた範囲では、ときがわはそういうことができている町です。それが、いままでマイペースなまちづくりを続けてこられた要因なのだろうと思っています。
右肩上がりの成長ばかりが解ではない

── いろいろと地域振興が抱える課題を伺ってきましたが、先生から見て、いま注目すべき自治体をひとつ挙げていただくとすると、どこになりますか?
たとえば、大分県に臼杵市というところがあります。私の出身地でもあるこの場所は、ここ数年移住・定住などで一定の成果を出しています。ほかにも、市を挙げて有機農業の普及に力を入れていたり、医師会と連携した地域包括ケアの仕組みを構築したりと、地域全体を巻き込んださまざまな政策に取り組んでいます。
── 臼杵市が成功しているのはなぜでしょうか?
「おんせん県おおいた」というキャッチフレーズがあるように、大分と言うと温泉地を想像する方が多いと思うのですが、うちの町には残念ながら、別府や湯布院のような有名な温泉がありません。その代わりに古い城下町があり、美しい伝統的な町並みや文化がまだ残っています。
その大きな要因としては隣の大分市のように、戦後に商業や工業が大きく発達しなかったことで、街を大きく開発する必要がなかったからでしょう。開発から「取り残された」ことで人口も減り、高齢化も進んでしまいました。しかし、そのおかげで残すことができた古い町並みを目的に、外から人が訪れるようになりました。
最近では古い空き家に移り住んでくる人も増えましたし、古い民家や文化財を積極的に活用するようにもしています。地元のお年寄りも、毎日昔ながらの畑仕事に精を出す人が多く、大変元気です。
20年ほど前に当時の市長が「まちのこし」という言葉を生み出しましたが、現状を維持してきたことが、今日の臼杵につながる流れをつくり出しています。

臼杵の町並み
── 「まちおこし」ではなく「まちのこし」。
「まちおこし」をしようとするから、うまくいかないんです。打ち上げ花火のようにイベントを打って、限られたパイをみんなで奪い合う姿は見ていてつらいですよ。うちの町はときがわ町同様、そういう無理をしなかった。それが良かった。
── 国も企業も右肩上がりの成長を求める中にあって、「現状維持の思想」には新鮮な響きがありますね。
でも、誤解しないでいただきたいのは、現状維持というのは、決してなにもしなくていいという話ではないということです。
世の中が激しく移ろう中で現状を維持し続けるには、どうとでも対応できるよう、その町のことを常に知っておかないといけないし、ネットワークも作らないといけない。臼杵に「まちのこし」ができたのは、残してきた町に誇りをもち、その上で外ともつながり、自分たちの相対的な評価ができたからです。
臼杵の「まちのこし」にしても、ときがわのコモリバにしても、成功した要因は、町の人々が地元にあったものを大事にし、行政が新しい状況に合わせて、うまくつないだことが大きかったのです。

Z世代、悟り世代などと呼ばれるいまの学生と接していて感じるのは、彼らは基本的に無駄なことをしたがらない、ということです。最短距離で答えを知りたがって、直接自分に役立つこと以外にあまり興味を示さないことが多い。
けれども、ハブになるというのはそもそも、その時点ではなにに役立つか分からないものを集める作業であるわけです。いつ、どこで、なにとなにがくっつくかなんて誰にも分からない。分からないが、集めてはおかないといけない。
── 答えばかり求める人からすれば、すごくつらい仕事に映るでしょうね。
そう。でも逆に言えば、日常的な営みを通じてネットワークを作れている人からすれば、そんなにつらいことなんてないはずですよ。どんなことがあっても対応できるわけですから。「ここがダメなら、こっちはどうか」と動くことができるから。
問いに対して一対一対応で答えを求める人には、そういうネットワークを作るのはなかなか難しい。だから、結果的に可能性が狭まることになり、自分を苦しめることになるんです。いまの学生にもそういうことを伝えたいと常々考えています。
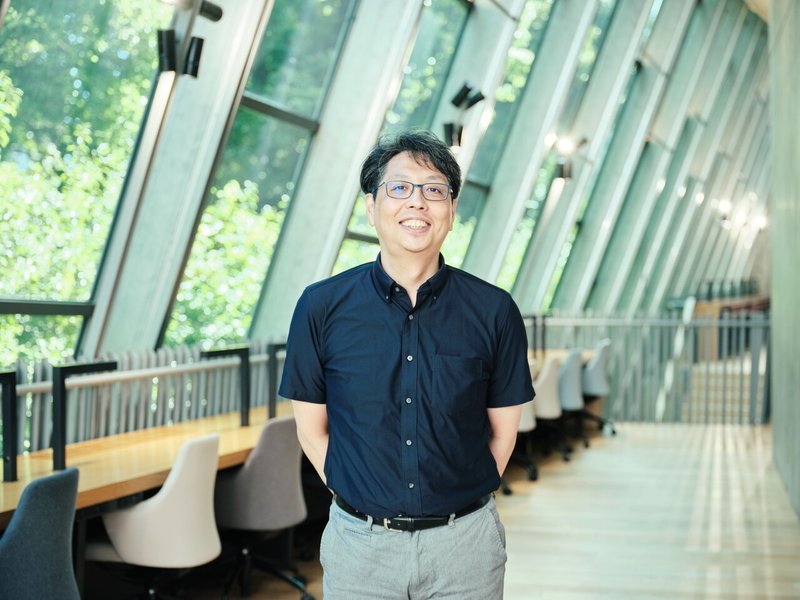
■稲垣先生によるランタントーク本編はこちら
國學院メディアではさまざまなジャンルの教授陣による、記事を公開しています。
本記事と合わせてぜひご覧ください
執筆:鈴木陸夫
写真:藤原慶
編集:日向コイケ(Huuuu)
