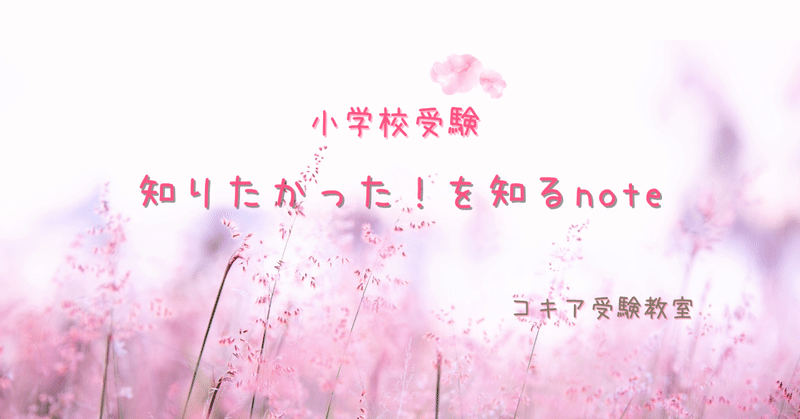
小学校受験 話を聞けない、にどう対応するか
❗️特典多数❗️
有料記事が全て無料で読めるKOKIA members labを是非ご検討ください♡
こんにちは。コキア受験教室の桜井です。
突然ですが、お子様はしっかりお話を聞けていますか?
今日は、もうすっかり完成しているご家庭には全く関係のない話、そうでないご家庭には少し耳の痛い話かもしれません。
というのは、小学校受験において、「お話を聞けない」というのは最も致命的な短所だと言っても過言ではないからです。
小学校受験の考査は、(一部の小学校を除き)字を読めることを前提としていないため、発問は全て口頭で行われます。もちろんペーパーだけではなく、全てです。
話が聞けない子は、全分野において圧倒的に不利な状況ということですね。
ペーパーだと、記号•色間違えに始まり、「使うものを選びましょう」と「使わないものを選びましょう」で間違えたり
運動では、右足と左足を間違え、「座って待つ」と「立ったまま待つ」を間違える
巧緻性では作業の順番を間違え、絵画では指定された条件に漏れが出て、行動観察では「これをやっちゃいけませんよ」と言われたことをやってしまう…
「話が聞けない」、ただそれだけでどの項目でも地雷だらけです。
どうしたら良いか。
はっきり結論を言ってしまうと、普通に育てている5歳やそこらの子どもは話なんて聞きません。5分でもお尻を椅子につけて座っていられたら万々歳です。
ですから、小学校受験を目指すのであれば、ペーパーやら巧緻性やらの前に、まずはそこを意図的にどうにかしていかないとなりません。
では、どうすればお話を聞く子になるか。
年長さんは、今の時期には当然できていてほしいと思ってはいますが、もしまだ不安があるなら本人にしっかりとお話しましょう。もう話したら分かる時期に来ていると思います。
なぜ、テストを受けるのか。
どうして、話を聞かねばならないのか。
これがきちんと分かっていないと、親だけがアクセル全開で子どもが置いてけぼりになりがちです。
受験というのは、受けるのは子どもで、通うのも子どもですから、本来は子どもが "自分ごと"としてやるべきことです。
とはいえ、弱冠5歳の子どもが自発的にそう考えるのは無理ですから、親の思いをしっかりと伝えていかねばなりません。
そして、具体的にどのようにすれば良いのかを教えてあげましょう。
私は、おはなしの練習講座というものを普段やっているのですが、始まる前に「お話の練習をするときに、先生が気をつけようねって伝えたことは何だったか覚えてる?3つあったよ。」という確認をしています。
それと同じで、「お話の記憶をやるときに気をつけることは何だった?」「ハサミ切りをやるときに気をつけることは何だった?」と確認していくだけでも、徐々に意識がついてきますよ😊
「例えば、◯◯ちゃんがお母さんに一生懸命お話してくれるとき、お母さんがスマホばっかり見て目を見てくれなかったらどう思う?」
自分に向かって話している人の目を見て話を聞くことは、人としての礼儀です。
「例えば、◯◯ちゃんが転んで右の足が痛いよーと言ったときに、お母さんが適当に話を聞いて左の足に絆創膏を貼っても怪我は治る?」
人の話は聞いたふりをしていても、内容を理解しなければ意味がないんです。
「例えば、◯◯ちゃんが好きなオヤツを次の日に食べるから取っておいてねってお母さんにお願いしたのに、お母さんが忘れて食べたらどうだろう?」
人のお話は、きちんと覚えておくようにしないと困るのよ。
そういうことを何度も何度も問いかけ、繰り返し繰り返し伝えているでしょうか。
年中さん、年長さんは、まずはしっかり座る練習をしていきましょう。おうちの方が見ていないと、結構ひどい姿勢になっていたりします。
そして、話を聞けるようにするには、やはり一番良いのは読み聞かせです。
前に少し話しましたが、以前、私は地域文庫で活動してまして、園児に定期的な読み聞かせをしたりしていたのですが、小さい頃からおうちでいっぱいいっぱい絵本を読んでもらっている子どもと、そうでない子どもの読み聞かせに対する姿勢は全然違います。もう明らかに。私が分かるくらいですから、学校の先生なら瞬時ですよね、きっと。
一人読みができるようになると楽ですよね。「うちの子、もう自分で本が読めるから」と言って読み聞かせをやめてしまう方もおりますが、私からするとこれは本当に色んな面でもったいない!
お話を聞くのが楽しいと知っている子は、どれだけ騒がしくしていても、お話を読み始めるとグッとその世界に入って他の声が聞こえなくなるくらい集中できるんです。
だって、思い出してもみてください。テレビやYouTubeに吸い込まれるのではないかと思うほど集中し、まるで親の呼びかけなど耳に入らぬ我が子の集中力を…
私としては、年中の春までに、毎日の学習に耐えうる程度には良い姿勢で座り、人の話を聞く態度を身につけておくと、そのあとの学習が全然変わってくると思います。
まだ試験まで時間がある皆さまは、まず「お背中ピン」の合言葉から学習をスタートし、聞く姿勢を整えていきましょう。姿勢が崩れてきたら、何度も何度も注意します。ここだけは、受験生の親として譲ってはいけないところです。
そして、読み聞かせで〈人にお話を読んでもらうことの楽しさ〉を覚えさせ、集中力をしっかり養っていくと、受験を超えた人生の収穫ができるかもしれませんよ😊
☆学習についてのご相談は、LINEでお気軽にどうぞ(無料です)☆
☆当教室の主催する講座については、アメブロでご確認ください☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
