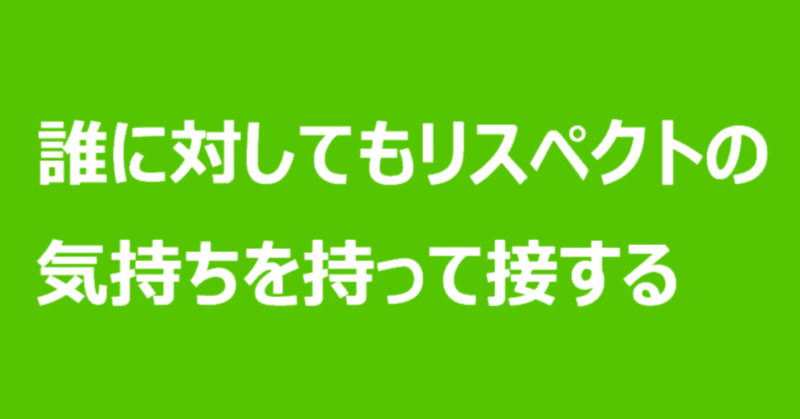
誰に対してもリスペクトの気持ちを持って接する(#23)
この記事の初出は、Software Design 2024年2月号です。
はじめに
技術が多様になった現代では、誰に対してもリスペクトの気持ちで接して、自分の知見になる事があったら吸収しようという真摯な姿勢が大切です。
チームメンバー同士でも、いつもお互いにそういうスタンスでコミュニケーションできると、開発も楽しく取り組めるようになると思います。
リスペクトの気持ちで接しようとする際、普段の言葉づかいは少なからず影響があります。
言葉づかいとは、例えば、同じチームの後輩に対して、名前を「さん付け」するか「君付け」するか「呼び捨て」にするかどうか、敬語を使うかどうか、などのことです。
筆者には、後輩の呼び方や敬語の有無において失敗談があります。
まずそれを紹介した上で、筆者の考え方を紹介します。
筆者の失敗談
筆者は新卒入社後、同じチームの後輩を「君付け」で呼び、敬語は使わずにタメ口で話していました。
当時の筆者は、社会人という意識が低く、会社の後輩に対して学生時代の部活の後輩と同じ感覚で話しかけていました。
また、当時の筆者は、後輩に対して甘く、厳しく指導すべき時にそれができていませんでした。
そんなある時、先輩社員から、筆者の後輩への接し方は、その後輩が成長する上でマイナスになっていると指摘されました。
そして、接し方を改める荒療治として、同じチームの後輩を呼び捨てするように助言されました(10年以上前の話です)。
学生時代から一度も後輩のことを呼び捨てしたことのなかった自分にとって、それは抵抗がありました。
しかし、筆者は後輩に対してもっと厳しく指導することも必要だと思って、呼び捨てで呼ぶことに取り組みました。
そのため、後輩に対して指示をする時の話し方を以下のように変えました。
変更前:小島くん、このタスクを明日までにできる?
変更後:小島、このタスクを明日までにやって。
このように、筆者は(良かれと思って)後輩に対して呼び捨て+命令口調で指示するようになりました。
最初は凄く抵抗がありましたが、少しずつ慣れていき、時間経過と共に抵抗がなくなっていきました。
そして、抵抗がなくなると共に、筆者は段々とその呼び捨て+命令口調に引っ張られて無意識のうちに、後輩が下で、自分の方が上だと勘違いするようになってしまいました。
その結果、後輩の良い面を見つけたり、後輩から学ぼうとする姿勢が薄れていました。
そのように相手をリスペクトしようとする姿勢が欠如していると、信頼関係は作りづらいと思います。
もちろん、呼び捨て+命令口調で話していても、ちゃんとリスペクトの姿勢で接している人は、たくさんいます。
呼び捨て+命令口調が悪いわけではありません。
ただ、筆者のように自分が扱う言葉に引っ張られやすい人は、気をつけた方が良いと思います。
リスペクトの気持ちを持つ
前述の反省もあり、現在は会社の新人や後輩に対して「さん付け」で呼び、敬語で話しています。
敬語で話すようになったきっかけは過去の反省だけではありません。
筆者が運営している Serverless 技術のコミュニティ(こちら)のイベントにて、学生が発表者として参加してくれたこともきっかけの1つです。
その学生が発表してくれた内容は、筆者が知らなかった内容でした。
まだ学生でありながら、ITエンジニアが集まるイベントに参加し、筆者が知らない技術を分かりやすく発表し、質疑応答にも答える姿を見て、その学生に対してリスペクトの気持ちを持ちました。
リスペクトの気持ちを持つと、その相手から積極的に学びを得ようという気持ちになり、自分の成長にとって良い効果があります。
20年近く前は、社内のベテランのエンジニアが若手エンジニアよりも、あるゆる面で知識も技術も勝っていることが、しばしばあったと思います。
しかし、今は技術の細分化・専門化が進んでいるため、ベテランの知らない技術を若手が知っている事もあります。
だから、新人や後輩からも学びを得ようとする姿勢は大切です。
今振り返ると恥ずかしい話ですが、過去の筆者は「自分の狭くて古い常識」にあてはめて「こんな常識的な事を知らないの?」と後輩に言ってしまったことがあります。
それは「自分の常識が、相手にとっての非常識」である可能性を考えない視野の狭い言動だったと反省しています。
自分の常識に固執していては、その常識がいつの間にか常識でなくなり、時代に取り残されてしまうかもしれません。
技術が多様になった現代では、誰に対してもリスペクトの気持ちで接して、自分の知見になる事があったら吸収しようという真摯な姿勢が大切だと思います。
だから筆者は、その気持ちを忘れないために、学生にも後輩にも敬語で話しています。
ここまで相手に対する言葉づかいを題材にしてきましたが、最も大事なことは、リスペクトの気持ちを持つ姿勢だと思います。
学生や後輩に敬語を使っている人も使っていない人も、そこを大事にすれば、きっと良い関係が作りやすいと思います。
(おまけ)親しみを込めた呼び方も有り
毎日一緒に開発する同じチームのメンバーに対しては、「さん付け」とは違った呼び方をするのも有効だと思います。
実際に筆者は、チームのコミュニケーションを促進するための施策として、皆でニックネークかファーストネームで呼び合っているという事例を目にしたことがあります。
そこで、筆者のチームでもやってみました。
ちなみに筆者はチームのメンバーからファーストネームで「優介さん」と呼ばれています。
名前は毎日何度も呼ぶため、親しみを込めた呼び方により親近感が高まる効果があります。
ただ、呼び方を決める際には、注意点が3つあります。
1つ目は、本人が呼ばれたい呼ばれ方を自分で決めることです。本人が望まない呼び方は良くないからです。もし名字で呼ばれるのが良いならそれを尊重します。
2つ目は、同期や先輩から呼ばれる時の呼び方だけでなく、後輩から呼ばれる時の呼び方も合わせて決めることです。後輩からすると先輩を「ちゃん付け」するニックネームは呼びづらいため、そこをしっかり決めないと呼び方が定着しません。
(例) 先輩からは「まこっちゃん」、後輩からは「まこっさん」
3つ目は、呼び方を変える前に、チーム全員が納得した上で始めることです。筆者のチームの場合は、ニックネームやファーストネームで呼び合う事例の紹介記事を皆でいくつか共有した上で、チームビルディングのプラクティスとして試しにやってみようということで始めました。
それまで名字で呼び合っていたチームが、急にニックネームかファーストネームで呼び合おうとすると、最初はとてもむず痒く感じます。
ただ、2週間くらいで慣れるので、試す場合は最初のむず痒さに耐えてください。
そこに耐えると、その後はチームのメンバー同士の距離感が縮まり、フラットな関係に感じてシェアドリーダーシップ(チームの誰もがリーダーシップをとること)が発揮しやすくなると思います。
連載「ハピネスチームビルディング」の次回の記事はこちら↓
前回の記事はこちら↓
読んでいただき感謝です!何か参考になる事があれば、スキを押していただけると励みになります。毎月チームビルディングの記事を投稿してます。 Twitterもフォローしていただけると嬉しいです。 https://twitter.com/kojimadev
