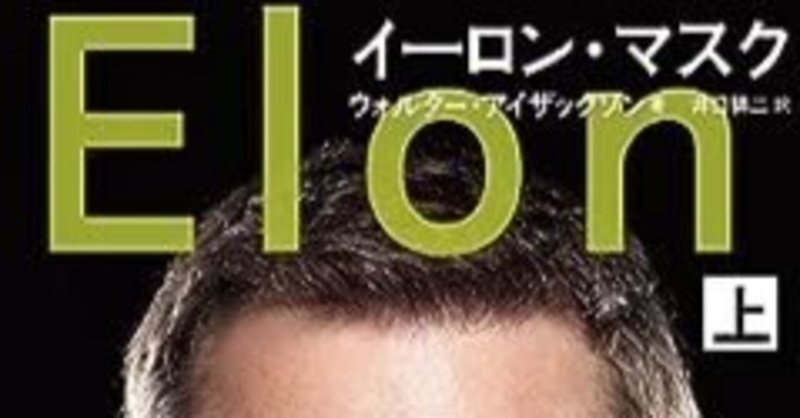
イーロン・マスクの伝記本を読んで
9月13日にイーロン・マスク伝記本が発売された話をしました。
今回は、その(要約でなく)感想を上巻中心に述べてみたいと思います。(タイトル画像の出所は言わずもがなですね。直視が怖いので額から上だけ切り抜きました☺)
まず、基礎情報を割愛するために、過去記事にも載せた事業遍歴を再掲しておきます。
今回は、何をやったか、というよりどういう人だったか、に絞ろうと思います。世界中で話題の人なので、今回の伝記本での個人的な期待値はむしろそちらです。
で、おそらくは例示されるだろうなぁ、とおもっていたのが「スティーブ・ジョブズ」です。
他人に接するときに、過渡に攻撃的になる逸話がいくつも出てきます。そして、スティーブ・ジョブズ伝記本を読んだ人にはおなじみの、「現実歪曲フィールド」という言葉も登場します。
今見たら、Wikiにものってますね☺
1つだけ今回の書籍内ケースを取り上げます。
なお、節々でマスクによるコメントが挿入されており、おそらくアイザックソンは1年以上(Twitter買収時も)彼と行動を共にしたようです。
ただ、もちろん名うての伝記作家で、ジョブズ伝記本を読んだ方はわかる通り、マスクの攻撃対象の人の言い分も触れて、出来る限り中立的に書くスタイルです。
「現実歪曲フィールド」という言葉が初めて出たのは、2002年に起業したSpaceXで初号機のエンジンを開発中のころでした。
マスクは、一言でいえば完璧主義者で。自分の納得のいくまで徹底的にこだわります。
当時、ロケットの部品はサプライヤー調達が常識で、そのあまりの高さに納得がいかず内製化を進めていました。(はじめはロシアで中古エンジンを買おうとして決裂したそう)
例えば、ノズル制御のアクチュエーター(動力を与える機器です。解説は例えばこちら)1基12万ドルと言われ、洗車機に使われているバルブを改造したという話もあります。(さすが・・・ですね)
ということを積み重ねて、ロケット(今でこそ有名なファルコン9の1号機)の開発をスタートして数年後には内製率70%となります。(結構これは際立った数値だと思います。日本の自動車業界で大体2・3割が普通)
勿論コアにあたるエンジンも内製ですが、(開発者の視点で)困ったことに、当時マスクはテスラという電気自動車事業も手掛けており、その重量価格比であまりにコストが高すぎる! というなかなかな乱球が飛んできたそうです。(そこ比較するか?・・・と心の中で叫んだことでしょう)
ただ、これがある意味業界の常識を変えることにつながります。
当時の航空宇宙産業は、軍やNASAの仕様要件に忠実に則って開発されており、「その常識を疑え」というのがマスクのスタンスでした。
開発者からすると仕様は絶対ですが、それを口にするとコテンパンにやられたそうで、その仕様を作った組織どころか個人名までおさえておけ、という指示もあったそうです。
これはイノベーションを起こすには重要な問いで「何を、の前になぜやらなければならないのか」に対する追及は、さすがマスクと敬服せざるをえません。1つだけこのテーマでしびれた文を書籍から引用しておきます。
要件は、すべて、勧告として扱え。それがマスクのやり方だ。疑う余地のない要件は、物理学の法則に規定されるものだけだ、と。
という背景の中で、初号エンジン開発を担っていたエンジニアが、従来の開発期間の半分というチャレンジングな提案をマスクに持ってきました。
さすがマスクの下で働いているのですごい!と思うでしょうが、マスクはそれを見て「これをまた半分にしろ」と無茶苦茶な指示をします。
当初は抗ったものの、こういうケースでマスクが折れることはほぼなかったようです。(例外はEVテスラ初号機で、販売直前で(ある意味社内のコアにあたる)ダッシュボードが気に入らないと言い出し、さすがにそれは後回しになったようです)
ただ、当然無理なものは無理なので、実績としてはエンジニアの提案した時間までかかってしまいます。
その個人をそれで罰したとまでは書かれておらず、当事者のコメントで「だからこそ業界一番になれたのだ」ともあります。
とにかくマスクは失敗を恐れない反復型アプローチを好み、それによって問題点を早めに改良する、というある意味まっとうな考え方です。
それだけならよく聞く起業家像ですが、その徹底ぶりがすさまじいのと、そして上記引用でふれたように、マスク自身が物理学・工学にある程度精通しているのも異色な点です。
上巻の8章「ペンシルバニア大学」に「物理学」という小節があります。
大学の専攻は物理学で、エンジニアの心髄は物理学の基本原則まで問題を深く理解することにある、と当時から考えていたそうです。
ただ、同時にビジネスの感度も高く、こういった興味深い発言があります。
「物理学を修めて製品を開発することと、ビジネスの学位を持つ人の下で働くのは絶対に避けること、これが目標でした」
さらっと載った一文でしたが、なぜかこれが印象に残りました。
単なる精神論やビジネススキルだけでなく、なんなら自身が物理原則までさかのぼって現場のエンジニアと議論できるほどの知的体力、なかなか両立しえないこれらがマスクの超越的なよりどころなんだろうなぁと感じています。
今回は上巻の前半をとりあげましたが、一旦ここまでにしておきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
