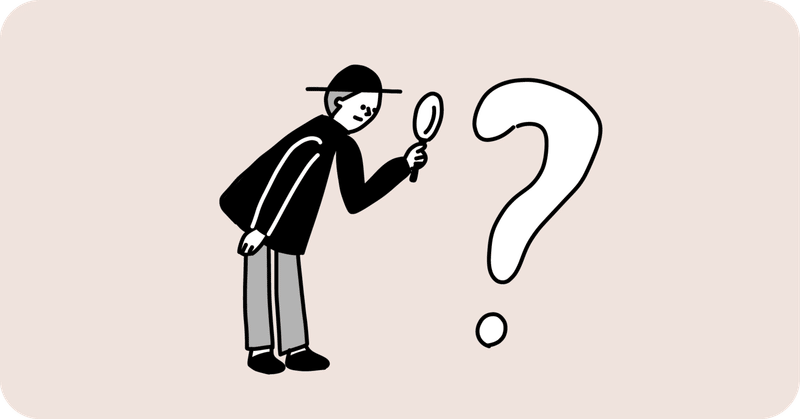
いざ、聞き取り調査へ[森ネズミのトト 就農奮闘記 vol.3]
農家さんから聞いた新規就農制度について
役所関連に聞きにいってみようと思った2021年 夏。
どんなところで話を聞いたかをまとめてみます。
1. 徳島県農業会議
インターネットで「徳島県」「新規就農」を検索。
トップであがってきたのは、県庁のHPでした。
しかし、内容は新規就農についての要項でした。
以前、県庁に勤めていたときの感覚として、
ある政策に対して県は市町村の取りまとめの仕事が主で、
具体的な相談や審査、承認は市町村に任せている
というのがあったので、県庁への聞き取りは不要かなと判断しました。
そこで検索結果の次にあがってきていたのが、
「徳島県農業会議」
県の農業政策に対して、それらを補完するような機関のようです。
さらに「新規就農相談センター」なる、自分にピッタリの窓口も用意されており
そのまま電話でアポを取得しました。
シュタタタ≡≡≡ヘ( ; ¯ д¯)ノ
技術なし、土地なし、機械なし、お金なし
何もないところからのスタートです!
と担当者の方に伝えて、新規就農についてのいろいろを伺いました。

この冊子は徳島県農業会議が発行しているもので、
新規就農について流れや考えるべきことなどが
分かりやすくまとまっています。
(いま振り返ってみても、よく書かれていると思います)
あとは徳島県の地域別特産野菜の資料や、
県内の農業法人をまとめた冊子などと一緒に新規就農の流れについて
説明を丁寧にしてくれました。
その中で気づいたことは2つです。
1. 自分には実務経験が必要
2. 新規就農の認定は各市町村
やはり、まずは実務経験。
新規就農にあたっては営農計画がとても重要になるため、
それを計画できるだけの知識と経験があり、
さらに計画の具体性があるということを証明しなければいけません。
そうなると必要となってくるのが実務経験です。
この時には果樹ではなく、野菜を作っていきたいと考えていたため、
野菜全般の栽培を学べる場所へ転職しようと決めました。
そして、新規就農の認定は各市町村。
各市町村には農業委員会が設置されていて、
そこが地域の農業をとりまとめている行政機関です。
自分が作付する農地の主な所在地となる市町村が
認定をしてもらうところとなります。
ということで次に向かうは「農業委員会」です。
2. 農業委員会
農業委員会ときくと、行政の人ではないのか?
と思いましたが、そうではありません。
機関の名称としては「委員会」とついていますが、
実際は市町村のなかの一部署であり、従事されているのは公務員の方々です。
当時、私と妻は離れた市町村に住んでいました。
結婚や就農を視野にいれたとき、離れて暮らすことは考えられなかったので
妻が住み、働く市町村の近くで就農するつもりでした。
そこで妻の職場のある市町村へ向かいました。
シュタタタ≡≡≡ヘ( ; ¯ д¯)ノ
農業会議と同様に
技術なし、土地なし、機械なし、お金なし
何もないところからのスタートです!
と担当者の方に伝えました。
・・・あれ?顔ゆきが険しいぞ?
農業会議では親切に対応してもらっていたがために
そういうのを期待していましたが、
思ってたのと違います。。。
就農について今すぐに独立とも思っていなかったため、
技術に関してはこれから技術を学べる会社に就職予定と伝えました。
問題はその後です。
土地のツテはあるのか?
土地はどうやって見つけるのか?
本当にその土地で野菜がつくれるのか?
機械もお金もないのに一人でやっていけるのか?
作った野菜はどうやって売るのか?
結婚する予定であれば、就農して家族を養っていけるのか?
新規就農される方の多くは、親からの引き継ぎの方が多い。
などなど、耳が痛くなることをたくさん聞かれ
意気消沈しました。
新規就農にむけて具体的な解決策やアドバイスはなく
このまま相談は終わりました。
確かに指摘事項はとても真っ当なことです。
今ならば、どれも本気で考えて計画すべきことなので
課題として捉えることができます。
しかし、当時の私は目標に胸をワクワクさせていただけに
これらの指摘事項が刺さりました。
だって新規就農には、「新規」ってついてるじゃん!
農家の担い手少なくなってるってニュースとかでいってるじゃん!
親が農家でなくても就農できるように国が制度を作ってるんじゃん!?
融資制度とかで機械を用意するんじゃないの?
など、突き放されてしまった気がして、モヤモヤしました。
(これもいま思うと、生半可な思いで就農するなよという
突き放す必要があったんだと思います。
半端な気持ちで就農したいという人が挫折して、
手をつけた農地がまた耕作放棄になったり、
せっかく税金を使って援助をしたのに農家が増えなかったりと、
その人にとっても地域にとっても好ましくない結果となる可能性が
あるんだと思います。)
また、農業委員会の担当者は技術的なことはよく分からないとのことで、
県の農業支援センターにも伺ってほしいと言われました。
これが行政の伝家の宝刀「たらい回し」!
以前は私がこの宝刀を抜く立場でありましたが、
振るわれる側に立つこととなりました。
ただ、この伝家の宝刀には理解があります。
公務員は多様な業務をさせられることが多く、
同じ部署にいられるのはわずかな期間です。
そのためその業界に精通するというのは、
公務員のシステム上とても難しいのです。
よって、たらい回しが起きてしまうのは仕方がない面があります。
また、仮に担当者の方とどうしても馬が合わないことがあっても
いくつかの人が関わっているため、全員と馬が合わないという可能性は低く、
数年我慢すれば担当者が変わる可能性も高いです。
そんなこんなで、次は農業支援センターへ向かうこととなります。

3. 農業支援センター
支援センターは県の出先機関のひとつです。
主に農業実務を専門としている部署です。
なので、イチゴのエキスパートの職員さんがいたり、
キャベツのエキスパートの職員さんがいたりします。
農業委員会と同様に就農の意思を伝えたところ、
概ねは似た反応をされました。
また、私は農薬に頼らない方法(有機農法や自然農法)で
野菜づくりを行いたいことを伝えました。
ちょうどその頃の時期に追い風となる国の政策がありました。
2021年に策定された「みどりの食料システム戦略」です。
健康な食生活や持続的な生産・消費、
環境にも配慮した持続可能な食料システムを構築することが目的のものです。
この中のひとつの目標に、2050年までに耕地面積に占める
有機農業の割合を25%に拡大(2017年時では1%にも満たない)する
というものがあります。
支援センターには、いわゆる慣行農法における野菜づくりの
マニュアルやデータがあります。
ある野菜について、この時期に種まきして、
特定のタイミングで何回肥料を与えると、これくらいの収穫が見込める
というようなもののデータの蓄積があります。
しかし、農薬や肥料に頼らない農法についてはデータの蓄積がなく、
これまで業務でもほとんど触れてくることがないため、
支援センターとしてどのように評価して、サポートしていいか
分からないということでした。
国政策としては有機農業を広めていきたいと考えているが、
始まったばかりで実務レベルにおいては対応できるに至っていないようでした。
新規就農の制度を利用するのであれば、それは税金を利用することなので
第三者としての評価と判断がしっかりできないと、
認めることができないというのは理解できます。
4. 話を聞いて、、、
ここまで3か所で新規就農について相談に乗ってもらいました。
率直な感想は、「簡単にはいかないな」でした。
技術なし、土地なし、機械なし、お金なし
何もないところからのスタートという自分の状況が、
それを生み出しているので仕方がありません。
指摘されたことを課題としてしっかり捉え、
できることからやっていこうと気持ちを切り替えました。
まず手をつけられるところは「技術」です!
前に書いた、思っていたのと違う会社を離れ
農薬に頼らない農業をされている会社にて野菜づくりを学ぼうと
決心しました。
技術を磨いていくなかで土地や機械、資金などについて
少しずつ解決していこうとも思いました。
次は、新しい就職先についてことを綴っていきたいと思います!
追伸
いまは農業委員会、農業支援センターの方々には、
前向きなアドバイスやサポートを頂いていて、とても感謝しています。
当時の私にとっては、対応について正直あまりいい印象ではありませんでした。
しかし、新規就農の助成金をもらう、もらわないにしろ
地域で就農するためには切っては切れない関係者です。
一度、好ましくない対応をされたからといって毛嫌いするのではなく、
何度も顔を合わせることで、こちらの人間性ややる気を理解してもらう
ということはとても大事です。
担当者の方々も地域農業の課題について真剣に取り組んでいるので、
就農しようという人にとっての敵ではありません。
味方です。
(以前、私も公務員であったため、そこは力強く断言できます)
ただ、真剣に考えているだけに就農する人の本気度も重要になってきます。
そこは諦めずに、お互いで支えあう関係になれるように
努力することが大事だと感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
