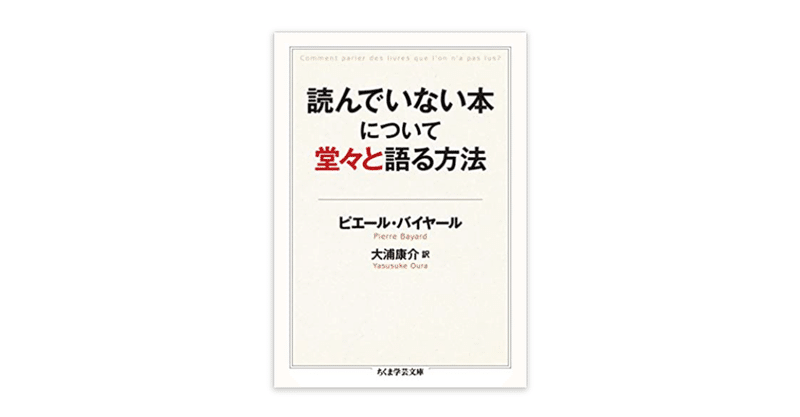
「優等生の書評」にならないために―書評『読んでいない本について堂々と語る方法』ピエール・バイヤール
ずいぶんと人を食ったようなタイトルの本だなあ…というのが、はじめてこの本を書店でみかけたときの印象でした。
ちくま学芸文庫から出されていることもあり、さすがに「トンデモ本」のたぐいではないのだろう…そう思いつつも、いかにも「ハウツー本」めいたタイトルゆえに、今日まで手をださずにいました。
…が、だまされたつもりで読みはじめて(だれに?)、結局、あまりのおもしろさに最後まで傍線を引く手がとまりませんでした。ピエールさん(そして訳者の大浦康介さん)、安易にハウツー本あつかいしており、すみませんでした。
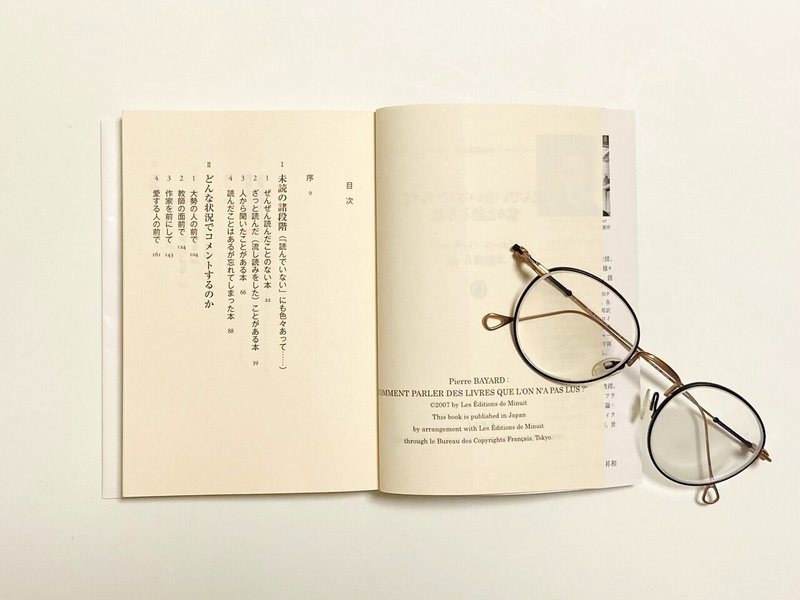
著者の主張には、かなり挑発的なものがあります。たとえば著者は、序文でこのように言いはなちます。
ある本について的確に語ろうとするなら、ときによっては、それを全部は読んでいないほうがいい。いや、その本を開いたことすらなくていい。むしろ読んでいては困ることも多いのである。(p12)
しかし、読みすすめていくとしだいに明らかにされるように、著者がこんな主張をする背景には、一貫した理由があることがわかってきます。
というのは、著者は、わたしたちが「みずから創作者になること」を重視しており、その創造のためには、「書物から一定の距離をとる」必要があると感じているということです。
あらゆる読者には、他人の本に没頭するあまり、自身の個人的宇宙から遠ざかるという危険があるのだ。読んでいない本についてのコメントが一種の創造であるとしたら、逆に創造も、書物にあまり拘泥しないということを前提としているのである。(p270)
うーん。この指摘は、書評を中心としたnoteを書いている立場として、じつに身につまされるものがあります。
書評というのは、どうしても受動的な行為にとどまります。というのは、それが、なるべく丁寧にその本を読み込み、なるべくその本の主題をはずさぬように筋道をたてていく作業に尽くされるからです。
しかし、そうして、その本の「レール」にしたがおうとすればするほど、その書評は、どうしても平板でありきたりなものにならざるをえません。せいぜいが、「あらすじ+感想文」。だれも傷つけないかもしれないが、その代わり、だれから注目されるということもない。いわば、窓ぎわに座った優等生のような文章…。
でも、これでいいんですかね、本について語ることって。
主観的にものごとを語るということには、それなりの(いや相当の)覚悟と勇気が必要です。そのことばは、意図せずしてだれかを傷つけるかもしれませんし、無知なその発言を笑われる危険性もつねにつきまといます。
ただ、わたしがおもうに、そのように自由闊達に「主観的」に語れるようになるためにこそ、「客観的」に本を読む訓練が必要なのではないか、ということです。
そもそも、この本で著者が、読んでいない本について語る方法を指南するために言及している文学者って、ポール・ヴァレリーとか、ウンベルト・エーコとか、モンテーニュとか、オスカー・ワイルドとかなんですよね。
冷静になってみれば(冷静にならなくたって)わかるように、そんな連中とおなじ読書法が、わたしのようなボンクラにできるわけがない。
あやうく、ほんとうに、だまされるところでした。危ない、危ない笑
あまり真に受けすぎてはいけませんが、とはいえ、「話半分」もとい「話4分の3」ぐらいで耳をかたむけるには、とてもおもしろい(おもしろすぎる)一冊です。
最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。
