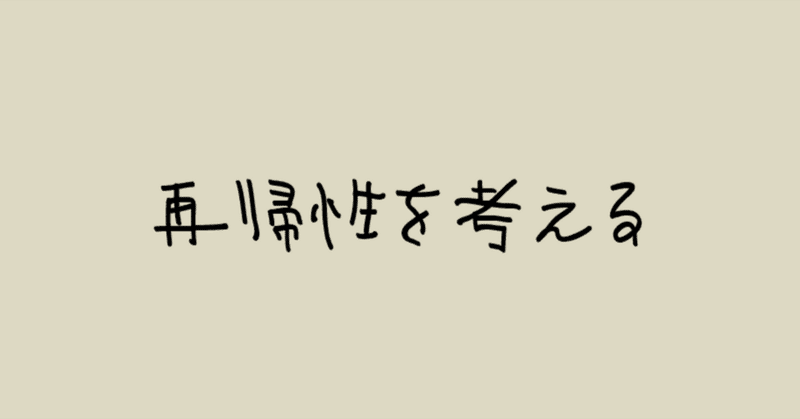
再帰性(2):Berger(2015)の感想
今回の記事では,Berger(2015)を読んだ感想をまとめておきます。
簡単ではありますが,論文の概要を整理した後に,私のたんなる感想を列挙しておきます。
読んだ論文はこちら:
Berger, R. (2015). Now I see it, now I don’t: Researcher’s position and reflexivity in qualitative research. Qualitative research, 15(2), 219-234.
論文の概要
本論文では,研究者の社会的立場(性別,年齢,人種,移民,性的指向など),個人的経験,政治的・職業的信条が再帰性に及ぼす潜在的影響について取り上げる。
再帰性は,質的研究の品質を管理するための主要な戦略であるため,研究者の特性や経験によってそれがどのような影響を受けるかを理解することは最も重要である。
研究者の立場が3つのタイプに分かれる場合の再帰性の利点と課題についてBerger自身の研究事例を用いて議論している。
(1)研究者が研究参加者の経験を共有する場合の再帰性,
(2)研究者が研究の過程で部外者の立場から内部者の立場に移る場合の再帰性,
(3)研究者が研究対象について個人的な知識や経験を持たない場合の再帰性である。
考えたこと
1.タイトルかっけぇ
論文のタイトルは「Now I see it, now I don’t: Researcher’s position and reflexivity in qualitative research.」です。
これをどう訳すかは難しいですね。
マジシャンが舞台でマジックを披露する際に「Now you see me, now you don't.(見えますね。ほら,消えた)」と言うこともあるようです。
小説にも似たような一文が登場するようです。そのときは「一瞬前には見えたのに,今は見えない。」と訳されているそうです。
この論文は,研究者の立場によって見えるものが異なること(研究者のポジショナリティー)に関わっていますし,前半の「I」と後半の「I」がそれぞれ異なる立場を取る「I」だとすれば,「さっきの私には見えたのに,今の私には見えない。」となるでしょうか。
違っていたらすみません。
どこかでパクって使いたいワードです。
2.Beger(2015)で引用されている論文読もう
Berger(2015)の主題は,再帰性と研究者のポジショナリティーなので,これらに関する論文がかなり引用されています。
次回以降の記事はそれらの論文を読んでいこうかと思います。
例えば,
Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and “ethically important moments” in research. Qualitative inquiry, 10(2), 261-280. とか。
おすすめの文献などありましたらご教示いただけますと幸いです。
3.再帰性の3つの分類を援用できそう
Berger(2015)では,研究者の立場と再帰性の関係について,(1)研究者が研究参加者の経験を共有する場合,(2)研究者が研究の過程で部外者の立場から内部者の立場に移る場合,(3)研究者が研究対象について個人的な知識や経験を持たない場合の3つに場合分けされて議論されています。
この場合分けを,私の研究で援用できそうです。
論文のアイディアを含むのでこの辺にしておきます。すみません。
今週は短いですが,以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
