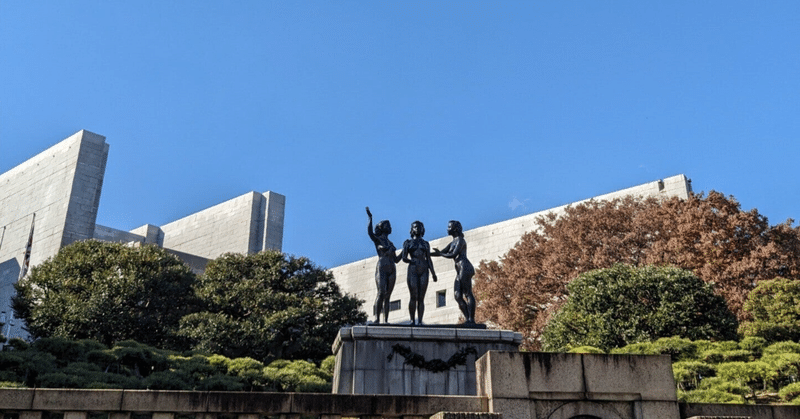
法制審議会家族法制部会最新資料を見る4~資料34-1~監護者指定・監護分掌について
まだまだ、弁護士は、家族の問題のニーズに応えきれていないのではないか
離婚事件なんてどんな弁護士でもできる
— RK (@koga_r) December 7, 2023
勝手に別居して、もぬけの殻なんてよくあること
警察が行方不明として捜査することはない
9割は母親が親権者 残りの1割はよほどなケースのみ
面会交流の約束破っても罰則はない
会わせないの当たり前
そんな逃げたもんがちで大丈夫なのですか?
→大丈夫です
資料読んどこ
3 監護者の定め及び監護の分掌に関する規律についての論点整理
⑴ たたき台(2)第2の3⑴については、第32回会議において、監護者 指定を必須とすべきであるとの修正意見が示されたが、どのように考えるか。
⑵ 父母以外の第三者に監護者指定の申立権を認めるべきであるとの意見について、どのように考えるか。
たたき台(2)の内容(部会資料32-1より再掲)
3 監護者の定め及び監護の分掌に関する規律
⑴ 離婚後の父母双方を親権者と定めるに当たって、父母の一方を 子の監護をすべき者とする旨の定めをすることを必須とする旨の 規律は設けないものとする。
⑵ 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は監 護の分掌(分担)については、父母の協議により定めるものとし、 この協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、 家庭裁判所がこれを定めるものとする(注1)。
⑶ 子の監護をすべき者が定められた場合には、子の監護をすべき 者は、民法第820条の監護及び教育、同法第822条の居所指定 及び同法第823条の職業許可を単独で行うことができるものと する(注2)。
⑷ 子の監護をすべき者が定められた場合には、親権を行う父母(子 の監護をすべき者であるものを除く。)は、上記⑶の規定による子 の監護をすべき者の行為を妨げない限度で、上記1の規律に従って、監護及び教育に関する日常の行為を行うことができるものと する。
(注1)【P】父母以外の第三者を子の監護をすべき者と定める場合に関する規律を 整備するものとする考え方がある。
(注2)本文⑶の規律により監護者が身上監護権を単独で行うことができるものと 整理した場合であっても、監護者による身上監護の内容がその自由な判断に委 ねられるわけではなく、これを子の利益のために行わなければならないことと の関係で、一定の限界があると考えられる。例えば、監護者による身上監護権 の行使の結果として、(監護者でない)親権者による親権行使等を事実上困難に させる事態を招き、それが子の利益に反する場合があるとの指摘がある。
(補足説明)
1 監護者の定めの要否
⑴ 部会のこれまでの議論においては、離婚後の父母双方を親権者とするに当たって、その一方を監護者(子の監護をすべき者)と定めることを必須とするかどうかが議論された。そして、一部の委員・幹事からは、監護者の定めを必須とすべきであるとの意見があったが、これに対しては、離婚後の子の養育の在り方がそれぞれの家庭によって多種多様であることを念頭に、監護者の定めの要否は個別の事案によって異なるため、監護者の定めを一律に要求する必要はないとの指摘がされた。 そこで、たたき台(2)第2の3⑴では、離婚後の父母双方を親権者と定めるに当たって、父母の一方を子の監護者とする旨の定めをすることを必須とする旨の規律は設けないものとすることを提示している。
⑵ 第32回会議においても、監護者の定めを必須とすべきであるとの立場から、その理由として、監護者の定めをしないことにより不都合が生じ得るケースがあるとの指摘があった。 もっとも、現段階における議論の焦点は、監護者の定めをしないことにより不都合が生ずるケースがあるかどうかというレベルでの議論ではなく、全ての事案において監護者の定めを必須としなければならないかどうかであると考えられる。 そこで、この点を改めて整理するために身上監護に関する親権行使の ルールと監護者を定めることによる効果を再確認すると、まず、たたき台 (2)で提示された規律によれば、離婚後の父母双方が親権者と定められた場合には、監護者の定めの有無にかかわらず、①監護及び教育に関する日常の行為については、父母の一方が単独で(他方の同意等を得ることな く)行うことができ、また、②日常的な行為以外の親権行使についても、 急迫の事情があれば、その一方が単独で(他方の同意等を得ることなく) 行うことができるものとされている。そして、監護者の定めがされた場合には、③監護及び教育に関する重要な事項(日常的な行為以外の行為)について、急迫の事情がない場合であっても、単独で(他方の同意等を得ることなく)行うことができるという効果があるほか、④監護者でない親権者が監護者の身上監護を不当に妨害することができないものとされる結果として、身上監護に関する事項(日常的な行為を含む)について父母間の意見対立が生じた際には、監護者の意見が常に優先されることとなる。 この部会のこれまでの議論の過程では、親権行使を父母の一方のみの 判断に委ねるよりも、父母双方がその責任を負い、双方の関与の下で意思決定がされるものとした方が、子の利益の観点から望ましいことが多いとの価値判断を踏まえた意見が示されてきた一方で、父母の一方のみが子の養育に責任を負い、最終的な決定権限を集約させた方が、監護の継続性や安定性を確保することができる点で子の利益の観点から望ましいとの価値判断を踏まえた意見も示されてきた。監護者の定めを必須とすることを求める上記修正意見は、このうちの後者の価値判断を重視する観点から、一切の例外なく一律に、身上監護に関する親権行使について父母の責任に差を設けることを求めるものと整理することができる。
⑶ また、監護者の定めと類似するものとして、監護の分掌の定めをするこ とも考えられるほか、紛争解決手段としては、身上監護に関する事項を含む特定の事項に係る親権の行使を父母の一方に委ねる裁判制度(たたき台(2)第2の1⑶)の利用も想定され、これらの異同を整理することが有益であると考えられる。この部会のこれまでの議論の過程では、例えば、「監護の分掌」として、子の監護を担当する期間を父と母で分担したり、監護に関する事項の一部(例えば、教育に関する事項)を切り取ってそれを父母の一方に委ねたりといった定め方があり得るとの指摘がされていた(注)。監護者の定めがされた場合には身上監護に関する事項全般(日常的な行為を含む)について包括的に父母の一方が優先的な地位を獲得することとなるが、監護の分掌として、子の監護の期間等に応じて柔軟に父母間での役割分担を定めることや、父母間の協議又は家庭裁判所の判断により上記特定の事項の範囲で親権を行う父母を定めることも考えられる。 さらに、(上記⑵で述べたような効果を生じさせるものとして)監護者の定めがされていない場合であっても、父母の協議により「父母のどちらが子と同居するか」が定められる場合もあると考えられるところ、これも監護の分掌の一つの形であると捉える考え方や、親権のうち身上監護に 関する特定の事項(たたき台(2)第2の1⑶にいう「特定の事項」)に 限ってその行使を父母の一方に委ねたものと捉える考え方も成り立ち得るところである。 監護者の定めを必須とするかどうかを議論する際には、上記のような 形で身上監護に関する各父母の役割分担を定めることとの関係の観点からも議論することが有益であると考えられる。
⑷ このほか、第32回会議では、監護者の定めを必須としない場合には、 家庭裁判所において、父母双方が親権者と定められる事案において監護者を定めるか否かが争われたときに、父母双方を親権者とすることにより子の利益を害するとは認められないにもかかわらず、その一方を監護者と指定することが必要となる事由として、どのような事由を想定するかを議論する必要があるとの指摘があった。 たたき台(2)第2の2⑹及び注2に提示された判断枠組みによれば、 父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるようなケースでは、裁判所が父母の一方を親権者とすることが想定されている。また、 上記のとおり、紛争解決の手段として、たたき台(2)第2の1⑶によれば、親権行使に関する特定の事項(例えば、子の居所をどちらに定めるか)について父母間の意見対立が生じた場合には、当該事項について親権を行う者を定めるという形での調整を図ることが可能である。なお、同第2の3⑵の「監護の分掌」により各父母の役割分担を定めることもできるとの考え方もあり得るが、監護者の定めを必須としない場合には、これらの規定相互の関係を議論することが必要であるとの指摘があった。 このような規律によれば、個別具体的な事案において父母の一方から監護者指定の申立てがされた際に、家庭裁判所がその申立てを認容するかどうかを判断するに当たっては、父母間にどのような事項についての意見対立があるのかを見極めた上で、特定の事項についての個別的な調整で足りるかどうかや、監護の分掌による役割分担を定めることが適切かどうかなどを考慮することが考えられる。また、その判断の際には、監護者の定めの効果(監護者の定めがされた場合には身上監護に関する事項全般について包括的に父母の一方が優先的な地位を獲得することとなる)を生じさせることが子の利益の観点から最善の選択肢であるかどうかを意識した審理をすることが考えられる。 (注) 「監護の分掌」をどのようなものとして位置付けるかについては、この補足説明の本文に記載のとおり、①子の監護を担当する期間の分担を定めるほか、②監護に関する事項毎にその役割分担を定めることもできるとの考え方もあり得るが、このうち、 ②に関しては、父母間で現実に紛争となっている特定の事項については、当該事項に 係る親権の行使を父母の一方に委ねる制度(たたき台(2)第2の1⑶)による解決が想定される。そうすると、この特定の事項に係る親権を行使する父母の定めとは別に、 「監護の分掌」として父母の役割分担を定める場面として、どのような場面を想定し 得るかについて議論を深める必要があり、父母双方を親権者とすることが相当な場合 に、未だ父母の意見対立が具体化していない将来的、抽象的な事項についてあらかじ め父母の役割分担を定めるニーズがあるかといった観点や、分かりやすさなどの観点 から、「監護の分掌」をどのようなものとして位置付けるかを議論することが有益であると考えられる。
2 父母以外の第三者からの監護者指定の申立てについて
⑴ 第32回会議では、一部の委員・幹事から、「子の利益のために必要が あると認めるときは、家庭裁判所は、親権を行う者、子又は子の親族の請求により、現に子を監護する子の親族を監護者に指定することができる。」 旨の規律を設けることを求める意見が示され、これに賛同する意見もあった。 ⑵ もっとも、このような意見に対しては、父母の監護能力に問題があるケ ースを念頭に置いた際に父母以外の親族が子の監護に関わることが有益であること自体は肯定しつつも、そのようなケースに対応する手段としては親権制限や未成年後見等の制度を活用する方向での検討をすべきであるとして、慎重な意見も示された。 そのため、これらの既存の制度との関係をどのように整理するかを議論する必要があると考えられる。例えば、第三者からの監護者指定の申立ての要件と親権制限の要件との関係や、監護者となった第三者による監護の適切性を担保するための仕組みの要否、監護に要する費用や報酬等の要否などが問題となり得る。 また、父母以外の第三者が子の監護に関わる必要がある場面は、父母の別居や離婚の場面に限られず、父母の婚姻関係が円満である場合も含まれ得ることを踏まえた検討が必要であると考えられる。
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!
