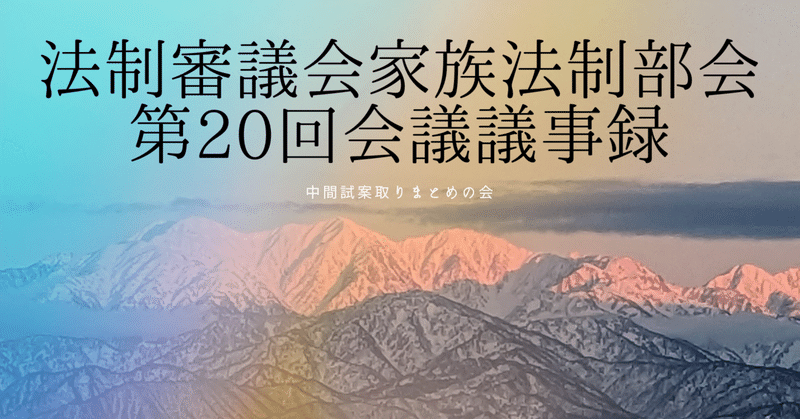
法制審議会家族法制部会第20回会議議事録4~棚村委員・原田委員・柿本委員・武田委員
新聞買った
甲①BΓ!! https://t.co/jHKX0A8L8Z
— RK (@koga_r) February 9, 2023
今日も議事録を読んでいく
○棚村委員
早稲田大学の棚村です。当事者を支援する立場とか、委員の皆さんの中にも法制度が変わることによってどんな影響があるかということを非常に心配されているということについては、よく理解ができます。ただ、私自身は中間試案ということの意義ということを考えますと、一刻も早く取りまとめをすべきではないかと考えております。その理由として、今回の中間試案は、これまで様々な御意見を頂いて、ヒアリングもして、海外法制についても聞かせていただいて、意見交換をした結果を具体的な形にして、広く国民の皆さんの意見もお聞きしたいということで出されるものです。そういう意味で今回の中間試案では、ある一定の方向が示されるというよりは、賛成反対の両論併記という、これが分かりにくいとかいろいろ言われているのですが、例えば離婚後の共同親権ということの可能性を認める考え方と、現状維持というのですかね、そういうような考え方が随所に示されて、ある意味では甲案、乙案とか、それに更に細かくいろいろな選択肢の可能性とか、組合せとか、分かりにくい点はあるとは思うのですけれども、何か一定の方向が示されて、こういうふうな形になるのだというような形で聴いているわけではないのではないということが第1点であります。
それから、第2点は、法制度と支援や税制とか社会保障を含めた支援体制の関係についてです。その両方の関係なのですけれども、前に、4回会議でも出ていたと思いますし、それから12回会議辺りでも出ましたし、随所で出てくるのは、支援は法制度との関係ではとても大事だという点です。幾らいい法制度を作ろうとしても、十分な支援というものが欠落したりすればうまく機能しないことがあるだろうというのは皆さんの御了解だと思うのです。
ただ、残念ながらここは、法務省組織令54条ですか、法制審議会が何をするかというときに、法務大臣の諮問を受けて、民事法とか刑事法とか、そのほか法務の基本的な事項について調査審議するということになっております。つまり、法制審議会家族法制部会の場で、できること、やれること、決められることは限定されているということになります。そういう中で、この場では、法制度ということを中心に議論をある程度せざるを得ないという限界が、みなさまもお認めになっているようにあると思うのです。
その上で、法制度をいいものを作っていくためには支援が必要だから、それについて要望するとか、注文を付けるとか、お願いするとかというのはできると思うのですけれども、ここの場でできるのかという話が窪田委員からも出ていましたけれども、そのことはやはり考えないといけないと思います。ここで決められないのだとすれば、是非そういうものを要望したりお願いするようなことでコンセンサスが得られるようであれば、場合によっては補足説明というような形で、そこに記載をさせていただくということはあり得ます。幾らいい法制度を作ろうとしても、支援制度を充実させないと駄目だということで、それはあり得ることだと思うのです。
法務省は私が見て関わっている限りでも、非常に実態調査とかエビデンスを一生懸命探したり、それから、他の省庁との関係する部分でも、調査研究ということで予算を付けて、自治体の支援モデルみたいなものを現行法の枠の中でも、できる限り身近なサービス、市民サービス、住民サービスみたいなことで、当事者のみなさんを法制度や専門職、関係機関につないでいけるかどうかとか、弁護士会とか司法書士会との連携とか、これまでの法制審議会の取組も、非常にいろいろなところとの関係も配慮していたのですが、特に今回、国民の生活や家族、こどもに非常に直結する問題なので、今までの法務省にないぐらい気を使いながら、やっておられるようなところもあります。
ですから、最終的にこの場で決めること、それから、やらなければいけないようなことというものは、どうしても民事法制とか家事法制とかという議論が中心になってしまいます。ただ、それについて要望という形で何らかの形で、今回意見表明がされたようなことをどういう形で示していくかということについても、多分今後の進め方を含めて、補足説明でどういうふうに書くかというようなことで御意見を頂ければいいと思うのです。
ただ、例えば(前注)に書くとか、要するに、ここで決められるとか責任を負えないことについてまでこちらが、諮問事項との関係もそうですけれども、書いてしまうということは、逆に言うと、それぞれの箇所で責任を持ってやらなければいけないことに対して、要望とかお願いを越えて、できるのかどうかという能力や権限という問題が出てくるのではないかということを危惧いたします。
もし今回、中間試案の取りまとめのこの時期に、また遅れを生じることがないように、できる限り、これまでの議論の積み重ねを生かした取りまとめにつなげるべきと思います。前回までの流れを考えると、分かりにくいとか、表現をどうしようかということで、国民に負託された審議会の部会としての使命は、個人のいろいろな御意見とか、私も理想はあるのですけれども、そういうものを越えて議論をして調査審議が進められた中で、皆さんで合意をしながら、共同作業を進めてきました。その中で、早く国民の皆さんの御意見を聴けるような形で、できる限り分かりやすいものを示して、次のステップにつなげるという重要な時期だと思いますから、そういう意味では今日、取りまとめをしていただいて、これまで議論していただいた中でも、もし足りないところとか、表現が適切でないとか、こういうものを付け加えてほしいという御意見はよろしいかと思います。しかし、それを越えて実質的に大きな変更をするということについては、中間試案の取りまとめの時期がまた延びて、更に時間が掛かるということもなりかねず、やはり審議会としても、全体としては大切な責任を本当に果たすということにつながらないのではないかと心配をしております。
ですから、まとめますと、中間試案というのは飽くまでもこれまでの議論やそういう御意見を頂いたものをまとめて、どういうような形でもって今後進むべきかということを、むしろ幅広く国民の皆さんの御意見を聴くためのもので、ある一定の方向が示されているものでもありません。しかも税制とか社会保障というのは非常にそういう意味では、ここが扱って決める場という形ではないことに関わることですから、むしろ国会だとか関係する省庁にお願いをしていくという事項だと思うのです。それをこの中間試案の中に盛り込んでいくということは、決められること、やらなければいけないことの範囲を越えたことをやるということにもつながりかねないので、非常に心配であると思います。
ですから、支援とか、税制も社会保障も充実することは大切ですから、それを補足説明にどういう形で盛り込んでいくかとか、示していただくような要望を出すかということについては、意見交換ができるのではないかと思うのです。できるだけ早く中間試案というものを、少し前回取りまとめの予定だったものが遅れているわけで、それをできるだけ早い形で出して、御意見を伺って、次のステップ、審議に参考にさせてもらうということをやるべきだろうと考える次第です。
○大村部会長 ありがとうございます。棚村委員からは、今までの何人かの委員が示された考え方、中間試案についてはこのままで、御指摘については補足説明の中で対応をし、本日取りまとめをすべきだという御意見を頂戴いたしました。その中で、中間試案というものの性質についての確認もなされていたかと思います。これはパブリック・コメントに付すための案として作られていて、最終的にこれで決めるということではないので、これを取りまとめて、更に議論を次の段階に進むというのがよろしいのではないかということだったかと思います。
○原田委員
ありがとうございます。弁護士の原田です。私はこの前のときに、部会資料19-1についてはもう意見ありませんと言いましたが、ただ、今御意見が出た点については本当に重要な点で、私は共同親権とか、共同養育とか、面会交流とか、いろいろなものに賛成、反対するについて、それを入れたら制度がどうなるのかということが分からないと答えられないという方もたくさんいらっしゃるのではないかと思うのです。それで、補足説明の中で、賛成意見や反対意見の中に、これを導入した場合の、例えば諸外国ではこういう制度でこうなっているとか、こういうことが起こるおそれがあるとかいうようなことを意見の根拠として入れていただきたいと思います。
○大村部会長 ありがとうございます。補足説明についての御要望ということで伺いました。
○柿本委員
柿本でございます。時間を取っていただきまして、ありがとうございます。私は一市民でございますので、法務省のパブリック・コメントの様式などについて理解できていない部分があるということを申し上げて、発言させていただきます。
パブリック・コメントに付すに当たり、部会としての問題意識として、子の最善の利益の確保のためには様々な配慮が必要であるということを、皆様の合意の上、補足意見として書き込んでいただきたいと思います。原田委員の発言にもありましたけれど、市民には、その法律を変えることによってどのような影響が及ぶのかというようなことは、全く分からないことばかりでございます。ですので、導入した場合の、例えば諸外国ではこういう制度でこうなっているとか、こういうことが起こるおそれがあるとかいうようなことを意見の根拠として入れているという原田委員の提案した方法を採用することに賛成いたします。
○大村部会長 ありがとうございます。柿本委員からも、パブリック・コメントに向けて適切な対応を望むという御意見を頂きました。
○武田委員
親子ネット、武田でございます。まず、赤石委員、大石委員、戒能委員、柿本委員からの意見表明資料、拝見を致しました。ここまでのやり取りも聞いてという上で、意見を述べさせていただければと思います。
赤石委員がおっしゃった、例えば家裁で当事者の話を聴いてくれないとか、研修とか体制が不足している、こういう御指摘の内容に関しては、私も正に同じように感じておりまして、そういう要素はあるだろうと思っています。しかしながら、感じたのは、少し唐突だなということです。ここまでの議論では4月末に中間試案を取りまとめましょう、両論併記で行きましょうということで、議論を重ねてきました。8月はああいった形で流れましたけれども、意見集約が進んできたと理解しております。このタイミングで改めて社会保障や税制などを今後の検討事項にという話かなと思いますが、法学者の先生方がおっしゃったのと同様、部会の中でこれらの要素をまとめていけるのかと懸念します。更に言えば、現在、中間試案が両論併記となり、方向性も定まっていない中で、それに対して個々の税制をどう取り扱うとか、それぞれのパターンを作っていけるのか、これはこの部会でやる議論ではないと思っています。仮にやるとしても非常に膨大なパターンがあり、取りまとめることは極めて困難であると思います。したがいまして、これまでの議論から離れ、唐突であるということを申し上げさせていただければと思います。
この部会資料20-1に関しましては、内容として両論併記ということでそれぞれの案が網羅され、整理されてきたと、そのように感じております。私は別居親当事者団体の立場で参加させていただいておりますが、もっと書きぶりをこう変えられないかなどのそういう意見はございます。しかしながら、ここまで議論を積み上げてきて、私がほかの委員の先生方から賛同をいただけずに記載されなかったこと、これもまた現時点の結論でございますので、私としては可能な範囲で希望する両論が入ったということをもって、取りまとめに入っていただきたいというのが私からの意見でございます。
○大村部会長 ありがとうございます。個別にはいろいろ御意見がおありだということだろうと思いますけれども、これまでの経緯を踏まえて、中間試案としてはこれで取りまとめるということでよいのではないかという御意見として承りました。
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!
