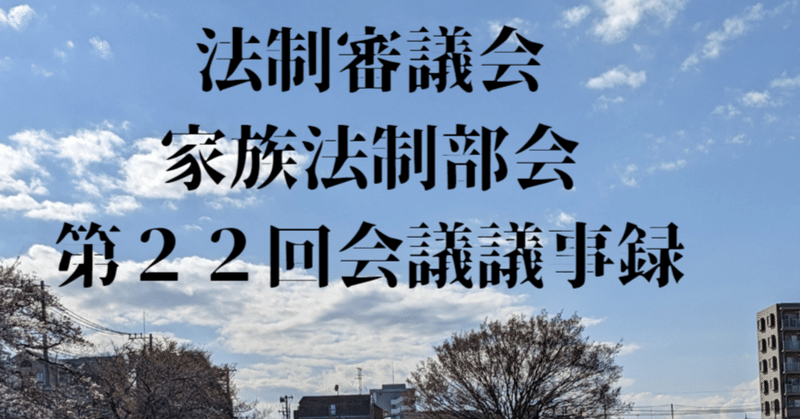
法制審議会家族法制部会第22回会議議事録2~戒能委員・遠藤参考人・菅原委員・柿本委員・久保野幹事・赤石委員・武田委員
共同親権day に世界一の日本、世界から注目される
#共同親権day に単独親権制の闇を思い、それはそれとして、日本優勝世界一が素晴らしい!!
— RK (@koga_r) March 22, 2023
先週の卒園式で将来の夢でサッカー選手を語った子は3人位いたけど、野球はゼロ
でも、中学生は、野球部かなり楽しく盛り上がっていて、まだまだ野球文化は続くねhttps://t.co/m9hcLl21QZ
1日とんだけど、議事録読んでいく
○大村部会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの遠藤参考人からの御報告の内容につきまして、御質問があればお願いを致します。なお、質問される場合には、まずお名前をおっしゃった上でお願いできればと思います。後の参考人もいらっしゃいますので、14時20分ぐらいを目途に皆さんの御質問をお願いしたいと思っております。どなたからでも結構です。
○戒能委員
戒能でございます。遠藤参考人、大変リアルで実態に即したお話を頂きまして、現状がよく理解できたのではないかと思っております。中でも、この部会で必ずしも十分に議論されていなかった点、つまり、子どもへの性虐待のことを、より深刻に受け止めるべきだということは大変心に響きました。
それで、リスクを回避する制度的な設計が必要であることと、最後に支援とワンセットにした法整備ということをお話しになったのですけれども、遠藤参考人が今まで直接的な支援、相談もなさってきて、それから、性暴力のSNS相談ですね、あれについても関わっていらっしゃったと聞いておりますが、そういうお立場から、性虐待は長期間言えないのだと、介護に至るまで言えないのだというような現状からいえば、加害者である父との面会交流とか、それから親権で関与せざるを得ないという状況は、大変危険なものだということ、子どもの意思の尊重ということはいわれてきましたが、子どもへの影響の深刻さですね、それがずっと長期にわたり、そして影響がより深刻化していくということを考えると、やはりそういう制度設計は、子どもの利益、子どもの人権の尊重からいえば、リスキーであるという認識をすべきだということでよろしいでしょうか。
まず1問ということなので、そこまでにいたします。
面会交流によって深刻化の前に避難できたケースとか実務ではあるよ
○遠藤参考人
多分ですけれども、想像ができないことだと思います。性虐待ということが、本人が気が付く時期もすごく遅いです。あれは一体何だったのだろうというのが、すごく心身症状が出ていても、ずっと遅くて、30代とかになって突然に分かる。「私の中のわたしたち」とか、いろいろな本が出ていますので、多重人格とかそういうものの原因も実に多いのですけれども、だから、分からないのだけれども、これはいけないことのようであると小さいときに思っている一群があって、分かっていて絶対に嫌だという一群があって、幾つもいろいろなバリエーションがあります。
なので、私が今、相談を受けたり、その後の回復にお付き合いをしたりしながら思っているのは、外側からですね、第三者の目で探せるような制度がまず必要。いろいろなサインは出ております。子どもたちは様々なサインを出しているのですけれども、それを見過ごされてしまう。ごめんなさい、たくさんいらっしゃると思うのですけれども、弁護士の方とか司法の関係みたいなところですと簡単には分からないです。時間はゆっくり掛ける。話をして、じっくり考えて、本人たちの自覚も必要なものですから。それが難しいのですけれども。
司法の中で何とかワンストップにならないかというのは、中に少し書きましたけれども、例えば離婚調停とか面会交流とか、そういうのを審判を致します。そういうときに台湾なんかですと、そこの場所にNGOのブースがあって、支援者を配置というとおかしいですけれども、希望すればそこできちんと伴走型の支援をしてくれる方がつきそってくれる。 そこで話をしていくと、見えなかったものがようやく見えていく。見えることがすごく必要なのですよ。見える化をしていただきたい。見える化をしてから、どうするかを考えるというステップにしていただくのがすごく重要で、そうでないと、本人たちのダメージは、回復のためのケアを始めるまでダメージは続くのですよ。自分でそうだと思い、それについてのケアを始めるまで、ずっと続いていくのですよ。分からなくても続いていく。介護のことや、言葉に出せなくて、休みになったら家に帰らなければいけないとか、そういうことを繰り返し、繰り返しやっていったら、ダメージが続いていくのです。何とか言語化して、その話をこちらが受け止めて、回復に向けていくというスキームをどこかで入れない限りは、今、戒能委員がおっしゃったみたいに、ダメージは続き、深刻化していくと、それはそのとおりであると思います。
○大村部会長 ありがとうございます。
今、オンラインで3人の方、菅原委員、柿本委員、久保野幹事とお手が挙がっておりますが、ほかに御発言希望の方はいらっしゃいますか。赤石委員と武田委員。では、5人ということで進めさせていただきたいと思います。時間が限られていますので、質問もお答えも短い形でお願いできればと思います。
虐待があるケースこそ、会わなければ解決でもないところが悩ましいのよ
○菅原委員
ありがとうございます。大変重要で貴重なお話、ありがとうございました。では、手短に、お願いいたします。おっしゃっていただいた伴走型の支援を組み込むというのは、私たちにとっても非常に重要なご示唆であると思いました。ありがとうございます。今、遠藤様のセンターでは、どのようなメンタル面でのスタッフを配置されていらっしゃるのかということと、今後類似の支援機関を設置する時には、どういう専門家をそろえていくのがよいとお考えか、お教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○遠藤参考人
今、例えばよりそいホットラインで精神科の先生を雇っているとか、そういうことはできませんので、連携の中で、なのです。それで今、御相談として何十万件も取り扱っておりますけれども、直接お会いする方というのは大体6,000から7,000ぐらい、その中で子どもたちというのはまた減るわけですけれども、そのときに、全国ですから、いろいろな地域で民間の支援団体の方に連携をさせていただいて、例えば富山ならこの先生、神奈川ならこの先生と、カウンセラー、PTSDのことがおできになるような先生というのは限られてございますので、そこのところにつながって、まずは医療のところからということかなと思います。ですから、地域の中でネットワーク化をしているところにおつなぎをし、伴走型をするときにはうちのスタッフはずっと伴走していきますけれども、専門的なところはそちらの方にお任せすると、こんな形になろうかと。
それで、理想的に言えば、裁判所にドメスティック・バイオレンスと虐待については専門の入口があって、その案件があったらもうそこのところへ行くと、お医者さんもいるし、ソーシャルワーカーも大事なのです、ソーシャルワーカーもいるし、カウンセラーもいるし、そこで警察の方も関係していて被害届も出せるしと、こういうふうに、そこで一回自分が声を出したらうまくいくと。警察も私は必要だなと思っております。
○大村部会長 ありがとうございます。
○柿本委員
柿本でございます。御報告ありがとうございました。私も実は支援スキルについてお伺いしようと思いましたけれども、ほぼ理解できましたので、もう1点ほかの質問をさせていただきます。
結婚前にDV加害者や被害者を作らないための講座などが必要であるというお話だったのですけれども、具体的にはどのようなものをお考えですか?
○遠藤参考人
DVの被害者とか虐待の被害者を作らないための教育というのは、もうカリキュラム的にはかなりありまして、予防教育と呼んでおります。小学校とか中学校とか高校とかでやっているのもあるのですけれども、今回、中間まとめを見せていただいたら、地方自治体で講座のような形でおやりになるというのがあって、私もいいなと思いまして、もしもできればですけれども、結婚前講座、両親学校があるように、結婚前に必要なもの、だから、こういうことがドメスティック・バイオレンスですよ、こういうことをしてはいけませんよ、もしもこういうことがあったら、相談窓口はここですよ、そのベースになるものですね、そういうものを、あの中間まとめが離婚後でお書きになったようなことが結婚前にできたらいいなと。予防教育ということで、カリキュラムはかなりもうきちんとあると思っております。
○大村部会長 ありがとうございます。
○久保野幹事
東北大学の法学部の久保野と申します。お話どうもありがとうございました。オンラインから失礼します。菅原先生から御質問のあった支援の拡充の方策と御質問が重なりますけれども、子どもの性的虐待という側面から見ていった場合には、児童相談所ですとか市町村の児童保護系の保護等の対応や関係機関等が考えられると思うのですけれども、それらの主体や活動と、裁判所でのDV等への対応の拡充ということとの関係について、何か児相等についての期待ですとか、あるいは限界といったものについて御意見等がございましたら、教えていただければと思います。お願いします。
○遠藤参考人
2方向あると思うのですけれども、児童相談所のキャパシティーとして、もう満杯だと思いますので、そこで丁寧なことは、それは難しいと思いますのが一つと、それから、御想像が付くといいと思うのですが、児童相談所についての子どもたちの風評、子どもたちがどういうふうに児童相談所のことを考えているか、SNSなんかですごく情報交換されていますけれども、「携帯を取られてしまう、絶対行きたくない」、DVのシェルターなんかでもそうですけれども、そういうのがあるのです。それで、自分が分かっていて、これは困ったことをされているから何とかして保護してもらおうという子たちももちろん一定数いるのですけれども、何だか分からないし、怖いし、行きたくないしと、こういう状態にある者がたくさんいるだろうと。ですから、一足飛びに児童相談所と一緒にやればうまくいくというふうなことでもないかなというのが偽らざる実感でありまして、何とかいろいろな入口から、その「子どもたちの本当」に近付けるような仕組みが必要であります。例えば、御両親がここで離婚の調停をなさると、そのときに裁判所なり家庭裁判所なりで、子どもさんが本当はどうなのだろうと聴くというのを制度化されてあると、その後から児童相談所の方とつながるという方がずっとスムーズかなというのがイメージでございます。
○大村部会長 ありがとうございます。
○赤石委員
しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。今日は遠藤事務局長、ありがとうございました。私も相談員として関わっていた事例を思い出して、本当に長い間性虐待を受けた後、苦しんでおられる相談を聞いていたなというのを思い出しました。非常に深刻だと思っております。
今日は家族法の改正ということなので、少しお聞きしたいのですが、この中間試案でも盛り込まれている中にフレンドリー・ペアレントルールというものがございます。明示的には入っていないのですけれども、相手方に対して寛容な側が、よりいろいろな権利を認められるような、そんな書き方をされているかと思います。少し今、不正確なのですけれども。このフレンドリー・ペアレントルールというのが非常に逆機能するといわれているのが、この性虐待の分野だと思います。アメリカで聞いた事例では、お母さんが、父親が子どもたちに性虐待をしているということを裁判所で訴えた場合に、このフレンドリー・ペアレントルールに反しているということでお母さんの側に親権が認められなくなり、虐待の加害者である父親側の方に多分、単独親権で認められたというケースがあったと側聞しております。非常に危険なルールではないかなと思っているのですが、こういったことが遠藤事務局長としてはどのように思われるかということを少しお聞きしたいと思います。
○遠藤参考人
フレンドリー・ペアレントルールというのは、すみません、不勉強でそれほど存じ上げないのですが、今の御説明で聞くと、ちょっと。
○赤石委員 もう少し説明した方がいいでしょうか。
○遠藤参考人 そうですね。
○大村部会長 かいつまんでお願いします。
○赤石委員
例えば、相手側に1か月に一度しか面会を許容しないようなお母さんと、父親側は相手側に100日の面会交流を許容すると申し出ているときには、この100日の面会を許容すると言った側の方が、より親権者として適当であると考えるような、これは一例ですけれども、そういうルールです。
○遠藤参考人
もしも隠れている性虐待があったら、それは危険というか、怖いことだなと。その子は大変に厳しい状況に行くでしょうねということと、もう一つだけ、すみません、付け加えさせていただくと、性的な虐待というのは幼い子どもたちだけではないのです。小児性愛と性的な虐待との大きな違いはそこでありまして、幼い子どもだけをターゲットにするということではなくて、コロナ禍で増えた中で本当によく分かってきましたけれども、年齢は、幼い子どもであるという必要があるわけではないということがあります。なので、今のようなお話ですと、本当に、もしもその子どもたちが言語化できない、相談ができない、自覚ができない中であるとすると、私は余りにも不安だなと思いました。それでよろしいですかね。
○赤石委員 ありがとうございます。
○大村部会長 ありがとうございます。
「それでよろしいですかね」っていう回答、って何?有識者???
○武田委員
親子ネット、武田でございます。本日は貴重なお話ありがとうございました。まず冒頭御説明あったように、殴る蹴るだけが暴力ではない、身体以外のDVにも注力していくべきというところ、非常に共感をするところでございます。ただ、遠藤参考人に私が申し上げるようなことでもないかとは思うのですけれども、例えば精神的DV、今日は余り説明ありませんでしたけれども、要件設定をどうするとか、事実認定をどうするといったことというのは非常に難しいのかなと、そんなふうに感じています。こういった要件設定とか事実認定の難しさ、あとは、基本的に保護命令以外というのは手続保障がない、要は誰かがきちんと認定するわけではない、と思っています。そういった部分が今日の遠藤参考人の資料にあったような、虚偽DVという表現がありましたけれども、こういう意見が出る要因にもなっているのではないかと、そんなふうに感じています。このような、要件が固まっていないからこそ、これがDVか、そうではないのかというところから、虚偽DVなどの表現が出てくると思っているのですけれども、こういう事象があるのかどうか、あるとすると、どう要件を整理していくのがよいのか、この辺りについて遠藤参考人の見解をお伺いできればなと思います。
○遠藤参考人
今おっしゃった虚偽DVというのは、資料の中の離別後の法的な手段を使った暴力、そこの中の例として挙げているものですか。
○武田委員 そうです、こういう意見が他方から出てくるということを表現されていらっしゃるのかと思うのですけれども。
○遠藤参考人 ドメスティック・バイオレンスを、認定をするというふうな制度的な流れというのは、それはないですから、私はどこまでお話ができるか、公的な立場でどうのこうのということでもないので、今それこそ法律改正がなされるところなので、内閣府の女性に対する暴力専門調査会ですか、そういったところで御論議されているところかなと思いますけれども、相談現場の実感として、性的なDVとか性虐待とかが、だんだんお話が引き出されていくのと同じように、その方がドメスティック・バイオレンスなのか、それともそうではないのか、私は、そうではない的なところは体験はございませんけれども、私は支援の側の方が分からないということはないと思っておりますので、やはりきちんとお話を聴くということに、相談支援の側からは、尽きるのかなと思っております。
○武田委員 ありがとうございます。
○大村部会長 ありがとうございました。
まだほかの委員、幹事から質問もあるかとも思いますけれども、先ほど申し上げましたように、後の参考人の方もお待ちになっておりますので、ここまでにさせていただきたいと思います。
遠藤参考人におかれましては、本日大変お忙しい中を当部会の調査審議に御協力を頂きまして、誠にありがとうございました。
○遠藤参考人 ありがとうございました。
○大村部会長 それでは、ここで遠藤参考人には御退席を頂きまして、次の参考人に入っていただきたいと思います。遠藤参考人、ありがとうございました。
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!
