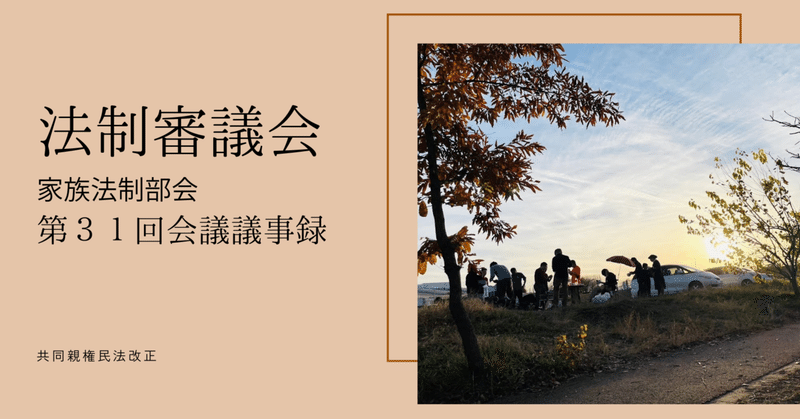
法制審議会家族法制部会第31回会議議事録読む4~石綿幹事・赤石委員・北村幹事・戒能委員
また朗報
#原則共同親権 が最多?
— RK (@koga_r) December 20, 2023
ありがとうございます!!またも、朗報✨ https://t.co/4ERIEEb9qU
文化よ変われ
子どもがね、遠くに暮らすおじいちゃんおばあちゃんに会いたいってなってたんだけど、家庭裁判所調査官がさ、祖父母には面会交流権ないですからね、って言い放って切り捨てたのさ#単独親権制 の民法で起こっていることよ
— RK (@koga_r) December 20, 2023
ちゃんと、子どもをしあわせにする日本にしようよ https://t.co/KRQNSx5blR
国賠のアプローチが芽吹く
松野先生が取り組まれてきた共同親権の欠陥の問題が是正されていますね!
— RK (@koga_r) December 21, 2023
婚姻中の共同親権には実は欠陥があり、だから、非婚時に拡充することができなかった問題を一挙解決です✨ https://t.co/A7wCA9HR5e
久々にご購読いただき、今日のマガジン追加はこれにしよう
久々にご購読いただきました✨
— RK (@koga_r) December 21, 2023
この戦略の有用性はまた語ろうかね~
離婚請求棄却大作戦【有料部分追記あり】|弁護士古賀礼子 @koga_r #仕事の心がけ https://t.co/buAAjIaQQH #note
で、議事録を読む
それでは、第1、第2だけではなくて、今日は最後まで行きたいと思うのですが、第1、第2について石綿幹事から御発言を頂いたところで、その他の方については、再度たたき台の修正版が出たところで更に御議論いただくということにさせていただければと思います。
○石綿幹事
幹事の石綿です。発言の機会を頂きありがとうございます。今の池田委員の御発言の第2の1(2)で、池田委員が同居親をという限定を付けることで分かりやすくということをおっしゃいましたが、これは限定を付けなくても、場合によっては解釈上成り立ち得るのではないかとも思います。同居親が決めたことについて別居親が口を出すということは、親権行使として子の利益に反すると解される場合があるということもあり得るのかなと思いますので、その辺りを次回の資料の際に整理していただければと。
○窪田部会長代理 ありがとうございました。石綿幹事からは、池田委員から先ほど御提案があった方向性について、必ずしも文言を修正しなくても、解釈論によっても実現できるのではないかという御示唆を頂いたものと思います。この点について、事務当局の方でも次回以降検討していただいて、ということになろうかと思います。
赤石委員の御発言までということで、一旦区切らせていただきたいと思います。
同居親至上主義、怖い
○赤石委員
お時間を頂きましてありがとうございます。赤石でございます。今日は第2から次に移るのだろうと思って、余り発言を用意していなかったのですけれども、第1、第2のところの議論がまだあったので、若干発言させていただきます。
まず、棚村委員の御発言を聞いていて、少し私の中での違和感がございました。こどもに対して両親が関わること、それは大変よい価値だと私も思っておりますし、私自身もできるだけそのように実践してまいりました。そのような価値を理想として掲げるということはいいし、理想として掲げることによって、またその教育効果等があるということもあるのかもしれないのですが、少し御発言の中で理想として掲げるところの重点が多く、そのために、それを掲げることによっての不利益を負う人間に対しての目配りが少し少ないなという、私はやはり同居親、主にひとり親の方たちを支援していると、理想を原則として示した方がいいとおっしゃっているのですが、しかし、では不利益を負う人たち、弱者の方をどのように配慮するのかというところの論点を一生懸命私どもは議論しているのだと思って聞いておりました。
なので、先ほど、共同親権になるときの考慮要素の中でもマイナスのものを示すのか、プラスのものを示すのかという議論がありましたが、やはり私はプラスになる、平穏にコミュニケーションがとれること、協力し合えることといったことをこの間も提案させていただいたのですけれども、そういったことがなければ、こどもにとってはかえって葛藤の現場に長く置かれてしまい、不利益になるのではないかと思います。こどもの利益というのは非常に抽象的な概念でして、何とでも言えてしまうというところが残念なところなので、しっかりそこを書き込まなければいけないと思います。
第2点は、今日私の提出資料として出させていただきました、医療4団体、日本産婦人科学会、日本法医学会、日本法医病理学会、日本小児科学会の4団体が法務大臣に宛てた要望書、私が提出しなくてもよいのですが、一応やはり非常に重要な要望書だと思いますので、提出させていただきました。やはり共同親権制度が導入された場合に、医療の必要なときに両方の親権者の同意を得るということが必要である場合に、非常に医療を実施することが不可能、あるいは遅延することを懸念しているといったことでございます。また、ドメスティック・バイオレンスなど、児童虐待があった場合に、一方の力関係で共同親権の取決めがなされてしまった場合にもこういった事情が生じるのではないかということが書かれていて、何回か前に私は滋賀医大のケースも新聞記事を出させていただいたわけですけれども、この問題はまだ解決していないと思っておりますので、ぜひ御注目いただきたいと思います。
今のところ、以上です。
○窪田部会長代理 ありがとうございました。赤石委員から2点、御発言を頂いたかと思います。1点は、こどもの養育に両親が関わるという重要性、その価値を理想として考えるということ自体は考えられ得ることではあるけれども、しかし、それだけであれば不利益を負担する人間への配慮が必ずしも十分ではないのではないかということで、共同親権に関して裁判所が判断する場合については、プラス要件をやはり積極的に示していくことが重要ではないかという御発言だったかと思います。もう1点は、本日提出していただいた資料で、医療行為に関する同意に関するものとして、医療関係の4学会から出された要望というものについて御説明を頂きました。これについては、恐らく医療行為についての同意の問題、それから共同親権との関係といったことが必ずしも法律上明確ではないので、当然医療関係者としては懸念を持つところであると思いますが、それについてどう答えるのかというのは別途検討が必要なことは間違いないのだろうと思います。これについて、事務局の方で何かお考えはございますか。
○北村幹事
事務当局でございます。医療行為の同意と親権行使が必ずしも同じかどうかということについては今、部会長代理の方から御説明がありましたように、一致するものではなく、議論があるところではございます。ただ、この申入れを頂いた団体は、この書面の冒頭にもありますように、その改正案の趣旨・理念については理解するところだということです。現在の状況については当然、これを法務省に頂いた際に、我々の方からもこれらの団体に御説明をさせていただきましたが、これらの団体の方々にも、現在の検討状況については一定の御理解を得ております。また、要望のあった部分についてはこちらの方の議論が進んでいく中で、関係省庁とも調整をしていくことになろうかと思っております。
○窪田部会長代理 ありがとうございました。そのように取扱いをお願いいたしたいと思います。
それでは、少し議論を切るような形になってしまいましたが、部会資料30-1の第1と第2の御議論はここまでとさせていただきたいと思います。
前回会議も含めまして、部会資料30-1の第1と第2について非常に様々な御意見を頂きました。事務当局から示されたたたき台に賛成する御意見もあれば、その修正を御提案いただくような意見もあったように思います。本日の段階では、こうした点の意見の集約を直ちに図るのではなく、皆様から御意見を頂いたということを受け止めさせていただき、今後事務当局において本日の議論を踏まえて要綱案のたたき台を更にブラッシュアップしていただくということになろうかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、中途半端な時間に休憩を入れることになってしまいそうなのですが、部会資料30-1の第3以降の議論に移りたいと思います。第3以降は第7まであるのですが、全部では少し多いので、残りの部分を大きく二つに分けて、まず第3と第4について御議論いただき、その後で今度、第5から第7までについてまとめて御議論いただくという形で進めていきたいと思います。
それでは、部会資料30-1及び2の第3以降の部分について、事務当局から資料の御説明をお願いいたします。
○北村幹事
部会資料の内容について御説明いたします。今回は前回に引き続いて、要綱案の取りまとめに向けたたたき台について御議論いただきたいと考えておりまして、部会資料30-1と30-2をお送りさせていただいておりますが、前回会議でも御説明させていただいたとおり、このうちの部会資料30-1のゴシック体の記載がこの部会での取りまとめの対象となるものですので、こちらの資料を中心に、その内容の当否や修正すべき内容について御議論いただきたいと考えております。それでは、第3から第7までまとめて簡単に御説明させていただきます。
まず、第3の1では、養育費等の請求権に一般先取特権を付与するものとすることを提示しております。部会のこれまでの議論においては、先取特権を付与する範囲について、一般債権者の利益との関係での調整が必要であるとの御指摘を頂きました。そこで、今回のたたき台では、先取特権を付与する範囲を下記の定期金のうち子の監護に要する費用として相当の額の範囲内とすることを提示しております。
次に、第3の2では、第29回会議における御議論を踏まえ、法定養育費を取り上げております。第29回会議では、このような制度を作る必要性やその正当化根拠を含め、幅広く御議論いただきました。今回の資料ではそういった御議論を踏まえ、仮に法定養育費の仕組みを新設するとした場合の具体的な要件や効果についても、ゴシックの(注1)から(注3)までに検討のたたき台をお示ししております。第3の3は、養育費等に関する裁判手続における情報開示義務に関する規律を提示しており、第3の4は、執行手続における債権者の負担軽減のための方策を取り上げております。
続いて、部会資料30-1の第4では、親子交流について取り上げております。第4の1は、子と別居する親とその子との交流に関する規律を提示しております。その内容は、部会資料29で御提示させていただいたものから大きな変更はございません。なお、ゴシックの第4の1の(注)では【P】を付した上で、父母以外の第三者と子との交流に関する規律についても記載しております。本日の会議では、まずは父母と子との交流に関する議論が中心となろうかとは思いますが、父母以外の第三者と子との交流についての御意見も頂けましたら、今後それを踏まえての会議資料を作成させていただきたいと考えております。
次に、第4の2は、裁判手続における親子交流の試行的実施に関する規律を提示しております。この論点については、この部会の第29回会議において、その要件をどのように設定するかなど、様々な御意見を頂きました。部会資料30-1では、こうした御意見を踏まえて、家庭裁判所が親子交流の試行的実施を促すための要件として、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことや、事実の調査のため必要があると認めることを要求するという案を提示しております。本日の会議でも、その要件や効果をどのように規律すべきかについて御議論いただきたいと考えております。
第5では、養子に関する規律を取り上げております。第5の1は、基本的に養子縁組後に誰が親権者となるのかという論点について現行法の解釈を整理し、これを明確化しようとするものであり、第5の2は、未成年者の利益を損なうような未成年養子縁組に対応する規律を整備することを提示しております。
第6では、財産分与に関する規律を取り上げております。第6の1では、考慮要素の明確化等について、第6-2では、期間制限の伸長について、第6の3では、裁判手続における情報開示義務について、それぞれ取り上げております。文言の表現ぶりなどを修正している点はありますが、資料で提示している規律の内容は、部会資料24の内容から実質的な変更をするものではありません。
最後に、第7では、夫婦間の契約の取消権、裁判上の離婚の事由の見直しや、その他の所要の整備について取り上げております。
資料の説明は以上です。
○窪田部会長代理 どうもありがとうございました。
それでは、部会資料30-1の第3及び第4について御議論をお願いしたいと思います。第3と第4、いずれについて御発言いただいても構わないのですが、御発言の際には、どの部分を念頭に置いての御発言なのかということを特定していただきますようお願いしたいと思います。それでは、どなたからでも挙手をしていただけますでしょうか。
養育費のこととか
○戒能委員
ありがとうございます。委員の戒能です。第3と第4、両方ということですので、第3の養育費の中の2の法定養育費の件と、それから第4の親子交流の2の試行的実施について、意見を述べたいと思います。
法定養育費制度を創設するということ自体にはもちろん賛成しております。しかし、その法定養育費の金額の問題がどうしてもあります。それで、極めて廉価なものになる可能性というのがあるとすると、そこはもう一度検討する必要があると思っております。
それで、部会資料30-1の資料の4ページの2、法定養育費のところなのですが、少し分かりにくいのが、この限りではないという条件が付いていて、支払側に支払能力を欠いているという点が一つ挙げられて、その次に、又はという、どちらかということなのですけれども、その金額の問題と大いに関わり合いがあると思われるのが、支払によって支払側の生活が著しく窮迫する、あるいは窮迫することを証明したときはこの限りではないというような書き方になっておりますけれども、これは支払能力がないというだけでいいのではないかと考えております。
それとの関係で、部会資料30-2の19ページを御覧いただきたいと思うのです。そこに法定養育費の額、その前の18ページから始まる(2)のところで、誰が請求権者か、父母の一方としているということなのですけれども、そこに、これは削除していただきたい、法定養育費として支払われた金銭を父母の一方が自らの遊興費に費消することを許容する趣旨ではなく、というのは不要な一文だと考えております。かなり偏見をもたらすものでありますし、先ほどのゴシックの方の、支払能力がない、それから窮迫するというような二重に守られるというような立場と著しく対等性、平等性を欠いておりますし、偏見をもたらすということで、この補足説明の19ページの記述は削除していただきたい、不要なものだと考えています。それが1点目です。
それから、親子交流の試行的実施のところなのですが、これもいろいろ、(1)で、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がない場合で、事実の調査のために必要があると認めるときは、試行的実施を促すという表現、それから(2)では、そういう試行的実施を行うときに、第三者の立会い等を決めて、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止し、というふうな規定があるわけですけれども、こういう注意的な規定の必要性はあるとは思うのですが、どれだけ実効性が、特に言動を禁止するという場合に、実効性が本当にあるのかどうかということも考慮しなければならないと。注意的に規定するということですからそこまで考える必要がないのかというと、そうでもないかなと思っています。
それで、これもまた補足説明の方なのですが、24ページに注書があります。(注1)と(注2)の両方なのですが、ここも少し御説明いただきたい。確かに、子の利益の点なのですが、(注1)の方は、本案と区別が必要だというようなところから、この資料では子の利益という文言は用いないと、それから(注2)の場合は、家事事件手続法第65条に、そこに書かれたような子の意思の把握について規定があるけれども、試行的な実施というのは飽くまで事実の調査であって、審判そのものに当たらないということで、家事事件手続法第65条は適用されないというようなことで、子の意思の把握の方法にすぎないというような位置づけがされているわけなのですが、子の利益の考慮というのは、本当にこの家事事件手続法第65条がいっている趣旨からいって、当てはまらないとか用いないということでいいのかという疑問を持つわけです。
むしろこれは、名古屋の事件を前々回御紹介したわけなのですが、それは子にとっては試行的実施であれ変わらないのではないかと、やはり影響を大きく与えるということがあります。しかも、名古屋の事件の場合は子の意思が重要なポイントになるわけですから、拒否しているのにもかかわらずと、その場合にどういう影響を子に与えるかということは重要な要素だと考えられますので、子の利益、これは子の利益というのは非常に中身がはっきりしないままここでは使われているという御意見があったと思うのですけれども、この場面で子の利益は十分に考慮していくべき要素ではないかと個人的には考えております。
以上でございます。ありがとうございました。
○窪田部会長代理 ありがとうございました。大きく2点、御意見を伺ったかと思います。一つは法定養育費に関して、金額について余り低額にならないようにしてほしいということと、支払能力を欠く場合、又は支払によって困窮が生じる場合ということなのですが、後者の方は不要ではないかということが御意見としてございました。それから、部会資料30-2の19ページの(3)のすぐ上のところについて、法定要求費として支払われた金銭を父母の一方が自らの遊興などのために費消することを許容する趣旨ではなく、という文言は不要ではないかということでした。これは、法定養育費の請求権者をこども自身ではなく父母の一方とすることとの関係で、飽くまで父母の一方に渡す種類のお金ではないということを書いてもらったのだろうと思いますが、恐らく御指摘は、こういう書き方をすると、ハレーションを起こすのではないかという、そういう御指摘もあったかと思います。
○戒能委員 ハレーションというか、誤解を生じます。
○窪田部会長代理 それから、親子交流の方に関して言うと、試行的実施ということについて、幾つかの文言について規定の実効性があるかということとともに、これは事務当局に対する御質問ということになろうと思いますが、24ページの(注1)の子の利益という文言は用いていない、(注2)の家事事件手続法第65条は適用対象ではないということについて、これは、子の利益が重要ではないとか、家事事件手続法第65条がこの場面では意味がないとかということよりは、多分、全体の枠組みの中で審判事項ではないということを前提としての説明だろうとは思いますが、事務当局の方から何かを補足的に御発言いただくことがあれば、お願いしたいと思います。
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!
