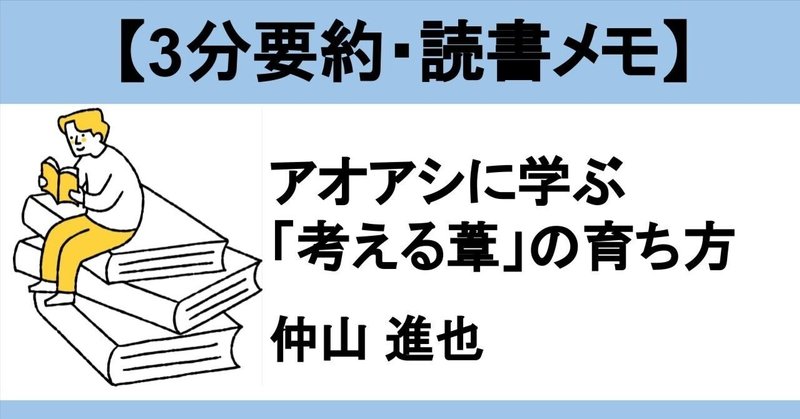
【3分要約・読書メモ】アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方 カオスな環境に強い「頭のよさ」とは
ご覧頂き誠にありがとうございます。
今回は「アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方」についての記事となります。
■著者
仲山進也(なかやま しんや)
慶應義塾大学法学部卒。シャープを経て、創業期(社員約20 名)の楽天に入社。2000年に楽天市場出店者の学び合いの場「楽天大学」を設立、人にフォーカスした本質的・普遍的な商売のフレームワークを伝えつつ、出店者コミュニティの醸成を手がける。
2007年に楽天で唯一のフェロー風正社員(兼業自由・勤怠自由の正社員)となり、2016年には「横浜F・マリノス」とプロ契約、コーチ向け・ジュニアユース向けの育成プログラムを実施。
著書『「組織のネコ」という働き方』『組織にいながら、自由に働く。』『あのお店はなぜ消耗戦を抜け出せたのか』『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則』など。
■まとめ
・「考えない人」は、単に「実行」を繰り返す。言われたことをそのままやる。上達するために、具体的な手法やテクニック、スキルを求める。しかし、それらを習得しても、答えのないカオスな状況で判断ができず行き詰る。
・「考える人」は、「観察→判断→実行」ループを高速回転させる。観察して得た「入力情報」を「価値基準」と掛け合わせて選択肢を考え、仮説を元に選ぶ。
・「考える人」は、「仮説→試行→検証→規範化」を繰り返しながら量稽古をするので成長する。まず、やってみる(試行)からスタートすることが大事。
■観察
・「よい観察」をするためには、まず視野に入ってくるもの(アクセス情報量)を増やす。視点・視野・視座を意識的にコントロールして、見るべきものを見る。そうすることで、「良い観察」から「よい入力情報」を得ることができる。
・ただし、物理的に視野に入ってきたとしても、自分が意識していないとインプットはされない。人は、自分が見たいモノを取捨選択して見みており、知らないモノや偏見があるモノは見ることができない。
・フラットにインプットするには、心理的柔軟性(評価を決めずに受け取る素直さ)を保つ必要がある。
■判断
・「良い判断」をするためには、「よい入力情報」と「よい価値基準」が必要。
・「判断」ステップで行われる処理は、「解釈・評価・選択」。
・価値基準をもとに入力情報の解釈が行われ、取り得る行動の選択肢が出ます。その選択肢を「こうすればうまく行くのでは」という仮説を元に比較評価し、選択する。このプロセスが「判断」
・選択する時には精神状態も大切。ご機嫌時と不機嫌時で選択は変わってしまう。
■実行
・「よい実行」をするには、「よい仮説」が必要。
・「よい仮説」を持つには、思考の結果を振り返る(検証)が大切。最初に「仮説」から入るよりも、まず試しにやってみることで、足元の「現実」が明確になる。それをもとに仮説を立てる。
・「現実」と「理想(仮説)」のギャップがハッキリすることで、課題が見えてくる。(課題=理想ー現実)
・「振り返り」を丁寧にすることで、課題を明確化する。
①何が起こったのか(事実)
②どう考えたか(解釈)
③得られた学びは何か(規範化)
④次どうするか(適用)
■才能
才能を発揮するには、まず最初に量をこなすことが重要。量をこなすことで、自分の適性に気づき、その才能を研ぎ澄ますことができる。多くの人が効率的に目標達成したいと考え、自分に合わない事や意味がないと感じることを避けるが、実は、量をこなすステップを踏まないと才能を見つけることも、開花させることができない。
好きだの嫌いだの言わずに、できることを増やす。できないことを減らす。
「自分の強みはこれなので、違いことはやりたくありません」と言わない
食わず嫌いをせず、とにかくやってみる。意味がわからなくてもいい。
できなくても、「向いていない」と決めつけないで、できるようになるまでやる
量稽古(同じことを繰り返すというより、あらゆるパターンを経験する)
できることが増えてくると、いろいろな仕事を任される(報酬は仕事)
そのうち、キャパオーバーになる。試行錯誤するうちにキャパの範囲内でできるようになる。ホンモノの強みが浮かび上がってくる。
■感想
ポッドキャスト「みんなの才能研究所「みんラボ」」の番外編で紹介。「みんラボ」は、才能博士 たかちんさん、株式会社COTEN 深井龍之介さん、株式会社YOUTURN 中村義之さんの3人が才能について研究し、新しい生き方を模索する番組。
番外編として、『楽天大学の設立者』仲山進也さんをゲストとして出演し、これまでの活動や、思考の'癖'について話す中で、著書「アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方」も紹介されていた。
本書では、サッカー漫画「アオアシ」のエピソードを通して、メタ認知と才能の見つけのヒントを学ぶことができます。「自分で考えて動く」ことが求められるビジネスシーンで、状況を理解し行動に移すメタ認知と、自分の強みを活かしたアクションをする才能の2つがとても変わりやすく解説されています。「アオアシ」を読んでいると理解が深まるでしょうが、読んでいない自分でも十分に参考になりました。自ら動ける自律型の人材になりたい人や、そんなチームをつくりたい人におすすめです。
最後まで読んでいただきて、ありがとうございました。
その他の記事はこちら
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagramもやっているので、もしよかったら覗いてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
