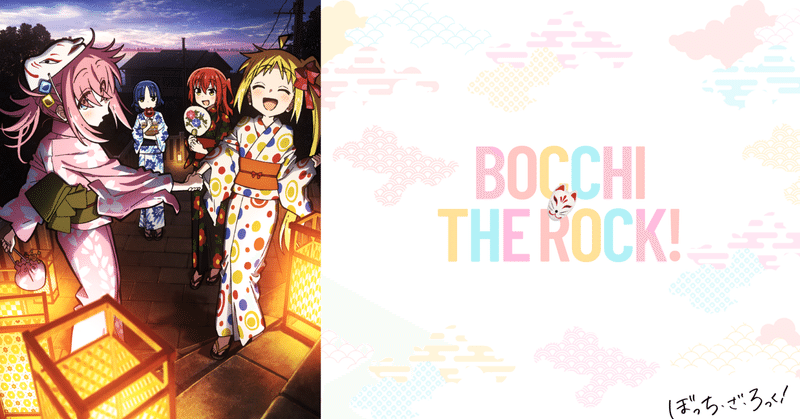
良作だったからこそ「ぼっち・ざ・ろっく!」に対して思ってしまった事
ぼっち・ざ・ろっく!ついて、自分なりの感じた事をつらつらと書いてみようと思います。
制作会社考察
2022年の秋アニメの話題作「ぼっち・ざ・ろっく!」について書く前に、ふと思い出すのは、2022年の夏アニメ「リコリス・リコイル」が大ヒットした事です。
リコリコと言えばANIPLEX傘下のA-1 Picturesが手掛けたアニメ作品ですが、ANIPLEX傘下にはもう1社CloverWorksという制作会社があり、そのCloverWorksが手掛けた作品がぼっち・ざ・ろっく!となっています。
そんなANIPLEXは、KADOKAWAと並ぶ、いや、それ以上のアニメ配給会社のため毎クール手掛けるアニメ作品数はかなりの数となりますが、その中でもクール内の「勝負作」に関しては、子会社であるA-1 PicturesかCloverWorksに制作を任せる事が多く、これまでもこのコンビによって数多くのヒット作が生み出されています。
A-1 Pictures
エロマンガ先生、ソードアートオンライン、冴えカノ、七つの大罪、かぐや様、エイティシックス、うたプリ、リコリコ
CloverWorks
青ブタ、約束のネバーランド、シャドーハウス、着せ恋、明日ちゃん、SPY×FAMILY
この通り凄い作品ばかりですが、この最強コンビが満を持して送り出した2022年秋アニメの勝負作が「ぼっち・ざ・ろっく!」であり、その自信作を実際に見て、そして感じた事について次から記載させて頂きます。
シナリオ構成
まず最初にお伝えしたい点です。
それは、この先ネガティブな事を書きます、という事です。
ですが、それは作品を下げたいわけではなく、むしろ良作だったからこそ、もっと高みを…!と、我がままを書きたくなってしまったのです。
ましてや、そんな我がままを書いているのはただの視聴者にしかすぎない1個人ですので、この点を含みおき頂きつつ、どうかゆるりと読んで頂けると嬉しいです。
では、早速本題に入っていきます。
実はこのアニメ、中盤までは猛烈にテンションが上っていて、早く続きが見たい!と気がせいていました。
めちゃくちゃ面白かったです。
なのですが。
実は、終盤は失速感を感じながら見ていました。
この感覚を言葉にすると、どんな表現が適切なんだろうと考えてみたら、ふと頭に思い浮かんだ言葉が次でした。
「はじめちょろちょろ中ぱっぱ、じゅうじゅう吹いたら火をひいて、ひと握りのワラ燃やし、赤子泣いてもふた取るな」
かまどでご飯を炊く時の名言ですが、シンプルにまとめるとこの作品は、まさにこの感じをトレースするような構成になっているなと感じたのです。
つまり、アニメの盛り上がりのピークが中盤に作られていたんですよね。
そしてこの名言の通り、率直に言うと、アニメ終盤は、やや火力不足を感じてしまったのです。
え!終盤も良かったじゃん!という意見がある事はわかっているつもりですし、むしろそちらが大多数という事も理解しているつもりです。
でも、何かが違った、いや、違う風に感じてしまったんです。
本作のメインテーマは言うまでもなくぼっちちゃんの成長であり、いつも誰かに引っ張られ、後ろをついていくだけだったぼっちちゃんが、いつの間にか仲間を引っ張る存在になる(なりつつある)事を描いた、ある種のサクセスストーリーとなっています。
そんな本作を毎週画面にかじりつき、食い入るように見ていた中盤は、序盤、目も当てられない程のコミュ障だったぼっちちゃんが、中盤になり様々な事や人と出会い、迷ったり、悩んだり、もがいたりしながら成長していく様が描かれていて、その1つ1つが、大なり小なり"あるある"に繋がっていて、共感を感じる事が多かったんですよね。
だからこそ、自分がぼっちちゃんのすぐ横に立ち、応援しながらぼっちちゃんを見つめる視点で作品を見る事が出来ていましたし、もっと言えば、自分に置き換えて見ていたからこそ、強い共感性や中毒性を生み出していました。
ですが、それは裏を返せば、これ以上に強い共感性が終盤に描けない限り、ぼっちちゃんの牽引力が弱まっていくという事を示唆していて、その示唆通り、終盤に悪い予感が的中した印象でした。
改めて中盤のシナリオ構成を振り返ってみます。
5話:リハーサルでギターを弾きながら熱く思いを語るシーン
6話:路上ライブを成功させてファンが出来たシーン
7話:初めて友達が家にきてくれたシーン
8話:虹夏の話をきいてタイトル「ぼっち・ざ・ろっく!」が回収されたシーン
これを見てわかる通りですが、メリメリぼっちちゃんが成長していく姿が畳み掛けるように描かれています。
1話~4話でただただ面倒だった子が、5話~8話で仲間と出会い、様々な経験を通し、1つ1つ成長していくシーンが毎話展開されていて、それを見ながら思わず心で手を叩き、「よく出来たね!ぼっち!」と、声に出して応援する事が沢山出来たのが中盤の展開でした。
”かまどご飯”でいえば、まさに火力全開の中盤という状態です。
そして実はこのアニメ、きれいにパックリ割れたシナリオ構成になっていて、全12話を1/3づつ、序盤、中盤、終盤と切り分けているんですよね。
1話~4話:コミュ障ぼっちちゃん物語
5話~8話:バンド活動を通しての成長
9話~12話:ある種の成長をしたぼっちちゃんの物語
キャラを印象づける序盤、強い共感性を生み出した中盤、それに続く終盤で構成されているのですが、強烈な中盤に続いた終盤では、制作側は1つステージが上がったぼっちちゃんの姿を描くという選択をしました。
え!成長!?言い過ぎでは?と若干思う部分はありますが、江ノ島でのエピソードや、学園祭に参加し、メイド服をちゃっかり着ていた事や、最終回のライブで酒瓶でピンチを脱出する場面は、これまでのぼっちちゃんならば”人前”という前提では確実に逃げ出しているか、あるいは気絶してミノムシになっているシチュエーションだと思うのです。
でも(プロセス上気絶をしたり逃亡したりはあったにせよ)、結果として最後はぼっちちゃん自らで気がついたり、考えたり、行動をするシーンに繋がるシナリオになっていたんですよね。
それともう1つ大切なポイントがあって、このアニメ、8話でタイトルを回収をしているんですよね。
つまり、9話以降はセカンドステージの位置づけになっていて、1段階上がったぼっちちゃんの姿を描く!と言う、運営のはっきりした意思表示になっているのです。
そんな状態で入った終盤に、中盤までと同じか、それ以上の共感性を感じるためには、レベルアップしたぼっちちゃんに対し、どれだけ沢山一緒に手を叩く事が出来るシーンが描けるか?がとても重要になってきます。
ですが(繰り返し書いてしまいますが)、自分はこの点において、それをあまり感じる事が出来なかったんです。
何故だろう?と考えてみると、恐らくそれはぼっちちゃんが”立派になりすぎた”からだと思っています。
あれで立派!?と思われるかもしれませんし、事実、まだまだあんな風ではありますが、それでも終盤のぼっちちゃんは、ある意味でしっかりアニメのヒロインをやってのけたのです。
これまで、自分と同じ目線にぼっちちゃんが立っていて、ある種の共感や応援で見ていた相手が、9話以降は少し上の位置にステップアップし、しっかりヒロイン的な位置づけで行動し、そして作品をひっぱる存在として登場していたんですよね。
このチェンジは8話でタイトル回収された時に、大きく深呼吸をし、自分の心に落として納得しておくべき事だったのですが、その準備が間に合わず、そしてその展開にびっくりしてしまい、結果、ギャップを感じてしまったのでした。
もちろん、全12話の中で起承転結をしっかりつけなければならない事は分かっています。
原作未読なのではっきりした事はわかりませんが、もっとシンプルな話、制作陣は原作に忠実にアニメ展開をしただけなのかもしれません。
そんな中でも、制作陣は鬼作画や演出強化を加速させ、最大限面白く見せようと努力をしてくれていた事も痛いほど伝わっています。
でも、終盤3話という短いスパンにおいては、中盤までの痺れるような強い衝撃をあまり感じる事が出来ず、少しお上品になったぼっちちゃんに対し、ちょっとだけ距離感を感じて見てしまったのは事実でした。
なので、最終話の酒瓶プレイも、きっとぼっちちゃんはこのピンチを乗り切るだろうなと、どこか冷めた目で見ていたりしました。
他のアニメ作品の名前を出すのはあまりよろしくないですが、本音で言えば、同じきらら枠のまちカドまぞくのシャミ子のように、ずっとおバカで居てほしかったなあと思ってしまったり。
別の言い方をすれば、ぼっちちゃんが急に遠くに行ってしまったような感覚すらあって、その点において寂しさを感じるとともに、共感性を感じづらくなって居たというのが本音でした。
ですが、ここまで下げて書いてフォローにならないかしれませんが、冒頭に書いた通り、このシナリオを駄目だなんて口が裂けても言えませんし、言いません。
テレビアニメである以上、1クールという限られた期間で表現しなければならないわけですし、結果、性急になってしまう部分が出る事は致し方ないです。
そう考えてみれば、数あるアニメ作品と比べ、あきらかに上位に位置する神アニメである事も間違い事実でして。
ただ、残り3話の展開が少し急だったので、突然普通の面白いアニメになったぼっち・ざ・ろっく!を、一般アニメとして見る事が求められた時に、気持ちの軸足をどこに置けば良いかが消化しきれませんでした。
実は、このもやもや感はシナリオ以外にも理由があって、それはキャラとの関係性にもあると思っています。
その点について、続けて深掘りしたいと思います。
キャラについて
キャラ同士の関係性ですが、原作がそうなっていた?声優ビジネスの事情?その他大人の事情?などはっきりした事はわからないのですが、ぼっちちゃんのメインパートナーが前半~中盤は虹夏だったものが、9話以降は喜多ちゃんになった事で、ぼっちちゃんの”良い意味でのうざさ”があまり引き出せなくなっていたように感じました。
あー、ぼっちちゃんうっざ、めんどくせー!でもがんばれー!を感じるシーンが減ってしまっていたように思うのです。
キャラには当然特徴や癖があって、濃淡が激しい程作品のエッジは際立ちますが、その点で見てみると、リョウはクールな感じや毒っぷりから支える側ではなくかき混ぜる側なのは明白ですし、リョウが荒らした場を整えるのが喜多ちゃんの立ち位置で、そこから落ちてしまった時の受け皿が虹夏の役割となっています。
このバランスは本当に秀逸で、ぶん投げるリョウ、整える喜多ちゃん、拾う虹夏が、ぼっちちゃんというバスケットボールを、みんなでゴールネットに鋭く投げ込むようなスピード感とテンポ感を生み出しています。
ただ、9話以降は、包み込む優しさを持つ虹夏の出演機会をほぼ無くしてしまった事で、結果、寄り添うタイプの喜多ちゃんでぼっちちゃんが止まってしまったんですよね。
この事によって、ぼっちちゃんが自ら走ってゴールネットに向かっていく事になり、そして、ぼっちちゃんが自分で得点を入れる事が増えました。
この展開は、上に書いた事の繰り返しですが、9話以降はそういう事を描くと決めての展開ですから仕方無いと分かっていますし、多少なりともぼっちちゃんは成長をしているので、いつまでも虹夏頼りでは駄目というのも分かっては居るのですが、でも、やっぱり、折角しっかりしたキャラ付けが出来ているのですから、最後まで、3キャラのバランスは変えて欲しく無かったなって思ってしまったんです。
もし虹夏が最後まで支える立場でぼっちちゃんを包み込むシナリオだったとしたら、きっとぼっちちゃんはもっと失敗出来ただろうし、その事によって、終盤も中盤と変わらない共感や距離感の近さを感じる事が出来たんだろうなと思うのです。
もちろん成長はあって良いです。それがなかったらただのお馬鹿です。
でも、それは中盤よりも10cm位上の、小さな成長であって欲しかったと言いますか・・・。
・・・これ以上書くと、ただの我がままになるのでこのあたりで。
まとめ
ここまで散々な事も書いてしまったように思いますが、これだけ書いておいてどの口が言うんだというのはありますが、この作品がとても好きだという事は改めて書かせて下さい。
ポテンシャルがある作品だと思いますし、色々な展開も期待できる素材だと思うのです。
そこに加えて、上で触れた通りアニメ作画は鬼ですし、声優の芝居も素晴らしかったでし、音楽も最高です。
ここ最近のアニメでこのクオリティのアニメを上げてみろ!と言われたらすぐには出てこないですし、パッと思いつくタイトルを上げると、片手に入る程の良作アニメである事は間違いありません。
だから続編がみたいです。
それを匂わせるように、この作品は、スッと2期に入る事が出来る終わり方をしてくれています。
この先もし2期があった場合、1つステージがあがったぼっちちゃんが、今度は12話という少しゆったりした時間軸の中で、更に、最初から心を整えた状態で見る事によって、今回感じた感覚とは全く違う印象を持てたり、気が付かなかった新たな発見を見つける事が出来るという気配もビシビシ感じています。
恐らくこの感想を読まれた方は視聴者だと思いますが、だからこそ、まだ見ていないという方が居られれば、見て損は無い作品ですのでおすすめしたい作品です。
ここまで書いて何言ってるんだ!という気持ちは一旦横においていただき、実際に目で見て、作品の良さを感じ取って頂けると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
