
新規事業を促進させるプロダクトデザイナーの役割とは?|ReDesigner Online Meetup Vol.3 :イベントレポート
こんにちは、KOELの田中です。
2021年2月10日に開催されたイベント「各社が考えるプロダクトデザイナーとは:ReDesigner Online Meetup Vol.3」にKOELのデザイナーである武田と田中が登壇しました。
イベントでは、Sansan社とKOELが「各社が考えるプロダクトデザイナーとは」をテーマに各社のプロダクトデザイナーの役割、キャリア、要求されることについてお話ししました。イベントの様子が気になった方はReDesignerのイベントレポートもありますのでご覧ください。

今回のイベントでは「NeWork™️」というプロダクトの事例を中心にお話しさせていただきました。


本noteでは、その中でもKOELのプロダクトデザイナーの役割と面白さを追い求める上で必要な3つの要素に絞ってお届けします。事業会社のプロダクトデザイナーの方やプロジェクトの進め方に課題や悩みを持っているデザイナーの方にぜひ読んでもらえたら嬉しいです。
1. デザインワークのアウトプットだけでなく、問い続ける
現場では「自社ではこれはできない」「こうでなければならない」という制約が出てくることがあります。リサーチや顧客体験設計、UIデザインのようなアウトプットに邁進することももちろん大事ですが、まず制約を取り払うためにこの制約に問いを立てることが重要です。
武田:弊社のようないわゆる「大企業」「レガシー企業」というのは、スピード感の欠如、しがらみ、上意下達、制約の多さといったイメージを持たれることがあります。正直、これら全部を「いや、全くないです」と言えるわけではありません。しかし、こういうところでこそデザイナーが価値を発揮できるのではないかと私たちは考えます。

例えば、僕らがよく使う口癖は「それ、なんでやるんですか?」という言葉です。「うちではこれはできない」とか「こうでなければならない」という制約って、紐解いていくと前例や過去の成功体験によるものがすごく多かったりします。制約なんて本当はなかったんだけど、自分たちであると思い込んでがんじがらめになっている。そういう制約の前提を明らかにして理由のないものは取り払っていくことが、当社におけるデザイナーの大事な役割なんじゃないかと思っています。
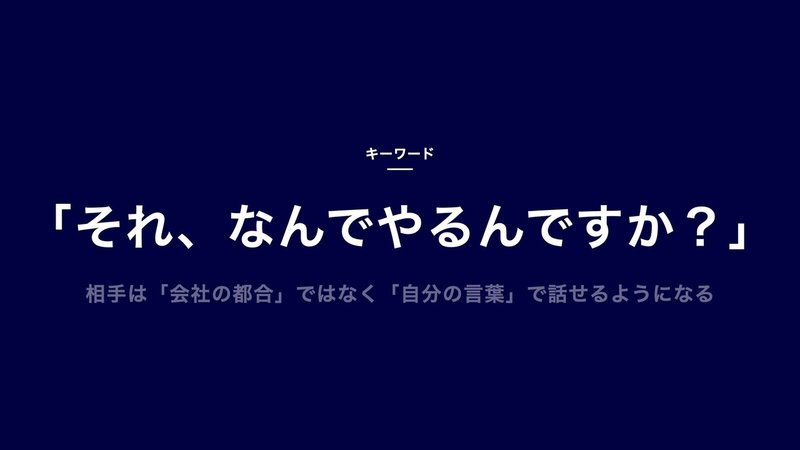
2. 人やチームをつなぐ
問い続けることだけでなく、プロジェクトのファシリテーションや開発〜プロダクトマネジメントサイドの間を繋ぐこと、さらにはチームをひとつにまとめ一人ひとりが本音を話せる環境を整えることも重要な仕事です。
武田:当初、「NeWork™」プロジェクトの体制は、プロダクト、デザイン、開発の各チームが完全に独立した縦割り組織が想定されていました。「デザイナーがコンセプトデザインとUIデザインを作ってくれたら、開発部門がそれを実装して、プロダクト部門がビジネスにするから」そう言われて、僕らは「もっと良い進め方がある」と思いました。2~3ヶ月で作っていくプロダクトなのに、それぞれのポジションからしか話ができない状況ではうまくいかないだろうと感じたのです。

武田:そこで我々の方から、検討からローンチまでは1つのチームとしてやりませんかと提案し、そこからはほぼ1つのチームとなってプロダクトを作りました。例えば、プロジェクトマネージャーにはコンセプトのところからがっつり入ってもらったり、エンジニアにはそれを見てもらい先立って検討を始められるところを作ってもらいました。3ヶ月という短期間でプロダクトがリリースできたのは、これまではチーム間で利害が一致せずにいがみ合っていたかもしれない部分で対話ができたからだだと思います。また、後になって聞いてみると、縦割り組織について「もっといいやり方あると思ってたけど言えなかったんだよね」という話も出てきて、部署や利害関係が違っても、同じことを一緒に経験していくとこのように本音が聞けるのだと実感しました。
3. 衝動を解放する
このようにメンバーのやりたいことの本音を引き出すことを私たちは「衝動を解放する」と呼んでいます。「衝動を解放する」機会を増やしていくこと、そのための発火剤になることがKOELの役割であり、存在意義の一つでもあります。

武田:このように「やりたいこと」の本音が出てくることを、僕らは「衝動を解放する」と呼んでいます。何か仕組みを与えれば、みんなが自分の言葉で話し出す。今回のプロジェクトのポイントは、様々なメンバーが自分の衝動を解き放つこ
とができた点だと思っています。このように「衝動を解放する」機会を増やしていくこと、そのための発火剤になることがKOELの役割であり存在意義なのではないかと思っています。当社は歴史が長いので、これまでの習慣や成功体験が前提にされていることが多いです。より良いものを作るためには「それ、なんでやるんですか?」と問い続ける姿勢を持つことが、ユーザーに近い立場にいる我々デザイナーには必要です。もちろん難しさはありますが、その壁を乗り越えることで、大企業にしかできない規模で多くの人と一緒にものづくりができます。それが大企業で働くデザイナーの楽しさであり醍醐味なのかなと思っています。
最後に
今回KOELのプロダクトデザイナーの役割をお届けしましたが、プロダクトデザイナーの役割や在り方に正解はありません。Sansan社ではSansan社のプロダクトデザイナーの役割があるように、会社の文化や環境によって役割や在り方は変化するものなのでしょう。
また、同じ事業会社で働くデザイナーとして、他社の体制、プロダクト開発でのデザインプロセスを知ることができ、大変参考になりました。登壇とともに、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。
本noteがプロダクトデザイナーの皆さんのお役に少しでも立てれば嬉しいです!
—————————————————————
—————————————————————
PR:NTTコミュニケーションズ・デザイン部門「KOEL」では、通信会社だからこそできる、新たなコミュニケーション、社会インフラを一緒にデザインしてくれる仲間を募集しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
KOEL note 編集チーム 福岡陽、八木 貴之
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
