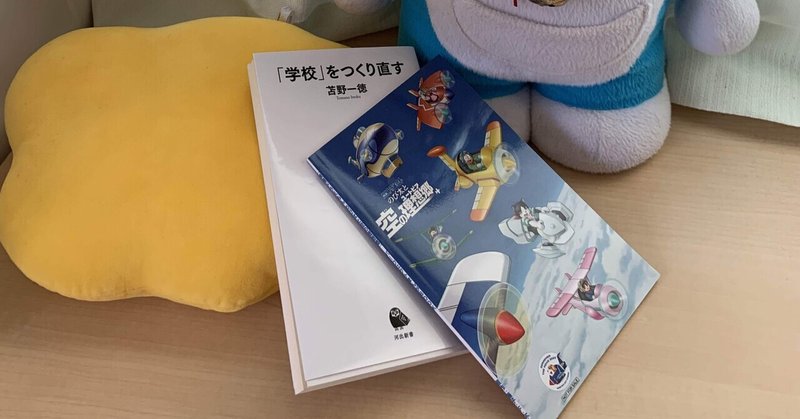
映画『のび太と空の理想郷』と小学校の授業参観で気づいたこと
先日小学校の授業参観がありました。
毎年観察していて、毎回あるモヤモヤ感がありました。
それは自分の子どもの頃の体験と大人になって”今”を生きている体験からくるものでした。
この辺りを書いてみたいと思います。
授業参観レポート
先日ドラえもんの映画を観てきました。
『映画ドラえもん のび太と空の理想郷』
うちの子どもは、ドラえもんの映画を好んで新旧関係なくわりと網羅しています。ドラえもんで育ち栄養をもらった自分としては感慨深い…。
製作者がそれぞれの時代背景を反映したメッセージを込めていて(昔と比べて説教臭いなあと感じること、ありますが…)感想はあえて聞いていないです。ちょうど授業参観後に観たので気づいたことを書きます。
のび太は不器用で怠け者。相変わらずテストの点数が悪くて落ち込み、”パーフェクト小学生”になりたくて理想郷の学校に通い始めます。
映画ではその学校の授業風景がありました。
「次は体育の時間です」生徒は運動場に移動します。算数と体育が一緒になっているようで、算数の問題に正解すると障害物をクリアして先に進めるアスレチックをしていました。周りの子はできない子を応援します。
給食では栄養バランスのいいものを出し、起床就寝時間がきびしく決められています。
結局決められたことをやっているのですね。
時間割もあるし、先生が教える一斉授業もあるし、生徒同士の協働もない。
この理想郷での教育は大人・管理者にとっての理想の教育です。
(まあ、映画のストーリーがそういうものなので意図的に描いているのでしょうね)
家では。ママが「宿題やったの?この点数はなに?」とガミガミいう(のび太のママは、熱心すぎるくらいのいわゆる”教育ママ”)
学校では。話に熱中していたら先生に「今は授業の時間だ」と怒られる。
のび太はテストの結果に一喜一憂し、0点のテストを隠す…。
今も変わらない一般的な光景がくりひろげられています。
(0点とれるのはある意味すごく特殊ケース…)
この光景はいまだに現実にあります。
テストの点数ではかる子どもの学力。
学校どころか家庭でも宿題というテスト勉強を強いられる。
机に座って静かに授業を受けなければならない子どもたち。
決められたことをやらされている子どもたち。
今まで授業参観で実際に観てきた子どもたちの様子は次のようなものでした。
※おことわりしておきますが、個々の先生の教え方を批判しているわけではありません。教育システムがそもそもの問題と捉えられます。
■2年生の算数。
黒板に先生がきれいな文字で問題を書きます。子どもたちはノートに書き写します。先生はどういう風に考えたらいいか質問をします。手を挙げた子が発言するのを繰り返して、それをまとめて正解に誘導します。
うちの子どもの様子を後ろから見てみると、手を動かして消しゴムと鉛筆でなにかを作って遊んでいました。
その時私はこう思いました。
[退屈な授業は確かにある。ガマン。内職する時間っていうのも大事かも]
■3年生の図工。
工作キットが配布されます。素材などすべて用意されたものです。初回どういうものを作るか構想する時間でした。「(参考にするので)タブレットで調べて良いですか?」「キャラクターはダメです」といったやりとりが聞こえてきます。一部の子はタブレットで画像を検索していました。おそらく教室外に見に行ったり図書室で調べるのと同じ感覚でしょう。子どもが移動するときに、机の間が狭く、前後の子にぶつかって物をおとしている光景をよく見かけました。※35人程度の学級でした。
後ろから見ていた子どもたちの様子は。
机に伏して寝ている子。真面目に絵を描いている子、ぼーっとして何も描かない子(何か描きなさいと注意されている)…いずれにしても、教室が狭すぎて大きな教材を床に置いたり、下絵の紙が机からはみ出していて描くのに苦労していたり…。
私はこう思いました。
[この時間内で描くのは難しいだろうな。ぼーっとしている子も実はアウトプットに時間がかかる子なのかもしれない。この環境だったら、勉強に集中できないのも無理はないなあ…]
■4年生の算数。
先生がグラフの書き方を教えます。先生は「これは書き方の一例です」と言われていましたが、子どもは予想以上に従順で人の真似をする性質があるので、子どもたちはそれを真似して同じようにノートに書き写します。ノートの使い方も指示された通りみんな一緒です。
子どもたちの様子にはやはり個人差がありました。とちゅうで「あ、この形(のグラフ)見たことある」と呟いただけの子、親が来ている為か集中できないでいる子、別の方法で正解にたどり着いている子…授業の進度が個々にあっていないようでした。
3年の時より教室内は落ち着いた雰囲気になっていました。※学級が半分になり教室も広くなりました。
私は思いました。
[子どもが授業に集中していないのは個々の学び方に合っていないからでは?
今勉強したいことと目の前の授業が違うのでは?
教室内が落ち着いたのは、子どもたちの成長もあるけど環境が良くなったからでは?]
それからあらためて気づいたこと。
[私の子どもの頃と学校の環境はほとんど変わっていない。それから学校は”張り紙”が多いな。”約束”、”学級のめあて”、”当番”…。]
子どもたちがいかに、
”○○しなさい”、”△△は禁止”といった規則に囲まれているか…
はたしてこれで、学校は子どもたちにとって”居心地のいい場所”、”安心できるリラックスできる場所”、”自律できる場所”になり得るのでしょうか?
(会社で”社是”、”規則・ルール”、”売上目標”などがいたるところに掲示されていて、出社のたびに目にすると考えるとぞっとしませんか?工場のように意図的にルール掲示が必要な職場もありますが、学校はそのような場ではないですよね?)

自分の子どもの頃の学校教育
私の子どもの頃は、先生が黒板に書いてノートに書き写し、先生の話をだまって聞く一斉授業が大半でした。私は耳から入る学習方法は得意ではなく、視覚からのインプットが得意なので、今考えるとこの授業スタイルは自分に合っていませんでした。当然授業も退屈でガマンしていました。
私の子ども時代は高度成長期であり、一流大学から一流企業へという価値観が主流でした。
(国民が一丸となって統制の取れた結果国力が増したという)成功体験がそのまま旧来教育を良しとしていたきらいがあります。そのため、明治時代から続く”国力をあげるための統制された学校教育”を良しとしてきたのです。
当時は子どもの数が多かったし、ラディカルなテレビ番組もあったり(ゲームや漫画といった)子どもの流行が大人にも受け入れられていたおおらかな時代だった気がします。ちびまる子ちゃんやサザエさんみたいな大人と子どもでそれぞれの社会があるイメージ。大人は子ども社会に口出しすることはそれほどなかったかもしれません。
学校の役割=勉強を教える(テストが学力の基準)
先生と保護者の関係=子どもの勉強が話題の中心
だったように思います。
今、これからの学校教育
今は学校の役割も多岐にわたります。
子どもの調停役、いじめの見張りなど、子どもへの過剰な見守り…
保護者との関係も、勉強だけではなく子どもの成長や学校環境に関する苦情まで、内容はより複雑になったような気がします…。
その中で何を学校に求めるのか。学校教育で子どもたちに何を学んでもらうのか。
今こそ原点から考えることが必要です。
1・教育の目的:子どもたちにより良い未来を作る”社会の形成者”になってもらうこと[日本国憲法、教育基本法より]
自由の相互承認によって平和な世の中をつくる[本1※より]
2・教育内容:世界の縮図を理解する(身近な社会から世界のことまで理解する)[本2※より]
3・教育方法(教育システム):一斉教育、オルタナティブと言われるさまざまな実践がある。じつは明治大正時代からも一斉教育以外の実践が試行錯誤されていた。(※これについてはまた別の機会に記載します)
※本1:「学校」をつくり直す 苫野一徳
※本2:学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田照幸
子どもたちに身に付けてほしい能力は時代とともに変わります。
おおまかにこのような変遷になるでしょうか…。
今まで(おそらく本や情報の入手が限定的で、知識へのアクセスが限られていた時代から)
■知識の詰め込み教育、たくさんの知識を覚えている能力
↓
インターネット社会になって、世界中の情報が流れ込んできています。
■知識を集める(検索)能力、知識を活用(選択)できる能力は今でも必要だと思います。
■情報の質と量”高感度”のアンテナを持っている人。
↓
そしてこれから、AIが社会に浸透する時代では…
■正しい知識を得るための問いを作る能力
■正解のない問いにどう答えを探すか=哲学的思考=自分の軸をもつこと
冒頭のモヤモヤ感の正体。
自分の子どもの頃の体験は時代が変わるとともにズレてきていたのです。
大人になって”今”を生きている体験では、あのころと価値観がだいぶ変わっています。それなのにシステムだけが変わらないでいると、システムの中にいる人たちに悪影響が及ぶのです。
夫婦別姓、同性婚、戸籍、男女格差、少子化、入管法…日本で問題になっているシステムの根は同じです。
例えば、アップデートできないレガシーなソフトウェアは、バグだらけで攻撃を受けるスキだらけで危険であり、実務にあわない不合理な業務を生み出します。不幸でしかありません。
150年間変わらない学校教育をどう変えるかも、喫緊の課題だと思っています。
再び授業参観レポート
さきほど書いた授業参観の感想。
①子どもが授業に集中していないのは個々の学び方に合っていないからでは?
②今勉強したいことと目の前の授業が違うのでは?
③教室内が落ち着いたのは、環境が良くなったからでは?
それぞれの解決案を次のようにあげてみます。
①個々にあった勉強方法(例えばタブレットでの個別学習)
②時間割は不要
③落ち着いた環境づくり
じつは、すでに実践している学校もあるのです。
そして、今の日本の法令や方針でそれを妨げるものは一つもありません。
ガマンには2種類あるといいます。
良い我慢はそれをすることで成長したり何かを得ることができるもの。
悪い我慢は苦痛に耐えるだけのやり過ごすためのもの。
例えば、自分に合わない授業を黙って座って受けている子は、ただ苦痛をやり過ごしているだけのガマン…。これをその子にあった教材で良いガマンに変えてあげられないでしょうか?

居心地のいい環境づくり
いきなり学校全体を変革するのではうまく物事を進められません。
多方面で合意を得るにしても、資金を調達するにしても、大きな変革は難しいです。
そこで”小さく始める”、”工夫でできること”を考えます。
③落ち着いた環境づくり
これはできそうな気がしませんか?
■案1 張り紙がないすっきりした教室
・極力張り紙をなくすことで、精神的な緊張や圧迫感から解放されると思います。デザイン面でもシンプルがいいでしょう(子どもには良いアート環境も必要)
・企業理念を貼りだしたからといって社員が覚えるわけでも実践するわけでもない[本※最軽量のマネジメント 山田理]
■案2 お気に入りのものを身近に
・大人でもお気に入りのマグで好きな飲み物を用意、お気に入りのキャラクターを配置してホッと一息つくことありますよね。
・ひとりで不安な子も、安心するものがそばにあれば過ごせそう。意外と高学年の子も男女かかわらず大小ぬいぐるみをかわいがってる。
[関連する記事※イギリスの学校教育とぬいぐるみ]
■案3 教室を飾り付ける
・置いてあるのは観察用の味気ない植木鉢だったりするので、好きに飾ってもらっていいと思う。
■案4 自在なレイアウト
・会社によってはフリーアドレスとして違う机で仕事するところもある。気分転換で時々入れ替えたり、集中したい授業は前列など、気持ちで使い分けができるといいかも。席替えで明暗がわかれ、不幸になっている子もいるかもしれない。
・授業によっては机をとりはらい、床や自作の椅子や、好きな場所でできたらいいと思う。畳をおいてもいい。学校は校庭もあるから青空教室もできる。環境を変えられる可能性はたくさんある。
学校を変える方法はいくらでもあります。公立小学校でも工夫次第で子どもの居心地のよい場所にできます。
[関連する記事※「どうやって子どもたち一人ひとりと向き合うの?」]
→kintoneを使用している点にも注目!
子どもを信頼して任せませんか?
放っておいても子ども同士で考えて調整する能力は充分あります。
公園で遊んでいる子どもを見てると、個々に動いていても公園の秩序は保たれているし、なにより子どもが幸せそうに楽しんでいます。
宿題もしかり。やりたい子はやればいいし、強制する必要はないと思います。学習指導要領により「すべての子の学力を保証しなければならない」とあっても、個々が身に付ける学力は必ずしも宿題とは無関係なはずです。
もし学習習慣をつけるための練習だとしたら、工夫次第で良い方向に転ぶので、宿題問題は柔軟にしておきたいです。[※下記の記事]
(子どもにとっては家庭=安らげる=好きなことをできる場所であってほしいのです)
じつは授業参観当日まで、私の気持ちは割と学校に対して批判的でした。
宿題をだしてくるのも私の教育方針とは異なり、学校教育を変える必要があると意気込んでいたんです。
しかし、今回の授業参観後に懇親会があり、学級運営について先生からの説明があり、(質疑というまでもなく終わりましたが…)批判ではなく一緒に変えていきたいと考えが変わりました。
対話の場があると心がほぐれるんですね。
もし保護者と先生が対立しているところがあればぜひ対話の場を設けてほしいと思いました。学校の様子を知ることで、私たちは話し合いができ、協力的になれるのです。互いを知らないことで生まれる分断があるんです。
分断させるものを取り払うことが、ものごとを解決させるコツです。
ちょうど同じことを語っている談話がありました。
うちの小学校もあだ名禁止ですが、保育園では自然に呼びたいように呼び合っていましたよ。まずはニックネームや手紙の禁止をオカシイと思い、話し合うことが大事です。
#46 教育・子育ての基本は「信頼して、任せて、待って、支える」 - 苫野 一徳 @ittokutomano
https://voicy.jp/channel/3397/510813
保護者も先生も自治体も様々な立場の大人が一緒に
子どもの最善の利益(子どもたちが学校で幸せに過ごせる)のために
出来ることから学校を良くしていきませんか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
